「発掘せよ!!産業人の原石、未来の輝石」をテーマに、第33回全国産業教育フェア福井大会(さんフェア福井2023)が10月28、29の両日、福井県生活学習館、福井県産業会館をメイン会場に開催される。同大会では全国の専門高校などの日頃の学習成果や技術、産業の魅力を発信する。今回は「作品・研究発表、展示」「意見体験発表」に参加する学校、生徒の日頃の取り組みなどをいくつか紹介する。
【目次】
◎作品・研究発表、展示
農業
工業
商業
家庭
看護
情報
福祉
水産
◎意見体験発表
◎ジュニアマイスター顕彰制度

(1)テーマ設定理由
私たちは、学校設定科目「沖縄の農業」の授業で、沖縄県のイチゴ栽培について学習した。沖縄県でのイチゴ栽培に興味を持った私たちは、科目「課題研究」の授業で県内のイチゴ農家を訪問し、沖縄県のイチゴ栽培の現状について調査した。
訪問したイチゴ農家によると、「県外から苗を購入しているため、苗代のコストが高くかかる」「県外産の苗は病害虫対策や栽培管理が大変で、収穫量も安定せずとても苦労している」と、県内でのイチゴ栽培には多くの課題があることを知った。
イチゴ農家の悩みを解決したいと考えた私たちは科目「植物バイオテクノロジー」と学校設定科目「沖縄の農業」で学んだことを生かし、沖縄オリジナルイチゴの育種と沖縄県における持続可能なイチゴ栽培を目指し「沖縄イチゴ未来プロジェクト」をスタートさせた。
(2)研究活動の成果
(1)人工交配を行い、播種、発芽、育苗へとつなぐことができた。
(2)茎頂培養実験を行い、培養技術を修得することができた。
(3)冷凍花粉による交配が可能であることが分かった。
(4)イチゴ農家と連携し育種を行うことができた(図1)。
(5)品種登録の方法について知ることができた。
(6)交配種から2株の優良株を選抜し、茎頂培養へつなげることができた。
(7)順化・鉢上げに適した培養土を調査することができた。
(8)持続可能なイチゴ栽培に向け地域交流を行った。
(3)最後に
私たちの取り組みが実現できれば、沖縄県内にもっと県内産イチゴが流通し輸送コストの削減や環境負荷を抑えられ、それはSDGs目標達成にもつながると感じている。持続可能なイチゴ栽培に向け、県民に愛されるおいしいイチゴ、全国、世界に誇れる沖縄オリジナルイチゴを目指し、これからも研究を続けていく。

秋田県南部の果樹地帯では、リンゴ栽培が盛んで、夏から秋には多くのカラスが飛来する。リンゴは7月から果実が膨らみ、着色するが、その頃にはカラスが数千羽にも増え、果実を食害する。果樹農家でインターンシップに参加した際、果樹園に「硫黄石」をつるしているのを発見した。硫黄石はカラスよけに効果を発揮するが、1キロ1万円と高価である。
秋田県仙北市玉川温泉は、日本一の強酸性を誇る硫黄泉である。中和された温泉水は手ですくうと「湯の花」がたまる。硫黄石と比較して、硫黄臭はきつく、無色である。この湯の花は川に流すことができず、廃棄物になっていることを知った私たちは、湯の花が硫黄石の代替資源になるのではないかと仮説を立てた。
実験では、防鳥ネットを設置しない早生品種で比較調査を実施した。標準区には何も設置せず、試験区Aに湯の花、試験区Bに硫黄石を設置した。設置後1カ月で、リンゴ1本当たり、標準区で100果中、53果、硫黄石区で100果中80果が守られたのに対し、湯の花区では100果中全てが守られた。この湯の花を多くの方々に届けるために湯の花キットを作製した。
湯の花キットは硫黄石以上の効果で、きつい硫黄臭か、薄い黄色が要因と考察した。また、SDGsの産業と技術革新基盤づくりによるアップサイクルをテーマにしたことで地域の未利用資源で製品を生み出した。今後湯の花の使用で硫黄石のエネルギー資源以外での生産や輸送コストを抑え、脱炭素社会実現にも貢献できる。キットは、地域を中心に無償配布を行い、報道機関の取材など全国に向けて普及啓発を実践中している。
循環型鳥害対策資材は、一定の成果を上げることができたが、今後も人間が持つ偉大な能力の可能性を信じ、鳥獣との駆け引きは続く。

本校は1939年(昭和14年)に設立され、今年で85周年を迎える。校訓『錬磨創造』を掲げ、機械科、電気科、電子工業科の3学科で約600人の生徒が在籍している。『ものづくり』を通して専門性を追究するとともに、クラブ活動や生徒会活動、ボランティア活動、資格取得などを通じて進路実現を目指し日々の活動に励んでいる。
本校では、3年次に履修する課題研究のテーマを考える際に、長野県で導入されている、生まれ育った地域について探究的に学ぶ「信州学」に基づき、地域の身近にある問題点をテーマに取り入れることを行っている。
今回のテーマ設定時、ある企業から寄せられた困りごとを生徒に伝えた。その困りごととは、穀物倉庫内に出没するネズミを、旧来の方法ではネズミが慣れてしまい駆除できないというものであった。自分たちが学んだ工業の力で解決できないかと考えた生徒は、解決策として実習で取り組んだドローンを使ってネズミを追い払うアイデアを提案し、企業・大学・本校で連携して取り組むこととなった。
企業がAIカメラによるネズミの検出を担当し、大学がネズミまでの軌道を決定しドローンを誘導する部分を担当。本校生徒はドローンをネズミまで移動させるドローン制御を担当した。現在、大学が軌道決定した情報によりドローンをネズミまで急行させる実験を行っており、今年度中にシステム全体の実証実験を行う予定である。
生徒が身近な課題を発見し主体的に問題に向き合い、独創的に解決策を探究し、科学的な根拠に基づき創造的に解決する力を養い、将来、社会を支え産業の発展を担うエンジニアとして羽ばたけるよう、今後も産学官連携の学びができる環境をつくっていきたい。

本校は、岡山県南西部に位置する浅口市にある。今年で創立100周年を迎え、普通科には、スポーツやIT、公務員など7コースと、機械科や調理科などの実業系4学科からなる中規模校である。
自動車科は1985年に設置され、姉妹校の岡山自動車大学校との一貫教育で多くの自動車整備士を輩出している。若者の自動車に対する興味・関心を高めてもらうために自動車科では、夢のあるものづくりに取り組んでいる。
これまで、高校生の技術力でギネス世界記録に挑戦した「世界一車高の低い車 MIRAI」、水陸両用車や、どの方向にも自由自在に動ける車など3年に一度、技術の集大成として数々の車両を製作している。
近年、ベンチャー企業を中心に「空飛ぶクルマ」の開発競争が過熱している。自動車について学んでいる生徒が近い将来、空飛ぶクルマの整備を担う可能性がある。空飛ぶクルマを購入する資金はないが、自らの力で製作することにより、その知識や技術は彼らに蓄積され生かされるはずである。
限られた予算と期日、専門的な知識を持ち合わせていない中で、これまでの車両製作で培ったノウハウを生かすことで、軽量かつ高剛性のフレームを製作することができた。小型で高出力なモーター、バッテリー、制御装置については、購入を依頼した会社の方がこの取り組みに賛同し、技術的アドバイスをしてもらった。試行錯誤の末、2021年1月に無人での室内フライトにたどり着くことができた。17回目のテストフライトで高度1メートル、3分間の安定飛行が達成できた時には、これまでにない大きな達成感を生徒とともに味わうことができた。
現状では、安全性の確保や飛行能力の向上、航空法を満たす飛行実験など課題が山積している。高校生では不可能と考えていたこの取り組みを通して得られたものは、彼らに未来への「希望」を抱くことができたに違いない。
これからも地域社会で活躍できる未来に希望を持った自動車整備士を育成していきたい。

本校は、1902(明治35)年に創立された群馬県内で最も歴史と伝統のある商業高校である。「燃えろ高商 未来にチャレンジ」のスローガンの下、生徒一人一人の人間力を向上させる教育活動を実践している。今回の産フェアでは、マーケティング部の取り組みを紹介する。
マーケティング部は、身近な地域で調査・取材活動などを行い、発見したビジネス課題に対して高校生の視点で解決策を企画し、実践している部活動である。授業で学習した商業の知識や技術を活用した実践力を育むことを目標としており、ビジネス社会で活躍できる人材の育成を図っている。
これまで、高崎市内での観光イベントの開催(2021年)や、高崎市の中心市街地にある店舗の一押し商品の販売(22年)などを実践した。さらに、これらの活動の成果を全国高等学校生徒商業研究発表大会(主催/(公財)全国商業高等学校協会)で発表し、2年連続で優秀賞を受賞した。
群馬県は、世界遺産に登録された富岡製糸場に代表されるように、古くから養蚕・製糸・織物の絹産業が盛んな地域である。しかし、高齢化による後継者不足で養蚕農家が減り、繭の生産量も減少している。
生徒は、このような絹産業の現状に興味を持ち、従事者への取材やアンケート調査を実施した。その際、絹産業を維持するために奮闘している従事者の姿を目の当たりにし、生徒は高校生の視点でできるイベントを企画した。シルク製品の販売を中心とし、「Silook」と名付けたイベントを開催した。
県内の企業から養蚕、製糸、織物に関連したシルク製品を仕入れ、ショッピングモールや道の駅で販売した。展示パネルを作成し、群馬県の養蚕と製糸について消費者の理解を深められるように展示した。さらに、繭をより身近に感じてもらうために、糸繰り体験や繭クラフトくじを実施した。
マーケティング部の活動は、地域の方や企業などの多大な協力によって支えられている。これからも感謝の気持ちを忘れずに、生徒が地域経済の発展に貢献できる人材として成長できるような活動をしていきたい。

人口20万人を超える中核市で魅力あふれる街である佐世保市だが、人口減少が大きな課題となっている。以前から若者の市外流出は顕著であったが、それに加えて全国平均を上回っていた出生率が2015年から減少に転じたことで人口問題は今後ますます深刻になる可能性は高い。
このような中、本校は18年度に学科を改編。情報マーケティング科を新設し、佐世保の発展に貢献できる人材を育成するために「アントレプレナーシップ教育」の充実を目指すマーケティングコースを開設した。
マーケティングコースで取り組んでいる「ミライの企業家育成プロジェクト」は、「させぼのミライはわたしたちがつくる」をキャッチフレーズに、地域の諸課題をビジネスの力で解決できる企業家、あるいは企業家のように働く人材を育成するために19年度からその取り組みをスタートした。1、2年次には企業家として必要な知識や技術を習得・活用し、3年次には実践とともに探究する。この一連のプロセスを通じて企業家として必要な資質・能力を身に付けていく。
これまでに実践した取り組みは、地元商店街や市内事業所で実施するインターンシップである「商いチャレンジ体験実習」や校内外で地元はじめ各地の一押し商品を販売する「販売実習」、産学連携による「商品開発実習」、社会課題を解決するための「ビジネスプランの提案」など、多岐にわたる。今年度の3年生は、SDGsにつながりかつ本校創立100周年にふさわしい佐世保のお土産開発に取り組んでいる。
さんフェア福井2023では、アントレプレナーシップの醸成を目指した本プロジェクトについて、これまでの取り組みを紹介する。

静岡県立御殿場高等学校は、121年の伝統を誇る工業、商業、家庭の3科の専門学科を持つ県内でも珍しい高校である。中でも生活創造デザイン科は県内の公立学校で唯一の家庭に関する学科である。2006年から設置したヒューマンサービスコース、デザインコースは今年度の3年生で廃止され、食物、保育、被服を中心に学ぶ学科に替わる過渡期である。
その中で、3年前から取り組んでいる特長ある活動として、市民会館ホールでの「卒業製作発表会」が挙げられる。3年生の生徒全員によるショー形式の発表会である。生徒が主体となって、実行委員会を開き、テーマ決定やポスター製作、ショーの組み立て、演出、ナレーション、照明、音響まで行い、3年間の集大成を披露している。
2021年度のテーマは「bloom」、22年度のテーマは「flower」であった。
ヒューマンサービスコースは、2年次に「ファッション造形基礎」で製作したじんべい、アウターパンツ、3年次に「ファッション造形」で製作したブラウス、自分でデザインし型紙から製作したワンピース、「課題研究」の被服分野を選択した生徒は、ひとえ長着、共同製作のドレスをショー形式で発表し、幼児服を展示した。
デザインコースは、「課題研究」で行った染色でのトートバックや手拭い、Tシャツをショー形式で発表した。これまでの学校設定科目「情報デザイン」の授業で製作したCGや学校設定科目「ライフデザイン」で製作したイラスト、ポスターなどの個人ブース作品展示を行い、来客の保護者の方々にも喜んでもらうことができた。地元新聞社にも取材してもらい、地域の方々にもPRすることができた。

本校は水戸市にあり、1909年に大成裁縫女学校として創設された。今年で創立114周年を迎え、普通科、家政科、看護科の3つの学科を有する、茨城県内で一番長い歴史を持つ私立学校である。
69年に衛生看護科を設置し、2002年に5年一貫看護師養成課程である看護科に改めた。地域には本校を卒業した多くの看護師が活躍している。看護師を目指す強い意志を持った生徒たちが県内外から通い、日々切磋琢磨(せっさたくま)しながら看護を学んでいる。
今回は本校の学習活動から、高校2年生の老年看護と専攻科1年生の小児看護学の学習成果を展示した。
高校2年生は、老年看護を学び始めたところで、加齢による身体的・心理的・社会的側面の変化を学んだ。2月にはデイサービスセンターでの老年看護臨地実習が控えており、高齢者が生き生きと健やかに生活を送るための支援について考えさせた。そこで、1人1台所持しているiPadを使って「あいうえおかるた」の作成に取り組んだ。高齢者の日常生活をイメージして、対話を深めながら楽しそうに制作していた。完成したかるたを相互鑑賞させると、笑顔と歓声が上がった。高齢者の特徴である視力低下に配慮した文字の大きさや、イラストの彩色に目を向けられるよう指導を重ねていく必要があった。
専攻科1年生は、小児看護学の授業の一環としておもちゃを製作した。ミトンをパペット風にアレンジした「ぱくぱく・ぱっくんちょ」は、子どもが気持ちを表現したり、遊びを通して食事や歯磨きを学んだりすることを想定した。製作した生徒は、小児看護学実習を通して幼児期前期は月齢によって発達の差があったり、自分中心に物事を考えたり、意志決定は自分でするといった特徴を学んだ。そこで、子どもが楽しめるように、モチーフが選択できたり、付け外しは磁石やボタンを用いたりした。安全に遊べるよう隙間がないように縫い付けた。
生徒たちの取り組みをみると、こちらの想像をはるかに超えた創意工夫に驚かされる。実際に生活する高齢者や子どもをイメージしながら、生徒が自分で何ができるかを主体的に考えることで、学びが深まっていくと考える。今後も体験的な学習活動の充実を図っていきたい。

本校は、本州と四国を結ぶ瀬戸大橋の玄関口となる香川県坂出市にある。本校は、1914(大正3)年の創立以来、香川を代表する商業高校として発展してきた。その後、高度情報化社会に対応すべく、専門学科情報科の「情報技術科」を四国で初めて設置した。本校情報技術科では、デジタルクリエイトコースとシステムコースにおいて高度な技術の習得を目指し、ビジネス社会で即戦力として活躍する人材を育てている。
坂商フェア「セキレ」(以下「セキレ」)は、商業、情報の授業で学んだ知識・技術を実践する場として生徒から出資を募り、模擬株式会社の形態で開催している。中心市街地を活性化させようと2010年からは校外で実施している。「セキレ」という名称は、校訓の「誠実・勤勉・礼節」の頭文字を取って名付けたものである。他校の文化祭とは違って「販売実習+文化部展、発表」が行われる本校最大のイベントである。
今回のパネル展示は昨年末に実施した「セキレ」の感染症予防対策として、混雑を軽減するという課題解決の経過報告になっている。本校の情報技術科2年生(現在3年生)がこれまで培ってきた情報の知識・技術を生かして「入退場管理システムの開発」に取り組んだ。
3年ぶりに「セキレ」を実施するために、入場者数を把握しリアルタイムで混雑状況などを複数の拠点へ示す必要があった。そのために、QRコードを利用した入退場管理システムの開発に取り組んだ。システムの開発に向けてプログラミングとテスト運用を繰り返し、「セキレ」当日のスムーズな運用に向けて、受付担当者への操作研修など事前準備に多くの時間をかけた。開発後は、「セキレ」当日に実際に運用し、来場者データの管理・混雑状況の把握・アンケート回答の回収などの自動化・省力化に貢献できた。
今年の「セキレ」は、JR坂出駅前広場で、12月9日(土)、10日(日)に実施する予定である。

本校は、1948年に創立された学校である。2020年丹南高校との統合により、新体制の下、新たなスタートを切った。2学科3コース4専攻となり、特色ある多様な学びが充実している。
その中の一つに健康福祉専攻がある。私たちが日々大切にしていることは「たくさんの人と出会い、相手を知ること」である。今年度特に力を入れたことは、外部の方々とのつながりである。施設見学や施設実習、交流会や学習会を実施し、多くの人と出会い協働する場を作った。
生徒たちは、高齢者や障害児者と接する時に、「自分たちが助けてあげなきゃいけない」と思う傾向が強い。だが接していく中で相手から教えられることや助けられることもあると感じるようになる。ある生徒は「偏見は持っていないと思っていたが、初めて会った障害者の方に驚いてしまった。自分の中にも偏見があったのかもしれない。障害の有無に関係なくみんなが助けたり助けられたりしながら生きている」と気付きを得た。自分と他者との相互作用により、生徒は自分の思いに気付き、考えを変容させることができたのだと思う。
このことから、まだ生活経験も浅い高校生が福祉を学ぶことは簡単ではない一方、高校生だからこそ学ぶことの重要性を改めて感じた。人口減少・認知症高齢者の増加など、課題のある日本において、若い世代の力が不可欠になってくる。自分たちが暮らす地域にいる多くの高齢者や障害者の方の中に、もし困っている人がいたら声を掛けられるようなそんな人材を育てたいと思う。
そして、健康福祉専攻では、人や地域とつながることで、そこでの体験や聴いた言葉が、これからの人生において、役立ったり救われたりする一助になればと願っている。

北海道には、水産科を有する高校が3校ある。
小樽水産高校は、創立118年の歴史ある学校で、学科は海洋漁業科・水産食品科・栽培漁業科・情報通信科の4つあり、さらに専攻科として漁業科・情報通信科がある。「わが国の水産業・海運業・通信業を双肩に担う人格・識見・力量を身に付けた人を育てる」ことを学校教育目標としている。
函館水産高校は、創立88年の学校で、学科は海洋技術科・水産食品科・品質管理流通科・機関工学科の4つあり、さらに専攻科として機関科がある。水産人として、「堅忍不抜の気魄・進取力行の態度・礼譲親和の気風・勤労愛好の精神」を身に付けさせることを目標としており、函水の伝統と呼んでいる。
厚岸翔洋高校は、厚岸水産高校と厚岸潮見高校が統合した学校で、普通科との併置校であり、水産系の学科は海洋資源科である。校訓は「一視同仁・精励恪勤」である。2022年度からマイスター・ハイスクール事業の指定校として、「IT技術を活用したスマート水産業」を目指して実践に取り組んでいる。
今回のさんフェア福井では、これら道内3校の学校・学科紹介や「マイスター・ハイスクール事業」の紹介、さらには、今年9月17日に天皇・皇后両陛下ご臨席の下、厚岸町で開催された「第42回全国豊かな海づくり大会北海道大会」の紹介などをするパネル展示を行い、各校の生徒の活動の様子を伝える。
また、総合実習などの授業において各校で製造している「さけたけのこ」「さばみそ煮」「サンマ水煮」などの缶詰の見本を展示するほか、小さな瓶に入った「透明骨格標本」と呼ばれる、魚の筋肉部分を透明にし、骨を青や赤に染色して、骨格配置などを調べるために開発された、見た目が美しい標本を展示する。

本校は福井市にある総合学科設置校であり「総合的な探究の時間」の授業では、『Mゼミ』と称し、自らが探究したいテーマをもとに、問いを立ててその解決に向けて活動していく。私たちは、母乳バンク寄付型自動販売機が本校に導入されたことをきっかけに、探究活動を始めた。
まずは母乳バンクとはどのようなものかを知るために、創設者の昭和大学の水野克己先生にインタビューを行い、説明を受けた。
母乳バンクとは、1500グラム未満の極低出生体重児へ母乳を与えるにあたり、何らかの理由で自分のお母さんから母乳を得られない場合に「ドナーミルク」を提供するため、母乳がたくさん出るドナーから寄付していただいた母乳を適切に処理・検査・保管する場所であると知った。
1909年にウイーンから始まったとされる母乳バンクは、2023年3月時点で東京に2カ所あり、災害などで提供が止まるリスクを考えて3カ所目に愛知県での設置が進んでいる状態であった。
次に、ドナーとして登録を行った静岡県の女性にもインタビューを行った。妊娠や出産を経て命の尊さを改めて実感し、善意で母乳を提供した経緯を教えてくださった。
23年3月には東京日本橋の母乳バンクを見学する機会を得ることができ、厳重に管理されているドナーミルクが多くの命を救うことを改めて理解し、私たちを育ててくれている周囲の方々への感謝の気持ちもより一層強まった。
将来出産・育児の経験をするかもしれない。ドナーミルク利用の選択をする場合、事前に知識を知っておけば、冷静に判断できるきっかけになるかもしれないと考え、現在は中学生や高校生に向けてパンフレットの作成や発表を通して啓発活動を行っている。
私たちは人工乳の使用を否定しているわけではない。しかし、早産・極低出生体重児にとってはドナーミルクの存在は生きる手段である。そして、生まれてきた命を社会全体で守るためにも啓発活動を続けていきたい。

岐阜各務野高校は2005年4月に岐阜女子商業高校と各務原東高校が統合され、旧各務原東高校の敷地にてスタートした新しい学校である。ビジネス科、情報科、福祉科という専門性の異なる3つの専門学科を設置しており、全校生徒約670人が在籍している。社会の要請に対応した高い専門性を有する人材の育成を目指すとともに、部活動においても女子ホッケー部が全国制覇70回を達成するなど高い実績を上げている。
情報科は、デジタルクリエーターを育てるための岐阜県内でただ一つの学科である。デザインやプログラミングだけでなく3次元CG、アニメーションや映像編集など、デジタル時代に必要とされるさまざまなコンテンツを「創る力」「伝える力」を高める授業を実施している。
私たちが入学した21年4月より教育課程が変更され、専門科目が選択制となった。1年生では、プログラミングやデジタルイラストの制作を通して情報を学ぶ上での基礎的な知識を身に付け、2年生以降は将来の夢などを踏まえ、プログラム分野とメディアデザイン分野の授業を選択する。
メディアデザイン分野ではデッサンの基礎から学び、デジタルイラストやアニメーション作品などのコンテンツの制作を行っている。制作したコンテンツは積極的に発信しており、多くのコンテストに参加している。22年度には世界エイズデーポスターコンクール高校生の部で最優秀賞をいただくことができ、どこかで目にしたことがあるかもしれない。また、地元企業のCMを作成する機会もあり、「自分が感じたことをどう表現すれば、人により良く伝わるのか」と考えるきっかけをいただいた。
私たちの3年間は最先端のデジタルテクノロジーに囲まれ、作品制作やプログラミングに没頭する毎日であった。その中で、これからを支えるテクノロジーには、人と人の関係をポジティブなものに書き換えることができると感じた。
「今、世の中ではどういったものが必要とされているのか」を模索しながら、デジタルの力を使って、新たな価値を付加し拡張することができるクリエーターを目指していきたい。
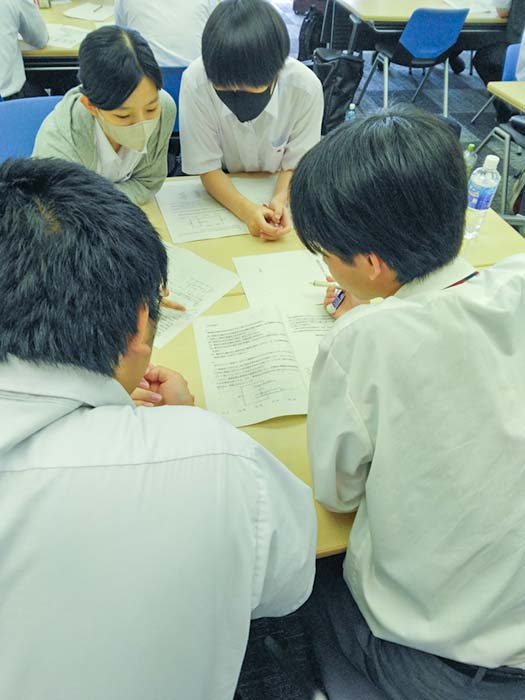
本校は、2023年度で創立116年の大阪で最も長い歴史のある工業高校です。22年度に大阪市の全高校が大阪府へ移管され、大阪市立都島工業高等学校から現在の校名となりました。卒業生は累計3万5000人を超え、産業界をはじめさまざまな分野で活躍しています。6つの専門学科を設置し、学科内に興味・関心・進路目標などに応じて選択するコース・系列を設け、生徒一人一人の目標を実現するための教育課程を実現しています。
23年3月卒業生342人の進路内訳は次の通りです。
4年制大学132人(国公立9人、私立122人、海外公立1人)
短期大学など10人(短期大学4人、高等専門学校4年次編入6人)
専門学校27人
民間企業139人
公務員26人
進学準備など8人
この多彩な進路実績と進学・就職がほぼ同数である点が府内の他の工業系高校と異なる特徴です。これには、前述の目標に応じた教育課程に加え、資格指導も就職・進学の双方に一役買っています。
大学には特定の資格の取得やジュニアマイスター顕彰を条件とした入試制度を持つ学校が多数あります。対象となる資格は高難度で高い専門性が求められるため、本校では次の取り組みをしています。
(1)教育課程の充実
7限授業により3年間の履修を102単位に引き上げ、普通科目の学習量を保ちつつ専門科目を充実させています。大阪府立の工科高校は総合募集で2年次から系(専門分野)に分かれるのに対し、本校は大阪市立の頃からの学科別募集を継続しています。入学時から専門科目を履修するため、基礎から応用へ3年間で系統立てた学習が可能です。この専門科目の充実は、放課後の資格指導などの学習効果を高め実績を上げる基盤となります。

(2)企業連携による合同学習
資格取得に向けた講習会は放課後の校内実施だけでなく、夏季休業期間に社会人や他校生との合同学習の機会を設けています。例えば、電気主任技術者試験の合格を目指す生徒には、電設企業で同試験の合格を目指す社会人との合同学習会を開催。また、今年度は社会人講師による学習会に近畿圏の工業系高校にも参加を呼び掛け、7月には2校、8月には5校が参加した合同学習会が実現しました。他者の視点での考え方を互いに得ることで、多角的に考察する力が育つ場となっています。
(3)先輩から後輩へのサポート
放課後の講習会は教員の指導が中心ですが、一部の学科では合格した上級生が下級生をサポートする「先輩の資格取得講座」に取り組んでいます。実際に合格した経験から生み出される説明上の工夫は、下級生の理解を促進し、次は自分が教える側に立ちたいという思いも重なって学習意欲を強めています。
こうして専門性を高めることで高難度資格取得者が増加し、昨年度の第一種電気工事士取得者は54人で、電気書院による全国高校生合格者ランキングで1位、第三種電気主任技術者試験でも上期で3人の合格者があり同ランキング1位でした。各種大会にも積極的に参加しており、高校生ものづくりコンテスト木材加工部門では、本校から大阪府大会に出場した2人がともに大阪府代表として近畿ブロック大会に進みました。この高難度資格の取得や大会実績は、ジュニアマイスター顕彰制度の受章者増加にもつながっています。
22年度卒業生342人中、認定された生徒は、ブロンズ10人、シルバー43人、ゴールド43人(うち特別表彰23人)の計96人でした。
顕彰されることで、取得・合格の喜びに達成感が加わり、希望の大学への特別な受験機会も得られるため、進学希望者も資格取得に熱心に取り組んでいます。

公益社団法人全国工業高等学校長協会(理事長・福田健昌東京都立六郷工科高等学校長)が2001年から工業系高校を対象に開始した「ジュニアマイスター顕彰制度」は、社会が求める専門的な資格・知識にチャレンジすることにより意欲と自信を持った生徒の育成、社会および大学や企業に向けた工業高校の評価の向上を担って創設された。
将来の仕事や学業に必要と考えられる国家職業資格や各種検定および各種コンテストの入賞実績を、ジュニアマイスター顕彰制度委員会が独自に調査し、点数化して全国工業高等学校長協会から各工業系高校に紹介、約290の資格・検定などと約90のコンテスト・競技大会などが登録されている。
その中から、生徒が在学中に取得した職業資格や各検定の等級、参加したコンテストで得た点数の合計によって、20点以上は「ジュニアマイスターブロンズ」、30点以上は「ジュニアマイスターシルバー」、さらに45点以上の特に優れた生徒には「ジュニアマイスターゴールド」の称号が贈られる。
顕彰された生徒数は、2022年度は9684人が「ゴールド」「シルバー」に認定。この制度を活用して就職や進学に生かそうと、積極的に取り組む学校や生徒が増えている。また、18年度から「ジュニアマイスターブロンズ」(受付は前期申請と卒業学年の追加申請のみ)を新設し、22年度は年間で5345人が認定された。
大学側でも、この制度を入学などの判断材料の一つにしているところがある。中央大学理工学部精密機械工学科では、5段階方式による評定平均値が3.8かつ数学・物理の評定平均が4.0以上で、ジュニアマイスター顕彰制度に応募し成果を挙げた者を対象に、高大接続型自己推薦入学試験の出願資格としている。文教大学情報学部(情報システム学科・情報社会学科)では、シルバー以上取得者を対象に総合型選抜(資格優先型)の出願資格としている。帝京大学理工学部(航空宇宙工学科ヘリパイロットコース・バイオサイエンス学科を除く)の入試では、学校推薦型選抜においてジュニアマイスター顕彰特別推薦枠を設けている。神戸芸術工科大学では、総合型選抜(資格取得型)入試による合格者の特待生制度で「ジュニアマイスターゴールド特待生」などの枠を設け、入学初年度のみ奨学金を給付している。
このように、この制度が大きな広がりを見せている中、同協会の渡邉隆事務局長は、「22年度の年間認定者数の上位校(学校番号順)を表に示しました。22年度も、新型コロナウイルス感染症拡大がなかなか収束しない状況の中で、各学校でもさまざまな対策が求められました。ジュニアマイスターのポイント対象となる資格・検定試験、コンテスト・競技大会などは、ほぼ通常どおり実施され、22年度の認定者合計1万5029人と21年度に比べて883人減少しましたが、コロナ禍にあって生徒がよく頑張りました。工業系高校生には、大会などを通して得た知識・技術を習得し、資格などを取得することで、ものづくりへの興味・関心を高めるとともに、何事にもチャレンジすることを忘れずに、目標を持ち続けて、日本を支える技術者として育つことを願っています。また、会員校においては、このジュニアマイスター顕彰制度を活用していただき、生徒の資質・能力や学習意欲の向上に役立てることを期待しています。そして、この顕彰制度を企業や大学、社会的にもさらに認知していただく必要があります」と語っている。