ここ数年、一般社会でクラウドの利用が浸透する中、教育機関においてもサーバーのクラウド化を図るところが出始めている。国際基督教大学(ICU)では今から10年も前にWebサーバーのクラウド化に踏み切り、安定的な運用を進めてきた。教育機関としては異例とも言える早期の導入には、どのような狙いがあったのか。2020年に行ったWebサーバーの刷新も含め、その経緯を取材した。
総務省の「情報通信白書」によると、クラウドサービスの市場規模は2兆2千億円(前年比29.8%増)に上るなど、ここ数年急速に拡大しつつある。その一方、教育機関においてはいまだセキュリティー面への不安から、オンプレミス方式を維持するところも少なくない。ある関係者は「現在のクラウドはセキュリティーの面でも優れているが、そうしたコンセンサスを学内で得るのが難しい」と、クラウド化に踏み切れない理由を語る。

そうした中、今から10年も前の2014年に、他大学に先駆けてWebサーバーのクラウド化に踏み切ったのが、東京都三鷹市に拠点を置く国際基督教大学(ICU)だ。教育機関はもちろん、世間的にもクラウドが広く認知されていない時代に、なぜそのような思い切った決断をしたのか。その経緯を広報戦略室パブリックリレーションズ・オフィスの吉良綾乃氏は次のように話す。
「国際的社会人の育成を目指す本学には、世界各国から学生が集まってきます。そのため、大学の公式サイトは、本学の理念を知ってもらう意味で大きな役割を担っています。クラウド化のきっかけとなったのは2011年に起きた東日本大震災で、大規模災害が起きても安定的に配信できるサーバー環境が必要だと考えました」
同学に在籍する学生の11%は外国籍で、出身国の数は50にも上る。「4月入学」のほかに「9月入学」を設けるなど、グローバルに門戸を開いている。その意味でも公式サイトが果たす役割は大きく、実際に入学者の中には「サイト上のコンテンツである『WHY ICU... ?』を見て、受験しようと思った」と言う人が少なくないという。
そうして早期にクラウド化を図ったことで、同学の公式サイトはその後、安定した運用がなされてきた。2020年以降のコロナ禍では、母国から日本に戻って来られない学生も数多くいたが、そうした際にも安定的に情報を届ける役割を公式サイトが担っていたという。
とはいえ、クラウドサーバーも障害のリスクがゼロなわけではない。実際に同学においても、2020年にWebサーバーのハードウェアが故障を起こしている。この時は緊急のバックアップサーバーに切り替えることでサイトの公開は維持できたものの、限られた情報提供になってしまったという。
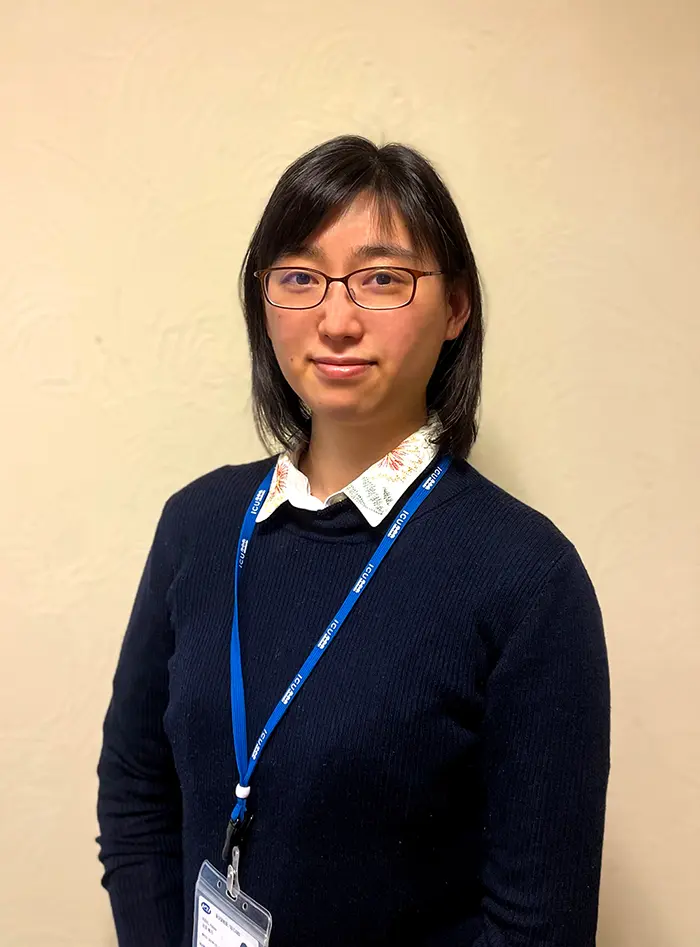
そのため、同学ではさらに安定的な運用を目指し、Webサーバーの刷新を図ることとした。そうして新たに導入したのが、アマゾン ウェブ サービス(AWS)の「Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)」と「Amazon CloudFront」であった。いずれも、Webサーバーを安定的に稼働させる上で大きな役割を担うツールで、同学の吉良氏は「サーバー障害のリスクを可能な限り減らし、安定的に稼働させるために導入を決めました。新しい導入が増えたものの、災害対応用のためのレンタルサーバーを契約する必要がなくなったことから、ランニングコストは同水準です」と話す。
そうして2020年6月にはサーバーの刷新が完了し、同学の公式サイトの安定性はより強固なものとなった。同学の公式サイトは、オープンキャンパスのある7~8月や学園祭のある10月にはアクセスが集中するが、システムを刷新したことで「安定して稼働しているし、安心感があります」と吉良氏は話す。
サーバーの安定性を格段に高めた「Amazon S3」と「Amazon CloudFront」とはどのようなものなのか。同学からの委託を受けてサーバーの刷新を行った株式会社アイディーエスサニークラウド事業部マネージャーの小山千晶氏は、次のように話す。

「『S3』はSimple Storage Serviceの略称で、クラウド上に大量のデータを保存できるシステムです。『イレブンナイン』と呼ばれており、99.999999999%の耐久性が実現できるようになっています。また、『CloudFront』はウェブコンテンツの配信速度を高速化させることができるサービスです。これを導入すれば、地球の裏側からアクセスしても、瞬時にサイトを閲覧することができます」
Webサイトには、クリックしてから表示されるまでの時間に多少なりとも差があるが、あまりにタイムラグが大きいと、アクセスを断念してしまうユーザーもいる。そのため、地球上のどこからでも瞬時に閲覧できるようになることのメリットは、グローバルな視点に立つ同学にとって小さくない。
同学がクラウドを導入してから、10年がたつ。今回、より安定的な稼働を目指して「Amazon S3」と「Amazon CloudFront」を導入に踏み切れたのも、そうした運用実績を通じて、クラウドのメリットを認識していたからに他ならない。「今後は、本学が重視する『リベラルアーツ』を視覚的に分かりやすく伝えるコンテンツを配信していきたいと考えています。また、中期経営計画にも記載されている通り、学術的な成果も積極的にサイトで配信していく予定です。その意味でも、Webサーバーが安定的に稼働していることの意味は大きいものがあります」と同学の吉良氏は話す。また、株式会社アイディーエスの小山氏は「機器の故障や大量のアクセス、外部からの攻撃、大規模災害など、あらゆるリスクに対応できる環境が整いました。Amazon社のサービスはユーザーも多く、運用のノウハウも蓄積されているので、今後のビジネス展開も図りやすいと思います」と話す。
大学という大きな組織が判断を下すには複雑な手続きが必要となり、ある程度の手間と時間を要する。そうした中で、同学がクラウドの導入や刷新にいち早く踏み切れた理由について吉良氏は「上層部にITに関する知識と理解があったこと、学内で比較的フラットに意見を言いやすい環境があったことが挙げられると思います」と分析する。サーバーのクラウド化に限らず、教育機関が変化の激しい時代を乗り切っていくためには、こうしたスピード感が必要になってくるのかもしれない。
