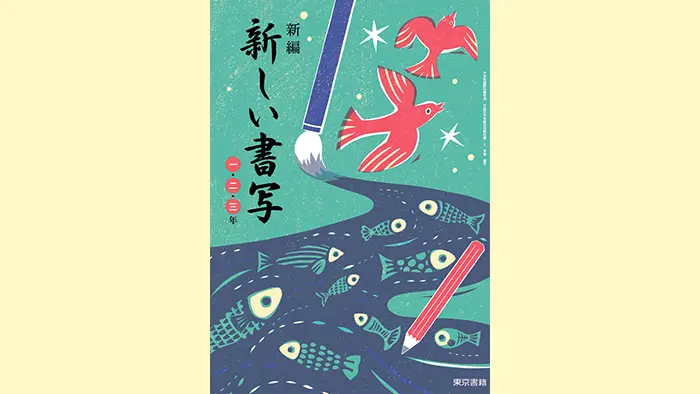
新編 新しい書写(押木秀樹ほか)
■基本方針
①中学生目線で手書きや行書の意味を考える。
―手書きをする機会が減っているなか、手書きの意味や行書の意味を考えるところから始めた。文字を正しく整えて書くためのポイント「書写のかぎ」を核とした課題解決型の学習過程で構成。学習のまとめや書写テストにより「書く」だけでない学びも充実。
②行書の基本を、考えながら身につける。
―行書を学ぶ意味から始め、形だけでなく動きも分析的に考えながら習得できる。
③書写の授業から、生活へ広げる。人生が広がる。
―活用単元「生活に広げよう」や巻末の「書写活用ブック」によって、学びを日常生活に生かす術を学ぶ。
■編集の特色
行書学習では特に書く際の動きを重視し、よく出てくる動きを4つに類型化して示すことで、動きへの意識を高めて汎用的に書ける力がつくように工夫した。紙面上の二次元コードなどから、運筆動画などのデジタルコンテンツも活用できる。また、国語と連動する題材にはマークを付けて可視化し、カリキュラム・マネジメントや活用力の育成に役立つようにした。
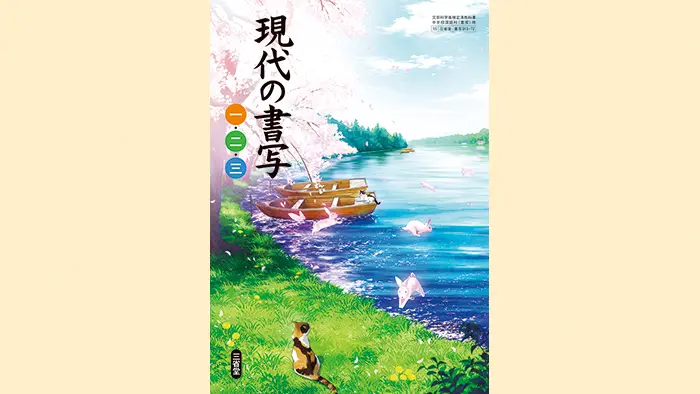
現代の書写
■5つの特徴
①ひとめでわかる学習内容
各教材を見開きで構成し、学習目標と振り返りを提示。見通しをもった主体的な学びを喚起。
②学習すべきポイントの明確化
何に気をつけ、どのように書くか、のポイントを明示した「書き方を学ぼう」を、具体的な字形例とともに提示。
二次元コード参照先サイトでは、左利きの子ども向けの運筆解説動画など、学習に役立つ多様なコンテンツを提供。
③普段の文字に生かすしくみ
毛筆で習得したことを他教科の学習や日常・社会生活で活用できるよう、硬筆による書き込みページを全教材に配置。
④豊かな文字文化にふれる題材・コラム
これからの文字文化の担い手である子どもたちに向け、「手書き」の意義を見つめ直す題材を設置。現代まで続く文字の歴史や文化を紹介。
⑤国語教科書との連携
三省堂国語教科書「現代の国語」と密接に連携し、効果的・効率的な国語カリキュラムを実現。国語の学年末活動と同じ活動の手書き作品例や、国語採録教材の言葉・一節を多数掲載。
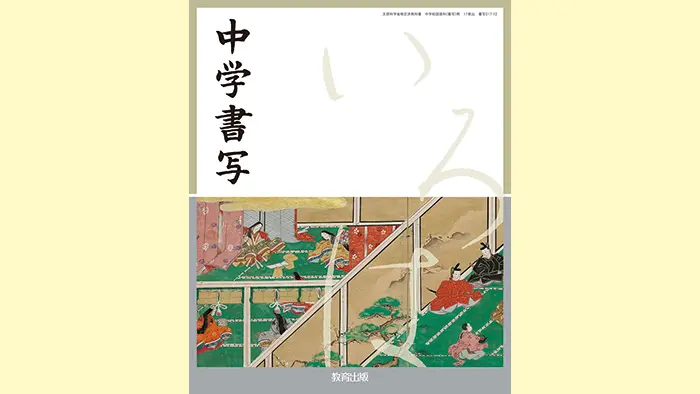
中学書写(長野秀章ほか)
■編集の基本方針
①書く力が身につくーすべての学びを支える
②学び方がわかる―自ら学びたくなる
③活用する力が育つ―考えて伝える力が身につく
■編集上の特色
①【まなびリンク】教科書掲載の二次元コードから全毛筆教材や硬筆の運筆動画などを視聴できる。
②【書く力が身につく見開き完結型紙面】右頁の毛筆教材を見て自らの課題を発見し、左頁でポイントを確認できる。
③【二色の薄墨による解説図版】行書特有の穂先の動きや筆の運びが理解できる解説図版を掲載。
④【国語と関連した授業計画が可能】各学年の硬筆教材は国語の古典などから取材。文学者など先人の味わい深い文字、平仮名の字源などを掲載。
⑤【他教科の学習や社会生活への活用力を養う】各教科のノートやレポート、掲示物、手紙やはがきの書き方など、日常に生きる書式例を多数掲載。
⑥【豊かな文字文化と現代的テーマを取材】過去から現在までの手書き文字文化を扱った「『書くこと』の変遷」コラムを新設。他に、全国の城址写真の紹介や、「活字について知ろう」のコラムではSDGsを題材とした作例なども掲載している。
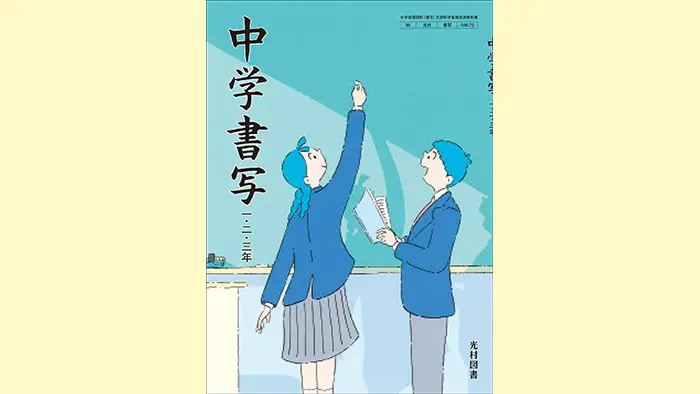
中学書写一・二・三年
今、改めて、子どもたちと手書きのよさを考える教科書。
■編集の特色
①デジタルと手書き、それぞれのよさや特徴について考える教材を新設。
②別冊の「書写ブック(硬筆練習帳)」には、硬筆で書く活動を豊富に位置づけた。習得と活用を効果的に繰り返すことによって、確かな書写の力を育成することを目ざした。
③中学校で初めて学習する「行書」を楽しくしっかり学べるよう、書くときのポイントを押さえた「行書スイッチ」を考案した。
④巻末には、「書き初めマスターブック」を新設。伝統的な文字文化である書き初めを、全8ページの構成で楽しくわかりやすく教材化した。
⑤全教材に学習のポイントがひと目でわかる「学びのカギ」を設け、他の文字を書くときにも普遍的に活用できる基礎・基本、原理・原則を明確に示した。
⑥国語と連動できる教材を各学年に設定し、必然性をもって学習に取り組めるよう工夫した。
⑦動画などの豊富なQRコンテンツを収録。姿勢・筆記具の持ち方が定着するよう、スポーツ科学の専門家の監修による「書写体操」を収録した。