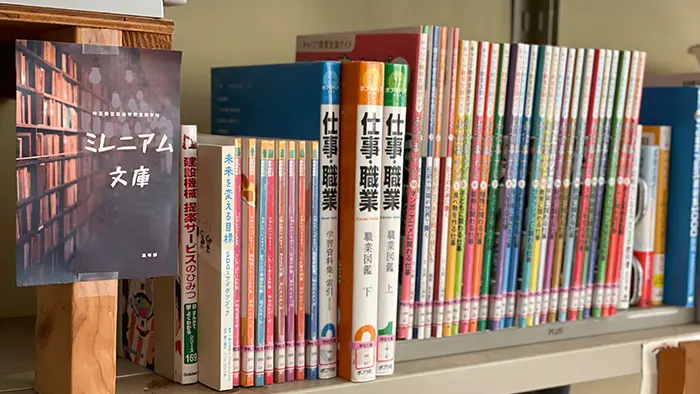
埼玉県立熊谷特別支援学校は、小学部、中学部、高等部の3つの学部がある、埼玉県北部に位置する県立の肢体不自由特別支援学校である。児童生徒の多様な障害に対応するため、4つの教育課程を編成している。
学校図書館は、校舎2階の中央に位置している。廊下側には、学校図書館の蔵書の紹介や、児童生徒による読書感想文が展示されている。しかし、蔵書数が増加するに連れて、学校図書館として活用している教室のスペースが狭くなり、車椅子を利用する児童生徒にとっては利用しづらい環境となっている。また、多様な児童生徒の実態に応じた読書方法を見つけることが難しくなっていた。その結果、さまざまな本と出会う機会が減少し、読書の楽しさを味わうことや、興味関心を広げて好奇心を育むことに課題が生じていた。これらの課題を解決するため、本校は、以前からつながりのあった県立久喜図書館と連携し、本実践を行った。
高等部の総合的な探究活動の時間において「陸や海の豊かさを守るためには、どのような取り組みを進めていく必要があるだろうか」という問いをテーマに探究学習を行った。その際、相互賃借サービスを活用し、県立久喜図書館から前述の問いを探究するのに適した書籍を借用し、実践を進めた。生徒は普段からタブレット端末などを活用しているため、インターネットでの検索活動には慣れていたものの、膨大なインターネット情報の中から問いに直結する情報を収集・整理することに困難さを感じていた。
一方で、借りた資料は、問いに対して深く情報を知ることができる上、整理されていたため、生徒たちにとって探究活動を進める上での強力なサポートとなった。その成果として、普段よりも早く正確な情報を収集することができるようになり、本を活用する良さに気付く様子が見られた。この経験を踏まえ、自身のキャリア計画を立てる際の参考にしてほしいと考え、キャリア教育に関連する書籍を借りて、生徒が普段生活している教室に設置することとした。普段から本に触れる機会を増やすことで、親しみを感じるようになるとともに、生徒自身の興味・関心に基づいた知識を広げることができた。
バリアフリー図書の紹介も含め「自分に合った読書スタイルを学ぶこと」を狙いとして、高等部に在籍する男女7人を対象に授業を実施した。はじめに、高校生向けの絵本の読み聞かせを行い、本の楽しさを生徒に伝えることができた。また、読むことに困難さがある人でも楽しめるさまざまな図書について紹介し、生徒は自分に合った読書スタイルを見つけることができた。質疑応答の時間では、「LLブックは何の略なのか」「録音図書に声優さんが声を録音したものはないのか」など、生徒の興味が高まっている様子がうかがえる質問があがった。

以前から本校の学校図書館に課題を感じていた高等部の生徒が中心となり、自分が面白いと思う本を紹介する『ピックアップ図書』活動が実施された。生徒は「学校図書館が小さい」という課題を感じ、その解決に向けて「本にもっと興味を持ってほしい」と願いを込めて本活動に取り組んだ。毎月展示されるこの取り組みは、生徒のみならず教職員からも好評を得ており、学校図書館の書籍を知るきっかけとなる活動となった(活動の様子については、本校ホームページにて紹介/学校ニュース2024年12月12日投稿)。
これまでの取り組みを踏まえ、今後の課題として2点が挙げられる。1点目は、学校図書館の規模である。毎年、蔵書数は増えているが、図書を管理する専属の図書館司書が在籍していない。そのため、管理や整理は司書資格の持つ教員の負担となっていることが課題となっている。2点目は、デジタル図書の活用である。電子書籍や録音図書は発行されているものの、それを十分に周知し活用するための機器が学校には整備されていない。これらの課題を解決するため、引き続き地域の図書館と連携し、改善に向けた取り組みを進めていく必要があると考える。
(埼玉県立熊谷特別支援学校教諭・大島啓輔)