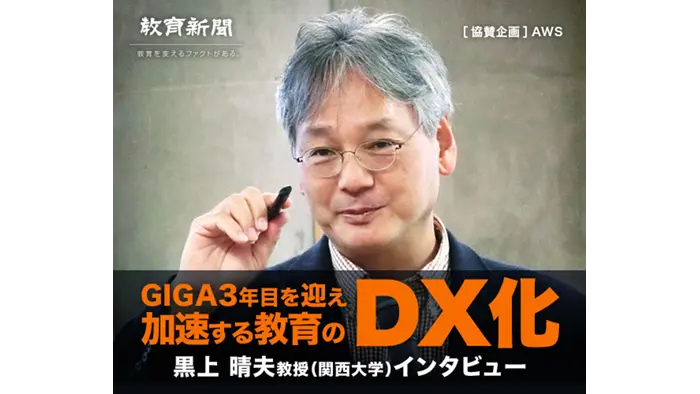
GIGAスクール構想で1人1台端末が整備されてから約2年が経った。活用に消極的な学校・地域はいまだあるものの、多くの学校では頻繁に端末が使われるようになり、子どもたちの学び方も変化してきている。有用性の高い教育系アプリ等も次々とリリースされる中、次なるステージではどのような変革が望まれるのか。長年にわたり情報機器を活用した学習の個別化・個性化等を研究してきた関西大学の黒上晴夫教授に、現状の成果・課題と今後の展望について語ってもらった。
――GIGAスクール構想で1人1台端末が整備されてから、約2年がたちました。現状をどうご覧になっていますか。

世界的にも後れを取っていた日本の学校のICT化ですが、GIGAスクール構想の前倒しによって、ハード面では世界トップ水準になりました。こんなに急激に端末が配備されたのは世界的にも例がなく、今振り返ってもよく実現したなと思います。
――一方で、急激な変化に「現場が追い付いていない」との声も聞こえます。
機器を入れた途端に、皆が一斉に使えるようになるなんてことはあり得ません。だから多少の戸惑いがあるのは仕方がないことでしょう。ただ、通信回線が不十分だったり、使えるアプリが入っていなかったりする自治体があったのは事実です。この点は、国レベルの問題というより、自治体レベルの問題だと私は捉えています。
――自治体によっては、セキュリティのレベルが高すぎて、授業で使いづらいとの声も聞きます。
確かに、そうした話はあります。例えば、私が運営に携わっている教育系NPO法人「学習創造フォーラム」では今年度、「コラボで自由研究」というプロジェクトを実施したのですが、そのサイトにアクセスできない自治体がありました。もちろんフィルタリングは必要ですが、先生や子どもが使いたいコンテンツにアクセスできない状況は、改善していく必要があります。
――個人情報の問題も、多くの自治体が神経をとがらせています。
クラウドサービスの活用に二の足を踏む自治体があるのは、そのためです。個人情報を自治体の外側に置くのが怖いのでしょう。でも、今は誰もが普通にオンラインバンキングなどクラウドサービスをごく当たり前に使っている時代です。二段階認証を活用すれば、情報漏えいのリスクは最小限にとどめられます。そうしてセキュリティを高めながら、全国のどこからでも教育データにアクセスできる環境が整えられれば、子どもたちの学びの充実につながるはずです。
むしろ、子どもが個人情報を端末に入れて持ち歩く方が、よほどリスクが高いと私は思います。そうした感覚を各自治体の方々には持っていただきたいですね。
――現状、端末の持ち帰りを認めない自治体もあります。この点は、どうお考えでしょうか。
持ち帰りを認めない自治体では、反転授業のような実践もできませんし、週末に自習学習に取り組むこともできません。もちろん、データがクラウド化されていれば自宅の端末からアクセスできますが、必ずしも自宅に子ども専用の端末があるとは限らないからです。
――端末を持ち帰らせることによる、「使いすぎ」を心配する関係者も多いようです。
今はどの家庭にもパソコンやゲーム機があります。だから、端末を持ち帰らなければ使いすぎの問題が解消するわけはありません。むしろ、持ち帰った端末で自主的学習する時間が少しでも増えれば、使いすぎの防止につながる可能性もあります。現在、持ち帰ることのデメリットばかりに目が向いていますが、持ち帰らないことのデメリットも考える必要があるでしょう。
――導入から2年がたち、成果も出ているように思いますがいかがでしょうか。
教科系の学力が上がったというより、子どもたちの学び方が変わったという点で、大きな成果が出ていると思います。端末の強みの一つは、社会や自然の事物・現象を子どもが写真・動画などに撮り、観察したり加工したりできる点です。つまり、実社会を教室に持ち込む上で、端末が絶大な威力を発揮するのです。
子どもたちが端末に入力した回答を電子黒板等に表示するなどして、考えや意見の共有が簡単にできる点も、端末の強みです。以前は特定の子どもだけを指名して進められていた授業が、全員の意見を共有しながら進められるようになり、一人一人の学習に臨む意欲・態度も変わりました。そうして意見を述べる機会が45~50分の中で4~5回もあれば、子どもたちの思考も深まります。また、教員は自分の端末からクラス全員の回答状況を把握できるので、授業の中でより多様な意見を拾えるようになります。
――ここ数年、民間の教育系アプリも数多くリリースされました。
教育系アプリが果たしてきた役割は、非常に大きいと思います。例えば、私自身も関わりのある「ロイロノート・スクール」にはシンキングツールが搭載されていて、授業の中で簡単に作成・共有できます。その他の授業支援アプリもそれぞれ良いところがあって、教員が課題を配付し、子どもが回答を書き込み、提出して皆で共有するという一連の流れが、効率的に進められます。
教育系アプリの進化は目覚ましく、経済産業省の「STEAMライブラリー」を見ても、良質なコンテンツがたくさん並んでいます。これらのコンテンツを上手に使って授業をすれば、教科という枠を超えたそれこそSTEAMな学びが展開できます。一方、ただ活用するだけでは「視聴して終わり」になりかねないので、教員には「子どもの思考をどう促すか」という視点で、授業を組み立ててほしいですね。
――中教審が答申で示した「個別最適な学び」を実現するツールとしても、端末や教育系アプリが果たす役割は大きいように思います。
「個別最適な学び」で言うと、端末やアプリを「自由進度学習のためのツール」と捉えてほしくはありません。子どもたち一人一人が自分の知りたいことを調べ、考えるような学びにおいても、端末の活用は有効です。
――「個別最適な学び」の「指導の個別化」だけでなく「学習の個性化」、さらには「探究的な学び」を促進する上でも、端末の活用が有効ということですね。
戦後間もない頃、子ども主体の探究的な学びが展開された時期がありましたが、「這い回る経験主義」と揶揄され、うまくいきませんでした。原因の一つは、リソースが足りなかったことです。でも、今は端末があるので、子どもたちは世界中のあらゆる情報にアクセスできます。
――子どもが「調べる」「まとめる」だけでなく、プログラミングなど「創る」活動ができる点も大きいと思います。
プログラミングはそれこそ「青天井」で、小中学生の中には大人が驚くほど高度なものを創り上げてしまう子もいます。その一方で、そこについていけない子への支援も必要です。「学習の個性化」もそうですが、個々の子どもが興味関心に基づいて活動できるように、教員がサポートしていくことが求められます。
――よく教員の役割が「ティーチャー」から「ファシリテーター」に変わると言われます。
すでにそうした役割を意識して授業する教員もたくさんいますし、そのようなスローガンを掲げる学校もあります。そうした考え方が、今後さらに広がっていくといいなと思います。
――今後、変革を広げていく上で、文部科学省や自治体にはどのような役割が求められるのでしょうか。
文部科学省は学びを変革していくことの必要性を強く認識していて、今回の学習指導要領にもそれは色濃く反映されています。次期学習指導要領では、恐らくその方向性がより明確化されるでしょう。問題は、現場がそうした読み解き方をできるかどうかです。
子どもの主体的な学びを促す上で、教科書をどう作るかも非常に難しい問題です。結論的なものを示してしまうと思考が深まりませんが、かといって何も書かなければ情報を伝えない教科書になってしまいます。
――教育系アプリには、どんな期待を寄せられていますか。
今、本格的な導入が始まりつつある学習者用デジタル教科書と教育系のアプリが、シームレスに使えるようになることを期待しています。学習者用デジタル教科書については、2024年度から英語を先行導入が始まりますが、ここで開発された便利な機能等が、他の教科でも援用されていくことを期待しています。
――数年後には次期学習指導要領の検討も始まりますが、今後子どもたちの学びはどのように変わっていくのでしょうか。
今般の改訂で、教科の「見方・考え方」という概念が示されました。このことは今後、資質・能力という柱を軸に各教科の学びをゼロベースから構築していく上での「布石」だと私は見ています。次期学習指導要領では各教科で教える内容は本当に大事なものだけに精査され、各学校が複数教科の学びが結び付くようにカリキュラム・マネジメントをする。そうした形で、学校教育の変革が進んでいくことを願っています。
アマゾン ウェブ サービス主催
ウェビナーのご案内
2023年7月13日 (木)
【学校・教育委員会向け】
「探究学習・プログラミング教育の授業実践」申し込みはこちら
(後日アーカイブ配信あり)
新学習指導要領で新たに始まった探究学習やプログラミング教育について、どのように取り組むべきか模索されていらっしゃる先生方も多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、関西大学 黒上晴夫教授に探究学習やプログラミング教育の進め方についてご講演いただくと共に、EdTechソリューションを活用した授業実践を先生方にご発表いただきます。
皆さまが今まさに直面している課題解決のヒントとして、是非、この機会を今後の情報収集にお役立てください。