2022年度から始まった高校新カリキュラムの「総合的な探究の時間」は、実社会や生徒の実生活から問いを見出し、解決する資質・能力を育むことを目標にしている。一方、現場では、生徒が主体的に取り組むために必要な「基礎的なスキルの不足」や「教員の業務負担の増加」に悩む声が少なくない。これらの課題を解決するため、(株)すららネットは生徒の探究スキルを高める独自コンテンツ「すらら Satellyzer(サテライザー)」をリリースした。導入を始めた東京都大田区の私立・蒲田女子高等学校を訪ねた。

蒲田女子高等学校(簡野裕一郎校長)は漢学者・簡野道明を学祖とし、1941年に創立された歴史ある私立高校だ。2024年春には校名を「羽田国際高等学校」に変更し、共学校として新たなスタートを切る予定だ。校訓「清・慎・勤」を堅持し、教育方針である「心も姿も美しく、思いやりを大切に、目標に向かって自ら行動する人間の育成」を続ける同校にとって、総合的な探究の時間「グローバル・キャリア教育 みらい」は、目指す生徒像に向けた重要な取り組みの一つだ。現在、「すらら Satellyzer(サテライザー)」を試験的に導入し、探究スキルの向上に役立てている。
「すらら Satellyzer」は▽日常生活や社会に目を向けて生徒が自ら課題設定をする▽課題設定、情報収集、整理・分析、まとめ・表現の探究の過程を経由する▽自らの考えや課題が更新され、探究の過程を繰り返していくーーといった探究における生徒の姿を実現するための「探究の導入コンテンツ」として構想された。開発は、学習コンテンツ開発力に強みを持つ(株)すららネットと、宇宙開発技術に関する専門知識が豊富なNECスペーステクノロジー(株)が共同で当たっている。
コンテンツ全体は「宇宙・人工衛星」をテーマにした19のユニットセットから成る。アニメーションと音声によるレクチャーを視聴した後、出されたミッションにチームで解決に当たることにより、「アイデアを出す」「自分の考えを共有する」「他者の考えを理解する」「情報を分析する」などの探究学習に役立つスキルを高められる。

宇宙・人工衛星をテーマにしたのは、実際の社会課題の解決方法がそうであるように、生徒のみならず教員にとっても未知の題材だからだ。人工衛星やロケットといった最新の技術をどう日常生活の課題発見・解決に結び付けられるか、教師も答えを知らないミッションに、生徒はチームで協働しながら挑むことができる。
蒲田女子高校では19のユニットのうち人工衛星とスマートシティに関するユニットを抜粋して、3年生が取り組んでいる。探究の基礎・前提となる知識は、「すらら Satellyzer」の「人工衛星と私たちの暮らし」のレクチャーを通して獲得する。その後、出されたミッションとして「スマートシティって?」を選択した。生徒はまず、身の周りの社会課題を解決するために、どんなスマートシティが実現するとよいかを考える。
さらに、実現に必要なデータを集めるオリジナルの人工衛星を組み立てて、打ち上げシミュレーションを行う。積める機材は、450㌔上空からでも人を識別できる「高分解能カメラ」や、電波の反射により地上を観測する「高分解能合成開口レーダー(SAR)」、地上のどこにいるかの位置情報がわかる「全地球測位システム(GPS)」などだ。どれを選ぶかは生徒たちが決める。
生徒たちが考えた「自分たちが解決したい社会課題」を見ると、「海のごみをなくしたい」「道路渋滞を解消したい」「山林での災害をなくしたい」などさまざまだ。あるグループでは「災害時に被災の予想ができるようにしたい」と決めた。地震や風水害などが起きたとき、レーダーで避難所の場所や、混み具合を知ることができれば、より安全に避難行動がとれるだろうという予想を立てた。「もし、避難所に人がいる、と分かったら自分も逃げようと思うはず。逃げ遅れる人を減らせる」「もうあるかもしれないけれど、その情報がスマホアプリで見られたらいい」など、さまざまな意見を交わしていた。

その後、各グループで人工衛星に必要なカメラなどのパーツやセンサーを選択し、コンピューター上の人工衛星に取り付ける。画面上には打ち上げにかかるコストや組み立てにかかる時間なども表示される。ゲーム感覚ではなく、技術を実装する際にぶつかる現実的な問題にも目を向けさせ、視野を広げてほしいという「すらら Satellyzer」の狙いがここに読み取れる。
最終的には、シミュレーションした人工衛星の打ち上げが成功したグループもあれば、失敗したグループもあった。結果の分析はPDFファイルでフィードバックされるので、改善に向けたさらなるグループワークの資料に役立つ。
最後に、この日の授業の自己評価を入力して探究の時間は終了した。「すらら Satellyzer」はこのほか、グループメンバーによる相互評価や、教員の評価を記録・補完する独自の評価システムを搭載している。いつでも時系列で自分の学びの足跡を振り返ることができるのも、探究には欠かせないプロセスと言えよう。このほかグループワークで使えるワークシートや、授業マニュアルも各ユニットで活用でき、探究の導入段階における教員の業務負担軽減に貢献する。
シミュレーションした人工衛星の打ち上げの成否が「すらら Satellyzer」のゴールではない。成功するまでにどのように知識を生かせたか、グループで建設的な議論ができたか、といった探究スキルを伸ばすことが目的だからだ。指導に当たった学年主任の内藤桂一教諭は、次回の授業で「課題解決につながるデータを、自分たちが考えた人工衛星によって取得できたかの振り返りや話し合いができれば」と話す。
グループワークでは、発言力の強い生徒やテーマに詳しい生徒の意見に流されてしまいがちだが「すらら Satellyzer」がテーマとする「宇宙」については、多くの生徒にとっては未知のもの。それだけにフラットな議論、少数派の意見も大切にする態度も育めそうだ。内藤教諭は「すらら Satellyzer」のような探究に特化したコンテンツを活用したり、教科横断的な授業にチャレンジしたりすることでそうした道も開けると期待をしている。「探究に必要なスキルは日々の習慣化によって身に付くのではないか。その意味では、総合的な探究の時間だけでなく、各教科や多様な場面においても探究する機会を設けることが重要だ」と話す。
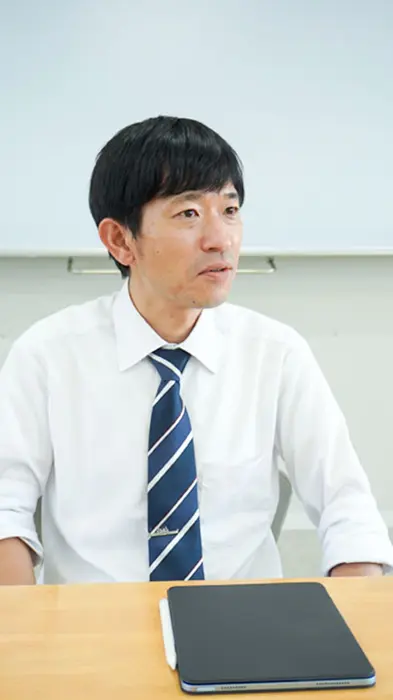
同校の探究は、これまでキャリア教育と関連付けた活動を中心に展開してきた。2021年度から株式会社JALスカイとANA(全日本空輸株式会社)グループとの教育連携を開始。社会人出身の教員が探究を担当し、自己理解やコミュニケーション力の向上、多様性理解など、生徒に幅広い視野、グローバルな視点を持たせることに力を注いできた。「1つの情報を受け止めるときに、これが正しい情報なのか、別の側面もあるのではないか、と多面的な視野で物事を考える力を育てていきたい」と話すのは、株式会社JALスカイから出向中の飯村真紀教諭だ。今後、新規開校する羽田国際高校でも「WINGS探究」の科目で、これまでの探究を昇華させていきたい考えだ。

教育新聞ブランドスタジオ主催「教育と研究のDXフォーラム」(後援:文部科学省)
働き方改革を実現する校務支援DX、個別最適な学びを実現する教育データ利活用
教育ICT/DXの最前線を学び
東京 8/24、大阪 8/28
申し込みはこちら(参加無料)
東京会場 8月24日(木)
午前10時30分~午後5時
TKP新橋カンファレンスセンター
【小・中・高校(K12)トラック】
10時30分~10時35分
ご挨拶・登壇
文部科学省 総合教育政策局 主任教育企画調整官・教育DX推進室長 藤原 志保
10時35分~11時15分
基調講演
放送大学客員教授 佐藤幸江
11時15分~12時
パネルディスカッション
「令和の日本型学校教育」構築のためのクラウドへの期待と課題 ~“個別最適な学び”実現に向けて~(仮題)
市川市教育委員会 教育センター 伊勢 太惇
葛飾区教育委員会 事務局 学校教育推進担当課長 江川 泰輔
放送大学 客員教授 佐藤幸江
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
13時~13時30分
講演
「教育ICT環境のフルクラウド・ゼロトラスト化」
新座市教育委員会
13時30分~14時
協賛セッション
「教職員の働き方改革を推進し教育の個別最適化を支援する新サービスのご紹介」
キヤノンITソリューションズ株式会社
14時~14時30分
協賛セッション
「AI時代に必要なイノベーション人材育成と教育の変化」
ライフイズテック株式会社
15時~15時30分
協賛セッション
「全国学力調査テストのデータを活用した傾向分析~指導・学習の個性化に向けた新サービスのご紹介」
コニカミノルタジャパン株式会社
15時30分~16時
講演
「相模原市におけるプログラミング教育の実践~生活や社会の問題を解決する『Alexaスキル』を活用した授業実践~」
相模原市教育委員会
大阪会場 8月28日(月)
午前10時30分~
大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス
【小・中・高校トラック】
10時30分~10時35分
ご挨拶・登壇
文部科学省 総合教育政策局 教育DX推進室 室長補佐 稲葉 めぐみ
10時35分~11時15分
基調講演
「学習データを活用した個別最適な学びと協働的な学びの充実に向けた現状」
園田学園女子大学 人間教育学部 教授 堀田博史
11時15分~11時55分
基調講演
「校務DXの現状と展望」(仮題)
鳴門教育大学 大学院学校教育研究科 教授
教員養成DX推進機構長 藤村 裕一
13時~13時45分
パネルディスカッション
「令和の日本型学校教育」構築のためのクラウドへの期待と課題~“個別最適な学び”実現に向けて~(仮題)
枚方市教育委員会 学校教育部教育研修課 主幹 浦谷 亮佑
鳴門教育大学 大学院学校教育研究科 教授
教員養成DX推進機構長 藤村 裕一
園田学園女子大学 人間教育学部 教授 堀田博史
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
13時45分~14時15分
協賛セッション
「教職員の働き方改革を推進し教育の個別最適化を支援する新サービスのご紹介」
キヤノンITソリューションズ株式会社
14時15分~14時45分
協賛セッション
「AI時代に必要なイノベーション人材育成と教育の変化」
ライフイズテック株式会社
15時15分~15時45分
協賛セッション
「全国学力調査テストのデータを活用した傾向分析~指導・学習の個性化に向けた新サービスのご紹介」
コニカミノルタジャパン株式会社
15時45分~16時15分
講演
「アマゾンエコーを活用した、プログラミング教育について」
枚方市教育委員会 学校教育部教育研修課 主幹 浦谷 亮佑
申し込みはこちら(参加無料)
<主催・協賛>
主催: 株式会社教育新聞社 教育新聞ブランドスタジオ
特別協賛: アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
協賛:キヤノンITソリューションズ株式会社、エクスジェン・ネットワークス株式会社、 株式会社Fusic、ライフイズテック株式会社、MEGAZONE株式会社