教育新聞社ブランドスタジオは、「教育と研究のDXフォーラム」を今夏、東京・大阪・福岡の3会場で開催する。(参加申し込みはこちら)
7月27日(木)の福岡会場では、小・中・高校に向け、「教育データの利活用」と「校務DX」をテーマにした講演やパネルディスカッションなどが行われる。開催に先立ち、冒頭の基調講演に登壇するICT CONNECT21会長の赤堀侃司氏に、教育データがもたらす個別最適化の学び、そして子供たちウェルビーイングについて、話を聞いた。
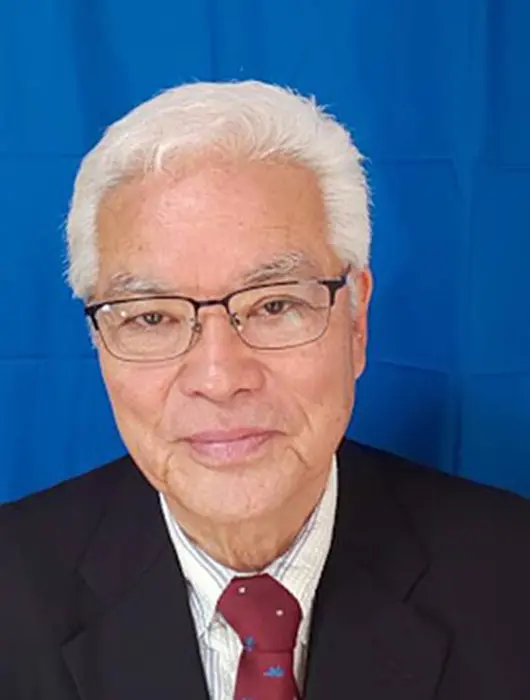
赤堀氏は、教育データを「学習履歴や性格、活動などが記録された、いわば子供たちのカルテのようなもの」とし、「医師が患者のカルテを参考に診察するように、教育においても学習カルテがないと、もはや一人一人に適合した指導ができないのではないか」と解説する。
一方で、医師の診察は科学的なデータに基づいている点が、学校と大きく異なる。また、テスト結果や素行などの最初の印象が悪いと、教員の頭の中に長期間にわたってそれがインプットされ影響を受けてしまうという研究もあるという。「子供は日々学び、成長している。だからこそ、情報をたえずアップデートして、子供を見る目、指導の仕方を変えるべきである」と、赤堀氏は話す。
教育心理学者のクロンバック氏が提唱した「ATI(適正処遇交互作用)」は、学習者の適性に応じた指導法がもっとも効果的であるというものだ。赤堀氏は、「これまでは一人一人ひとりに合った指導は難しいものだったが、GIGAスクール構想によって、1人1台端末が整備され個々のデータが可視化されたことで、ATI、つまり個別最適化の指導が可能になった」として、近年、教育データの利活用が注目されてきた背景を語った。
変化の激しい現代においては、日本特有の「みんな同じ」という教育観は通用しない。「一人一人の特性に応じた指導、子供自身のアイデア・考え方・価値観などに基づいて学習を進めていくこと」がグローバルスタンダードになりつつあり、それこそが、学習指導要領にも明示されている「個別最適の学び」でもあるという。
その際、重要になってくるのが「俯瞰的な視点」だと赤堀氏は話す。「テストの成績だけでは評価できないと、古くから心理学者のガードナー氏の『多重知能論』でも語られているように、人間は場面によって個性があり、得意と苦手をもっている」という。しかし、教員にはその場面ごとの子供たちの印象がインプットされがちで、全体的に見渡すことが難しい。そうした俯瞰的な視点をもつためのツールが、「教育ダッシュボード」なのだ。
教育ダッシュボードの利点は、さまざまなデータが可視化され、ひと目でその子供の状態が分かるような仕組みであることだ。「一元的な成績や運動能力だけでなく、“総合的な評価”ができるという」と、赤堀氏は話す。
そして、教育データの利活用が最終的に目指すものは「子供たちのウェルビーイングに他ならない」と、赤堀氏は力説する。「もちろん、学力は高いに越したことはないし、健康であることも大切だ。けれども、総体として、子供たちが自分の置かれている場所で幸せであること、ウェルビーイングであることは、もう世界のスタンダードになりつつある」と話す。
赤堀氏は、かつて視察に訪れたスウェーデンの学校のエピソードを挙げ、「現地の校長が、語った『子供たちがこの学校に来て良かった、この先生のクラスでよかった、この地域に生まれてよかったと思える、自分がそこで受け入れられていると思えた時が、子供のウェルビーイングです』という話に、とても共感した」と述べた。学校は環境を整え、ウェルビーイングな子供たちを育成する役割がある。そのためには、子供たちの状態を俯瞰して把握していかなければならない。その一つの見える化の尺度として、教育データの存在意義があるという。
では、これらの教育データを使って、評価をどのように行えばよいのか。
赤堀氏は、「そこにこそ、これまで子供たちを見てきた教員の経験値が必要」だと話す。
「データはあくまでデータに過ぎない。医師もデータだけで判断するのであれば、ChatGPTでもできるかもしれない。総合的な判断をできることが、人間たる、そして、教員たるゆえん」であるという。
ペルグリーノ評価理論では、データを直線的に結び付けて見るのではなく、そこに“認知”を通すことを重要としている。赤堀氏は、「データや子どもの表面だけを観察するのではなく、その奥にある部分を教員が認めなければならない。それはデータを越えたところにある」という考え方を示し、「最後は、教員がどう子供を見取るか、その認知にかかっている。それが、教育データ利活用の最も重要な見方である」と語った。
次に、赤堀氏は教育データの課題を挙げた。日本の教育データの利活用は現場ではまだなじみ深いものではなく、まずは国を挙げての「標準化」が必要であるという。
「しかし、標準化の前に『教育データとしてどのようなデータを扱うか』という分類をしなければならないが、それすらもまだ明確でない。最初に分類化があり、次にデータをコード化し、そして標準化されてはじめて流通する」と赤堀氏は解説する。
また、10年に一度改定される学習指導要領に沿ってコード化していく場合、データをどう刷新していくかという問題もある。この課題に対して赤堀氏は、「システムを自走させるためには、必要な情報を自動的に抽出しコード化していく生成系AIの活用が必要になるだろう」と考えを述べた。
赤堀氏は、GIGAスクール構想で1人1台端末が整備された学校での授業の在り方について、「誤った考え方をしている学校もあるのでは」と疑問を投げ掛けた。例えば、クラウド環境やICT活用でトラブルが起こった際、デジタルの手法にこだわってしまうため、そこで全員の作業を中断させてしまうケースがある。しかし、1人1台端末の環境における個別最適化は、「個に応じて選択肢が増えた」と捉えるべきで、クラウドで一元管理して指導が効率化できることが本来の目的ではないと話す。
赤堀氏は、「子供たちに目を向けてこその個別最適化であり、 個を大切にすること。『あなたのできる範囲でいい』という選択肢が増え、自由度が増したということが、個別最適化の基本であり、スタートである」と、語った。
さらに、赤堀氏はアメリカの学会で発表された「アメリカの教育におけるICT活用が進まないのは、教員の信念である“インターナルバリア”が原因である」という例を挙げた。
「『端末の故障やネットワークの不調などの外的要因は解決できるが、教員の内面的な壁、ティーチャーズビリーフが、最も活用を阻んでいる』という話のとおり、教員の信念を変えていかなければいけない」という。
そして、教員が信念を変えたことで、素晴らしい個別最適の学びが実現した例として、日本のある音楽の授業の話を伝えた。「好きな曲を作曲し、楽器を演奏するという授業で、譜面が読めない、楽器が弾けない子供たちがクラスの75%いた。そこで、プログラミングや音楽アプリという手段を取り入れ、『自分の好きなやり方でやっていい』と伝えたことで、子供たちは見事な作曲をした」という。
赤堀氏は、「楽器で演奏できることがベストではあるが、子供によって違うのであれば、選択肢を広げ、個を生かすことが個別最適な学びとなる。要は、子どもが幸せになればいい。『自分も、こんな曲を作ってみたい』と思え、それを実現できることが、最も大切。子供に諦めさせてはいけない」と、重ねて強調した。
赤堀氏は、7月27日の福岡会場で開催される「教育と研究のDXフォーラム」で、冒頭の基調講演とパネルディスカッションに登壇する。基調講演では、「教育データの利活用による次世代の学びの姿」をテーマに語る予定だ。
主催:教育新聞社ブランドスタジオ
特別協賛:アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
開催日:福岡会場 7月27日(木)、東京会場8月24日(木)、大阪会場8月28日(日)
※会場ごとに登壇者は変わります。
会場:西南学院大学 コミュニティセンター(福岡県福岡市)
開催時間:午前10時30分~午後5時
参加費:参加費無料(事前申込制)
参加対象:学校関係者、教育委員会、教育関係者の皆様 ※要確認
お申込み:下記サイトから申し込む
「教育と研究のDXフォーラム」
主催: 株式会社教育新聞社 教育新聞ブランドスタジオ
特別協賛: アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
協賛:キヤノンITソリューションズ株式会社、エクスジェン・ネットワークス株式会社 、株式会社Fusic、ライフイズテック株式会社、MEGAZONE株式会社
後援: 文部科学省、一般社団法人 ICT CONNECT 21、株式会社科学新聞社