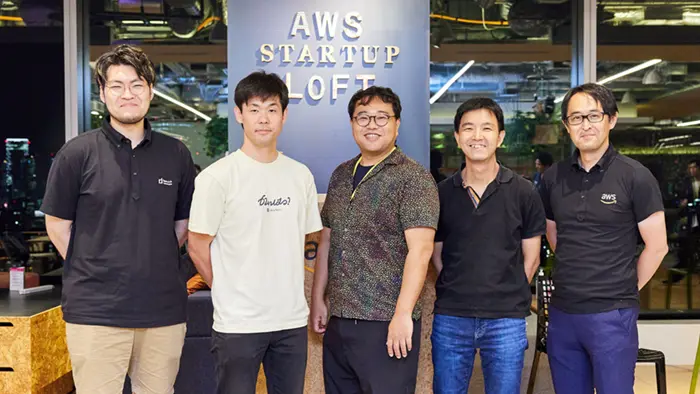
生成系AIと教育について考えるイベント『【Edtech Meetup】教育×AI ~生成系AIによって教育はどう変わるのか~』が6月28日、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(以下AWSジャパン)主催で開催された。世界中で話題となり、日本でも急速に普及が広がる生成系AI。連日さまざまなメディアで報じられていることもあり、実際に使ってみたという教員の方々も多いはずである。
文科省が7月4日、小中高校での生成系AIの扱いに関する初の指針を公表。AIの利用が不適切な例を示し、利用範囲を限定しつつ活用する方向性が示された。今後は、教員のAIスキルをより一層上げていくことも求められる。生成系AIの発展によって教育はどう変わっていくのか。当イベントレポートを通じて考えるきっかけにしてもらいたい。
当日は、人工知能(AI)や機械学習(ML)のプロフェッショナルであるEdtech業界のリーダーが登壇し、各社の事業を紹介したうえで、「生成系AIを教育でどう使っていくか」「生成系AIによって教育はどう変わっていくのか」というテーマでパネルディスカッションが行われ、熱い議論が繰り広げられた。モデレーターを務めたのは、日本CTO協会の広木大地理事である。
オンライン英会話事業を行う株式会社レアジョブテクノロジーズでは、生成系AIを組み込んでAIによる学習内容の提案を行っている。羽田健太郎CTOは、「当たり前のことではあるが、AIが対応できないような質問が出ることもあるし、AIが間違った回答をすることもある。教育分野で生成系AIを使っていくからには、やはりしっかりとモニタリングを行っていくこと、そして生徒さんからのフィードバックをもらいながら改善していくことが大事になってくる」との考えを示した。
続いて、IT・プログラミング教育サービスを通じて次世代のデジタルイノベーターの輩出を目指すライフイズテック株式会社の奥苑佑治CTOは、「イノベーター人材の育成において、生成系AIは可能性しか感じていない」と強調した。「生成系AIによって脳内を転写できる技術が確立すれば、これまで見えなかった子どもたちの才能や能力が見えるようになっていく。そういった次世代の能力、才能を社会側が制限したり抑圧したりすることが課題だと感じていて、逆に、AI時代の倫理観をしっかりと作っていくことができれば次世代の教育に可能性を感じる」と語った。
atama plus株式会社は、全国の塾や予備校向けに、AIを活用した個別最適な学習システム「atama+」を展開している。同社のアルゴリズム開発責任者を務める安本雅啓氏は、「先生にとって手間のかかる問題作成や答案の添削業務などに生成系AIを活用できる。たとえば、英語の長文を読ませるにしても、個人のモチベーションを上げるために、音楽に興味がある子には音楽の記事、バスケをやっている子にはバスケの記事というように個別の問題をつくるという方向性もあると考えている」という。一方で、「AIは人の代替にはならない。声掛けなども『人』を介して伝えていくことを大事にする必要がある」と指摘する。
次の話題は「教育の未来」だ。モデレーターの広木氏が、今の子どもたちが当たり前のように利用しているスマートフォンについて、「出始めの頃には今と同じように、子どもにスマホを持たせるか論争があった」と指摘したうえで、激動の生成系AIの今後を見据え、「生成系AIによって教育は何が変わり、何が変わらないのか」「未来の教育はどう変わっていくのか」についてディスカッションが行われた。
羽田氏は、マンツーマン指導で英会話能力を上げるという視点で「先生がこれまで定常的にやってきた業務や生徒へのフィードバックなどはAIに任せていく。一方、先生がやるべきことは、限られたレッスン時間内でモチベーションを高め、実際に会話すること」と話す。さらに、「どれだけ翻訳技術が発展しても、人と人とのコミュニケーション自体がなくなることはない。学ぶ時間を短くしたり英語自体を楽しんだりしてもらうために、先生、AIそれぞれがやるべきことを最適化していくことが重要」と付け加えた。
「膨大なバックグランド、知識をもったAIとバイアスのかかっていない子どもが議論したら、宇宙に住むための方法なども、すぐに生まれるのではないかと本気で思っている」と語るのが奥苑氏だ。子どもには規制が必要という声もあるが、「バイアスや知識と経験という考えの中で生きている大人が考えるよりも、社会、科学の発展に向けて期待が大きい。子どもたち達がどんどんAIを使える環境を整えていかないと未来はないと思っている。人類の科学の発展を信じるべきだと思う」との見解を示した。
安本氏は、今後教育では「どう学ぶか」「何を学ぶか」という2つの観点があるとし、「どう学ぶかは、個別最適化された学びが増え、一人一人の得意なことを伸ばし苦手を引き上げるというところが大きくなっていく」と説明。さらに「何を学ぶかは、基礎学力と社会でいきる力に分けられる。基礎学力とは英語や数学などの教科学習でなくなることはないと思っている。また、何をつくるかを考えてチームでコラボレーションしながら形にしていくようなクリエイティビティが社会でいきる力。AI時代でも大事なことの根本はこれまでと変わらない」と話した。
さらに、AWSジャパン パブリックセクター技術統括本部長を務める瀧澤与一氏は、過去20年以上生成系AIを開発してきたアマゾンの立場から「私たちが求めているのは、エンドユーザーの子どもたちや社会人のスキルが上がること」としたうえで、「教育の未来」について以下のように語った。
「ある人がどういうスキルを学び、どういう経験を得て、どういうやり取りをして、その後どういう人に成長したか?のライフサイクルを追っていくと、教育に何が必要かを考えられるようになる。今後その成長を生成系AIがサポートし、子どもたちやリスキルしたい社会人が結果的に新しい学びができる、そういう流れができると面白いと思っている」。
一方で、個人のデータを取り扱うことはセキュリティや倫理など課題があるが、「子ども達が何をしたいのか、どうなっていきたいかという未来へのスピードを速めていけたら」と強調した。
モデレーターの広木氏も、「たとえばプログラマーの仕事もAIの登場によってどんどん簡単になってはいるが、一方でプログラマーがやらなくてはいけない仕事は簡単になってはいない。むしろ、複雑で面白いことをやらなくてはいけなくなっているフェーズでは?」と指摘。AI時代においてもこれまでと同じように好奇心が強い、試行錯誤できる、グリッド力などのスキルがもとめられるとまとめた。
Q&Aの時間には、参加者から「教育現場での生成系AIの利用についてどんなガイドラインが必要と考えるか?」という質問が出た。
これに対しては、エンジニアの視点で、登壇者全員が「利用を推奨すべき、悪いものではなく使われることを前提とすべき」との見解を示し、「裏ではどのようなアルゴリズムが動いているかを伝えるのがよい」「イノベーションは止められないので、使われることを前提に先生側の注意点を明示した方がいいのでは」「ユースケースを出していくべき」といった意見が上がった。
イベントの最後には、AWSジャパン パブリックセクター技術統括本部のシニアソリューションアーキテクト 松井佑馬氏から、教育現場で使われているAWS サービスを活用した生成系AIのデモンストレーションも行われた。
教育業界においても大きな存在感を示すアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が特別協賛となり開催する教育新聞ブランドスタジオ主催フォーラム、「教育と研究のDXフォーラム」。教育DXについて情報収集及び交流の場としてご活用ください。
小・中・高校と大学の教育&研究DXの課題解決を探る
東京会場8/24(木)、大阪会場 8/28(月)
詳細はこちら