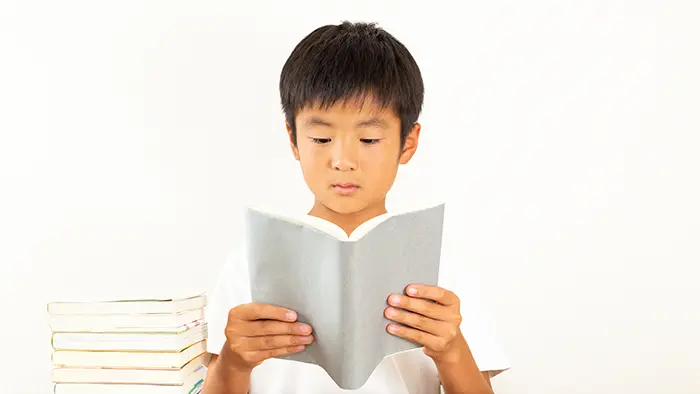
全ての公立小中学校などで学校図書館図書標準の達成を目指した第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」(2022~26年度)が2年度目を終了し、3年度目に入った。昨年度からは第5次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(23~27年度)がスタートするなど、国を挙げて子どもの読書活動の環境整備が進められている。この中で大きな役割が期待される学校図書館の充実のポイントなどについて、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課の小沢文雄図書館・学校図書館振興室長に聞いた。

――第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」の2年目が終了したところですが、進捗をどのように受け止めていますか。
第6次計画では、学校図書館の図書標準の達成に向けて、計画的な図書の更新や、新聞の複数購入、あるいは学校司書の拡充といったことについて、引き続き整備できるように地方財政措置が講じられているところです。2年度目が終了したばかりで統計的な把握はまだできていませんが、課題の一つとして挙げられるのが地域間格差です。
都道府県別に見ると、整備が進んだところでは100%、またはそれに近い数字の自治体もあれば、なかなか進んでいない自治体もあります。同じ県内でも地域によって、子どもや教職員の数、校舎内のスペースの問題など、図書の整備が進まない事情も異なります。こうした状況をいかに解決するかがこれからの課題だと考えています。
例えば、新聞に関して、東京都葛飾区では学校ごとに契約手続きするのではなく教育委員会事務局が一括で契約することで、忙しい学校現場の負担を軽減する取り組みを進めています。このような事例も紹介しながら、直接の関係者だけでなく周囲の方にも理解してもらい、学校図書館を充実することの重要性を共有できるような普及・啓発に引き続き努力していきたいと考えております。
第6次計画に基づく地方財政措置は使途を特定しない一般財源であり、各地方公共団体で予算化されることによって初めて学校図書館の費用に充てられます。各地方公共団体もさまざまな課題を抱えていると思いますが、学校図書館の現状把握と適切な予算措置をお願いしております。
一方で、各学校現場に、実際に学校にどれぐらい予算措置されることになるのか、現場で試算できる資料を昨年作成しております。ぜひご活用いただき、財政当局と話をする際にも筋の通った要望が出せるようにしてほしいと考えます。
――整備5か年計画と合わせて「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」も昨年度から始まりました。
この計画では、4つの基本的方針((1)不読率の低減(2)多様な子どもたちの読書機会の確保(3)デジタル社会に対応した読書環境の整備(4)子どもの視点に立った読書活動の推進)を掲げています。中でも、不読率(1カ月の間に1冊も本を読まない児童・生徒の割合)をいかに低減させていくかが課題です。(公社)全国学校図書館協議会が毎年調査していますが、中学生と高校生について23年は改善した結果が出ました。22年に高校生は51・1%、中学生は18・6%でしたが、23年は高校生43・5%、中学生13・1%と大幅に改善しています。さまざまな子どもの読書活動を推進している皆さまや関係団体の取り組みの成果だと考えますが、この流れを止めることなく進めていきたいと思います。
詳細な分析はこれからですが、例えば子ども読書活動の実践校では、全クラス対象の図書館オリエンテーションの実施、あるいは授業支援として図書館の持っている資料や情報を、先生たちが利用しやすいように準備・提供したり、またビブリオバトルなどにも取り組んだりしています。こうした実践例の地道な発信が、他校にも広がり改善につながっている面はあるでしょう。
また、朝の10分間読書のような取り組みは全国で行われていますが、習慣化は非常に大切で、それぞれの子どもたちの生活の中に読書習慣をどう位置付けていくかがポイントとなります。読書に対するイメージがどういう形で培われるかということでもあります。自分にしっくりくるポイント、例えば、本のジャンルに関してもスポーツをやっている子であればスポーツに関係する本もいっぱいあるので、そういう点を入口に、活字を読むことを普段の生活の中に位置付けてほしいものです。
――子どもの興味関心やニーズは多様ですから、多様なチャンネルを備えるためにも学校図書館の充実が欠かせません。
子どもたちの読書につながる多様な入口を準備するためにも、大人の側が土壌をしっかり作ることが大事だと思います。その上で、子どもも一緒になってさまざまな工夫をしながら読書活動を展開することを期待しています。例えば、高校生ぐらいになるとビブリオバトルなどの活動も広がっていますし、一般書店にあるようなポップを生徒が作成して読書紹介するような学校もあるようです。そうした子どもたちの取り組みが次々と生まれてくる雰囲気・環境ができるように、大人がまず環境整備を行って大人と子どもと一緒になって読書活動の取り組みが進んでいくことを期待しています。
その意味でも、司書教諭や学校司書の配置も基盤としてしっかり整えていくことも大事だと思っております。
――こうした2つの計画を中心に、本年度予算でも「読書活動総合推進事業」という形で盛り込まれていますが、具体的にどのような取り組みを推進していく予定ですか。
例えば「発達段階に応じた読書活動推進事業」では、小・中学、高校や公立図書館による先導的な読書活動や、発達段階や多様な子どものニーズなどに対応した取り組みを支援をさせて頂いて、その効果などを実証していただいて横展開していくモデル事業です。「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の4つの基本的な方針を意識しながら計画に対応した、先進的な取り組みを促して行くモデル事業です。
また、「学校図書館図書の整備促進事業」は、小・中学、高校や特別支援学校などでの取り組みを支援するモデル事業です。学習指導要領を踏まえた学校図書館を活用した授業を進めるため、SDGsなど新しいトピックに関連する書籍や新聞、優良図書、授業に必要な基本図書の整備状況などを再点検し、計画的な図書の更新を定めた図書整備計画の策定や図書館資料を活用したモデル授業の実践などを、広く発信していきたいと思います。学校図書館を直接整備する事業ではなくて、学校図書館を使った先進的な授業実践の指導案などを集積していただいてデータベース化して他校でも使えるようにするなど、学校図書館の整備促進に向けた取り組みを行う事業です。
学校や子どもたちが置かれている環境は多様ですので、現場での実感を伴って試行錯誤しながら取り組まれて成果を出している実質的な取り組みを支援して行きたいと考えています。
――「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の基本的方針にもありますが、今のデジタル化の流れの中での学校図書館の役割はどのようなものだと考えていますか。
図書館のデジタル化やDXを推進するための実証的な調査研究を進めていく予定です。学校図書館に関しては、図書情報のデータベース化であるとか、他校の学校図書館や公立図書館などをオンラインでつないで地域全体の図書の共同利用や図書の検索をできるようにすることで、多様な興味関心に応えられるような環境整備も可能になるのではないかと思っています。