萩生田光一文科相と麻生太郎財務相は12月17日、財務省で来年度予算案の事前閣僚折衝を行い、義務標準法で現在40人(小学1年は35人)と定められている公立小学校の学級編制を、来年度から5年間をかけて段階的に下げ、全学年で35人とすることで合意した。中学校は現行の40人を維持する。文科省は第8次教職員定数改善計画(2021-2025年)を策定し、小学校全学年の「35人学級」を計画的に整備できるよう、自治体に対して教員配置を担保する。

現行で40人(小学1年は35人)と定められている公立小学校の学級編制について、来年度から5年間をかけて、段階的に全学年で35人に引き下げることが決まった。中学校は現行の40人を維持する。学級編成の引き下げは40年ぶりの改革だが、一方で中学校が引き下げの対象とならないことや、学級数が増えることに伴う教員確保など課題も残る。

児童虐待の増加による児童相談所の一時保護の増加を受けて、総務省は12月15日、一時保護され、家庭での養育が困難であることから、児童養護施設や里親の下で暮らす子供の養育の課題に関する実態調査を基に、厚労省に勧告を行った。進学や就職で施設から離れて暮らす子供に、養育や必要な支援を継続することについて、指針などに明記して都道府県に周知することなどを求めた。

デロイトトーマツコンサルティング合同会社は12月17日、世界各地の児童労働の実態を初めてまとめた『児童労働白書2020―ビジネスと児童労働―』に関するオンラインセミナーを開催した。コロナ禍によって児童労働が増える可能性があるとの懸念を示し、企業側の人権ビジネスの取り組みに期待を示した。

政府の教育再生実行会議は12月16日、初等中等教育ワーキング・グループ(初中WG)で来年度の予算編成に向け、今月をめどに取りまとめを目指していた少人数学級に関する提言を見送ることを表明した。有識者間でさらに深い議論が必要だとして、教育再生実行会議全体の提言をまとめるタイミングに合わせ、来年5月に取りまとめを行うことを目指す。

特別支援学校に通う肢体不自由の生徒が、自分自身の夢や社会への提言を発表する「ミラコン2020~未来を見通すコンテスト~第3回プレゼンカップ全国大会」(全国特別支援学校肢体不自由教育校長会主催)のファイナルステージが12月16日、東京都世田谷区の都立光明学園(田村康二朗校長、児童生徒225人)で開かれた。

「月曜日の朝がしんどい」。そんな教師の気持ちに寄り添おうと、映画『みんなの学校』の舞台となった大阪市立大空小学校の初代校長・木村泰子氏が12月14日から、教師に向けてメッセージ動画を発信する新たな試みを始めた。NPO法人「共育の杜」が運営するオンラインサロンで、毎週月曜の朝などに定期的に配信される。

障害児に「子どもの権利」を教えてほしい――。12月14日に都内で開かれた厚労省「子どもの権利擁護に関するワーキングチーム(WT)」の会合で、6~19歳まで障害児施設で暮らし、現在は自立生活を送る井上龍之介さんが、自身の経験を踏まえ、障害児がもっと自由に意見を表明できたり、聞いてもらえたりする機会の重要性を訴えた。

総務省の中部管区行政評価局は12月11日、東海4県の8国立大学を対象にした「緊急時における大学の遠隔授業の実施に関する調査」の結果を公表した。遠隔授業を実施するに当たり、多くの大学で受講方法が学生に十分に説明されていなかったり、授業中に質疑応答の時間が設けられていなかったりすることが明らかになった。

ユニセフ(国連児童基金)のイノチェンティ研究所は12月11日、コロナ禍が子供の貧困問題に与える影響をまとめた報告書を公表した。政府の財政支出のうち、感染拡大の第1波の間に、子供や子育て世帯の支援に割り当てられたのは2%に過ぎず、子供の貧困リスクに対処できていないと警鐘を鳴らした。

千葉県船橋市によると、市立船橋高校で発生したクラスターは12月15日時点で、教員と生徒合わせて100人に上るなど、検査結果が出るとともに増加している。同日には、茨城県土浦市にある土浦日本大学高校でも教員と生徒15人の感染が確認され、両校の男子バスケットボール部が練習試合を行っていたことも判明した。
少人数学級の実現に向け、来年度予算編成を巡る文科省と財務当局の攻防が大詰めを迎えている。文科省は児童生徒の自然減があるため、教職員定数を現状の水準で維持すれば、財政負担を増やさなくても今後10年間で30人学級の実現が可能と主張。財務当局は自然減分をそのまま教職員の人件費に充てるわけにはいかないなどと反論しているといい、議論は平行線となっている。

政府は12月15日夕、臨時閣議を開き、今年度の第3次補正予算案を閣議決定した。文科省関連は総額1兆1830億円で、教育関連ではコロナ禍に対応するための教職員経費など感染症対策支援、GIGAスクール構想で対象となっていない高校のICT環境の整備、工業科や農業科など職業学科のICT環境を整備する「スマート専門高校」の実現、学校施設の衛生環境改善や老朽化対策などを盛り込んだ。

東日本大震災による津波で74人もの児童が犠牲となった宮城県石巻市立大川小学校の事故を踏まえ、宮城県教委の検討会議は12月14日、学校防災の抜本的な見直しに関する提言を盛り込んだ報告書を取りまとめ、県議会に報告した。震災から間もなく10年を迎えることから、教職員がその記憶と教訓を継承し、災害時に適切に対応できる能力を養成することや、地域の災害特性を踏まえた学校防災体制の構築などをうたった。

新型コロナウイルスの感染拡大による今春の臨時休校について、萩生田光一文科相は12月15日、来年度の全国学力・学習状況調査で、学習状況や環境に関する質問項目を新たに盛り込み、コロナ禍の影響について、さまざまな観点から把握・分析を行うとした。
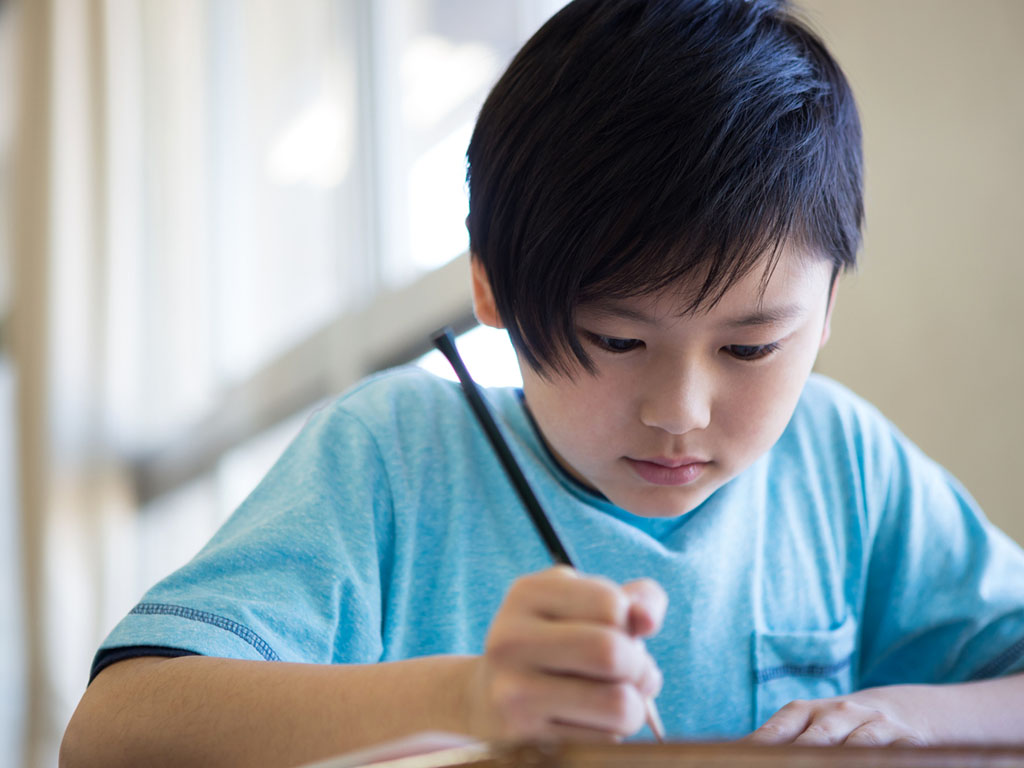
ユニセフ(国連児童基金)は12月15日、ヘンリエッタ・フォア事務局長による声明を発表し、子供たちへの学びの保障のためにも、教師への新型コロナウイルスのワクチン接種を優先すべきだと各国政府に呼び掛けた。

東京都東久留米市にある自由学園男子部(更科幸一部長、生徒214人)で、「種苗法」をテーマに生徒が議論を重ねた国語の授業がこのほど行われた。一見すると「国語らしからぬ」授業は、2学期の初めの授業での生徒の提案から始まったという。を生徒たちとの話し合いで決めている。……

北海道議会は12月11日の本会議で、公立学校教員への1年単位の変形労働時間制の導入を可能にする「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例」の改正案を可決した。

東京都は、これからの都の教育の方向性を示す次期「東京都教育施策大綱」の骨子案を、12月10日に開かれた今年度第3回総合教育会議で示した。東京の目指す教育として「誰一人取り残さず、すべての子供が将来への希望を持って、自ら伸び、育つ教育」を掲げ、その実現に向けてICT活用など基軸となる学びの姿を描いた。

山梨県の長崎幸太郎知事は12月11日、萩生田光一文科相に面会し、「新型コロナウイルスに感染した大学等受験者への受験機会の確保に向けた緊急要請」を申し入れた。新型コロナウイルス感染により高校生が大学などを受験できない場合、代替日程を設定するなどの柔軟な対応を行うことが重要だとして、大学に対する協力依頼を行うよう求めた。今後、全国知事会としても政府に要請するという。

担当する授業などに応じて勤務する「時間講師」について、高知県高等学校教職員組合(高知高教組)はこのほど、実態調査の結果を公表した。授業のない夏休み中に収入が途絶えたり、思うように休暇が取れなかったりといった、厳しい実情が浮き彫りになった。

マイナンバーを活用した行政のデジタル化に向け、政府は12月11日、菅義偉首相が出席してマイナンバーの利活用とデジタル基盤の改善を議論するワーキンググループ(WG)の第6回会合を開き、検討対象となっていた33項目を実現するまでのスケジュールを明記した報告を了承した。

学校や幼稚園など子供と接する仕事への就職を希望する人に性犯罪歴がないことを証明する、日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の制度創設について、萩生田光一文科相は12月11日の閣議後会見で、「職種横断的な仕組みは非常に有効だ」と指摘し、法務省や厚労省など関係省庁の動向に応じて積極的に協力する考えを示した。

大学入試改革の仕切り直しに向けた議論を進めている、文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は12月11日、第19回会合をオンラインで開催し、記述式問題の出題を中心に、委員間でディスカッションを行った。

学校統合や小規模校の魅力的な学校づくりについて考える、文科省主催の「学校魅力化フォーラム」が12月11日、オンラインで開催された。少子化・人口減が急速に進む中で、全ての地域の学校で個別最適化された学びを実現するための学校教育の在り方について、事例や研究発表があった。遠隔地からの通学に欠かせないスクールバス通学が、児童生徒の健康や学習面に及ぼす影響についての調査結果などが公表された。

千葉県船橋市は12月10日、市立船橋高校で生徒40人、教員6人の計46人にのぼる、新型コロナウイルスのクラスターが発生したと発表した。生徒40人のうち36人は同校の男子バスケットボール部員だった。感染者は全員が軽症か無症状で、重症者は出ていない。同校は9日から当面の間、臨時休校となった。

厚労省は12月10日、保育所などが医療従事者の子供を適切に受け入れることの徹底を、都道府県などに改めて通知した。各地で新型コロナウイルスの感染拡大が続き、一部地域で医療提供体制がひっ迫している状況を踏まえ、保護者が医療従事者であることを理由に、濃厚接触者に特定された子供と同様に登園を避けるような取り扱いをしたり、偏見や差別が生じたりしないよう求めた。

仮想現実(VR)で生徒が忍者の動きを体験する授業が12月10日、東京学芸大学附属竹早中学校(藤本光一郎校長、生徒432人)で行われた。生徒らは忍者の衣装に身を包み、「VRソード」や手裏剣を武器に敵を倒すアトラクションに挑戦。予想以上に俊敏な動きを求められ、息を弾ませていた。
