大詰めを迎えている来年度予算案の編成作業について、文科省は12月17日、自民党文科部会に財務省との折衝状況を報告した。席上、高橋はるみ文科大臣政務官は「小学校高学年における教科担任制の推進が残された大きな課題となっている」と報告。来週、末松信介文科相が鈴木俊一財務相との事前閣僚折衝に臨むことを明らかにした。

新設されるこども家庭庁がいじめ対策などに関わっていくことについて、末松信介文科相は12月17日の閣議後会見で、「とにかく教員の教育活動に支障が生ずることのないようにするのが、まず大前提だと考える。

いじめの重大事態への対応について検討している文科省の「いじめ防止対策協議会」は12月17日、今年度2回目となる会合をオンラインで開催した。日本弁護士連合会の村山裕委員が重大事態調査の課題や実態について、弁護士の視点から報告した。重大事態調査の中でいかにして「中立性・公平性・公正性」を担保するかについて、委員からは提案や意見が相次いだ。

野田聖子少子化担当相は12月17日の閣議後会見で、政府が創設を目指している子供政策の司令塔となる新しい組織の名称を「こども家庭庁」とする方針を決めたことについて、「児童の権利に関する条約の前文にも、子供は家庭環境の下で幸福、愛情および理解のある雰囲気の中で成長すべきと書かれている。

高校の新教育課程で学んだ生徒が初めて受験することになる2025年1月に実施される予定の大学入学共通テストについて、大学入試センターは12月17日、新たに追加される「情報」で、既卒者に配慮して現行の教育課程に基づく経過措置科目「旧情報(仮)」を出題すると発表した。

「男は仕事、女は家庭」といった性別に基づく無意識の思い込みが、個人の意欲や能力に応じた活躍を阻害する要因となることを踏まえ、内閣府は12月16日、こうした無意識の思い込みに気付くための「チェックシート」を公表した。同時に、それがなぜ問題なのかを解説した「事例集」も作成。内閣府は来年度から、これらを活用して地方自治体などへの啓発を進める予定で、担当者は「教育現場でも、無意識の思い込みが教員から子供たちへと再生産されていくことがある。教育関係者への周知も進めていきたい」と話している。
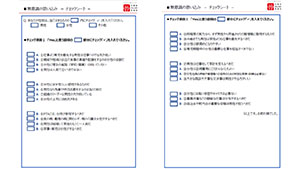
特別支援学校の教師の専門性向上のため導入が検討されている、特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラムについて、文科省の「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議」の下に設置されたワーキングループ(WG)が12月16日、初会合を開き、コアカリキュラム作成に向けた議論を開始した。

特別支援学校に通う生徒らが生活を通して感じた課題を分析し、解決に向けた提言などを発表する「ミラコン2021~未来を見通すコンテスト~プレゼンカップ全国大会」が12月16日、東京都世田谷区の都立光明学園で開かれた。全国から選ばれた7つのブロックの代表者が、学校内外での体験に触れながら社会を変えたいとの思いを力強く訴えた。

教師や教育系YouTuber、中高生らが垣根を越えて学校の授業について考える取り組み「授業スタジオHomie」が12月12日、スタートした。同日に都内で開催されたお披露目イベントでは、教育系YouTuberの葉一氏や「ムンディ先生」、お笑い芸人としても活躍する「タカタ先生」ら授業動画のプロフェッショナルが一堂に会し、会場に集まった教師や学生、中学生と交流を深めた。

国連のアントニオ・グテーレス事務総長は12月13日、ユニセフ(国連児童基金)の8代目事務局長として、米国大統領補佐官であるキャサリン・ラッセル氏が就任すると発表した。ラッセル氏はこれまで、米国政府の代表として、国際的な女性問題の改善などに取り組んできた。女性の事務局長はラッセル氏で4人目となる。

学校のICT活用を巡り、「十分な通信速度が確保できない」「全員の同時接続ができない」などネットワーク環境の問題を抱える学校現場が多いことから、文科省は12月16日、参院予算委の審議で、今年度補正予算案に計上した各都道府県のGIGAスクール運営支援センターを早急に立ち上げ、全国全ての公立学校で年度内にネットワーク環境の総点検を実施する考えを明らかにした。

文科省は12月15日、中教審の「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」の第5回会合で、来年度からモデル地域で5歳児~小学1年生の「架け橋期」におけるカリキュラムの開発・実践を進める方針を示した。モデル地域の自治体で関係機関からなる会議体を設置し、カリキュラムの開発を進めるとともに、教育の質についても検証する。

子供政策を一元化する司令塔として創設を目指している新たな組織の名称について、政府は「こども家庭庁」とする方針を固め、12月15日、自民党本部で開かれた同党の会合で示した。当初の基本方針原案で示した「こども庁」の名称に対して、党内から「家庭をしっかり支援する意味で『こども家庭庁』とすべきだ」などとの意見があったことを踏まえて修正した。

教員の1日の学校内勤務時間が平均10時間39分に上り、給特法(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)の改正後もほとんど減らないままとなっていることが12月15日、公立学校の教員を対象とする日教組の調査で示された。

部活動の地域移行を見据え、その受け皿となる地域スポーツクラブの産業化を模索している経産省は12月14日、アスリートらが今後の部活動の姿を語り合うオンラインイベントを開催した。

政府は12月15日、18歳以下の子供への10万円の臨時特別給付に関するQ&Aをまとめ、全国の自治体に通知した。養育している人の年収が960万円以上の世帯を除き、年内に子供1人当たり5万円の現金給付、来年春に向けて5万円相当のクーポンを基本とした給付を行うが、追加の5万円相当を現金給付としたり、10万円の現金を一括給付したりすることも可能とした。

岩手県山田町はこのほど、閉校した小中学校で使用していた物品を、フリマアプリ「メルカリ」が運営するネットショップ「メルカリShops(ショップス)」で販売する取り組みを始めた。処分費用の削減や循環型社会の実現が狙い。メルカリショップスで自治体が出品するのは、全国初だという。

卒業アルバムを自分たちで撮影してつくる——。東京都中野区の新渡戸文化小学校(杉本竜之校長、児童355人)では、6年生が卒業アルバムを自分たちでつくるプロジェクト「Memory Journey」を進めている。学校の卒業アルバムは通常、業者に任せる部分が多い。

日本の半導体産業が国際的に凋落する中、世界最大手の台湾の半導体メーカー「TSMC」が熊本県での工場建設を発表したことを受け、末松信介文科相は12月14日の衆院予算委で、「熊本県や経産省と連携して新工場で求められる技術知識を明確にしつつ、九州全体の高等教育機関が一丸となって半導体製造に携わる即戦力の人材育成を進めたい」と述べて、地元の工業高校などを中心に人材育成に取り組む姿勢を示した。

Society5.0時代の日本の再生と人材育成を説いた『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)の著者であり、先日発足した教育未来創造会議の委員でもある安宅(あたか)和人慶應義塾大学教授が12月13日、超教育協会が主催するオンラインシンポジウムに登壇し、「コロナ後のシン・ニホンについて」をテーマに講演した。
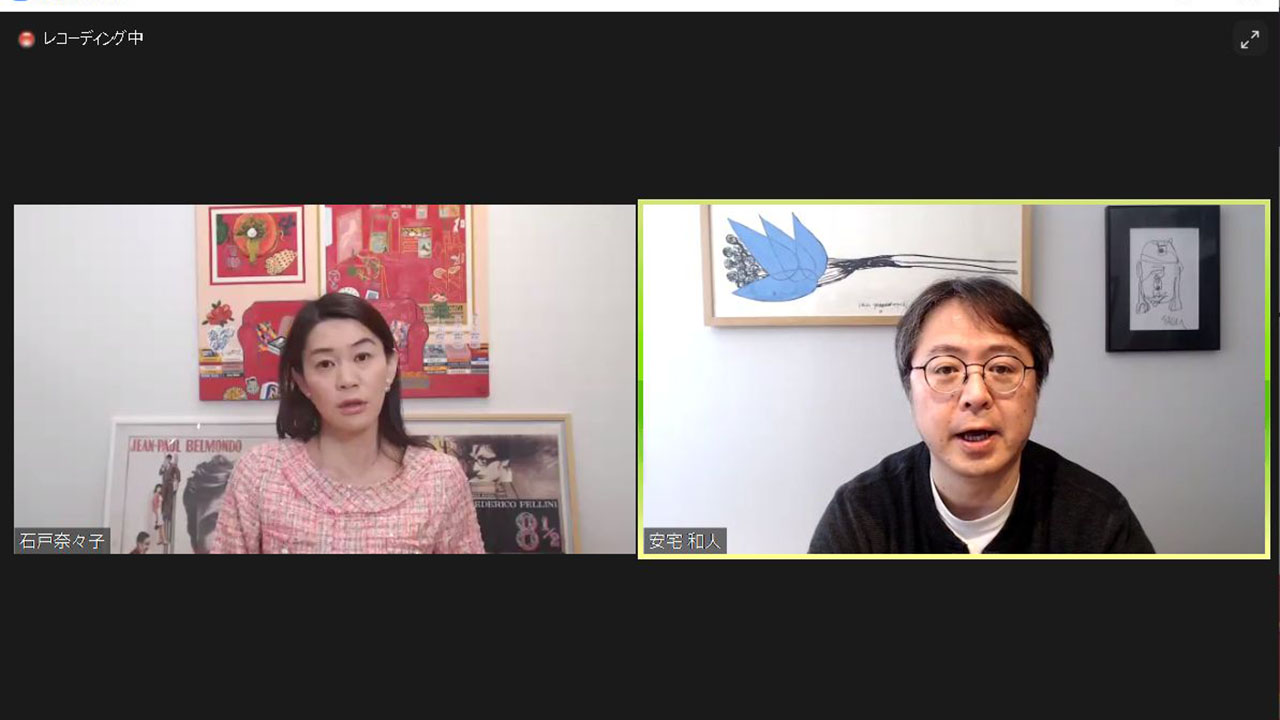
東京都教委はこのほど、1人1台端末を先行して導入した研究校の高校による成果報告会と、シンポジウムを開催した。端末の導入により、授業や探究活動が進めやすくなったという事例のほか、導入にあたって教員や生徒の間で工夫したことなどが報告された。東京都では来年度から、都立高校での1人1台端末の整備を計画しており、それに向けて好事例の周知を図る。

コロナ禍で経済的に困窮している子育て世帯の年末年始を支援しようと、国際NGOの「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」は、申し込みのあった家庭に食品などを送る「冬休み子どもの食応援ボックス」を実施する。12月14日には、千葉県内で発送作業が行われ、スタッフらの手によって、企業などから提供を受けた食品や文房具など3200セットが箱詰めされていった。

学校でのいじめを巡り、被害児童生徒や保護者と学校側との溝が時間の経過とともに深まるケースが目立つことから、いじめ問題に取り組む内田良・名古屋大准教授や藤川大祐・千葉大教授ら有識者や弁護士による団体が、生徒・教員・保護者の三者を対象としたアンケート調査を行い、12月13日、文科省内で記者会見を開いて結果を公表した。

文科省は12月13日、来年度の全国学力・学習状況調査を4月19日に実施する方針を、「全国的な学力調査に関する専門家会議」の第4回会合で報告した。教科に関する調査では国語、算数・数学に、3年に一度程度実施している理科を追加する。また児童生徒質問紙調査では、今年に引き続きパソコンやタブレット端末を使ったオンライン回答方式を導入。

文科省は、大学に飛び入学した学生が中途退学した場合に就職などで不利にならないよう、飛び入学者に高校卒業資格を付与する制度を、できるだけ早く省令改正をして創設する方針を決めた。12月13日に開かれた、特異な才能のある児童生徒への指導の在り方を検討する有識者会議(座長・岩永雅也放送大学学長)で明らかにした。

インスタグラムで950万人以上のフォロワーを抱え、ユニークなファッションや行動で注目を集めるお笑い芸人の渡辺直美さんがこのほど、10代向けEdTechプログラム「Inspire High(インスパイア・ハイ)」に出演し、参加者と「自分らしさ」について語り合った。

宿題がない、テストがない、“先生”がいないという「きのくに子どもの村学園」の一つ、「南アルプス子どもの村小学校」に1年間密着し、製作されたドキュメンタリー映画『夢みる小学校』の完成披露試写会が12月9日、都内で開催された。

来年4月から高校の必修科目となる『現代の国語』で、芥川龍之介や夏目漱石などの小説5作品を載せた教科書が占有率トップになったことが分かり、末松信介文科相は12月10日の閣議後会見で、「『現代の国語』に小説が盛り込まれることは、本来、想定していなかった。
