
不登校の増加やニーズの多様化を背景に通信制高校の生徒は増え続け、今や高校生の約10人に1人が通信制高校で学ぶ時代を迎えている。一方で国が毎年、通信制高校を対象に実施している点検調査では、国が求める教員配置や通信教育実施計画の策定が不十分な不適切事案が多数確認されている。

不登校の増加やニーズの多様化を背景に通信制高校の生徒は増え続け、今や高校生の約10人に1人が通信制高校で学ぶ時代を迎えている。一方で国が毎年、通信制高校を対象に実施している点検調査では、国が求める教員配置や通信教育実施計画の策定が不十分な不適切事案が多数確認されている。

特別支援学校・特別支援学級の教員に支払われている給料の調整額を巡って、阿部俊子文科相は4月15日の閣議後会見で、全ての教師が特別支援教育に関わることが必要となっているとして、現状の調整額を半減する方針を明らかにした。その上で、この調整額の引き下げは、今国会で審議されている教職調整額の引き上げに充当するための「財源捻出を目的としたものではない」と否定した。
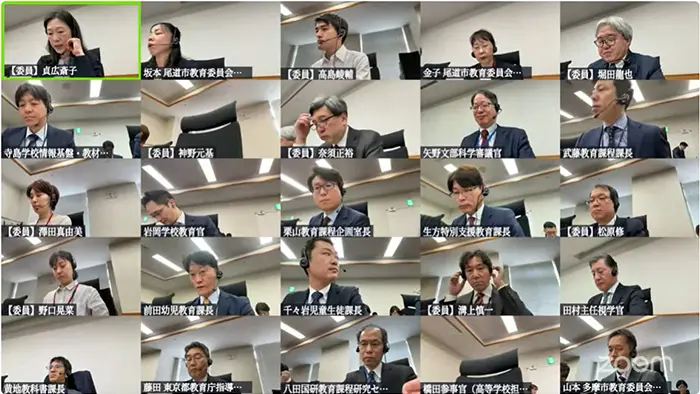
次期学習指導要領における教育課程の編成に関し、文部科学省は4月10日に開かれた中教審の教育課程企画特別部会第5回会合で、個々の児童生徒に着目した教育課程の特例として、新たに特定分野に特異な才能のある児童生徒や、不登校の児童生徒を対象にした特別な教育課程編成を認める方針を示した。日本語指導が必要な児童生徒に対する特別の教育課程も見直し、日本語の習得のみならず、デジタル技術や母語も生かして資質・能力を育成するものに改善する。

不登校の児童生徒を受け入れる「学びの多様化学校」について、文部科学省は3月19日、来年度に開校する23校を新たに指定したと発表した。指定数としては過去最多で、全国の学びの多様化学校の数は、23都道府県で58校になる見通し。同省は将来的に全国300校の設置を目指しており、「自治体の設置準備を支援するなどして、さらに設置を促進したい」と話している。

不登校の児童生徒を受け入れる「学びの多様化学校」が今春、全国で過去最多となる20校以上新設される見通しであることが、教育新聞が各都道府県教委などに行った取材で分かった。昨年4月時点の学校数は16都道府県35校で、今春には初めて設置される7県を含めて合わせて23都道府県で50校以上に増える見通し。文部科学省が目標に掲げる全国300校にはまだ道半ばだが、同省は「設置数の増加とともに各地でシンポジウムなどを通じて理解は深まっており、自治体の設置準備への支援などを通してさらに設置数を増やしていきたい」としている。
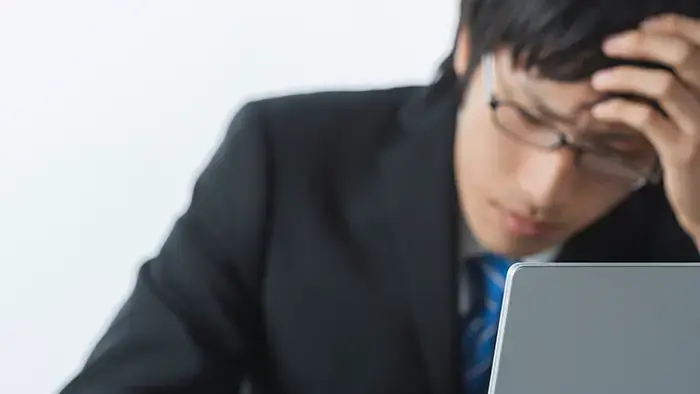
全国の小中高校の教員のうち、採用後10年までに特別支援教育に関する経験がない教員が全体の80%に上ることが、文部科学省が9月6日に公表した特別支援教育に関する調査結果で分かった。特別支援教育のニーズが年々高まる中、同省は全ての教員が10年以内に特別支援教育を複数年経験する措置を取るよう各都道府県教育委員会などに求めており、今回の調査結果を受けて同日、改めて各教委に速やかに人事上の措置を求める通知を出した。

文部科学省が2022年に出した特別支援教育を巡る通知を巡り、大阪弁護士会が3月、「子どもたちがインクルーシブ教育を受ける権利を侵害している」として、内容の一部を撤回するよう勧告した。通知は特別支援学級に在籍する児童生徒が通常学級で受ける授業数に制約を設ける内容となっており、障害者権利条約が定めるインクルーシブ教育の理念に反すると判断したという。これに対し、文科省側は「(通知は)インクルーシブ教育を目指したものだ」と真っ向から反論し、撤回には応じない考えを示している。論争の背景を取材した。