子供の自殺を巡る問題が深刻だ。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中で、休校措置や外出自粛など、子供たちを取り巻く環境は大きく一変した。生きづらさを抱えながらも、何とか日常をやり過ごしていた児童生徒たちの心に、どれだけの影を落としているのだろうか。
全国の学校や教員研修で子供の自殺予防に関する啓発活動を続ける髙橋聡美氏(中央大学客員研究員)は、「今すぐに着手しなければいけない、切羽詰まった問題だ」と強調する。髙橋氏が昨年12月に出版した『教師にできる自殺予防~子どものSOSを見逃さない~』をもとに、インタビューした。
まず、子供の自殺が増えている現状を発信しなければならないと危機感を覚えたからです。子供の自殺はそもそも世代別に見ると数が少ないので、横ばいに見えてしまいます。ただ正確にその数を追ってみると、年々増えているばかりか、戦後最悪の数字を記録しています。2019年と2020年の8月を比較してみると(図1)、中学生、高校生、大学生全てで増加しています。特に女子は顕著で、中学生が4倍、高校生が7倍にも膨れ上がっています。

次に、自殺が起こってしまった後の、社会の受け止め方についても課題感を抱えています。「クラスメートからのいじめが原因」「子供自身がSOSを出さないことが問題だった」などと、あたかも子供に原因があるかのような議論が多くなされているように思います。自殺予防教育を考えるときでも、子供の行動変容を促す内容が多く見受けられます。でも、それは、本当に正しいのでしょうか。
私はこれまで数多くの子供の自殺事案と向き合ってきましたが、何より思うのは、子供を変える前に大人が変わらなければいけないということです。子供のSOSを、大人がしっかりと受け止める素地づくりが急務です。
子供の自殺問題は、今すぐに着手しなければならない切羽詰まった問題です。私は全国の学校を巡り、講演会や教員研修などでお話ししていますが、それにも限界があります。一人でも多くの先生の目に触れるように、書籍として出版することにしました。
子供だけでなく、大人の自殺も増加傾向にあります。コロナ禍のように心理的・社会的に大きな危機状態に陥ったとき、ほころびが生まれやすいのは、平常時に対策が不十分な部分です。
例えば家庭に問題がある子供の場合、ステイホームで家にいる時間が長くなり、虐待やDVにさらされるリスクが高くなります。また、もともと自殺の動機として比率の高い学業問題や進路問題は、休校措置の影響で状況が悪化した子供が多くいるでしょう。さらに経済困窮が影響して、希望する学校に進学できない子供も増加傾向にあるようです。
このようにコロナ禍で、子供の抱える問題は確実に悪化しています。
これは子供に限らないことですが、自殺に至るまでのプロセスは複雑であり、決して一つには絞れないのです。
例えば、教師の指導があった後に子供が自殺した場合、「教師の指導」だけが原因とされがちですが、それは単なるきっかけにしかすぎません。「親子関係がうまくいっていない、勉強もうまくいかない、部活もいま一つ。楽しみがない」というようなさまざまな状況が重なり、先生に厳しく指導されるなど、何か心理的重圧がかかったことが引き金になり自殺してしまう。
WHOは自殺が起きてしまった後の対応として、「原因を特定しない」ことを挙げています。特定することで残された人たちが安心できる面はありますが、不用意な犯人捜しや原因の特定は、バッシングなど2次的な傷つきを生むばかりか、最悪の場合、新たな自殺を生む危険性も孕んでいます。
まず学校の先生ができることは限定的であると認識して、児童生徒と向き合っていただきたいです。その限られた状況で、守備範囲である学校の問題を丁寧にケアしてほしいと思います。児童生徒の自殺の原因や動機のデータを見ると、学校に関わるものが上位にきているのは事実です。
一方で、家庭に問題を抱えた児童生徒の支援も大きな課題です。先日も現場の先生から、「保護者に学校に行かせてもらえない、家庭で学習させてもらえないような児童生徒に、どう介入すればよいか」と相談を受けました。
このような質問をされたとき、地域のソーシャルワーカーときちんとつながることが大切だと回答します。虐待、貧困、ヤングケアラー……、子供が学校の外で抱える問題は多岐に渡ります。これら全てを学校がケアすることは、不可能です。
ただ現場の先生たちの多くが、児童生徒を思うあまり、そのソーシャルワーク面も自分たちで支援しなければという使命感を強く持っています。そして熱意があればあるほど、無力感にさいなまれ、ご自身がつぶれてしまうケースも後を絶ちません。
さまざまなところで指摘されているように、学校と地域社会のつながりの希薄化が進んでいます。そんな中でも教師や学校が抱え込みすぎないように、自治体や地域の機関と意識的に関わることが必要です。そして先生たちは、まず学校の中でできることに注力してほしいと思います。
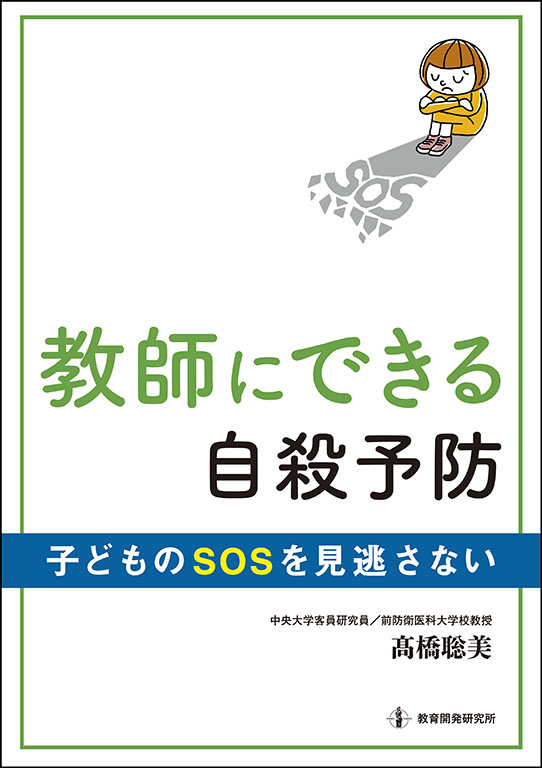
子供の自殺予防というと、子供がSOSを発してくれるのを待つ姿を思い浮かべる先生が多いかもしれません。ですが、「先生、死にたいです」とストレートにSOSを発してくれる児童生徒は、ほとんどいません。
では教師に何ができるかというと、「うちのお父さん、マジうざいんだよ」「最近友達とうまくいかなくて」など、彼らの小さな生きづらさを丁寧に聞き続けることです。事情もよく聞かないまま、「お父さんのことを、うざいなんて言っちゃだめだよ」などと否定してしまうと、子供たちはそこでシャットダウンしてしまいます。子供の言うことを上から目線でジャッジメントするのではなく、「そうなの?」「どうして?」とひたすら聞くことに徹する。その積み重ねが、児童生徒と教師の間にSOSを言いやすい関係をつくると思います。
「SOSの出し方教育」のスタートは、子供ではありません。助けを求めやすいように子供を指導するのではなく、教師をはじめとした大人側が日ごろから、「なんでも言ってOK」という雰囲気をつくることが欠かせません。
先生方は皆さん、子供の力になりたいと思い、解決に向けて一生懸命に取り組まれています。ただ教師の立場で解決できることと、できないことがあるのが現実です。できないことに対しては、それを受け入れるしかないのです。その子供が今見ている情景を、同じ目線から一緒に見つめ、葛藤する力も支援力です。先生方の多くが、その葛藤を抱えきれないがために苦しんでいるように思います。
いつかどの児童生徒も、先生のもとを離れていきます。彼らの生活上、性格上の問題は、本人自身が人生を掛けて向き合っていく課題です。だから、その子の力を信じて一緒に葛藤するしかありません。
いつか何年も経ったときに、「どんな自分でも受け入れてくれた大人がいた」という体験は、子供たちの生きる力になるはずです。