学校現場の深刻な課題となっている教員不足について、末冨芳日本大学教授や学校業務改善アドバイザーの妹尾昌俊氏らは5月9日、文科省内で記者会見し、3つの方向から対処法を整理した政策提言を明らかにした。提言では、速やかに教員を増やす「応急処置」、教員がやりがいを感じ教員志望者を増やすための働き方改革を進める「体質改善」、正規教員を増やし学校運営体制を構築し直すための「根本治療」――の3つの観点に分けて具体的な取り組みを明示している。末冨教授は「子供たちのために、新学期なのに担任教員がいないとか、専門外の教員が教科を教えるといった、教員不足の状態をなくすことがゴールになる。そのために、国や自治体を応援し、心をそろえて動きたい」と、プロジェクトの活動方針を説明した。
この提言は、末冨教授と妹尾氏、学校現場の声の「見える化」に取り組んでいる民間団体「School Voice Project」(武田緑Demo代表)が協力して立ち上げたプロジェクト「#教員不足をなくそう緊急アクション」がまとめた。今後、文科省など政府関係者や学校設置者である都道府県・政令市など自治体に働き掛ける活動を展開するという。
教員不足が起きている背景について、提言では▽特別支援学級数の増加▽休職者の増加▽講師登録名簿登載希望者数の減少▽若い世代の教員が増えて育休・産休が増えている――などの理由を挙げ、「いますぐ必要な教員必要数は増大しているのに、確保が追い付いていない状況がある」と指摘した。
末冨教授は「なぜ教員不足が起きるかを考えると、複合的要因がある。大事なことは、いま現在、講師登録名簿に搭載されている非正規教員がゼロという自治体があること。もし誰かが産休や育休をとったら、補充できる要員がいない、という状況になっている。この実態に対して、現実的な対応をすることがまず必要になる」と述べた。
提言では、まず、速やかに取り組むべき「応急処置」として、教員免許制度や採用の在り方について具体的な施策を示した。教員志望の学生を増やすために、教員採用試験の改善策として、民間企業との人材獲得競争を意識して大学推薦枠の拡充や試験実施時期の前倒しを提起したほか、教員になった場合に日本学生支援機構による奨学金が返還免除となる仕組みを復活させ、経済的な理由で大学進学や教員志望を諦める学生を減らす政策の実現を求めた。
教員免許を保有している社会人に向けた施策では、社会人経験などに応じた採用試験でのインセンティブを強化したり、中学校免許保持者の小学校現場での勤務を可能としたりするなど、教員採用を柔軟にするよう促した。一度離職した教員が安心して復職できるようにするための実習や研修の整備、募集から採用前研修まで全国規模で行う講師人材バンクの整備などを挙げている。
教員免許を保有していない社会人を教壇に立たせるための促進策も盛り込んだ。社会人特別免許状の授与にあたって、NPO・地域教育団体などで子供や学校への支援を行ってきた実績を評価する一方、研修や学校での実習の整備のほか、他の教員のサポート業務を行う期間を設けるなどの工夫で、教員としての質を保障する仕組みを構築することも求めている。
現職の非正規教員に対しては、同僚教員や子供たちの声をもとに校長が推薦することで正規教員に移行しやすい仕組みを作ったり、給与や雇用契約などの改善を図ったりすることを対処策としている。
次に、教員がやりがいを感じ教員志望者を増やすための「体質改善」として、働き方改革を進める必要を強調した。
第一に、教員が担う業務の見直しを挙げ、▽部活動を含むさまざまな業務の地域や外部への委託・移行▽学校事務職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ICT支援員など、教員以外の専門職・支援員の増員や常勤化--を求めた。これらはすでに文科省が進めている働き方改革をさらにスピードアップする形になっている。いわゆるモンスターペアレンツ対策として保護者とのトラブル回避や訴訟・紛争リスクへの支援などの相談と救済、教職員間のハラスメント対策など、職場としての心理的安全性の確保も明記した。
教員の働き方をもっと柔軟にするための取り組みも列挙している。育児や介護をしながら働きやすいように時短勤務ができるための環境整備や、正規職員としてフレックス制やシフト制を導入したり、週3日勤務・週4日勤務を実現したりする取り組みも求めた。職務を離れて研究に打ち込むことができるサバティカル制度の導入も盛り込んでいる。
持ち帰りも含めた業務量のモニタリングなど勤務時間の可視化、業務改善チームの育成、使い勝手のよいICT環境の整備、非効率な事務や手続きの断捨離など、職場レベルでの業務改善の支援と必要なインフラ整備も、必須アイテムとして改めて確認している。
3つ目の観点となる「根本治療」では、「教員定数」や「国庫負担(予算)」について、国と地方の負担構造を抜本的に見直すところまで踏み込んでいる。まず、少人数学級化の推進を通じて、義務標準法(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律)が定める基礎定数を改善し、正規教員の人員を増やすことを求めた。その上で、教員の人件費などとして国が自治体に回す義務教育費国庫負担金について、現状の3分の1から2分の1へ戻すことを求めた。
義務教育費国庫負担金は、地方分権を進めるための「三位一体改革」で、消費税などの財源を国から自治体に移管するとともに、2006年度から3分の1に圧縮された。これを2分の1に戻すことにより、提言では「都道府県・政令市の財政事情により、国が定める標準より少ない正規教員しか雇用できていない地域もある。都道府県・政令市の財政負担を改善することで、正規教員を雇用しやすくなる」と説明している。
非正規教員の割合に上限を設定することも取り組むべき施策に挙げた。現行制度では、義務標準法に基づく正規教員の定数で算出される教職員給与費について、総額の範囲内で自治体の裁量によって非正規教員にも充てることができる。自治体のニーズに応じて特色ある教育ができるようにするための仕組みで、「総額裁量制」と呼ばれる。これについて、提言では「非正規教員の割合に規制がないために、非常勤講師への依存が高まり、授業以外の負担が正規教員等に集中してしまう課題がある」と指摘した。
さらに、教員1人当たりの授業の持ちコマ数に上限を設定し、小学校教員の中には週28コマの授業を持っているケースもあるという現状の改善を求めた。
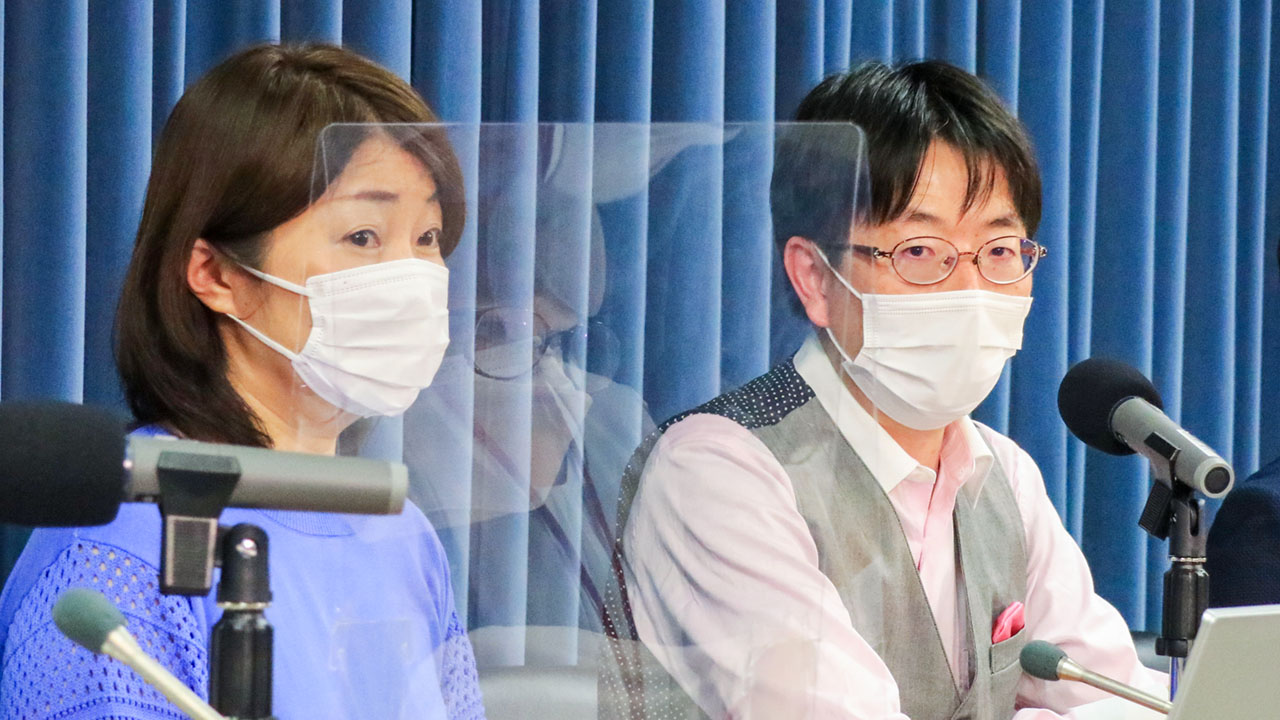
義務教育費国庫負担金の国の負担割合や総額裁量制の見直しは、「三位一体改革」に基づく現行の地方分権制度の見直しに関わる抜本的な議論が必要になる。これについて、末冨教授は「三位一体改革が行われた当時、もっとも強く反対したのは全国知事会だった。地方の声は『国庫負担の割合を2分の1で維持して正規教員を雇いたい』というものだった。それが総額裁量制となり、財政的に苦しい自治体は非正規教員を雇わざるを得ないという苦しい状況が続いてきた。これがいまの教員不足の根本的な理由であり、だからこそ根本治療が必要になっている。いま最も大切なことは、正規教員を年度当初に教員不足を起こさない数だけ、きちんと確保できる仕組みを保障すること。そのために、義務教育費国庫負担金と総額裁量制の運用をアップデートしていくことが必要だと考えている」と説明した。
このプロジェクトでは、School Voice Projectを通じて、教員不足の実態調査について、教職員、副校長・教頭、保護者それぞれにウェブアンケートを5月22日まで実施している。5月8日時点の集計によると、全ての学校種で4割前後の教員が4月の始業式時点で今年度も教員不足が起きていると回答した。教員不足が起きている学校では、1人不足が55%で最も多く、次いで2人が28%だったが、3人以上という学校も9%あった。
調査内容を説明した妹尾氏は「アンケートで非常に多かったのは、育児休業に入った教員の補充ができない、という声だった。いま学校現場では、育児休業を上限の3年間、取得する教員が増えている。それだけ、小さいお子さんを抱えながら復帰するには、しんどい職場だということ。その上、育休中の教員の補充ができないとなると、教育委員会にとっては、産休や育休の取得を喜べないという現実がある。こういう状況を変えていかないといけない」と述べた。
〇教員免許を保有している(取得見込みの)学生向け施策
〇教員免許を保有している社会人向け施策
〇教員免許を保有していない社会人向けの施策
〇現職の非正規教員向けの施策
〇教員が担う業務の見直し
〇安心安全な労働環境づくり
〇柔軟な働き方の実現・許容
〇職場レベルでの業務改善の支援とそれを可能とするインフラ整備
〇基礎定数の改善
(少人数学級化の推進により正規教員の人員を増やす)
〇義務教育費国庫負担額を現状の現在の1/3から1/2へ戻す
(都道府県・政令市の財政負担を改善し、正規教員を雇用しやすくする)
〇非正規教員の割合に上限を設定
(総額裁量制の改善)
〇教員一人当たりの授業の持ちコマ数に上限を設定
(義務標準法の”乗ずる数”を調整し配置人数にゆとりを持たせる)