『教師の育て方』(学事出版)の刊行を記念して、著者の(一社)ジェイス代表の武田信子氏と教育アドバイザーの多賀一郎氏による講演がこのほど、都内で開かれた。大学の教師教育について武田氏は「誰でも教師になれる時代が来てしまった。だからこそ、教師教育をきちんとしなければいけない」と訴え、多賀氏は多忙化などで困難を極めている学校の教師教育について、「基本的な教師教育の在り方が、少なくとも各教育委員会単位で確立されるべき。教師教育者の研修とマニュアルの策定が必要だ」と考えを示した。
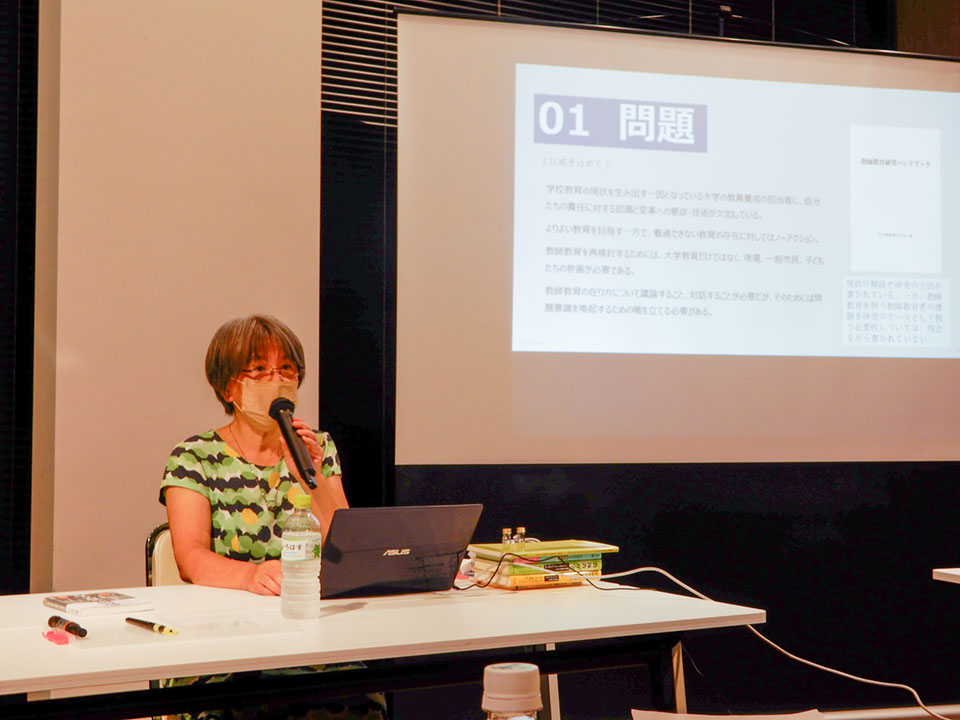
教師教育を専門とし、全国の教委や学校、大学の教員養成課程などで子どもの養育環境の改善を訴えてきた武田氏は「今の学校教育の現状を生み出す一因となっている大学の教員養成の担当者に、自分たちの責任に対する認識と、変革への意欲や技術が欠けている」と指摘。「苦しんでいる子どもたちの授業を担当している教師をどこかで育てた人がいる。教員免許を与えてしまって、教員採用試験に通してしまった人がいる。そうした事実に対して、私も責任を感じている」と話し、「こうした問題は、大学教育だけでなく、学校現場や市民、子どもたちも参画して、対話していくことが必要だ」と訴え掛けた。
武田氏は教員志望者が減少し、教員免許状取得者が誰でも教員になれる現状に危機感を示し、「教師教育者は教員免許を与え難い学生に対して、自分がゲートキーパーの役割を果たすべきだと考えていない」と話した。
また、「子どもの将来が心配だから、学歴をつけておかなければいけない、いいところに就職させなければいけない。そうやって親も教師も、子どもたちを商品のように扱っている。その結果が、不登校児童生徒や自殺する子どもの増加だ」と、大人から子どもへの社会的マルトリートメントが起こっている現状の危うさを訴えた。
「子どもの発達は昔とは変わってきている。今の子どもたちの発達状況を学んで、どう対応するかを知っている教師教育者が、教師になろうとする人たちにきちんと教えていかなくてはならない。そうしないと、どんどんマルトリートメント状況は進んでしまうだろう」と警鐘を鳴らした。
教育アドバイザーとして全国各地の学校現場で指導する多賀氏は「学校現場を回っていると、非常に優れた初任者指導担当もいるが、そうではないケースも多い」と学校現場の教師教育の現状を指摘。「初任者というのは、その地域の教育を40年担っていくような人材。でも学校には、そういう意識が薄いのではないか」と訴えた。
また、学校現場には若手教員がどんどん増えているにも関わらず、OJTが成立しにくくなっていることにも触れ、「若手を指導できる中堅世代は、子育てワークシェア世代だ。自身の子どもの送り迎えなどで早めに帰るなど、OJTを成り立たせるための時間そのものがなくなっている」と説明した。
そうした現状に加えて、学校現場では「初任者に何をどう教えるのか」ということが、初任者を指導する各教師個人に全て任せられていることが問題だとした。「このままでは安定した教師教育ができない。基本的な教師教育の在り方が、少なくとも各教育委員会単位で確立されるべきだ。教師教育者の研修とマニュアルの策定が必要だ」と強調した。

多賀氏が「例えば、新人の大工が入ってきたら、ベテランの大工がまず教えるのは“すごい技術”などではない。くぎの打ち方やかんなのかけ方、電動のこぎりの使い方など、どんな大工でもできないと仕事にならない基礎基本の技術を教える。同様に、初任の教師にも、優れた教師になるための教育技術ではなく、基礎基本の教育技術を教えなければいけない。まず3年間をしのぎ切るための方法を教えなければいけないと、私は思っている」と話すと、会場の参加者からも納得の声が上がった。
参加者からは「初任から3年間をしのぎ切るために、大学時代に学んでおくといいこととは」という質問があった。多賀氏は「例えば、子どもたちの訴えの聞き方や対応の仕方。子どもというのは大概、時間がない時に訴えてきたり、何人かが同時に訴えてきたりする。教師は瞬時に対応する必要があるので、さまざまな『対子どものケーススタディー』を学んでいくべきだろう。宿題忘れにどう対応するか、こういったことも若手の教師にとっては大きな問題になる」と答えた。