学校現場などで「話す力」の育成に取り組む(一社)アルバ・エデュは2月15日、2022年度から日本財団の助成を受け、複数自治体において実施してきた「Speak Up! プログラム」の成果報告会を、都内の会場とオンラインで行った。同プログラムの効果測定報告に加え、導入自治体であるさいたま市の細田眞由美教育長、埼玉県戸田市の 戸ヶ﨑勤教育長、東京都文京区の成澤廣修区長らが意見を交わし、細田教育長は「子どもたちが自信をもって考えを伝えられるようになる。能動的に学び続ける力が育まれるのではないか」と話した。
「Speak Up! プログラム」は、子どもの「話す力」および教員の意識の向上を目的として、複数回のモデル授業と教員研修を実施するプログラム。昨年12月までに小・中学校を中心に、延べ5万人超の児童生徒に授業を実施してきた。また、今年1月時点で1都11市区町の自治体が導入している。
アルバ・エデュ代表理事の竹内明日香氏は「社会ではコミュニケーション能力が最も求められているにもかかわらず、学校はまだ『読み』『書き』が中心で、『話す』にはあまり比重が置かれていない。日本人は話を聞く力は長けているものの、初めての人の前や複数の人の前で話す力がとても低い」と指摘。「話す力」を教員にも全ての子どもたちにも育んでいく重要性を訴えた。
同プログラムではモデル授業の実施前後に効果測定が行われており、その検証結果について三菱UFJリサーチ&コンサルティングの野田鈴子氏が報告した。例えば、モデル授業を2回経験した実験群107人と、受けていない対照群71人に対して実施したアンケートでは、対照群に比べて実験群では「プレゼンの重要性に対する認識」や「プレゼンへのポジティブな感情」「プレゼンに対する自信」「世の中を知りたい、社会の役に立ちたい」という思いが有意に上昇していた。野田氏は他にも検証結果から見えてきたこととして、「実際に発表会でプレゼンすることで自己開示が進み、学級の心理的安全性が高まる可能性もある」と述べた。
続いて、同プログラムの導入自治体から報告があった。市を挙げて探究的な学びを推進しているさいたま市の細田教育長は「探究的な学びに取り組む中で、それを誰かに伝える力、つまりプレゼン力が大事だということに気付いていった」と話し、全ての子どもたちに系統立てたプログラムでプレゼン力を育みたいと同プログラムを導入したという。市内のある小学校では、「プレゼンは苦手だったけれど、すごく好きになった」といった子どもの声や、「自分の考えを深める活動をすると、こんなに子どもたちが生き生きと発表するのかと驚いた」といった教員からの感想があったといい、細田教育長は「子どもたちが自信をもって考えを伝えられるようになる。能動的に学び続ける力が育まれるのではないか」と話した。
文京区では2017年から同プログラムを導入。まず小規模の公立中から導入していったところ、「うちの子が公開の授業で手を挙げているのを初めて見た」と保護者から声が上がるなど、内向的な性格だった子どもたちにも大きな変化が出てきているそうだ。その後は幼稚園や小学校でも導入を進めており、成澤区長は「今後、新たなカリキュラムの開発などにも共に取り組んでいきたい」と意欲を示した。
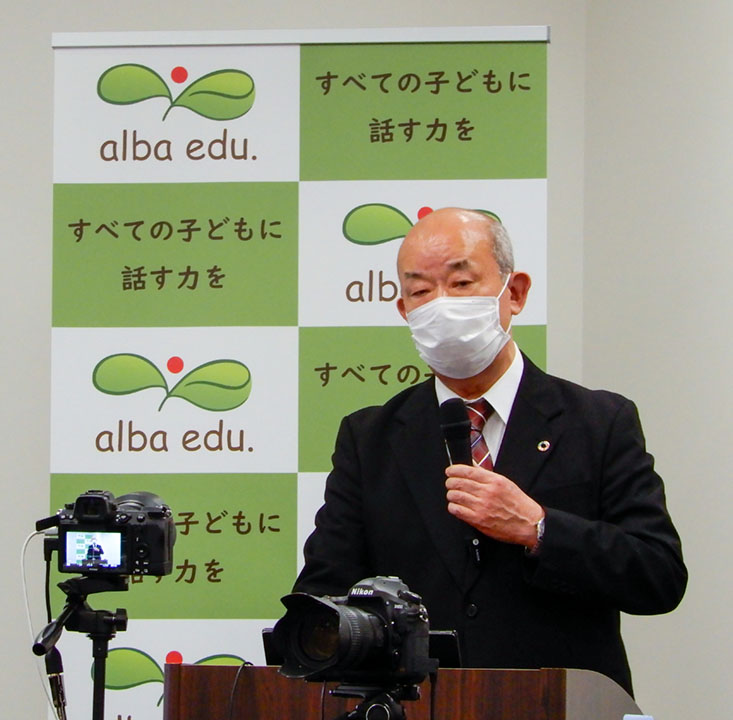
また、戸田市ではPBLを取り入れた授業づくりを推進しており、16年からは市内の小中学生全員が参加するプレゼンテーション大会を実施している。戸ヶ﨑教育長は「PBLを含め、アウトプットについて考えていた時に同プログラムを導入しようと考えた」と話した。同市立美谷本小学校では2月3日から教員研修が始まり、今月中にモデル授業も2回行われる予定。研修を受けた教員からは「明日から確実に変わりそうだ」と期待の声も上がっているという。
その後の意見交換では、これからの教育について成澤区長は「『私はこう思う』と一人称で伝えられる子に育ってほしいと思っている。それが社会を変えることにつながるのではないか。ディベートのような相手を打ち負かす力ではなく、プレゼンで仲間を増やすような能力を育むことが必要だ」と述べた。
また、細田教育長は、同プログラムを導入している小学校校長が「子どもたちの授業だけでなく、教員研修がセットになっていることが魅力的」と話していたことが印象に残っていると述べ、「子どもたちのプレゼンスキルを高めるだけでなく、教員たちが自分たちのアプローチを変えていく必要があると気付けることが重要なポイントではないか」と話した。
戸ヶ﨑教育長は「多様な他者といかにコミュニケーションを取っていくかが問われている。学校教育にも、日常的に多様な他者とコミュニ―ケーションを取る活動を入れていかなければならない。他者理解のためにも『話す力』は重要で、今後のカギになっていく」と力を込めた。
今後の展望について、竹内氏は「オンラインなども活用しながら、より多くの学校に同プログラムを届けていきたい。また各教科の教材へのサポートも考えている。『話す力』は全ての教科における土台だということを伝えながら、活動を広めていきたい」と述べた。