2021年度に始まった大学入学共通テストでは英語4技能試験の導入が見送られ、総合的な英語力の評価は、各大学の個別試験に委ねられることとなった。一方、東京外国語大学(以下、「東京外大」)は既に19年から、英ブリティッシュ・カウンシルと共同開発した独自の英語スピーキング試験を実施しており、文科省の「2021(令和3)年度大学入学者選抜における好事例集」でも、「先進性があり、波及効果は高い」などと評価された。今春も全学部でスピーキング試験を実施したという同学。なぜ英語民間試験の活用ではなく、自前でスピーキング試験を開発したのか、また導入のハードルの高い試験をどのように軌道に乗せたのか、青山亨副学長(教育・入試・点検評価担当)に聞いた。
「英語では読む・聞くという受信の力だけでなく、書く・話すという発信の力が重要。本学ではこれまでの読む・書く・聞く、の試験に加えて、新たなスピーキング試験により、自分で考えて言葉を組み立てて発信する力や、コミュニケーション力を測ることが非常に大事だと考えていた」。青山副学長は、独自の英語スピーキング試験を導入した理由について、このように振り返る。
同学にはもともと、言語テストを専門とする研究者がいた。スピーキング試験の導入にあたってはこうした専門家が中心となり、英国の公的な文化交流機関、ブリティッシュ・カウンシルと連携。同機関の英語力評価ツール「Aptis(アプティス)」の仕組みを活用し、高校の学習指導要領に準拠した試験を開発した。試験時間は約12分間で、主に同学が作問、ブリティッシュ・カウンシルが採点を担う体制としており、数営業日のうちに採点結果が届くようになっている。
同学が外部の英語民間試験を活用するのではなく、独自の試験を開発した背景には、受験生の英語力が比較的高いという事情がある。「外部の英語民間試験では、スピーキング試験のみの利用はできず、会場や日程も他の試験科目と同一には実施できなかった。また、受験生のレベルに合わせて、入試問題の内容や質を管理する必要があった」と青山副学長は説明する。採点基準や採点の体制、サンプル問題と解説などは同学のウェブサイトで公開しており、受験生が一人でも対策しやすい工夫もしている。
東京外大は19年2月、国際日本学部の一般選抜(前期日程)で、初めてこうしたスピーキング試験を実施。同学部は他学部と比べて規模が小さく、受験生は100人ほどで、パソコン教室を利用した。21年からはブリティッシュ・カウンシルが用意したタブレットを活用。この段階で「本学が求めている英語のレベルが、間違いなくその試験で判定できるということを確認できた」(青山副学長)といい、昨年スピーキング試験を全学部(1500人規模)に拡大。今年も全学部で実施した。
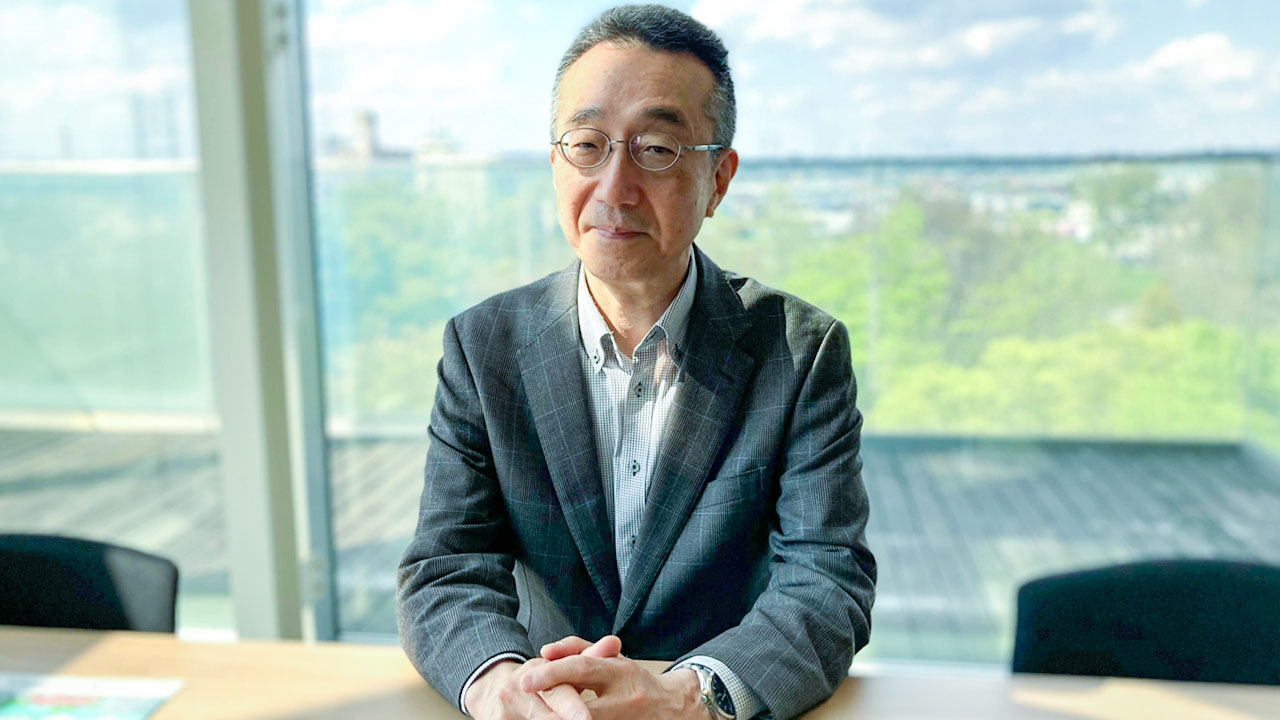
初めて全学部に拡大した昨年は、試験の進行を各教室で合わせるため、待ち時間を十分に設けるなどの対策を入念に行った。一方、待ち時間が長過ぎたという声もあり、今年の試験ではそうした時間を短縮。「大学側の習熟度も上がってきた」と青山副学長はみる。これまでヘッドセットの不具合により予備機で対応したなどの事例はあったものの、「大きな問題は起こっていない」(同)という。「受験する教室や機材については、隣の受験生が話していても集中できるような環境作りなど、改善の余地があるかもしれない」(同)。
スピーキング試験を速やかに軌道に乗せることができた理由として、青山副学長は「学内に専門家がおりノウハウがあったこと、最初はパソコンを使用して少人数から始め、徐々にステップを踏んできたこと、ブリティッシュ・カウンシルの既存のシステムを活用できたこと」を挙げる。さらに、「グローバル志向で英語が好きな受験生や、留学を目指している受験生が多く、スピーキング試験の必要性が理解されやすかった」(同)という背景もあるようだ。
今後の展望について青山副学長は「このスピーキング試験は、本学以外でも実施体制を整えることが可能で、汎用(はんよう)的に活用できるものだと考えている。他大学にも普及させていければ」と意気込む。