企業経営などで今、自分の思いや考えを安心して言える「心理的安全性」に注目が集まっている。それは学校も同じだ。さいたま市立大砂土東小学校(武田泰之校長、児童1122人)の天野翔太教諭は、数年前から心理的安全性を意識した学級づくりを実践し、優れた心理的安全性の構築事例を表彰する「心理的安全性AWARD2023」(㈱ZENTech主催)で、小学校の学級経営では初めてとなるシルバーリングに輝いた。心理的安全性を高めるために、天野教諭はどんな工夫をしているのか。実際に天野教諭が担任をする2年1組の教室を訪ねた。
1学期も残すところ数日となった7月中旬、5時間目の授業が始まる少し前に教室に入ると、目に飛び込んできたのは黒板の前の「スペシャル席」。5つの席はそれぞれ違いがあり、マットと座椅子の席もあれば、キャンプなどで使われる折り畳みの椅子もある。
「その日にジャンケンで勝つと座れる特別な席」とある男の子が教えてくれる。教室の一番前は敬遠されがちだが、このクラスではどうやら一番人気の場所らしい。「でも、勝てたとしても座らないこともできる。僕も一度ジャンケンで勝ったけど、座らなかった」と別の男の子。得られた権利を使うかどうかという選択も、ここでは保障されているようだ。
このクラスでは、そんな子どもたちにとっての楽しみが、至るところに仕掛けられている。
例えば、任意提出となっている家庭で取り組む自学ノート。ページ数などに応じてシールがもらえるが、それが30枚たまると「自学がんばったで賞」として、「先生の机で学べる」「リクエストした曲を優先してかけられる」「給食のおかわりを優先してもらえる」「1日ぬいぐるみと一緒に学べる」など、さまざまな選択肢の中から、使いたい権利を選ぶことができる。
また、良いことをしたり、褒められたりすると、天野教諭からクリップをもらえる。このクリップをクラス全体で瓶にためていき、それがいっぱいになれば、自分たちがやりたいレクリエーションができるそうだ。

さて、5時間目の授業は算数。最初にちょっとしたミニゲームで気持ちを高めつつ、「頭を切り替えて」という合図で子どもたちの気持ちは授業に集中。この日は「算数マジック」と称して、0~9までの異なる数字を組み合わせて2桁の数をつくり、その十の位と一の位の数字を入れ替えた数を引き算して出た答えを、天野教諭が当ててみせるというもの。例えば、子どもが5と8を選んだ場合、「85-58=」の計算を子どもが行って、1の位の数が7であることを天野教諭に伝えると、天野教諭はすぐに「十の位は2だね」と答える。子どもたちが数字を選ぶところから答えを出すところまで、教室の後ろにいる天野教諭がその様子を盗み見ていないか、クジで選ばれた見張り役の子どもが目を光らせている。
ところが、何度やっても天野教諭が当てるので、子どもたちはその秘密を探りたくて次第にうずうずしてくる。教室のあちこちで議論が始まり、ノートを開いて考えたり、タブレットの電卓機能で検算したりする子どもも出てきた。記者の下にも「ヒントを教えて」と子どもたちが集まってくる。天野教諭は机の間を回りながら、良い気付きや学び方をしている子どもがいると、大きな声で褒める。すると、それを聞いて学び方をまねする子どもや、その子に教えてもらおうと近寄る子どもが現れる。そのうちに、何人かの子どもたちが答えの数の一の位と十の位を足すと必ず9になることに気付き始めた。
子どもたちの活動は一見するとばらばらのように感じる。机に座ったまま考えている子もいれば、いろいろな子に聞こうと歩き回る子、黒板の前で友達同士で話し合う子など、さまざまだ。しかし、彼らは今、同じ課題に対して、それぞれ違うアプローチで取り組んでいるのだ。
授業で印象的だったのは、はしゃぎ過ぎて椅子の上に立ってしまった子に、後ろの子が「座ってよ」と注意した場面だ。天野教諭は「言っていることは正しい。でも、今の『座って』と言うのを、どう言えばいいだろう」と声を掛けた。すると子どもたちは「座ってくれるとうれしいな」などと口々に答え、また何事もなかったかのように授業は再開した。
「学級づくりの最初に、子どもたちには『○○して』『○○は駄目だよ』と言われてうれしいかな、といつも話している。子どもたちはどう言われたら相手が嫌な気持ちにならないかを考え、『○○してくれるとうれしいな』『○○できるといいね』などの、いわゆる(『私』を主語にした)アイメッセージの言葉掛けを意識してくれるようになる。これこそ、心理的安全性をつくる言葉だと捉えている」と天野教諭。
アイメッセージの「アイ」は英語の一人称の「I(アイ)」を指す。「私」を主語にして、自分の要望や考えを伝えることで、 相手に対する非難や責めている印象を与えにくいコミュニケーションの方法とされる。
天野教諭は「心理的安全性をつくることでは、リーダーの資質に注目が集まりがちだが、リーダーだけでなく組織にいる全員がそうした言葉を掛け合うことが大事だ。でも『先生がそう言っているから』ではなくて、こちらが問い掛けて、子どもたちに考えてもらうようにしている」と話す。
ところで、天野教諭は子どもたちに、心理的安全性をどのように伝えているのだろうか。心理的安全性AWARDでは、心理的安全性を▽話しやすさ▽助け合い▽挑戦▽新奇歓迎――の4つの因子で審査している。天野教諭はこの4つの因子をより具体的にして、学級開きで伝えているという。「例えば話しやすさや助け合いでは、困ったら助けてって言おう、助けを求めていいんだってことを強調する。そして、助けを求められたら喜んで力になってあげられるといいね、困っていそうなら声を掛けられるようになれるといいね、人が困っていることに気付ける人になろうと呼び掛けている。今のクラスの子どもたちは、それを『友達』という言葉で捉えている。自分の中の友達観に落とし込んで、安心して過ごせて、困ったら助けてくれる人がたくさんいるクラスだと感じているようだ」と天野教諭は説明する。

また、挑戦や新奇歓迎を促す役割を果たしているのがICTだ。2年1組ではクラスのコミュニケーションツールである「Teams」は常にオープンな状態にしていて、タブレットをいつどのように使うかは子どもたちが自ら考えて判断している。「算数の授業で図を使った表現があると、それをタブレットで撮ってすぐにTeamsに共有する子もいる。そうやって、子どもたちは学習のためにICTで有益なことをしているのだと信頼している。授業の中で一斉にICTを使ったり、使うのをやめたりするのはどこかねじれている。一人一人が意思決定できるようにするからこそ、心理的安全性は高まる。もちろん、チャレンジした結果、失敗することもある。そのときは、本当はどうしたかったのかと問い掛け、考える癖をつけるようにしている」と天野教諭。使い方を教え合うなど、協力の面も含めて、ICTの活用は心理的安全性を高めることにつながると確信する。
そんな天野教諭だが、現在の学級経営にたどり着くまでは、さまざまな試行錯誤を繰り返してきたという。
「子どもの頃は、先生から『やりなさい』と言われると、なぜこれをやるのかな、と内心では疑問を抱いていた。でも、いざ自分が教師になると『ハイ!』と元気よく返事ができて、整列したらきれいにそろっているといったことを子どもに求めていた。自分も同じことをやってしまっていると気付いたのが、教師になって5、6年目のころ。そこからどこまで緩めようか、子どもたちに委ねようかと模索が始まった」と天野教諭。
まず始めたのは、大きな声でのあいさつと返事を求めないことだった。「若手のときの自分は子どもに大きな声であいさつをしていたが、それを子どもにも求めていた。大きな声を出すのが苦手な子に対しても『昨日より大きな声で返事ができたね』と声を掛けていた。でも今思うと、その子にとって、大きな声を出すことはしんどかったかもしれない。そもそも、気持ちの良いあいさつは人によって違う。だから、子どもがあいさつをしてくれたときも『元気なあいさつだね』とは言わずに、『あいさつしてくれてありがとう』と言うようになった」と天野教諭は振り返る。
良いことをしたり、褒められたりするともらえるクリップ。クラスで瓶にためて、いっぱいになると好きなレクリエーションができる
そうやって天野教諭はこれまでの実践を見つめ直し、「それは何のためにやるのか」と自らに問い続けながら、今のやり方を少しずつ確立していった。例えば、良いことをするとクリップを渡す取り組みも、個々の子どもの成果だけに特化してしまうと、単なる外発的動機付けの仕組みで終わってしまう。しかし、個人だけでなくクラス全体で頑張ったときに「今日の頑張りはクリップ何個分だろう」と問い掛け、みんなの貢献を可視化したり、誰かのために行動したことがクリップで還元されたりするようになることで、それ以上の効果を発揮する。このように、天野教諭の実践の一つ一つには、必ず明確な狙いが設定されている。
そんな天野教諭の思いと多様な実践を一つに集約した言葉こそが、心理的安全性だった。「とにかくそこにいて安心できることが第一条件。はたからこのクラスを見ると、こんなに子どもが自由に立ち歩いていていいのか、と思うかもしれないが、普段は緩くて、やるときはやるくらいがちょうどいい。それに、子どもたちはこう見えて真剣に学習している。学校が楽しくて、今日はこんなことがあったな、と毎日思ってくれることが何より大事だ。同調圧力の限界を感じて試行錯誤して、そしてたどり着いたのが、心理的安全性だった」と天野教諭は語る。
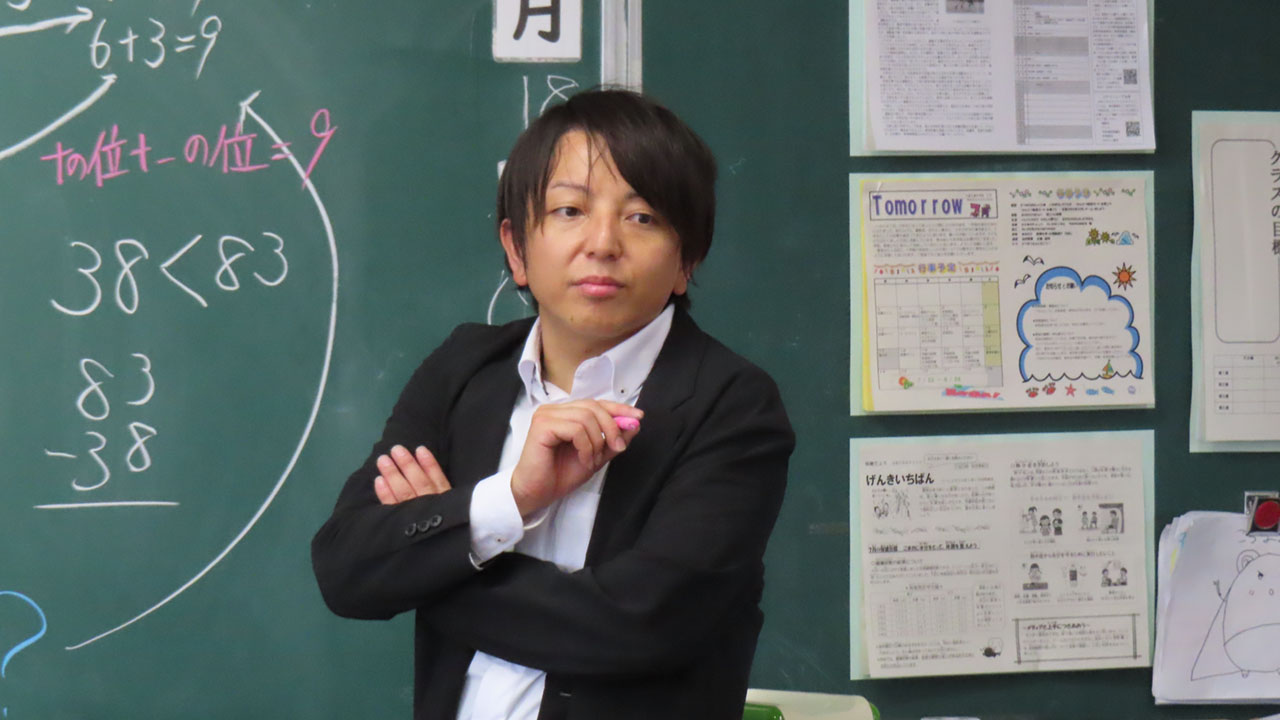
天野教諭は「教師にとっても心理的安全性は大事」と話す
もしかするとそれは、教師も同じかもしれない。天野教諭は次のように警鐘を鳴らす。
「子どもも大人も関係なく、何かにチャレンジしてうまくいかないときはある。失敗したら誰かが一緒に考えてくれたり、傍らにいてくれたりする。うまくいかなかったときに、自分が安心できる環境が学校にあるだろうか。そういう環境があれば次に生かしやすい。教師にとっても心理的安全性は大事。先生が『ちゃんとやらなければ』『しっかりしないと』と思い込んでいるほど、自分自身の心理的安全性が失われていって、子どもたちとうまく関われなくなっているのかもしれない」