中高生にプログラミングに対してもっと興味を持ってもらおうと、東京都教育委員会は8月14~16日の3日間、都立学校に通う中高生がアプリ開発に挑む「ハッカソン」を東京都港区の日本マイクロソフト品川本社で開いた。中高生はチームに分かれて、「青春の問題をITで解決する」というテーマで、オリジナルのアプリを制作。16日は開発したアプリを披露し、審査で最優秀賞などを決めるプレゼンテーションが行われた。
都教委では今年度、IT人材の育成を目的にさまざまなプログラミングイベントを実施しており、このハッカソンもその一環で初めて開催した。都立学校の中高生約60人が参加し、16のチームに分かれて、初日と2日目はアイデア出しからアプリの企画・開発まで集中的に取り組んだ。アプリ開発には、マイクロソフトが提供し、画面上で視覚的にプログラミングができるウェブアプリ作成のためのプラットフォームサービス「PowerApps」を用いた。
最終日は、各チームが開発したアプリのコンセプトや特徴を説明する予選を午前中に実施。午後には予選を通過した6チームが持ち時間10分でプレゼンテーションを行い、ITエンジニアなどの専門家からの質問に答えた。
審査員特別賞に選ばれた都立国際高校2年生のチーム「International Beginners」は、中高生の青春には何かと出費が伴う点に着目。欲しい物を買うために必要な金額まで貯金していくと、愛らしいキャラクターが育つスマート貯金箱アプリを提案した。チームメンバーの前田幸芽さんは「時間を効率的に使うアプリはすでにあるが、お金を目標に向けてためていくアプリは見たことがなかった」とオリジナリティーを強調。「中学生も参加していたが、どのチームもアプリの完成度やプレゼンテーションのレベルが高くて驚いた」と振り返っていた。
都立小石川中等教育学校と都立晴海総合高校の連合チーム「さんどうぃっちず」は優秀賞に輝いた。中高生はストレスを抱えやすいとし、その日の感情を8つの色で直感的に表現するシンプルなアプリを構想。選んだ色によって、感情に対応したメッセージを表示させたり、過去の写真や音楽などをひも付けたりすることができるという。小石川中等教育学校5年生の長谷川真緒さんは「アプリのアイデアには自信があった。いずれ社会にこのアプリを出して、メンタルヘルスなどの分野で活用してもらい、人を幸せにすることができれば」と展望を語った。
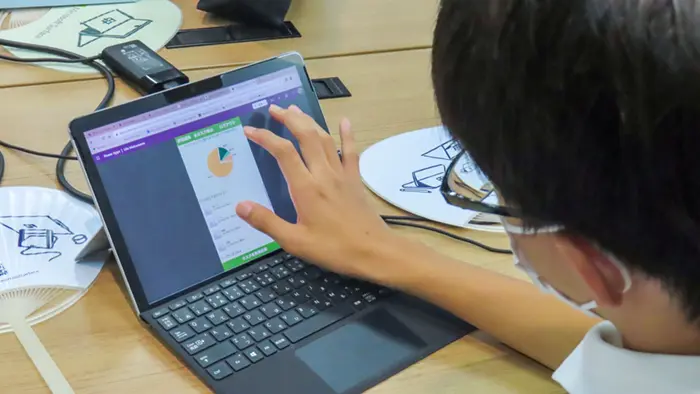
最優秀賞のチーム「くらげ」は、担任に勧められて参加したという都立晴海総合高校の1年生5人組。海が身近にあったことから、宿題などのタスクを達成していくとクラゲが育つアプリを考えた。将来的には、AIを利用してタスクを自動設定できるようにする構想も発表の中でアピールした。主にプログラミングを担当した笹子悠月さんは「PowerAppsはあまりコードを書く必要がなく、スライドをつくるような感覚で視覚的にプログラミングができるので、初心者でも使いやすい。むしろ、みんなでアイデアを考えることや、自分たちがやろうとしたことをどう伝えるかといったことの方が重要だと感じた」と指摘した。
ハッカソンを企画した都教委総務部の江川徹情報企画担当課長は「高校では昨年度から新学習指導要領への移行が始まっており、プログラミングが必修となった『情報Ⅰ』は、大学入試の科目に入る動きもある中で、『情報Ⅰ』で学んだことを発揮できる機会になればと思って企画した。中高生のアイデアは、われわれが当初想定していたものとは違っていたが、テーマの『青春』についてより自分自身の問題として彼らなりに考えていたのだと思う。われわれも生徒から学ばされた」と手応えを感じていた。