2月6日は「サーメの日」だった。サーメは、トナカイ遊牧の民として知られる北欧の先住民族である。今年も、1917年の同日に行われた初のサーメ集会を記念して、各地でサーメの旗が掲げられ、さまざまな催しが開かれた。
サーメが暮らす地域は現在、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、そしてロシアの一部である。サーメには、侵略や同化政策によって自らの言語や文化、アイデンティティーを失ってきた歴史がある。しかし、第二次世界大戦後の復興とともに、サーメに対する権利保障や教育制度が進められてきた。
特に、ノルウェーではサーメのための教育制度が整備されている。サーメの生徒のための「サーメ・ナショナル・カリキュラム」では、国のカリキュラムと同レベルの教育水準に加え、サーメ語やサーメ文化が各科目に盛り込まれている。このカリキュラムで教育を受けてきた若者たちが、サーメ・アイデンティティーを表明し、サーメ語を第一言語として活躍する地域が生まれつつある。

ノルウェー中央部に位置するスノーサは、人口が2000人ほどの小さな村である。もともとサーメが多く居住しており、南サーメ語を保護する特別な言語行政地区に指定されている。そのため、道路標識や看板、自治体が発行しているパンフレットなどには、全てノルウェー語と南サーメ語が併記されている。村のスーパーでも南サーメ語で書かれた陳列棚が見られた。
スノーサには、公立のサーメ学校がある。そこでは「サーメ・ナショナル・カリキュラム」を基に、南サーメ語の教育が行われている。また、最近では幼稚園でも南サーメ語を学べる環境が整ってきた。
現在21歳になるヨンマは、幼稚園に南サーメ語教育が導入された最初の学年の生徒だ。そのため、幼稚園から高校まで継続して南サーメ語や文化の授業を受けることができた。南サーメ語学習アプリを活用して、常にスキルアップもしてきた。彼女はその語学力を認められ、高校卒業後、ノルウェーの国営テレビ放送(NRK)の南サーメ局に就職が決まった。彼女は「私の第一言語は南サーメ語です!」と誇らしげに語る。
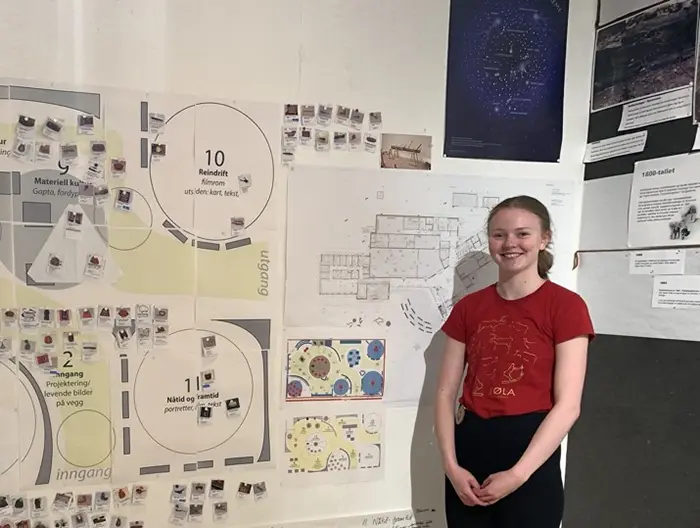
実は、幼稚園や学校で南サーメ語を学習し、流暢に話す子供たちを見て、その親世代が南サーメ語を学び始めている。言語継承の逆流現象と言える。
40代半ばのアンナ・リーサさんもその一人だ。彼女は、自治体が提供する成人対象の南サーメ語コースで学んでいる。理由を尋ねると、2人の娘たちが、自分を通り越して祖母(アンナさんの母親)と南サーメ語で会話をしているのを見てうらやましくなったからだと言う。
アンナさん自身も子供の頃サーメ学校に通っていたが、当時は今のように充実した授業がなかったそうだ。そのため、彼女は南サーメ語を理解はできるが、流ちょうには話せない。娘たちのように流ちょうに話せるようになりたい、彼女たちと南サーメ語で会話できるようになりたいと思ったことが、コース受講の大きな動機だそうだ。彼女のような動機で南サーメ語を学び始めている親たちが、最近は少なくないという。

南サーメ語学習者の動機には、言語継承という意味合いに加えて、就職のためという実利的な面もある。
スノーサの役場に設置されている言語教育センターのヴィーク理事長は、南サーメ語が必要な職場について次のように話してくれた。
「まずは、学校(小学校から大学まで)や幼稚園の教師。南サーメ語を話せる教師がまだまだ足りない。また、さまざまなサーメ組合団体、スノーサにあるサーメ複合文化センター、インターネットやメディアの会社にも南サーメ語話者の雇用の場が広がっている。役場も、南サーメ語の通訳や翻訳者を必要としている」
また、病院や老人ホームでも、南サーメ語が必要になるという。高齢者の中には認知症が進むと、子供の時に使っていた南サーメ語しか話さなくなってしまうケースがあるからだそうだ。
同センターでは、国による評価・認定制度を導入しており、コースを修了すると南サーメ語の資格が得られる。就職の斡旋も行っている。ヴィーク理事長によると、最近では、語学力に加えて、ジャーナリズム、グラフィックデザイン、インターネット技術、企画力などの技能のある人材が必要とされているという。現に、南サーメ語に堪能な若い南サーメの人たちが、自治体内のさまざまなクリエーティブ部門で活躍しているそうだ。
南サーメ語や文化に精通した若者に新しい雇用の場を提供しようと取り組んでいるスノーサ自治体と、南サーメ語に加えて、専門分野に特化したキャリアを持つ新しいタイプの“スーパー・サーメ”とも言えるような若者たちが、地域社会の活性化とサーメ語・文化の維持発展に相乗効果を起こしている。