「校庭で転んで足を擦りむいた」「ボールが鼻にあたった」「お腹が痛い」――、さまざまな症状を訴えて、ひっきりなしに子供たちが保健室を訪れる。「自分で傷を水で洗えるかな?」「ばんそうこうを貼ろう」「少しこのソファで休んでいこうか」などと子供たちの様子や症状を見て瞬時に対応していたのは、黒い医療用服姿の男性の養護教諭だった。東京都にある立川市立西砂小学校(丸山秀武校長、生徒729人)で保健室を担当している阿部大樹養護教諭は、全国的に数少ない男性の養護教諭の一人だ。「男性もきちんと保健室の仕事ができるのだということを証明していきたい」と力を込める。
阿部養護教諭が「保健室の先生になりたい」という夢を持ち始めたのは、高校時代だ。野球部のマネジャーとして、肩を脱臼した3年生のリハビリを手伝った。長く試合に出られなかったその選手が、最後の試合に代打として出場し、センター前ヒットを放った。その姿に感動した。「こんなふうに児童生徒の健康を支える仕事がしたい」と思った。
しかし、男性の養護教諭は「狭き門」だった。文部科学省の2022年度の「学校教員統計調査」によると、全国の小学校~高校と特別支援学校の養護教諭約3万4000人のうち男性は60人余りと、現在でも極少数だ。まずは養護教諭としてプラスになる看護師の資格を取り、医療の経験を積むことにした。
病院で看護師の仕事をしながら大学の通信教育で勉強し、2年かけて養護教諭の教員免許を取得した。その後、教員採用試験に臨んだが、「男性で大丈夫ですか?」などと聞かれ、男性であることをつらいと感じることもあった。それでも4回挑戦を続け、ようやく採用された。看護師になって7年がたち、30歳になっていた。「早く養護教諭になりたかった。その夢がかなってとてもうれしかった」
1校目は都立の特別支援学校で、女性の養護教諭との2人体制だった。養護教諭の大半は単数で学校に配置されるが、特別支援学校や児童生徒数の多い大規模校は複数で配置される。男性の養護教諭のほとんどは、全国的にみても数少ない複数配置校で勤務していた。「複数配置校だと自宅から遠くなるケースが多い。家庭の事情で、将来的に自宅近くの学校に勤めていきたかったので、単数配置校で仕事をしたいと思った」と阿部養護教諭は振り返る。
公募を受け続け、採用された学校は、離島にあった。3年間勤務し、学校評価の「学校保健に関する3項目」全てで、保護者から9割以上の支持を得て、自信を持った。
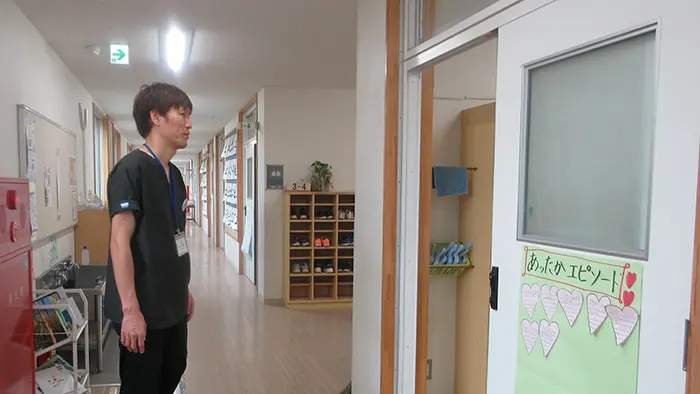
そして、2020年から現在の西砂小に勤務している。生徒数700人を超えるこの学校も単数配置で、保健室を一人で運営している。
男性の養護教諭だということで、「内科検診の時に女子児童にどう接するの?」とこれまでよく聞かれてきた。導き出した答えは、「男子と女子、どちらのプライバシーにも配慮する」だった。
それまで西砂小では健康診断の時、男子は上半身裸、女子は下着を外してTシャツのみ着用していた。学校医と相談した上で、男子もTシャツを着衣し、女子も下着を着用したままに変えた。また、学校医が検診しているところを他の児童が見聞きできないようにするため、パーテーションをして、次の順番の児童は距離を置いて待機することにした。そして、LGBTの児童がいるかもしれないことを考慮し、それまで男女別に実施していた検診を混合にした。
男子のプライバシーも保護しようと、それまで廊下から丸見えだった男子トイレの入り口にカーテンを設置した。また、全ての女子トイレに生理用品を置き、生理の仕組みなどを説明するポスターも貼って、その相談に女子が直接、保健室に来なくてもよくなる工夫をした。

保健教育の面でも改善を行った。それまで5年生の宿泊行事の前に、女子児童のみを対象に実施されてきた「宿泊前保健教育」を、男子も一緒に、混合で実施することにした。それぞれの体の仕組みや、性自認についてなども盛り込み、昨年度は産婦人科医を招いて講義してもらった。「誰でも得意なことと苦手なことはあり、自分の強みを生かしたいと思った。最も大切なのは、性別に関係なく、養護教諭としてどのような仕事をしていくかだ」と話す。
ある放課後、男子児童が担任の教員に連れられてやってきた。「頭を切っているみたいで、少し血が出ているんです」
「気持ち悪い? フラフラする?」。阿部養護教諭は傷の状態を素早く見て洗浄後、ガーゼをあてて包帯を巻いた。傷口を撮影した写真を児童に見せながら、「1、2ミリくらい切れているね。たぶん、縫わなくてもいいだろうけど、縫わなくてはという判断になる場合もあるし、病院に行った方がいいね」。保護者の迎えを待つ間、泣きじゃくる児童を優しく諭した。「泣いていたらきちんと診断が受けられないこともある。まずは落ち着いて」
「病院に行った方がいいような怪我は、月に2回くらい。それらの事例はICTを活用して、すぐに他の教職員と共有するようにしている」と阿部養護教諭はパソコンを開いた。どこでどのようにけがをしたのか、どう予防できそうかなどを写真とともにスライドにまとめてオンラインで発信し、重大事故の防止に努めている。

ほかにも、ICTを活用して保健委員会の児童らと熱中症予防や感染症対策に関する動画やポスターを制作したり、保健室の前に設置しているデジタルサイネージでそれらを配信したりしている。また、児童の欠席連絡を保護者がアプリを通じてできるようにし、教職員たちの朝の電話対応の負担を減らした。
「養護教諭として、教職員の仕事を減らす『働き方改革』にも貢献している」と西砂小の丸山校長は評価する。男性の養護教諭と仕事をするのは初めてで、最初は驚いたというが、「結構細かいところまで見てくれるし、看護師として養ってきた知識を生かして子供たちに適切な対応を取れているので、とても安心して任せられる」と信頼を口にする。今では、「今後も男性の養護教諭と仕事がしたい」と思うようになったという。

5児の父でもある阿部養護教諭を慕う児童も多い。昼休みに続き、放課後も、次々に子供たちが保健室に遊びに来た。「阿部先生はやさしい。けがをした時にしっかり見てくれる。髪の毛を切った時もすぐに気が付いてくれる」と女子児童。「保健室の守護神」「いつも笑顔で、『大丈夫?』って寄り添ってくれる」と男子児童たちも笑顔で口々に話した。
離島の小学校に勤務していた時、男子児童の一人が、将来の夢に「養護教諭」と書いた。自分の影響もあったのかな、と思った。「男性女性に関係なく、養護教諭っていいな、なりたいなと思う子がいたら、差別や偏見なく、なれる世の中になってほしい」と阿部養護教諭は願いを話す。
自身のこれからの目標は、「中学校、高校でも養護教諭をすること」。不登校になったり、いじめなどで自殺したりしてしまう生徒が増えていることに心を痛めている。「子供が好きだから、子供たちに苦しんでほしくない。あの高校時代の野球部でけがをして立ち直った選手のように、子供たちが元気に、笑顔になってほしい。そのための手助けができたら」と意気込む。
男性の養護教諭が世の中から認められ、より仕事しやすくなるように、自ら模範を示していきたい――。阿部養護教諭の挑戦は続いていく。