テレビ出演の傍ら大学やオンライン講座の講師を務めつつ、登録者2万7000人超のYouTube番組で動画配信し、「教育AI」を冠したイベントでは必ずと言っていいほど登壇する――。異色のキャリアを持つ元高校教諭・安藤昇さんは、さまざまなメディアを通じ最先端の情報を発信し続けている。青山学院中等部講師やスタディサプリ講師なども務める安藤さんに、インタビューの第1回では学習評価や調査書・推薦書の作成でAIを活用する方法などを聞いた。(全3回)
――今年2月の教育カンファレンスで、生成AIを活用して調査書などのたたき台を作る方法を解説されていました。いとも簡単に、教員が実際に書いたかのような文章が出来上がったので驚きました。
調査書や評価などに生成AIを使う理由は、「業務を効率化できる」という以外に、もう一つ重要なことがあります。評価については、人間だとなかなか難しい部分があって、どうしても結果だけを見てしまう傾向があるからです。一方で、生成AIを使えば評価に至る途中の過程や、生徒の普段の学び、日常生活などを踏まえた、本当の意味で的を射た所見文が書けるようになります。
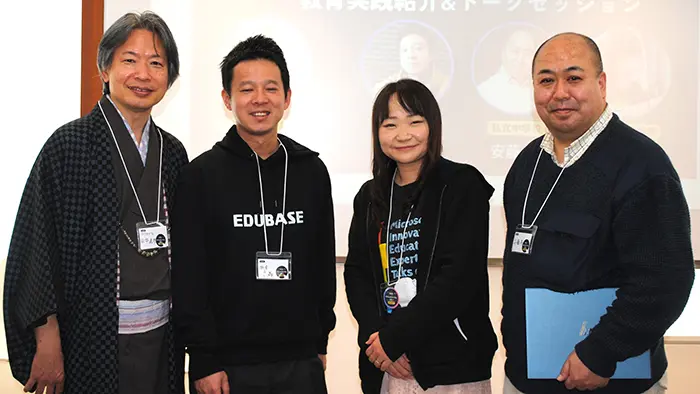
――確かに、これまでの評価は「成果主義」だという指摘がされてきました。
「成果主義」だった評価を「プロセス主義」にしていくことも、AIを取り入れるメリットの一つです。そうすることで、生徒も「自分の普段の姿をしっかり見てくれている」と感じられるようになります。また、AIを使えば「授業の中でどういった活動をしたか」「どのくらい努力して、どんな達成感があったか」を判断できるので、評価を踏まえた指導に変えていくこともできます。
――具体的にどのようにするのでしょうか。
1年間の記録をエクセルシートに残していきます。その際、項目を細かく分けて、例えば「基本情報」「学習態度」「学習成果」「強み」「成功」「改善が必要な部分」などとします。
そして、AIに示す手本として、それらの項目を基にしたレポートを1回作成します。その上で、このようなプロンプト(指示文)を入力します。
◇ ◇ ◇
# 対象: 小学校
# 作成するもの: 通知表の所見の200字程度の短い簡潔な文章
# 出力文: - [] 通知表の所見の内容 - [] {対象}の先生が生徒に語り掛けるような「~ですね」のような優しい口調 - [] {対象}の生徒が理解できる優しい文章 - [] 短所も肯定的にとらえてコメントをする
# 指示・目標: - [] GPTは{対象}の先生です。{作成するもの}を書くために入力文の内容から、制約条件に基づいた{作成するもの}の出力文を生成してください。
◇ ◇ ◇
これに続けて「# 制約条件」として、項目ごとに「学習態度と参加**: - 授業への参加度 - 課題やプロジェクトへの取り組み姿勢 - 学習に対する意欲や関心」などと細かく指示すれば、より精度の高い出力が得られます。
こうすれば、例えば200人分の生徒についてでも、エクセル上で一気に文章表記による評価ができるのです。
――今年2月の時点では、「今すぐは使えない」と話していました。
その当時のAIのバージョンでは、ハルシネーションを起こす状況があったので、生徒の1年間の記録を基に評価を書くには不安な状況もありました。でも、最近はだいぶ精度が上がってきたので、そういう不安もなくなってきました。AIに面談をさせて、それに対して調査書や推薦書を書くということもほぼできるようになっています。
――「面談をさせて」というのは、AIが生徒と面談をするのですか。
はい。通常、高校の先生方は毎年10月ごろ、大学の推薦書を必死になって書きます。そのために9月ごろから約1カ月かけてクラスの生徒一人一人と面談をするなどします。それを、AIがやるのです。
実際には、大学の総合型選抜や学校推薦型選抜を想定したものとして、AIの面接官を作るのです。例えば、私は日本大学の理工学部物理学科卒なので、そこをこれから受験するとしましょう。その場合、あらかじめ日本大学のアドミッション・ポリシーなどをAIの面接官に教えておきます。
実際に面接を始めると、AIが生徒にいろいろと質問します。例えば「志望動機」。それに対して、「自分は小さい頃からアインシュタインに憧れていて、相対性理論などの本に非常に興味を持ちました。それから自然現象にも興味を持つようになり、日本大学理工学部物理学科を志望しました」といった具合に、模擬面接のようなことをAIと生徒がやっていくのです。
これを生徒1人当たり30分くらいやったら、AIに「面接の内容をもとに、高校の担任の先生がこの子の大学への推薦書を出します。大学に合格するような素晴らしい推薦書を800字で作成してください」と指示します。これで推薦書のひな型ができます。
教員が書く推薦書だけでなく、「高校生が書く自己推薦書として作成してください」と指示すれば、生徒本人が提出する推薦書のひな型も作れます。同じデータを基に、自由自在に形を変えられるのです。すでに私が講師をしている青山学院の中等部や高等部でも活用していて、高く評価いただいています。
――通常は担任が30分ほどの時間をかけて生徒と面談し、字数を勘案しつつ30分から1時間ほどかけて作る推薦書のひな型が、数秒でできてしまうのですね。働き方改革がかなり進む印象です。
そうですね。AIを上手に使えば、業務の効率化ができます。でも、重要なのは実はそこではないのです。
調査書や推薦書などについて、「本当に人が書かなくていいのか」と言われることがあります。でも、私は教育の本質は生徒と共に歩むこと、共に教育活動をすることだと思っていて、決して「文章で何かを表す」ことではないと考えているのです。
私は佐野日本大学高校で30年教員を務め、部活動の指導にも力を入れてきました。「体育系と文科系の両方で、顧問をする部を日本一に」という目標を掲げて指導し、実際に体育会系は剣道部がインターハイ個人優勝、団体3位の成績を残しました。
文化系で顧問をしていた放送部は、NHK放送コンテストなどでいつも決勝まで行くものの、残念ながら準優勝止まりでした。このように教員として30年間、毎年合宿などで生徒と共に話し合うなどして、日本一の部を育てようと取り組んでいました。
――そのようにして生徒と共に歩むのが教育の本質、と考えているのですね。
大学合格のための推薦書は教育の結果でしかなく、3年間の全てではないと考えています。ですから、なるべくそんなことには時間をかけず、事務的な作業などは全部コンピューターやAIに任せて、生徒と共に学び合うことに時間を割くのがいいと考えています。

【プロフィール】
安藤昇(あんどう・のぼる) 青山学院中等部講師、青山学院大学非常勤講師、スタディサプリ講師。BS日テレおよびネット番組Huluにて配信中のプログラミング教育番組の講師を務める。元佐野日本大学高校教諭、2019年に上京し現職。AI活用に関連した講演を多数実施している。自宅のスタジオにはプロ並みの配信機材を備え、「テクノロジーで教育を楽しくする!」をテーマに発信するYouTubeチャンネル「GIGA ch.」の登録者数は2万7000人に上る。前任校で顧問を務めた剣道部が全国優勝したほか、放送部が県大会14連覇、NHK杯全国大会準優勝2回の実績を残した。