面白過ぎる教員生活を送るための仕事術について、多くの著書を刊行してきた現役公立小学校教員の森岡健太教諭。「SNSやメディアによって『学校=ブラック』のイメージが浸透してしまっている」と語る同教諭に、インタビューの最終回では教員生活を「楽しい」と言い続けるための極意、森岡健太流の問題解決方法を聞いた。(全3回)
――「おもしろすぎて」というシリーズで著作を出されているのがよく分かるくらい、森岡さんの話からはご自身が楽しんで教職をされている様子がうかがえます。教員生活を「楽しい」と言い続けられる極意は、どんなところにあるのでしょうか。
教育の面白いところは、やったことがすぐ結果として、子どもの新たな姿となって返ってくるところです。
もちろん、うまくいかないときもあります。そういうときは仕事をミッション化します。例えば、指導案を書く場合は「何分で完成するか試してみよう」などと考えながら作成します。あとはハードルを下げること。一つの指導案を一気に完成させるとなったら気が重いので、「今日は1ページ目の上半分だけができたら合格」などと決めて作成します。そうやって小さな喜びをたくさん積み重ねるようにしたら、楽しくできると思います。
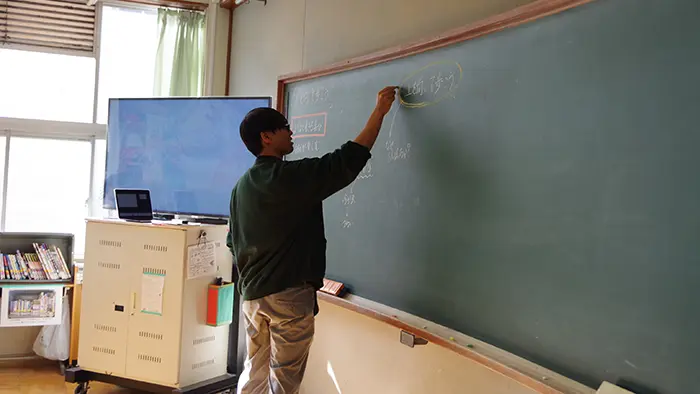
――「今日中に終わらせる」などと生真面目に考えず、柔軟にスモールステップで進めていくというのは、働き方として効果がありそうですね。
そうですね。若手の頃は、夜8時とか9時まで学校に残っていることもありました。当時は問題意識も持っていなかったのですが、コロナ禍で働き方を見直そうという声が出てきた中で、「どうやったら効率良くなるのだろう」と考えるようになりました。
――業務効率化を進める中で、「教員なら長時間、学校にいるべきだ」などと批判されることはなかったですか。
確かに「こうすると効率がいいですよね」と言ったら、「教育に効率を求めてはいけない」と怒られたことはあります。当時は「そうか、効率化よりも子どものために頑張らないと駄目なのだな」と思いましたが、教師だって自分の人生や生活があるわけです。だから効率化は必要だと思うようになりました。
――「こんにゃくメンタル」を提案されている森岡さんならではですね。そういった柔軟性を支えているのは、どんな思考なのでしょう。
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という言葉をいつも心にとどめています。保護者とのトラブルも研究授業も、働いていて嫌だと思うことは誰にだってあります。でも、どんなに嫌だと思っている時間も必ず終わるし、終わってしまえば別にどうってことはないのです。
学校はありがたいことに1年たったら変わるのです。どれほど大変な状況になっても、学級崩壊が起きても関係性が悪くなっても、1年たてば年度が替わり、新しい気持ちで始められます。「いつか終わりが来る」わけです。
――教員不足や教員採用試験の倍率低下などが起きている中で、森岡さんのように「教員は楽しい」と発信している先生がいるのは心強いことです。
確かに長時間労働という実態はありますが、それがメディアを通して受け手に届くまでに、ブラックな部分がより凝縮されているように感じます。
例えば、SNSでは「学校がブラックでしんどい」といった投稿に「いいね」をしたら、それに関連する「学校=ブラック」的な投稿が表示されやすくなるのです。そうするうちにタイムラインが「学校=ブラック」で埋まってしまいます。
テレビなども同様で、例えば私の勤務校では、午後6時ごろにはほぼ全員が帰宅していますし、常に雑談や笑顔があります。ごく一般的な学校です。そういう学校も多いと思うのですが、決してメディアでは放送されません。「教員が和気あいあいとやっています」なんて学校は放送されず、大変な学校や先生ばかりがピックアップされ、発信されているのです。
――確かに以前、テレビ番組で「小学校の先生が給食を1分で流し込んで仕事をしている」といったことが報じられ、SNSでも話題になっていました。
実際には、かなりまれな例だと思います。うちの学校で言えば、今日の昼休みは半分近くの先生が職員室に戻ってきて、自分のお子さんの話なんかをしていました。
もちろん、子どもと関わるのが好きで、ドッジボールをしているような人もいますが、絶対にしなければいけないということはありません。

――森岡さんの話からは、学校での楽しい様子がうかがえます。日常的にさまざまな問題も起きていると思いますが、自分なりの解決方法も見いだされているのではないでしょうか。
そうですね。道徳の研究をやってきたからかもしれませんが、問題が起きたときはまず、「なぜだろう」と考える習慣が付いています。
例えば先日、若手教員のクラスに入ったとき、教室にごみが落ちていたのです。それを見て、「落とさないよう注意した方がいいよ」「拾うように指導してね」といった声掛けをしても、本質的な問題は解決しません。
そうではなく、「どうしてごみが落ちているのだろう」というところに目を向けると、もしかしたら先生が忙し過ぎて、ごみが落ちている状態に気が付かないのかもしれません。あるいは、先生は指導していたのに、子どもが聞き入れない状況があって、先生が諦めているのかもしれません。
いろいろな要因があるはずだから、その部分を考えていくことが大事で、そうやって考えた後に次のステップとして、その先生と対話をするのがよいと考えています。
――さまざまな事象を冷静に分析するタイプなのですね。道徳の研究をしてこられたからとのお話でしたが、それだけではないように思います。
趣味が囲碁だというのも大きいかもしれません。家族の影響を受けて子どもの頃から将棋が好きだったのですが、中学生になってからは漫画のブームもあり囲碁にはまりました。
囲碁の世界は、「自分がこう打ったら、相手がこう来る。だから、次はこう打つ」といったことの連続です。そういう思考の癖がついているのかもしれないですね。
それと、囲碁に「布石を打つ」という言葉があります。これを学級経営や授業に当てはめると、「こういう種をまいておいたらどうなるか」ということになります。
だから、年度の最初のうちは、多少授業の進度が遅れても、聞く力を伸ばすことや基礎的な生活習慣を付けることに時間を割きます。それが後々、絶対に意味を持つと分かっているので、布石を打っているわけです。
そうやって先を見据えていると、後になって時間が生まれます。そういったことの積み重ねが、余裕があって楽しい教員生活につながっていくのではないかと思っています。
【プロフィール】
森岡健太(もりおか・けんた) 京都市立小学校教諭。主な著者に『おもしろすぎて』シリーズがある。SNSで道徳と学級経営のことを発信。指導書の執筆や教育誌の連載を手掛ける。近著は今年6月刊行の『授業づくりが楽しくて仕方なくなる森岡健太の道徳板書』(明治図書出版)。