「教員が自分の体裁のために動くようなら、活力ある新しい学校としての意味はない」と力強く語るのは、広島県立広島叡智学園中学校・高校の福嶋一彦校長。瀬戸内海の小さな島に新設された全寮制の国際バカロレア認定校(IB校)で、開設2年目から学びの変革をけん引してきた福嶋校長に、「離島にある公立のIB校」ならではの難しさや課題解決の方法を聞いた。(全3回)
――学習指導要領改訂の時期に新しくできたこの学校が、IBのフレームワークにぴったりだと思ったとのことですが、具体的にはどういうことなのでしょうか。
私は日本のよき文化を大切にしながら集団行動を重視する学校に勤務したことがあります。その学校には全校生徒が800人以上いましたが、「体育館に入る時にはシューズが1センチたりとも乱れずきれいに並んでいるように」とか「校長が登壇する時にはコトリとも音がしないくらい静かにしているように」という感じで、礼節を非常に重んじる学校でした。
この学校は逆ですね。180度違っています。全て子供に判断させる。特にIBはヨーロッパでスタートしたものなので欧米型の学習のスタイルで、自分で課題を見つけて自分で取り組んでいきます。そういう学びというのは、われわれが思う以上に、子供が興味関心のあることをどんどん深めて行くんです。これは私にとって、今までの学校では経験したことがない子供たちの学びの姿でした。
子供たちは本当に自由に学んでいます。ある子はソファーに座ったままレポートを書いている。ある子は芝生の上で楽器の練習をしている。いろいろなことをやっています。
ただ一方でネガティブな面で言えば、来客時に日本の礼節を踏まえた対応をしているかというと、生徒たちはフランクな対応をしますので、見方によっては「行儀が悪い」と捉えられるかもしれません。日本が本来持っている、日本らしい良さの部分については、課題があるかもしれませんね。いろいろな見方はあると思いますが、この学校でわれわれがやりたいと考えていることとIBのスタイルは、今は合っていると思っています。

――生徒の主体性を大事にすると、従来型の学校の観点から批判が起きるというのは難しい問題ですね。
縛る方が簡単なんですよ。自由にさせる方がリスクは伴いますし、コントロールが難しくなります。
校則一つを例にしても、IB校の特性でもあると思いますが、この学校では自分が納得しないと前に進まないんです。「校則だから守りなさい」ではなく、「この校則はこういう理由があるから、必要だと皆で決めた規則だから守ろう」と言ったら、「分かりました」となりますが、例えば「上に着るのは白のシャツじゃないと駄目です」などと言ったら、「その必然性がないじゃないですか」と言って絶対に聞き入れません。
もちろんまだ判断の軸も発達段階にある子供ですから、こちらが譲れない部分はあります。だから、いろいろなことを子供たちに決めさせているとはいえ、本当に「GO」を出すには校長が認めないと駄目だということを教員には伝えています。
でも、実際にそこまで行くほどもめることはほとんどなくて、たいていのことは全て子供と教員の間で決めて動いています。ただ、それでいいのかという評価を受けるのはこれからでしょうね。
――「もめることはほとんどない」とのことでしたが、うまく収まらずに生徒が反発したということはありましたか。
大きな反発ではないですか、最初に入学した1期生が高校1年生になった時、それに近い出来事がありました。
本校は中学の定員が40人なのに対し、高校は1学年60人です。その差の20人分の出願資格があるのは、「日本以外の国籍を有している」か、「日本国籍しか持っていないが、海外での就学経験が5年以上あること」なんです。それと第2言語は英語と決めていますので、英語について一定以上のスキルを有していることというのが出願の要件です。
ちょうど1期生が高1になった時は、まさにコロナ禍のピークで、海外から日本に入るのは難しく、何とか入国して入学できたのは10人でした。その子たちは英語が母語でしたが、実はこの学校の教職員も全員がバイリンガルというわけではなく、日本語しか分からない教員もいるので、日本人の生徒が、ボランティア的に通訳をしながら、留学生たちの支援をしていました。
そうしたらある時、職員会議をしていたところに、生徒が「ぜひ校長先生に聞いてもらいたいことがある。意見させてください」とやってきたんです。「留学生の支援で自分の勉強に身が入りません。トランスレーションにも疲れました。何とか助けてください」という訴えでした。
それで解決したかと言うと、われわれが何かをできたわけではないのですが、教員も一緒になって悩みながら、子供たち同士でもいろいろ悩んで、留学生が日本語を早く覚えられるように支援しながら、少しずつうまく行き出しました。
――新しい学校を、子供たちと教員が一緒に悩んで試行錯誤しながらつくり上げてきたのですね。
それもありますね。ただ、子供たちと教員だけでは難しい、この学校ならではの要因があります。
この学校がある大崎上島は、橋が架かってない離島なんです。コンビニエンスストアもありません。人口も7000人をきっており、いわゆる超高齢化の島なんです。こういう島の全寮制の学校ですから、子供たちは同じメンバーで24時間ずっと一緒です。路線バスも1時間に1本あるかどうかというところで、同じ環境の中にずっといるのはフラストレーションになったり、学びに対するモチベーションが上がりにくくなったりするということがあります。
こういう環境だから、外のリソースを使って子供たちに刺激を与えるというのは絶対に必要だということは、ずっと考えていました。実際に大きく動き出したのは着任して3年目からで、特に海外からの刺激を取り入れる取り組みを始めました。
というのは、この学校はIB校で、英語にかなりウエイトを置いているから、海外に出ていくことに対して子供たちのハードルがものすごく低いんですよ。たくさんの生徒が海外の大学に行きたがっています。
そうした海外の大学へ行くための進路指導についても、われわれが手探りでやらなければいけないことは分かっていました。そして、子供たちの心を動かさなければ進路活動をさせても意味がないとも思っていたので、大学訪問ツアーの計画を3年前から立てて、昨年度から行き始めたんです。
ヨーロッパではオランダ、ドイツ、ハンガリー。アジアではマレーシア、タイ、台湾。これらの国の大学への訪問を実施しました。そうしたら子供たちのモチベーションはずいぶん変わりましたね。
――身近な上級生がそうやって動いているのを見たら、下級生の意識も変わりますね。
そうですね。下級生に関して言うと、大学の進路となると高校にウエイトが置かれがちですが、中学校段階でも何か刺激を与えてあげなければということで、今年度からはフィジーとフィリピンのセブ島での語学研修を夏に組みました。
セブ島には英語力が初歩レベルの子を、フィジーにはそれよりレベルが上の子をという分け方をしましたが、ただ語学研修だけというのではもったいないから、現地の文化を学ばせようと、いわゆるゴミ山で生活する人たちとの触れ合いの場を持たせるといった体験なども随所に組んでもらって、これが中学生にとっていい刺激になったようでした。

――海外でのさまざまな学びができて、生徒も保護者も、IB校に入学したからこその良さを実感できたのではないでしょうか。
そうですね。ただ、IB校はインターナショナルスクールが多く、インターナショナルスクールは年間の授業料だけで150~200万円程度かかります。それに対し、この学校は県立の学校ですから、中学校は義務教育なので授業料はいらない。高校でも月額9900円で、保護者の経済状況によっては高等学校等就学支援金の対象となることもあります。本校においては、一般的な経済力の家庭の子がほとんどです。
そして、専門のエージェントを利用してヨーロッパの大学訪問をすると、100万円近い費用がかかることになってしまいます。それでは参加できないという家庭もあるので、本校では教員が手作りで企画し、実施しました。飛行機も比較的安価なものを利用するなどいろいろな工夫をしながら、一人当たりの料金を一般的な旅行よりかなり安くしました。
――節約のために、エージェントに一切依頼せず、先生方が全ての手配をしたのですか。学校としてのノウハウもない中、大変だったのではないでしょうか。
そうなんです。特にヨーロッパ方面で大学訪問をする際は、エージェントが入れば全部やってくれますから、お金は必要ですが手間はかかりません。だけどそうしてしまうと、どの大学とどんなつながりを持つかという海外訪問の重要な部分が、いつまでもエージェント次第になってしまいます。
本校の教員が大学と直につながらないと意味がないという考えは、われわれの間にずっとありました。本校の教員にも英語が堪能な者は何人もおりますので、メールのやりとりやZoomを利用しての打ち合わせもしながら、いろいろな大学の手応えを感じて、関係性を作って、綿密に準備を重ねました。
このように、この学校の子供に合った学びを目指して草の根的に積み上げてきたことが、完成までは至っていないにしても、具体的なアクションになっていますし、子供への刺激やモチベーションの向上にもなっていると手応えを感じているところです。
中学2年生の始めに実施しているインターンシップについても、来年度に向けて教員に検討をお願いしています。
これまでは島の中の事業所でインターンシップを実施してきましたが、その狙いである勤労観や職業観の育成、働いてくれている保護者の方への感謝に本当につながっているかという疑問が、ずっと私にはあったんです。島の事業所の方は優しく生徒に対応していただいて、本当に感謝しています。一方で、インターンシップでは生徒にもっと働くことの大切さや営利を伴う活動の苦労や大変さなどを、もっと体感させることが必要ではないかと思っていました。
来年度からは、生徒たちの活動の場を広げ、島内だけではなく日本全国どこへでも行けるようにと、教員が具体的に計画を進めてくれています。「中学生にそこまでやるの」と言われるくらいダイナミックなことをしていかないと、のどかなところにある学校だけに、子供に刺激を与えたり、学びに向かうモチベーションを維持向上させたりすることはできないと思っています。
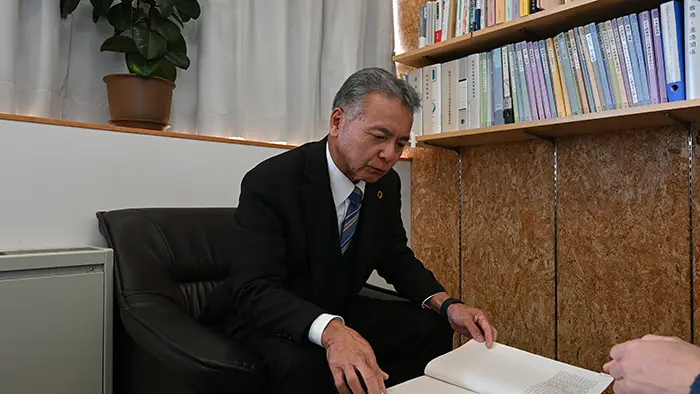
【プロフィール】
福嶋一彦(ふくしま・かずひこ) 広島県立広島叡智学園中学校・高校校長。広島県三次市出身。1985年度から広島県立高校教諭。98年度から県教育委員会指導主事。2003年度に文部科学省初中局参事官付産業教育係。04年度から広島県教育委員会指導第二課専門員等。15年度に県教育委員会管理部教職員課長。18年度に県立西条農業高校校長。19年度に県教育委員会教育部長。20年度から現職。