2025年度がスタートした。この1年の教育に関する私の最大の注目点は、生成AIの影響である。生成AIに関しては、文部科学省が昨年12月に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」のVer. 2.0を発表しており、今年3月下旬には26年度から高校で使用される教科書で生成AIが多く扱われていることが報じられている。
生成AIの学校での活用に関しては、本欄で昨年10月にも取り上げたが、その後の状況の変化もあるので、改めて今回、生成AIについて取り上げたい。というのは、ガイドラインや教科書も追い付きにくいくらいに、生成AIの機能向上が急速に進んでいると考えられるからだ。
23年ごろは、ChatGPTなどの生成AIが小中学生でも分かるような間違い(ハルシネーション)を起こすことが多かった。科学的な事実や歴史・地理に関する知識、簡単な計算問題などについて、生成AIが誤情報を出力することが多く見られた。
しかし、24年後半くらいから、誤情報の出力は限定されるようになった。生成AIがネット検索機能を備えるようになり、インターネット上で簡単に検索して答えられるような問いに対しては、誤情報の出力はあまりなされなくなった。それでも、日本語での数に関する処理(例えば、「9.11と9.9のどちらが大きいか」、「整数123,456,789を日本語でどう読むか」といった問いへの回答)や、文字の入った図における文字の出力(図1のように実際にはない文字が書かれてしまう)に問題が見られた。

だが、25年3月までに、こうした問題はほぼ解消した。ChatGPT-4oで、「9.11と9.9のどちらが大きいか」、「整数123,456,789を日本語でどう読むか」といった問いに対しては適切な回答がなされ、図の中の文字も図2のように実際の文字になっている。

生成AIの機能改善は、ハルシネーション回避にとどまらない。25年になって、ChatGPTをはじめとする多くの生成AIに「ディープ・リサーチ」と呼ばれる機能が追加された。これは、生成AIが数分の時間をかけて多くのサイトを調べ、詳細な報告を作成する機能である。例えば、図3のような報告が出力される。
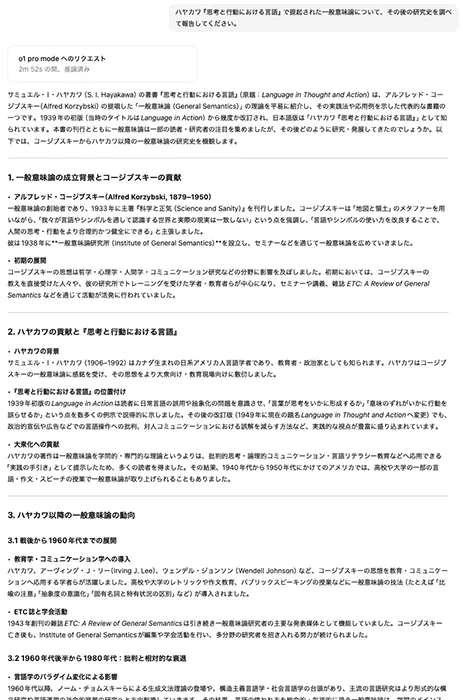
もちろん報告されている内容が事実か否かについては確認が必要であるが、物事を大まかに理解するにはかなり有用である。
他にも、例えば次のような使い方が可能である。
・行いたい授業の概要(授業の目的、使用する教材、対象学年、時間数など)を入れて、学習指導案のたたき台を作ってもらう。
・学習指導案を入れてどのような授業になるかシミュレーションしてもらい、架空の授業記録を出力してもらう。
・ゲーム型の教材のルールなどを入れて、各プレーヤーが最善の行動をした場合にゲームがどのように進むかを説明してもらう。
・思い付いたアイデアについて、関連する研究や議論の有無を出力してもらう。(例えば、ミツバチの活動を経済と捉える研究はあるかと問うたら、社会生物学や生態学の研究、人間社会の「ミツバチモデル」の研究などがあるという回答が得られた。)
・子どもになったつもりで特定の概念について生成AIと対話し、その概念の教育における扱いについて示唆を得る。(例えば、「お金って何?」という話を幼児の立場で問い、回答に対してさらに疑問を投げ掛けるという対話を行うことで、お金が価値の尺度や交換の手段であるというだけでなく、幼児にとっては計算や判断のトレーニングの機会となったり、社会的ルールの理解の促進につながるものであったりするという示唆が得られた。)
すでに生成AIは、人間が思い付く疑問に対して、集合知(インターネットで検索可能なあらゆる情報)に基づく暫定的な解を瞬時に提供するツールとなっている。もはや私たちは、さまざまな課題に対してゼロから考える必要はなく、かなり使えるレベルの暫定的な解を横に置いて考えることができる。
ChatGPTを提供するOpenAI社は、AIの発展を次のように5段階で示している。
レベル1:チャットボット、会話言語をもつ AI
レベル2:推論者 (Reasoners)、人間レベルの問題解決
レベル3:エージェント、行動を起こせるシステム
レベル4:イノベーター、発明を支援する AI
レベル5:組織 (Organizations)、組織の仕事ができる AI
現状のChatGPTはレベル2に近づいているとされており、これは博士号レベルの教育を受けた人間と同等の問題解決ができるレベルと説明されている。だとすれば、私たちはあらゆる分野の専門家に取りあえず相談ができる状況にあるとも言える。一人で学んでいても、私たちは決して孤独ではない。知りたいことがあり、粘り強く生成AIとやりとりする根気と言語能力とがあれば、中学生や高校生であっても短期間で高度に知的な活動を行うことが、すでに可能である(中高生が生成AIを駆使して携帯電話回線を大量に不正契約して売却した事件は、このことの悪い象徴であろう。)
25年度は、このように生成AIが進化しつつある中で、教育の在り方が改めて問われる1年間となるだろうし、そうしなければならない。学校が何もしなくても、検索サービスやスマートフォンの基本ソフトに生成AIが組み込まれるなど、多くの人が意識せずに生成AIを日常的に使う状況が始まっている。きっと多くの子どもたちは「AIを使えば何でも分かるのに、なぜ自分が学ばなければならないのか」と疑問を抱くだろう。だからこそ私たちは、人間にしかできないであろう「問いを生む力」「価値観の形成」「創造的な思考」といったものをいかに育てるかを、具体的に議論し、実践に生かしていく必要がある。