ゴールデンウィークは、しっかり余暇を楽しめているだろうか。近年、若い世代を中心に仕事や子育てだけでなく、休日などの余暇の過ごし方を重視する価値観が広がっている。そうした中、静岡大学の塩田真吾准教授はヤマハと共同で「人生を楽しむための余暇図鑑」を開発した。ヤマハで働く社員のさまざまな余暇の過ごし方を通してキャリアを考えられるユニークなサイトとなっている。さらに塩田准教授は、千葉県柏市教育委員会ともタッグを組み、「教員のライフキャリア図鑑」を制作。学校以外で教職員が夢中になっていることを紹介しており、教員の仕事以外のプライベートな側面から、教職の魅力を伝えている。
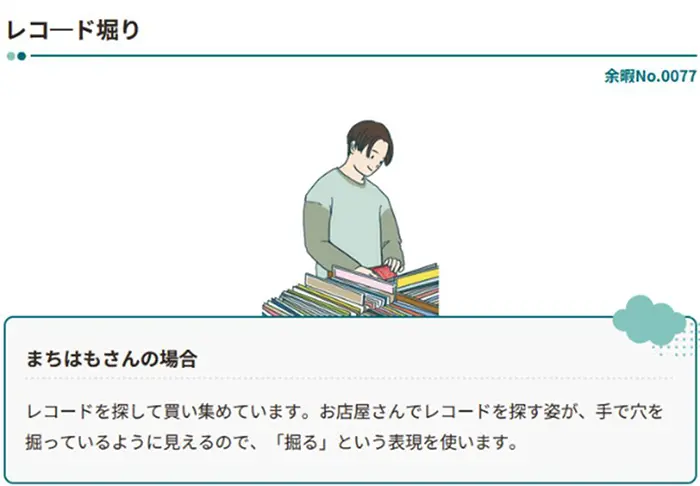
1人バンドや自動車の改造・修理、競技麻雀の鑑賞…、余暇図鑑のサイトには、「本当にそんな趣味があるの?」と興味を引かれるものから、料理やドライブ、ランニングなど、子どもでもイメージしやすいものまで、約100人の多種多様な大人の余暇の過ごし方がずらりと並ぶ。
載っている余暇には、物珍しいものや高尚とされているようなものだけでなく、ちょっとした隙間時間にお金をかけずにできることもある。例えば、音楽鑑賞にしても、生演奏を聞きに行くのが好きなのか、部屋で聞く際の音響機器にこだわっているのかなど、幅を持たせている。いずれも、募集に応じた実在するヤマハの社員のエピソードで、その趣味とは具体的にどんなものなのかや、打ち込むようになったきっかけ、その魅力がインタビュー形式で語られている。
趣味そのものの面白さはさることながら、余暇の過ごし方を切り口に、その人の生き方や考え方を深掘りしていくのが特徴だ。
同社の飯塚茜さんは「大人になると仕事をしなければいけない。子育てもしなければいけない。そんなマイナスのイメージではなく、『大人って楽しい』ということが伝わって、将来はこういう人になりたいと思ってくれたら」と、余暇図鑑に込めた思いを語る。
余暇図鑑は小学校高学年以上を対象にしており、学校のキャリア教育の授業で使うことを想定したワークシートも用意した。子どもたちは興味を持った余暇の過ごし方から見てもいいし、自分がやっていることと同じような趣味や、いつか大人になったらやってみたいことから選んでみてもいい。カテゴリーやタグ付けされたキーワードから探すこともできる。そこから自分の好きなことを掘り下げたり、余暇も含めたキャリアイメージを膨らませたりする。
しかし、どうしてキャリア教育で「余暇」に着目したのか。その理由を塩田准教授は「キャリア教育は仕事について学ぶだけでいいのか。仕事だけではなくて、人生を楽しむことも必要だ。それから、われわれも子どもの余暇を調査したが、スマートフォンで完結してしまっていることが多く、そもそも余暇の種類が少ない。それを踏まえて、仕事だけではなくて人生全体を楽しむことを学べる図鑑をつくろうと考えた」と説明する。
協力したヤマハは、楽器や音響機器を製作し、余暇とも密接に関わりのある企業だ。次の世代である子どもたちが余暇をどのように捉えているのかを知ることは、企業としてどのような価値を提供できるかを考えることにもつながるとして、この余暇図鑑の制作に取り組んだという。今後、他の企業にも呼び掛け、紹介する余暇の過ごし方も充実させていく予定だ。
ところで、この余暇図鑑はヤマハ社内でも話題になったそうで、子どもだけでなく大人も見て楽しいものとなっている。もしも就職活動中の学生の目に留まれば、その企業に対して好感を持つきっかけになるかもしれない。
そこに目を付けた塩田准教授は、柏市教委と連携し、「教員のライフキャリア図鑑」を制作した。
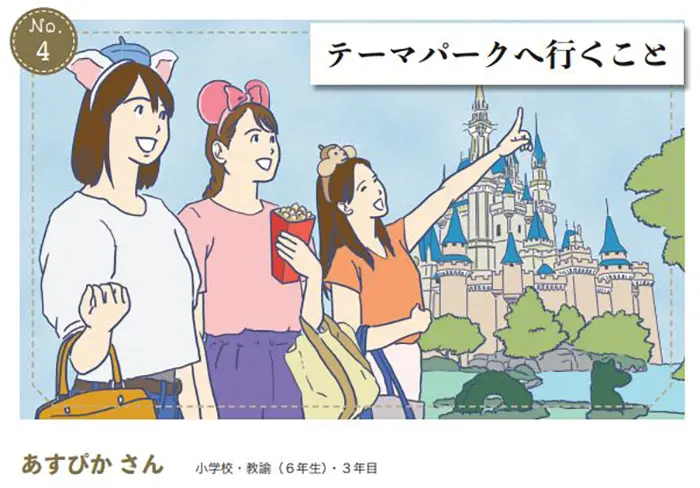
「教員について考えてみると、これまでは『教師ってこんなにいい仕事ですよ』と、教職そのものの魅力しかアピールしてこなかった。もっとライフキャリアを推していかないと、学生をはじめ若い世代には響かないのではないかと感じていたので、提案した」と塩田准教授。実際にライフキャリア図鑑を開いてみると、テーマパーク巡りやプロ野球観戦といった休日の趣味から、社会貢献活動、楽しみながらの子育てなど、学校では普段知ることのない教職員の一面が紹介されている。
若い世代をターゲットにはしているが、年代は若手からベテランまで幅広く、最後に同世代へのメッセージもある。教員だけでなく、学校事務職員などの事例も載っている。
昨年度まで市教委の教育研究所所長としてライフキャリア図鑑の作成に携わった金岡幸江柏市立柏第二小学校校長は「子育て世代の先生も何人か出ていて、その先生たちの工夫を読むと、『自分の頃はそんなふうにできなかったな』と思ったり、みんないろいろなことをやっていたりすることに気付く。こういうことを話題にするだけでも学校の中でさまざまな話ができて、同僚性が広がっていくと思う」と話す。
ただ、炎上してしまった文部科学省の「#教師のバトン」プロジェクトのように、教員の長時間労働が社会課題となる中で教職の魅力を発信した結果、「現実は忙し過ぎてこんなふうに楽しめない」などの声が上がれば、逆効果となりかねない。
その疑問に市教委の平野秀樹学校教育部部長は「確かに『そんなこと言ったって…』と思われる懸念はあるが、柏市は全国に先駆けて部活動の地域展開に取り組むなど、学校の働き方改革を推進してきた自治体なので、比較的受け入れてもらえる風土はあるのではないか」と答える。その上で平野部長は「単に早く帰れるようにする働き方改革ではなくて、教職を含めた人生全体を充実させるような働き方改革を進めていこうというメッセージになれば」と期待を寄せる。
塩田准教授は「よく教員は忙しいから何もできないと言われる。教員の仕事には終わりがないので、ある程度区切りをつけていくしかない。その区切りをどうつけるかというときに、やりたいことがある程度決まっていないと、いつまでも仕事をしてしまうのではないか。区切りをつけるためにも、やりたいことが決まっていた方が働き方改革もしやすいのではないか」と呼び掛ける。
柏市では、このライフキャリア図鑑を教員研修などで活用していく方針で、教員志望の学生への配布なども視野に入れる。
ライフキャリア図鑑は学校と企業の連携を支援する「プロフェッショナルをすべての学校に」のサイトで見ることができる。
【キーワード】
キャリア教育 人が生涯を通じてさまざまな役割を果たす中で、自らの役割の価値などを見いだし、積み重ねていくキャリア発達を促す教育。社会的・職業的な自立に向けて必要となる能力や態度を育てることを重視しており、扱われるテーマは就職や進学だけではない。