教員不足が深刻さを増している。各自治体では、教員免許を有しながら教職に就いていない「ペーパーティーチャー」を対象としたセミナーなどを開催しているが、果たして教員になる人はどのくらいいるのだろうか。今年度当初に、82人のペーパーティーチャーが任用されるなど、成果を上げている埼玉県教育委員会の取り組みを取材した。
今、学校現場で起きている教員不足の構造的な要因には▽大量採用により20~30代の教員が増加し、産休・育休を取得する教員が急増していること▽あらかじめ学級数の見込みを立てにくい特別支援学級数が増加していること▽既卒受験者の正規教員としての採用が進み、臨時的任用教員のなり手が不足していること――などが挙げられる。
こうした教員不足を解消するカギとして期待されているのが、「ペーパーティーチャー」の存在だ。
2022年7月に改正教育職員免許法が施行され、教員免許更新制が廃止されて以降、各自治体ではペーパーティーチャーを対象としたセミナーや研修を開催し、採用試験への挑戦や、講師登録を勧める動きが強まっている。
文部科学省の調査によると、23年度に現職以外の教員免許保有者向けの研修などを実施したのは50自治体、実施していないのは18自治体だったが、24年度については58自治体が「実施する予定あり」、10自治体が「実施する予定なし」と回答している。
そうした中、ペーパーティーチャーの任用に成果を上げているのが埼玉県だ。
同県では、22年度から「ペーパーティーチャーセミナー」をスタートさせた。22年度には3回のセミナーを実施し、翌23年度当初に24人が任用された。23年度には7回セミナーを実施し、計226人が参加。そのうち122人が講師登録し、24年度当初から53人が任用された。
24年度はさらにセミナー回数を増やし、9回実施。参加者総数は273人で、そのうち137人が講師登録し、今年度当初から82人が任用され、県内各校で勤務している。
年々、講師登録者や任用の増加につながっているのは、同セミナーのブラッシュアップにある。同県教委の担当者は「まず不安を払拭して、教員の仕事への興味を持ってもらうことからだと思っている。主体的に参加してもらえるよう、体験活動も増やしている」と説明する。実際にどのように行われているのか、セミナーに足を運んでみた。
5月下旬、同県川口市内の会場では、今年度1回目となるペーパーティーチャーセミナーが開かれていた。例年、9月以降にセミナーをスタートさせていたが、今年度は実験的に早い時期から開催することにしたという。
この日は10人ほどが参加していた。「支援員をやっているうちに、もっと深く関わりたくなった」「今の仕事は全国転勤のある仕事だが、地元に根付いた仕事がしたい」「定年後、学童保育で支援員をしているうちに、家庭環境などによる子どもたちの学習格差を何とかしたいと思った」「子育ても落ち着いたので、何か役立つことをしたい」――。志望動機や年齢層もさまざまだ。
セミナーが始まった。教員として任用されるまでの流れや、さまざまな勤務形態がある非常勤講師、給与や休暇などの福利厚生について一通り説明があった後、「今の学校」がどうなっているのかが①主体的・対話的で深い学び②1人1台端末の活用③個に応じた指導・支援――の3つの視点で紹介された。
実際の授業の様子などが動画で流れると、熱心に見入る参加者たち。また、セミナーの後半には、参加者が生徒役になっての模擬授業体験や、子どもたちが使っている端末を実際に触りながらのICT機器操作体験、日本語指導体験も行われた。
特にICTの活用についてはハードルの高さを感じるペーパーティーチャーも多いようで、同県教委の担当者は「ICTが原因で教員になるのを諦めるのだったらもったいない。研修も充実している。簡単なことから始めて、やってみたら楽しいということを実感してほしい」と強調する。
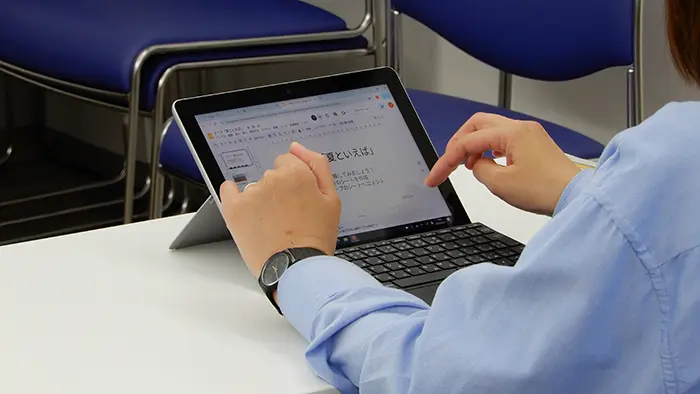
今回のセミナーで初めて取り入れられたのが、今年4月から実際に県内の学校に本採用されている教員とのパネルディスカッションだ。
この日は県内の公立中学校で勤務している男性教諭と、県内の公立小学校で勤務している女性教諭の2人とオンラインでつないで、話を聞いた。
公立中の男性教員は、教員にチャレンジした理由について「いわゆる就職氷河期世代で、教員採用試験はものすごい倍率だった。別の仕事に30年近く就いていたが、ずっと教員になりたい気持ちがあり、夢を諦め切れなかった」と語った。
また、女性教諭は民間企業で働きながら、通信課程で教員免許を取得。「自分自身が子育てをする中で、これから成長していく子どもたちと関わる仕事がしたいと思うようになった」と思いを述べた。
2人からは「時間外在校等時間は月30時間ぐらい。土日はどちらかに部活動の練習試合などがある」「保育所に自分の子どもを送ってから出勤し、18時ぐらいに退勤することが多い。仕事を持ち帰ったりもするが、勤務校にも同じように子育てしている先輩教員がいるので、なんとか助け合っている」などと、働き方のリアルな実情も語られた。
最後に「教員になる前は不安もあったが、子どもたちを前にするとすぐに吹き飛んだ。今の教員の仕事の方が、心の躍動がある。うれしく感じることが多くなった」と教員になってからの変化が語られると、会場の参加者にも笑顔が広がっていた。

セミナー後、参加者からは「今の学校での授業についてよく分かった」「ICTを実際に体験してみて、もうちょっと自分なりにできるようになりたいと思った」「いろいろと体験できたので、非常に分かりやすかった」といった、前向きな声が聞かれた。
加えて、この日の参加者は「まずは週に数時間など、短時間から働きたい」「今の仕事とダブルワークのような形で非常勤講師がやりたい」と、限定的な働き方を希望する人も多かった。
こうした希望を踏まえ、その後の希望制の個別相談では、校種別に担当者が対応。同県教委の担当者は「それぞれの働きたい条件や、学校に対する不安なども違うので、しっかりと個別相談で答えていく」と話した。
また、終了後には、希望に応じて講師登録するための面接や教員免許状の確認なども実施しており、その日に登録することも可能だ。こうした手続きのスムーズさも、参加者にとっては大きなメリットになりうる。
こうしたセミナーなどを実施する自治体は増えているものの、「任用につながったのは数人」といった自治体もある。文科省総合教育政策局の担当者は「教員免許を持っている人は、どこの自治体にもいる。ただ、免許を持っている人を探すだけでは、教員不足の解消にはつながらない。セミナーや研修の内容が非常に重要で、『自分にもできそう』という学びがないと、任用にはつながらないのではないか」と指摘する。
埼玉県では、今年度も計9回のペーパーティーチャーセミナーを実施予定だ。同県教委の担当者は「学校現場に入ったことがない、もしくは長く離れていた人にとっては、どんなICT機器を使っているのか、どんな授業になっているのか、とにかく不安が大きい。セミナーで少しでも『今の学校』を体験することで、見えてくることがある。まずは非常勤講師など、短時間からでもいいので、学校現場に入ることにつながってくれたら。今後もセミナー参加者の声を生かし、さらに内容を充実させていきたい」と話した。