米国カリフォルニア州サクラメントに、海外から移住した生徒と米国人の生徒向けに「英語」「社会科」「ELL(英語学習者および英語以外の言語を母国語とする生徒向けの英語)」「国際バカロレア」の4教科を教えている教師がいる。ルーサー・バーバンク高校のラリー・ファーラッツォ(Larry Ferlazzo)教諭だ。これまでに12冊の本を出版し、教師へのアドバイスや指導なども活発に行う。19年間にわたって地域社会のまとめ役である「コミュニティ・オーガナイザー」として働いた後、教師になって今年で20年目。外国人の生徒を支える難しさやコツなどをファーラッツォ教諭に聞いた。
――4教科を教えていますが、まず、英語の授業について、特に外国人向けの指導で取り組んでいることを教えてください。
今年度は、米国史のクラスで35人の中級のELL(英語学習者)、英語のクラスで25人の新入生のELL、そして3つの「国際バカロレア知識論」のクラスでそれぞれ30人の生徒を教えています。

私は、生徒の学習に対する内発的動機付けをサポートするような教室の環境を作ることを、心掛けています。
特に力を入れているのは、生徒の「自律性」をサポートすること。理由は、どんな年齢層であっても、自律性が内発的動機をサポートする条件となることが、研究により明らかにされているからです。例えば、「題材や自分が理解したことをどう説明するかを、生徒が選べるようにすること」。これは生徒の自律性をサポートする重要な方策となります。
自律性とともに、内発的動機を作り出すための重要な手段としては、「関係性(自分がしようとしていることは、自分が好きな人や尊敬する人との間に、良い関係をもたらすか)」「適性(問われたことを理解するためのサポートはあるか)」「関連性(問われたことは自分の目標や夢の達成に役立つのか、あるいは楽しいと思えるか)」が挙げられます。
少人数で行うグループワークは「関係性」をサポートします。見本の文章や出だしの文章などの足場を提供することは「適性」をサポートします。生徒の希望や夢を知り、それを授業につなげること、学習ゲームを授業に取り入れることなど、「関連性」をサポートするための方策もあります。
――ELLには、多様な文化的・言語的背景を持つ生徒がいると思いますが、生徒はどのような課題に直面し、どのような学習・生活上の配慮をしていますか。
これまで中国、タイ、ベトナム、フィリピンなどアジアから来た生徒たちを多く教えてきましたが、日本人の生徒は教えたことがありません。
新しい国に移り住み、新しい言語を学び、新しい文化に順応しなければならないことは、生徒たちにとって当然ながら大変なことです。特に、移住の決断に際して(大人の家族が決めることのため)、生徒たちはほとんど意見を述べることができないのですから。
モン族、アフガニスタン人、メキシコ人、中央アメリカ人など、戦争やギャングによる暴力にトラウマを持つ生徒も多く、それがさらに新たな課題となっています。
教師は生徒の良い聞き手となり、生徒との良好な関係を築き、(学校が)カウンセリングサービスを提供することが、全ての生徒をサポートする鍵となります。
――日本では、子供たちの英語力、特にスピーキングの力を伸ばすことが長年の課題となっています。日本で英語教育に携わる教師にアドバイスをお願いします。
新しい言語で話すのは怖いものです。 スペイン語学習者である私は身をもって体験しています。私は教室で、生徒が適応し、練習し、演じることがしやすいように、(英文の)短くて面白いせりふを作るようにしています。
また、ピアチューター(生徒の学習を支援することで単位をもらえる、年上の生徒たち)と一緒に、毎日、短い実用的な英会話をする練習もさせています。生徒たちに自分の人生について絵や文章を書かせ、その絵や文章についてビデオで説明させて、最後にそのビデオを教室で皆に見せるというのは、楽しくてプレッシャーの少ないスピーキング練習方法となります。
最近ではAI(人工知能)を使い、ELL(英語学習者)に即座に発音をフィードバックするオンラインツールもたくさんあって、とても便利だと思います。
しかし、以上のような授業のアイデアを利用したとしても、日本の英語教師にとって最大の課題があります。それは私が米国では直面しない課題です。つまり、日本にいる日本の生徒たちは、授業以外で英語を話すことを強制されることがないため、英語を勉強する必要性が感じられないこと。これは大きな課題だと思います。
一方、米国では、英語を母国語とする国のため、生徒は暮らしの中で使うために、英語を学ばなければならないという大きな動機付けがあります。
――社会科や国際バカロレアの授業について、何かユニークな指導法はありますか。
先ほど述べた通り、私が担当する社会科の授業も、内発的動機付けをサポートする方策を用いています。例えば、過去に起きた出来事を学んだとしたら、それが現在の社会にどのような影響を及ぼしているか、そのことを生徒が自分で確認するように促しています。

また、私の学校は、IB(国際バカロレア)の学校ですが、多くのIBの学校とは違います。なぜなら、ディプロマ・プログラムの受講者は比較的少数なのです。つまり、全てのIBクラスを履修し、IBディプロマを取得する生徒はそれほど多くはいません。しかし、生徒の大半は少なくとも一つのIBクラスを履修しており、IBクラスを履修したい人はぜひ履修するようにと勧めています。
私はIBの「知識論」の授業を担当しています。多くの英語学習者の生徒にこの授業を勧めています。
――現在、取り組んでいることは。
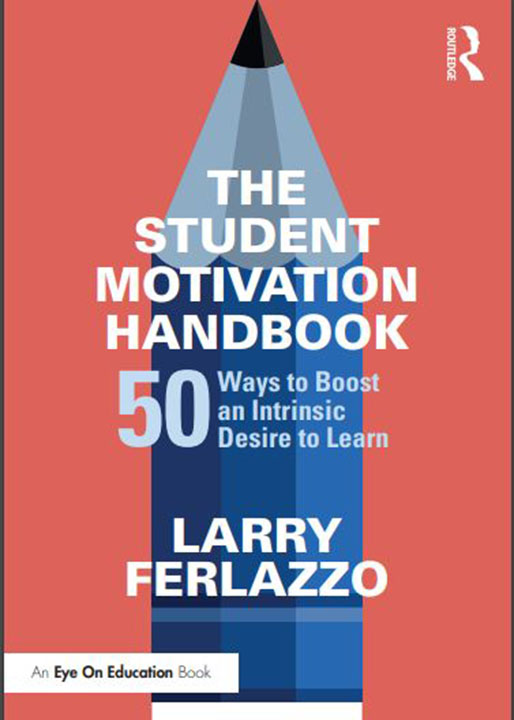
私は高校の専任教師であると同時に、教育に関する執筆活動も多く行っています。 これまでに12冊の本を執筆し、現在、13冊目の本を出版する予定です。その本は、『The Student Motivation Handbook: 50 Ways To Boost Intrinsic Motivation』(生徒のためのモチベーション・ハンドブック:内発的動機を高める50の方法)というタイトルで、生徒のやる気を出させる方法について書きました。
私のサイトにあるブログ『Larry Ferlazzo's Websites of The Day』の執筆や、教育専門紙『Education Week』に教師向けのアドバイスコラムも掲載し、教師向けポッドキャストのホストも務めています。
現在、同僚で共著者のケイティ・ハオ(Katie Hull)と私は、ELLの教師向けの本『The ELL Teacher's Toolbox』(ELLを教える教師のためのツールボックス)の第2版を執筆しているところです。
――これまで出版された12冊の本は、そのほとんどが教師向けの本です。どのような理由で書かれたのでしょうか。
書くことは考えること。知的な刺激を受け、より良い教師になることができているからです。
――現在抱えている課題や取り組みたいことは何ですか。とりわけコロナ禍以降、最も変化したことは何ですか。
コロナ禍におけるプレッシャーにより、多くの生徒が、学問的な内容を十分に学べない状況に追い込まれました。しかし、それと同時に、「困難な状況から立ち直ること」や、「やる気」については、間違いなく多くを学ぶことができる状況にもなりました。
コロナ禍では、生徒たちだけではなく、皆にプレッシャーがかかり、教師たちにも負担がかかっていると思います。
大きな課題として、本校を含む多くの学校では、代替教員として働いてくれる人の数が圧倒的に少ないことが挙げられます。代替教員がいないことで、私たち教員は欠勤した教員のために自分の時間を割かざるを得なくなり、たまに取りたいメンタルヘルス休暇も取れなくなります。また、専門的な能力開発を行う能力も劇的に低下しています。
――なぜ「コミュニティ・オーガナイザー」から転職して、教師になったのですか。
私がコミュニティ・オーガナイザーだった頃、30代、40代、50代の多くの人たちが、地域を良くする仕事を通じて、重要なリーダーシップを身に付けていくのを目の当たりにしました。その年代の人たちは、人間関係の構築、政治的分析、交渉の仕方、そして自分たちや他の人たちの生活をより良くするための力について学んでいたのです。
その人たちがもっと早い時期からその力を身に付けることができれば、素晴らしいことだと思ったのです。それで教師になりました。
――多くの教科(英語、社会、国際バカロレアクラス)を教えている理由は何ですか。
少し特殊な状況ですが、私が複数の教科の教員免許を持っていることも理由の一つです。私が教えられることによって、生徒たちの教育を手助けできることは喜ばしいことです。私にとってもやりがいがあります。
――教師をやっていて一番苦労していること、一番幸せなことはどんなことですか。
私は教えることが好きです。それと同時に、毎日150人の異なるニーズを持った生徒たちと接することは、疲れることでもあります。クラスを少人数制にして、計画的な時間がもっと持てるようになれば、少しは楽になると思いますが。
しかし、矛盾していますが、大勢の生徒と接するのは大変なことである一方で、生徒たちとの交流があるからこそ、やりがいがあるのも事実です。
――これまでの教師としての体験で、最も学んだ重要なことは何ですか。
授業がうまくいかず、教室運営もうまくいかないような日もあります。私にできることは、その失敗から学び、失敗を過去のものとし、次の日にベストを尽くすこと。それによって、事態は好転する、ということを学びました。
昔、インドの独立運動でガンジーと一緒に行動していた人に会ったことがあります。その人は、「ガンジーの成功の鍵は、全ての問題を苦痛ではなく、チャンス(機会)として彼が見ていたことだ」と教えてくれたのです。私は若い頃にこの言葉を聞いて、それを実践したことで、私の人生は計り知れないほど良いものになりました。