いじめ防止対策推進法の施行から今年で10年を迎えるが、深刻ないじめの事件は後を絶たない。世間では学校や教育委員会の不適切な対応が取り沙汰される一方で、全国でいじめの解決に向けた支援を行うNPO法人プロテクトチルドレン代表の森田志歩さんは、保護者の一方的な要求に疲弊する学校現場や、大人同士の対立の裏で置き去りにされ、孤独を募らせる子供たちの姿をたくさん見てきたという。昨年10月には、学校の働き方改革を訴える記者会見を文科省で開いた森田さん(弊紙電子版2022年11月1日:「『保護者も社会も教員の労働実態を知って』 NPO代表ら訴え)。教員に子供たちと向き合う時間を取り戻すことが、何より大切だと強調する。また今年2月に打ち出された、重大ないじめについて「学校から警察に相談・通報する」「国が積極的に関与する」といった国の方針についても、「学校現場の実態が伝わっていない」と懸念を隠さない。

「いじめの事件が起きると、世間では教育委員会と学校が不適切な対応をしているなどと問題視されるが、学校や教員が困っていることは、ほとんど明るみに出ない。実際は何千人という先生が毎年、精神疾患で休職している。あまりにも不平等、理不尽だ。先生たちは十分頑張っている。もう、一人で頑張ろうと思わなくていい」
そう訴える森田さんが、いじめ問題に取り組むようになったのは、自身の息子がいじめで不登校になったことがきっかけだった。学校や行政と交渉を重ねる姿が報道されるにつれ、いじめの被害者や保護者からさまざまな相談を受けるようになった。中立的な立場で介入するに当たり、保護者だけでなく学校や教育委員会の話にじっくり耳を傾けてみると、保護者が一方的な要求をしているケースも多々あることが分かってきたという。
「保護者は、いじめの現場を目撃したわけでもないのに『加害者にこんなことをされて、こんなに傷ついている』と断言する。学校も保護者から相談を受ければ確認をするが、子供同士のことなので、事実確認ができないことも往々にしてある。そこで『事実確認ができなかった』と保護者に報告すると、保護者が態度を豹変(ひょうへん)させ、『いじめを隠ぺいされた』『学校がうそをついた』とネットで騒ぐ――、そういう事例をたくさん見てきた。教育委員会や学校には守秘義務があり、何もかも開示することはできない。保護者にはそれが『隠ぺい』だと捉えられ、専門家やマスコミに伝わると、教育委員会や学校ばかりが批判される」
そうした保護者からは、「『子供のために早く問題を解決してあげよう』という気持ちではなく、『私の子供に何ということをしてくれたんだ』という、親の意地やプライドを感じる」という。「学習支援や登校支援をしてほしいというのではなく、とにかく『加害者を追い出せ』の一点張り。なぜ、自分の子供の支援について相談しないのか、本当に不思議だ」。
森田さんもかつて被害生徒の保護者だったことから、「もとは同じ立場だったのに、なぜ分かってくれないのか」と責められたこともあるという。「確かに、いじめ解決の支援を始めたばかりの頃は、学校や教育委員会に問題が多いのだろうと思っていた。しかし、実際に話を聞いてみると、必ずしもそうではなかった。私が介入したケースで、教育委員会や学校が本当に『隠ぺい』していたことはほとんどない」。
森田さんが関わった教員たちはこう語るという。「子供たちのトラブルは日常茶飯事だが、その中でやっていいこと、悪いことを学ぶ場所が、本来、学校であるはずだ。子供たちと一緒に、一つ一つの問題にじっくり向き合いながら過ごしていきたいし、その場で注意したり、話をしたりすればすぐに解決できる問題もたくさんある」――。しかし、それが保護者の耳に入ってしまうと、話が大きくなって、それどころではなくなってしまうのだという。
こうした状況の中で森田さんは「とにかく子供たちの声を聞いてみよう」と考え、2022年1~2月、全国の小中高生に対してアンケートを実施。2万6652人から回答を得た。「いじめをした生徒には、どうしてほしいですか」という問いには、小学生の68.3%、中学生の62.0%、高校生の80.5%が「反省して謝ってほしい」と回答し、一方で「教室に入らないようにしてほしい」と回答した割合は全体で4.9%とわずかだった。保護者の要求と、子供たちの気持ちにずれが生じている可能性が浮かび上がった。
森田さんは子供たちから直接、相談を受けることもある。中学生、高校生からよく聞くのが「大人のやっていることが、パフォーマンスにしか見えない」という言葉だという。「誰が悪い、何が悪いと言うばかりで、誰も助けてくれない」「相談しても結局、否定されるから、相談する気にもなれない」「『いじめは絶対許さない』なんて言っておきながら、大人だってSNSで誹謗(ひぼう)中傷しているじゃないか」――。
相談してくる子供たちの周りには、保護者や教員もいるし、地域の相談窓口などもある。それなのに、縁もゆかりもない森田さんを相談相手に選ぶ。「子供に『相談してください』と言うのではなく、子供たちが本当に相談したくなる環境を作るのが先ではないか。『親に心配を掛けたくなくて、相談しない子供たちもいる』という反論もあるが、それを言うなら大人の側が、子供たちの悩みに気付いてあげる努力をしなければ」。
いじめへの対応では、早期発見や未然防止の大切さが指摘されることが多い。しかし、森田さんは「学校に余裕がなければ、早期発見なんてまず無理だと思う。やりたくてもできないことが他にもたくさんある中で、教員がいじめだけを探して歩くことなど、できるわけがない。担任は1年で交代するのに、子供たちの性格や本質を把握した上で、その変化に気付くのは至難の業だし、子供たちの側も、学校でいじめられているそぶりは見せないだろう」と、学校だけに早期発見を求めることの難しさを語る。
「子供のことを一番理解しているのは保護者なのだから、学校と家庭の両輪で、しっかり連携していかなければならない。子供の命より大切なものはないはず。子供がなぜ自殺してしまうのかといえば、やはり孤立感や絶望感からだと思う。常に子供に寄り添ってあげるのも難しいのかもしれないが、命がなくなって後悔するくらいなら、その前に周りの大人が、子供の話にちゃんと耳を傾けてほしい」と力を込める。
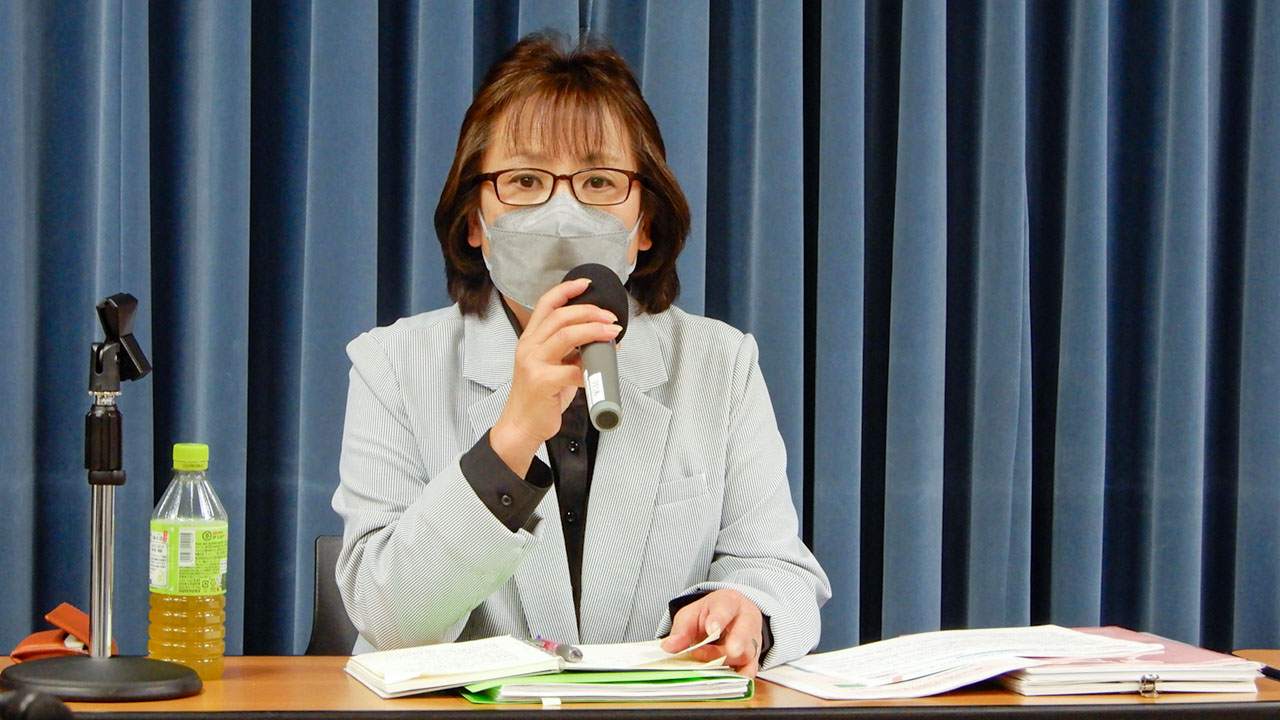
13年にいじめ防止対策推進法が施行されてから、今年で10年を迎える。しかし、文科省の調査(21年度時点)では、いじめの認知件数は61万5351件、重大事態の発生件数は705件に上る。加えて、小中学校の不登校児童生徒は過去最多の24万4940人、小中高生の自殺も368人に上り、深刻な状況が続いていることが分かる。
こうした状況の中、文科省は「いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議」や「いじめ防止対策協議会」での検討を踏まえ、今年2月7日に、犯罪行為として取り扱われるべきものなど重大ないじめ事案について、「直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めること」などとする通知を出した。
警察庁は以前から、「被害の届出を即時受理した上、学校等と緊密に連携しつつ、被害少年の立場に立った捜査・調査活動を推進する」という通知を出している。しかし森田さんは、保護者から「警察が被害届を受理してくれない」という相談を受けることがあるという。「警察署の職員からは、通知の内容を知らないという声も聞く。通知を出して終わりではなく、実際に学校や教育委員会と連携して、適切に対応しているか確認してほしい」。
今回の関係府省連絡会議ではまた、いじめの重大事態について、教育委員会などから文科省への報告を求めるという方針が示された。ただ、森田さんはこの点についても懸念を示す。「実際にいじめの対応をするのは設置者である自治体や学校が中心で、文科省にできることはそれほどない。それなのに報告書の作成を求めるとすれば、現場にさらなる負担が掛かることが容易に想像できる。重大事態と認定したがらないケースも出てくるだろう」。
次々と打ち出される国のいじめ対策を巡り、森田さんは「学校現場から距離がある政治家や官僚に、実態が伝わっていない。大人が満足して、納得する制度ができさえすればよい、という風潮を感じる」と憤る。「学校現場にばかり責任を押し付けたり、いじめの加害者を排除しようとしたりしても、子供たちの命や尊厳は守れない。もっと多くの人に、学校現場の実態を知ってもらいたいし、有識者やマスコミ、その他の当事者ではない人たちも、もっと冷静に考えて行動してほしい」。
その上で「もっと先生たちのことを大切にしてほしい。学校の働き方改革は、先生たちのためではなくて、子供たちのためでもある。次々と新たな対応を学校に求め、現場を追い込むのではなく、子供たちと向き合う時間を、心のゆとりを作ることが何よりも大事だ」と訴える。森田さんは今年3月、永岡桂子文科相に直接、申し入れを行うつもりだ。