1000人の大人に出会いながら、自分の人生設計を考えていく探究学習に、東京都板橋区立板橋第十小学校(冨田和己校長、児童601人)の4年生101人が挑戦している。総合的な学習の時間を使って1年かけて取り組んでおり、企画した同校の小泉志信教諭は「さまざまな業界の仕事をしている大人に出会うことで、将来の選択肢はたくさんあるということを知ってほしい」と話す。6月16日には、SNSのインフルエンサーやテレビ局職員、広告などの「伝える仕事」に携わる大人たちが、ワークショップ形式でそれぞれの仕事を体験できる授業を行った。
5月から始まったこのプロジェクトは毎週金曜日の総合的な学習の時間に行われている。3回目の授業となった6月16日は、「SNSのインフルエンサー」「テレビ局」「広告などのクリエーティブ」「記者・ライター」の大人たちが来校。子どもたちは、4時間目と5時間目で一つずつ、自分が興味のある分野の授業を選んで参加した。
「SNSのインフルエンサー」の授業は、Instagramで約6万5000人のフォロワーを持つ公立小学校教諭のゆきこ先生(弊紙連載「先生が幸せに働くためにできること」)、同じく約3万3000人のフォロワーを持つフォトグラファーのもんちゃん、約11万3000人のフォロワーを持つインスタグラマーの小菅彩子さんが担当した。授業に参加した子どもたちは、全員が「Instagramを知っている・見たことがある」ものの、「Instagramで発信したことがある」のは4分の1ほど。ゆきこ先生が子どもたちに「今日はInstagramで発信する仕事を実際に体験してみよう」と呼び掛けると、「やったー!」「投稿できるの?」と前のめりの反応を示した。
子どもたちに出された投稿テーマは、「来年度入学する新1年生が『板橋第十小学校って楽しそうだな』とわくわくするようなInstagramの投稿をつくろう」。まずグループで一つ、学校の紹介したいことを決めていく。「1年生の教室がいいんじゃない?」「いろいろな先生の写真を撮ろうよ」など、続々とアイデアが出された。そして発信したい内容に合わせた写真を撮りに、1人1台端末を手に校内へと駆け出していった。
あるグループは、校庭に咲いているさまざまな花を撮影してきた。「第十小には色とりどりのお花が咲いているから、新1年生にも紹介したかった」と笑顔。「投稿では春と夏の花だけ紹介する。秋と冬の花は新1年生が入学してきてから、自分たちで見つけるお楽しみにしてもらおうと思って」と、わくわくする仕掛けにも考えを巡らせていた。

子どもたちの活動を見守っていた小菅さんは「この学校のオリジナリティーを出そうと、いろいろな先生の写真を撮影しているグループがあった。投稿を見てくれる人がどう思うかを考える視点がとても大事で、どのグループもそれができていた」と感心しきり。もんちゃんも「先生の写真を撮るときにいい笑顔を引き出そうと工夫していたり、撮影前に撮ってもいいか許可を得たりするなど、配慮ができていることに驚いた」と話した。
ゆきこ先生は「Instagramの発信では、『伝える』と『伝わる』の重なっているところを考えることが大事。みんなどうすれば新1年生がわくわくできるのかをしっかり考えられていた」と、相手を意識して投稿をつくろうとしていた子どもたちの活動を賞賛した。
この日は時間切れで投稿するまではできなかったが、後日、今回のために作ったInstagramのアカウントに投稿される予定で、子どもたちは「早く自分たちの投稿を見てみたい」と期待に胸を膨らませていた。
「広告などのクリエーティブ」の授業では、クリエーターの飯島夢さん、藤田隼輔さん、安村晋さんが先生役として登壇。学校にある当たり前を疑って、新しいルールを提案してみるというワークショップに挑戦した。
子どもたちはまず、学校に当たり前にあるルールを出し合っていく。「いじめはしない」「廊下は走らない」「先生が言ったことは守る」「仲良くする」「宿題をする」「ランドセルじゃないとだめ」「水筒にジュースは入れない」など、次々に出てくる。飯島さんが「その中で、『そのルールって本当に必要なのかな?』『そのルール、こうすればもっと良くできるんじゃないかな?』というものはあるかな?」と問い掛け、子どもたちは悩みながらも「みんなで変えてみたいルール」をグループで一つに絞っていった。
その後は、「みんなで変えてみたいルール」のどの部分を変えたいのか、新しいルールの名前、新しいルールが広がるとどんないいことが起きるか、ルールを変えたときに困る人はいないか、ルールを変えようとしたときに応援してくれそうな人は誰か、について考えながらワークシートに書き込んでいく。
「給食中、立ち歩かない」というルールを変えたいと考えたグループは、「月に2、3回、どこで給食を食べてもいい日をつくる」ことを提案。当初、このルールを変えたい理由を「遊びたい、自由にしたい」と話していたが、藤田さんが「それだと先生を説得できるかな?」と問うと、子どもたちから「どこで食べてもいい日があると、違うクラスの子とも仲良くなれるよね。この理由は、先生も納得してくれるかも」といった意見が。新しいルールを「歩く給食デー」と命名し、発表していた。
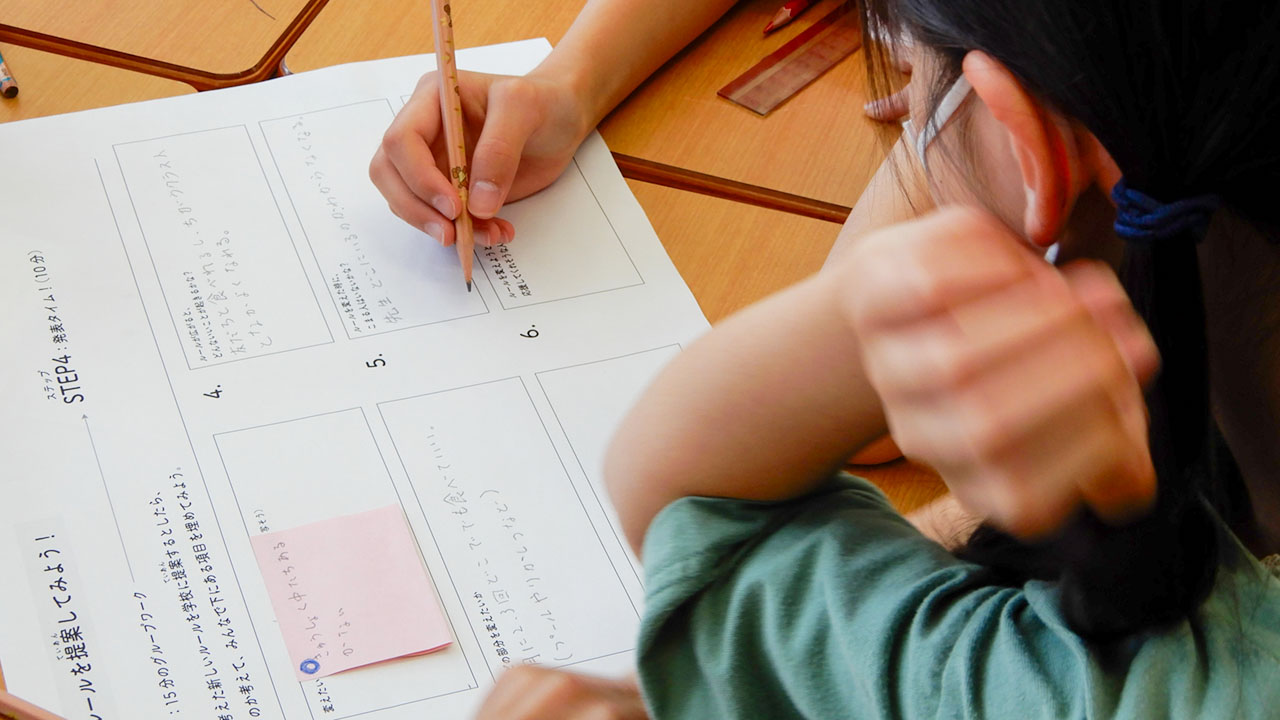
藤田さんは子どもたちとの授業を振り返り、「子どもたちが『なんで?』と疑問に思っていることに対して、真面目に大人が向き合うことが大事だと感じた」と話す。また、安村さんは「いくつかのグループは、ワークシートを校長先生に持っていくと言っていた。実際にルールが変わるきっかけになるかもしれない」と今後の展開にも期待を寄せていた。
飯島さんは「自分のやりたいことと、周りのやりたいことの真ん中を探していく体験ができたのではないか。自分がやりたいだけじゃなく、どうやったら周りの人も納得してくれるかを考えるのが、クリエーターの仕事。少しでも興味を持ってくれたらうれしい」と話した。
このプロジェクトを企画した小泉教諭は「子どもたちの大人像がとても狭いことを課題として感じていた。多様な大人のキャリアに触れ、いろいろな選択肢があるということを知ってから、自分の人生設計を考えてほしい。そうしたら、たとえ失敗しても『こっちが駄目でもこんな道もある』と、横にも縦にも柔らかく考えられるようになる」と、意図を語る。
また、「1000人の大人に出会えば、子どもにとって、人生観を変えるようなかけがえのない1人と出会えるかもしれない」と期待を寄せる。実際、プロジェクトが始まって以降、将来やりたい職業だけでなく、例えば「友達を助けるようなことをしていきたい」と、自分の核となる考えを持ち始めた子もすでに出てきているそうだ。
今後も1学期はほぼ毎週、いろいろな大人に出会う授業が繰り広げられていく予定。2学期からは大人と協働してプロジェクトを形にし、3学期にはそれまでの経験を生かして自分の人生設計をつくってみる計画を立てていく。「子どもたちの力になりたいという大人が、こんなにたくさんいるということを改めて感じている。たくさんの大人の力を借りながら、子どもたちの学びを形にしていきたい」と小泉教諭は展望を語った。