青森県が今年6月に就任した宮下宗一郎知事のもと、革新的な教育改革に乗り出した。7月31日には、知事直轄の諮問機関「青森県教育改革有識者会議」の立ち上げを発表。知事参与として知事と二人三脚で改革に取り組む、同県出身の大谷真樹氏(インフィニティ国際学院学院長)を議長に据え、委員には森万喜子氏(北海道公⽴学校初任段階教諭指導講師)や日野田直彦氏(武蔵野⼤学中⾼・附属千代⽥⾼中⾼学園⻑、千代⽥国際中校⻑)をはじめ、工藤勇一氏(学校法人堀井学園理事 横浜創英中学・高校校長)、住田昌治氏(学校法人湘南学園学園長)ら、そうそうたる顔ぶれがそろう。

有識者会議の設置に関し同日、県庁で会見に挑んだ宮下知事は「未来を担う子どもたちに時代にふさわしい教育を提供することで新しい青森県を創造していく。このことこそ新県政における最重要課題の一つとして位置付けている」とした上で、「できることからスタートし、4年後には青森県の教育が大きく変わったなと言っていただけるようにしたい。100年後にはこの有識者会議の設置が一つの大きな節目となったと言われるような会議にしたい」と意気込みを語った。
有識者会議は知事直轄で新設し、県内の学校教育を巡る課題や施策について委員が議論を重ね、教育大綱を策定する知事に提言する。
有識者のメンバーは次の通り(敬称略)。【常任委員】▽大谷真樹(議長)▽森万喜子(副議長)▽日野田直彦▽藤岡慎二(産業能率大学経営学部教授)▽平井聡一郎(未来教育デザイン代表社員)▽三戸延聖(弘前大学教育学部教職実践専攻・教職大学院教授)▽森山達央(スパイスアップ・アカデミア代表取締役)【顧問】▽合田哲雄(文化庁次長、元文科省初等中等教育局教育課程課⻑・財務課⻑)【特別委員】▽生重幸恵(特定非営利活動法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長)▽江川和弥(フリースクール全国ネットワーク代表理事)▽工藤勇一▽讃井廉智(ライフイズテック取締役、最高AI教育責任者(CEAIO))▽澤田真由美((株)先生の幸せ研究所代表取締役)▽島康子(Yプロジェクト代表取締役、青森県教育委員)▽陳内裕樹(東北芸術工科大学客員教授)▽住田昌治▽橋本大也(デジタルハリウッド大学教授)▽本間正人(京都芸術大学・社会構想大学院大学客員教授)
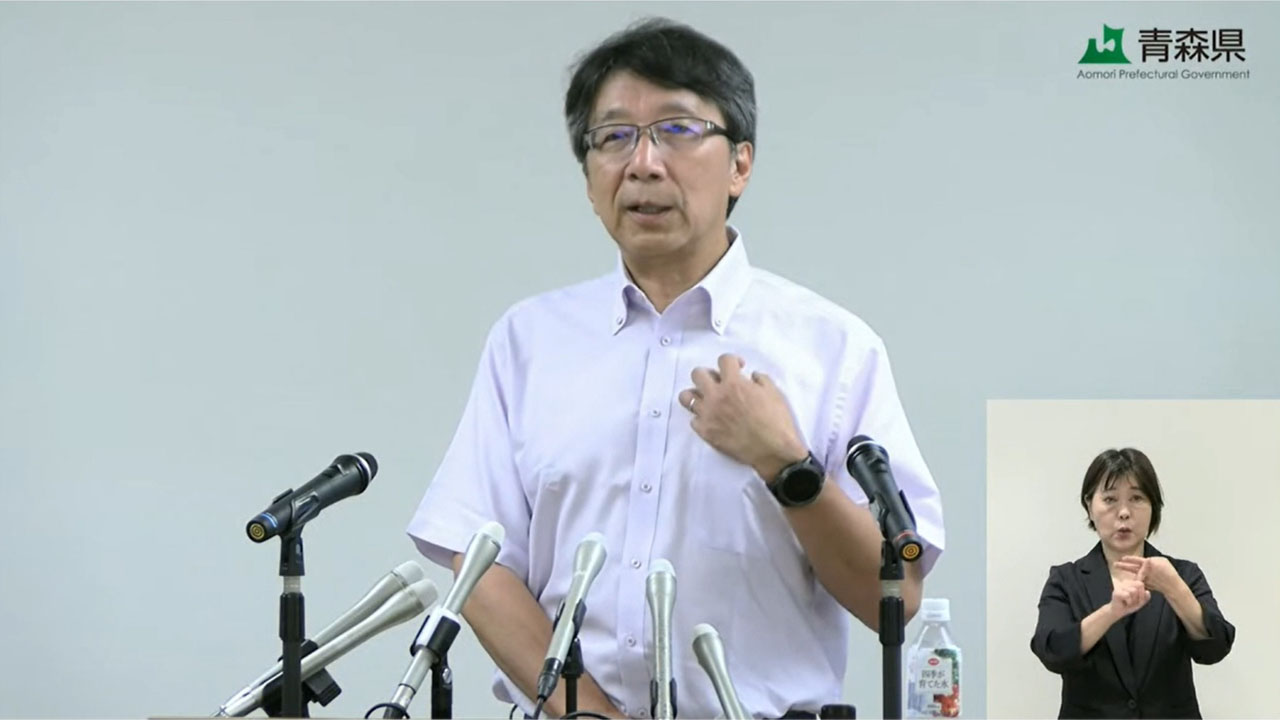
教育新聞の個別取材に応じた大谷参与は、メンバーの選定について「評論家ではなく実践者。結果を残し、評価できる材料を持っている人にこだわった」と強調する。「評論するばかりで、結局何もできずに終わってしまう会議が多い。今回こだわったのは、実際に現場で汗を流している実践者たち。好事例だけでなく、失敗事例にこそ価値があると思っている。実践者たちの失敗から学べることがあるはずだ。全国各地の取り組みの“いいとこどり”をしたい」と、展望を明かす。
会議は「定例会議」と、教員の働き方や学校運営など一つのテーマに特化して議論を深める「テーマ別会議」の両輪で進める。常任委員や顧問は原則全ての会議に参加。特別委員は専門分野ごとにテーマ別会議に参加し、実践事例の報告やアドバイスをする。
全国各地に散らばる委員と密に情報交換し、開かれた会議を目指すために、オンラインを活用する運営も特徴の一つだ。初回会議は8月22日を予定し、YouTubeライブで県民をはじめ全国に発信する。オンラインと対面のハイブリッドで今年は定例会議とテーマ別会議をそれぞれ月2回ほど開催し、急ピッチで改革に着手する。今年度中に提言の取りまとめを目指し、来年1月中旬をめどに知事への提言を予定する。
また有識者会議の検討材料を集める、オンライン上のワーキンググループも設置。すでに元教員や育休中の教員、大学院生、社会人など20人以上がボランティアで集まり、業務改善などの事例を集めている。集めた情報は、ChatGPTなどオンラインツールを駆使して精査。それを会議の参考資料として生かす。また委員たちはチャットでつながり、オンライン上でも随時議論を進めるという画期的なスタイルをとっている。
有識者会議の運用にあたり、大谷参与は「学校現場の声を教育長や知事に届ける」と強調する。「『改革』と聞くと新しいことをどんどんやるイメ―ジを持たれるかもしれないが、まずは現場の余白をつくる。先生の余白をつくった上で、子どもたちに向き合う環境整備を、さまざまな実践例をもとに提言していきたい」と、優先的に教員の働き方改革に取り組む意向を示した。
現場の声を吸い上げる足掛かりとして、8月から県内の全教職員を対象にした大掛かりなアンケートに着手する。個人がQRコードからアクセスでき、学校現場で困っていることや改善してほしいことを自由記述で回答し、生成AIが集約する仕組みだ。これまで国や教委がやってきた紙ベースで煩雑なアンケートと違い、回答者の負担をできるだけ軽くした上で現場の本音が集まりやすいように工夫した。さらに同様のアンケートを地元新聞社の協力を仰ぎ保護者にも実施し、多面的に学校教育の課題を捉える。
働き方改革をはじめとした学校現場の課題について、大谷参与は「『これを止めよう』と、誰かがトップダウンで変える必要がある」と説明する。
「何かを始めるためには、まず何かを止めなければならない。今の職員室は、前例や慣習で積み上がった業務が膨大にある」と指摘した上で、「ボトムアップで学校は変われない。職員室のなかの軋轢(あつれき)があったり、校長や教委の壁があったり……。だからこそ誰かが、トップダウンで変える必要がある。今回は知事直轄の組織ということもあり、公教育が変わる大きなチャンスだと思っている。これだけのメンバーが集まると、かなり変えられるのではないか」と期待を込める。
さらにこの取り組みが、全国各地の学校教育を捉え直すきっかけになってほしいとの願いもある。
「青森県でうまくいけば、オセロゲームのように全国各地が変わっていって、日本の教育が変われるのではないか。青森県でできたのだから、うちでできないわけがないと思ってもらえるよう挑戦していきたい」と、大谷参与は言葉に熱を込める。