教室に張られた習字の清書、いつでも楽しく分かりやすい授業をしてくれる先生――。これらを当たり前とする風潮に「待った」を掛けるのは、『不親切教師のススメ』の著書である千葉県公立小学校の松尾英明教諭だ。「『親切』を受け続けた子どもは駄目になる」と指摘する松尾教諭に、見直すべき学校の「当たり前」について聞いた。(全3回)
――昨夏、『不親切教師のススメ』を刊行されました。当初は「悪い教員になろう」ということかと勘違いしていました。
学校教員は基本的に真面目で、とても親切です。自分のことは後回しにして、身を削ってでも子どもや保護者のために尽くします。でも、それが本当に子どもの成長にとって良いと言えるのでしょうか。
私は「不親切な指導こそが子どもの主体性を伸ばし、教員の負担を軽減する」と考えています。「きめ細かな指導」と言えば、現代の教育に求められる手立ての一つのように見えますし、いつも綿密に授業準備をして、楽しく分かりやすい授業をしてくれる面白い先生は、多くの職場で高く評価されるでしょう。
でも、この「いつも楽しい授業をする」「子どもから『面白い先生』と言われる」といった「当たり前」こそ、真っ先に疑うべきです。どちらも「親切」であるがために起きている現象ですが、私はこういったサービス精神に満ちた「親切」を受け続けた子どもは、駄目になると考えています。
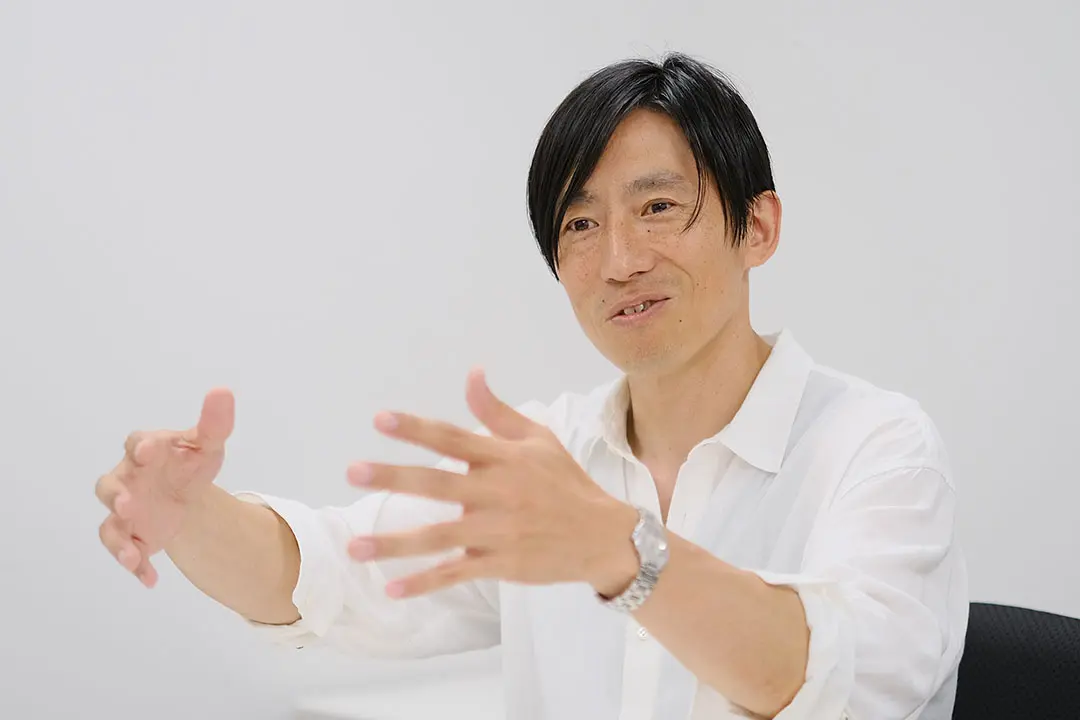
――確かに、子どもは「面白い授業をしてもらうのが当たり前」と考えるかもしれませんね。
一見して「良いサービス」に見える「親切教育」は、裏を返せば完全に受け身の「お客様」を育てることにほかなりません。本来、学校で育てるべきはお客様精神ではなく、主体性をもって社会的な価値を自ら生み出していく側の人間であるはずです。
これからの授業は、「楽しい授業」「面白い先生」という当たり前を捨てて、子どもが課題に自ら気付き、解決に必要な力を獲得していく場にすべきです。そのために教員は、「教えるべきこと」と「子ども自身が考えるべきこと」の見極めをする必要があります。その見極め作業をしながら教材研究を行い、子ども自身が考えるべきことを「発問」という形で投げ掛けながら、子どもの学ぶ力を育てるのです。
――「子どもの学ぶ力を育てる」授業については、著書で詳しく説明されています。第2章のタイトルに「習字の掲示をやめる」とあり、ハッとさせられました。
習字が張り出されているというのは、小学校の教室ではごく当たり前の光景です。子どもが頑張って書いた習字の清書を全員分、教室のどこからでもよく見えるところに掲示してあげるという、「親切心」の賜物と言えます。

でも、そもそも習字の清書って、何を目的とした行為なのでしょうか。現行の学習指導要領は、書写の指導内容を「姿勢や筆記用具の持ち方」「正しい点画の書き方や字形、筆順」と示しています。つまり、習字の清書とは、お手本の字を可能な限りそっくりに真似て写す作業の成果物です。その点で、芸術的表現活動である「書道」とは違うのです。個性が表現できる図工などの作品とも違います。
表現では上手・下手は明確に言えませんが、習字の清書はそれがはっきりと出てしまいます。正解の定まったテストの結果に近いものです。そうして優劣がはっきりしているものを全体にさらしてしまうのが、習字の掲示なのです。
――全員分を掲示するという教員の労力に反して、デメリットが生まれてしまうのですね。
習字の清書に限らず、「子どものために」と思って担任が一生懸命掲示したものは、労力の割に見られておらず、子どものためにもなっていません。
実際に私自身、持ち上がりで担任した学年の学級開きでは、教室の壁に避難経路以外、何も張っていない状態でスタートします。そんながらんとした教室で子どもにこう語ります。「見ての通り、教室には何も張っていませんし、何も置いていません。あなたたちが過ごす新しい空間だからです。今日から自分たちの手で、この教室を作っていきましょう」と。
子どもが自分の手で作ったり撤去したり更新したりする掲示物は、「生きた掲示物」になります。「もっと見てもらいたい」「もっと楽しませたい」という欲求が生まれ、自然と工夫し始めます。そのうち階段や靴箱にも掲示したいと言いだし、創造性や主体性が教室を飛び出していきます。
一方で、教員が作った掲示物だらけの教室では、教員の「親切」が裏目に出て、子どもの使えるスペースがつぶされてしまいます。これは単に物理的な余白をなくしているだけでなく、子どもの成長の可能性までつぶしてしまう行為ではないでしょうか。
――教員の「親切」が、子どもの成長という観点からはマイナスに働いているのですね。
学校の中で常識になっていることって、誰にも変えられないんですよね。学習指導要領で定められていることは仕方がないとしても、学校には「ずっと前からこうだった」「皆、これをやるものだと言われている」と慣例的に行われていることがたくさんあります。子どももそれに慣れているので、「決まっているから」「やらなきゃ駄目なこと」と納得してしまっています。でも、「本当かな?」と思うこと、疑問に思うことは数多くあります。

習字の掲示はその一つですが、その他に「背の順」もあります。「背の順に並ぶ」は、どの学校でも当たり前にやっていますが、実はほぼ必然性がありません。よく「前がよく見えるから」と説明する人がいますが、実際には同じくらいの身長の子が前にいるわけで、全く見えません。そのため、実際の全校集会などでは体育座りをして壇上を見ています。
――確かに、社会に出てから「背の順に並んでください」とは言われません。
実際、避難訓練のときはほとんどの学校が名簿順で並びます。それは名簿と照らし合わせて全員がそろっているか確認する必要があるからです。
「背の順」での整列には変動性があるため、緊急時の人員確認には不適切なのです。また、子どもの中に妙な競争意識も生まれます。特に男子の場合は背が低いと感じることがコンプレックスになりやすいですし、女子の場合は逆に「背が高いのが嫌」と言う子もいます。その意味でも、わざわざ「背が高い」「背が低い」を比べて示す必要はないんです。そもそも、誰かが「嫌だ」と思っているようなことを一律にやるところに問題があると思っています。
昨今、よく「多様性を認めよう」と言われますが、これについてもよく考えずに一律に進めることに問題があると思っています。なぜなら「多様性を認めよう」という言葉は、「多様性を認めない」という「多様な意見」を押さえ付けてしまうからです。
例えば、最近よくジェンダーレストイレについて論じられていますが、「身体的に女性ではない人がいるのは不安だ」という女性の意見を「多様性を認めよう」という言葉で押さえ付けるのは、本当の意味での「多様性の尊重」にはなりません。「多様性を認めない」といった声は、現代ではマイノリティー側になるかもしれませんが、そうした声が「間違った意見」「誤った意見」として消されていくのも、今の日本社会や学校の構造的な問題ではないでしょうか。