ニューロダイバーシティ(脳や神経由来の多様性)という概念は、発達障害の子どもだけでなく、通常学級に通う子どもたちが自分に合った学びを選べるかどうかの課題にもつながると臨床心理士の村中直人さんは語る。インタビューの第3回では、本質的な意味でのニューロダイバーシティの考え方を基に、通常学級の在り方を見直すことについての提言を語ってもらった。(全3回)
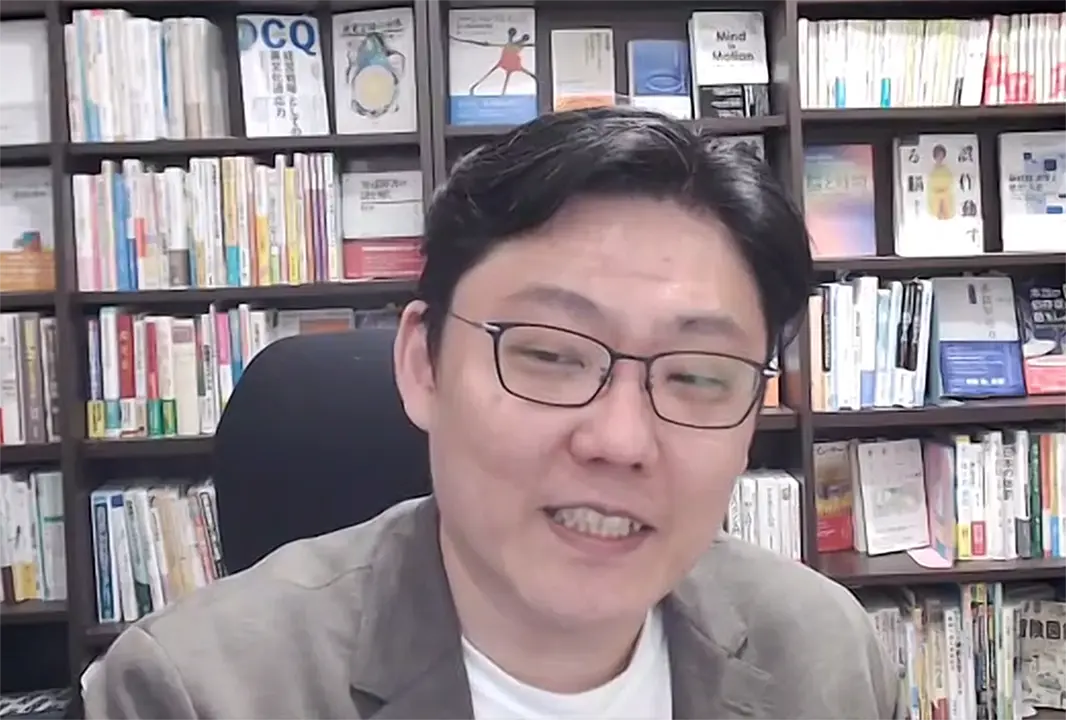
――前回、ニューロダイバーシティは発達障害の子どもの学びだけでなく、通常学級の子どもが自分に合った学び方を選択する上でも重要だと提起されました。
私は「ラーニングダイバーシティ」(学びの多様性)と呼んでいるのですが、地域でこの概念がどれだけ尊重されているかということと、その地域における特別支援教育のニーズには相関関係があるはずだと考えています。特別支援学校・学級にはその道のトップランナーの先生がいらっしゃるし、通常学級にもいろいろな改革の旗手がいらっしゃいます。でも、現状はそれぞれが別の取り組みとなっていて、相互にやりとりがなされていないように思います。
私のようにずっとそのはざまで仕事してきた人間からすると、通常学級で学び方を子どもたちが選べたり、自分のペースで決定できたりすることが保障される程度と、その地域における特別支援教育のニーズは、自明の理として連動するはずだと考えています。
発達障害の子どもが6.5%から8.8%に増えたという文科省の報告書も、私には結構ショックでした。数字が増えたことがショックなのではなく、報告書には学校側の在り方を問う言葉が一文字もなかったからです。子どもたちにはクロノタイプ以外にもさまざまな多様性があって、一人一人に合った学び方を提供するために通常学級の在り方を見直さなければならないという話につながれば、本質的な意味でニューロダイバーシティという言葉が使われていくだろうと思っています。
――教育の在り方自体が問われるというお話ですが、社会が変わらなければ教育も変わらないようにも思います。
おっしゃる通りです。それこそ、発達障害の調査レポートは方向性として、特別支援教育の枠に入っていない子たちを管理職がリーダーシップを発揮してちゃんと拾っていくべきとしているんですが、どこにそんなにリソースがあるのかという話でもあります。
つまり、通常の枠と特別な枠があって、現時点で特別支援教育の対象となっている子たちの数倍のボリュームの子たちを特別な枠に送り込みましょうという、成立するはずのない話が書かれているように感じるんです。そんなことをすれば、結果として通常学級の先生がそこに取られてしまって、教員の負担増や教員不足にもつながります。
それこそ、穴が開いているバケツに、穴をふさがず水だけを注ごうとしているようなものです。ですから、通常学級の在り方をどこまで変えることができるかという、ある種の思想的なよりどころ、考えの根拠となるキーワードとしてニューロダイバーシティという言葉が使われてほしいと思います。
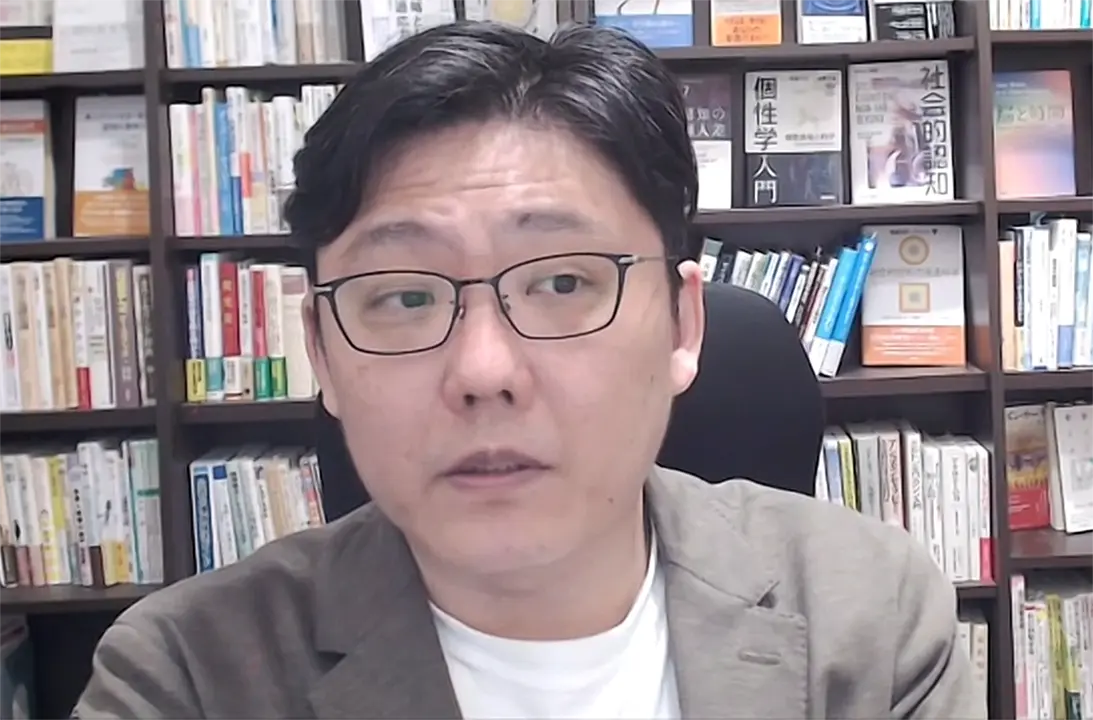
――ニューロダイバーシティ視点で教育改革を進める上で、具体的な提案はありますか。
日本の教育を根本から変えていくためのポイントが2つあると思っています。一つは全員一律一斉授業の比率を下げること。具体的には手始めに3割程度、一斉授業を禁止するような方法がよいかもしれません。もう一つは教科書教材から学年の表記を消すこと。裏側には、生物学的年齢と学ぶコンテンツのつながりを緩やかにするという意味があります。
そもそも日本の学校はニューロユニバーサリティ的で、「3年生のこの時期にこれを学ぶのが適切」ということが全員に当てはまるという価値観に基づいています。この2つを変えるだけで日本の教育は変わると思っています。全授業の約3割、子どもたちが自分のペースで学ぶ時間が確保されるだけで、子どもたちの学びの捉え方が根本的に変わると思っています。
――現場の教員にできることは何でしょう。
例えば、3桁の数字の書き方を習う前に、「2桁+2桁=3桁」になる足し算を暗算で計算できる子がいます。でも、今の日本の教育では3桁の数字を習う前に、そうした計算は絶対させません。ひょっとしたらその先にどんどんできることが広がっているかもしれないのに、学び方を逆にすることはできないんです。
そのレベルまで自由度を高めていかないと、本当の意味でのニューロダイバーシティ的な個別最適化は実現できないと思います。ある子は「1+1は何」といった遊びをする中で、だんだん数字が大きくなって、気付いたら2桁3桁の数字を就学の時点で答えられるようになっていました。興味のあることを自分で選んで試行錯誤していけば、子どもは自分の認知の在り方や神経の在り方にとって最適なものを選ぶんです。
つまり、試行錯誤の中でそこへたどり着く力があるんです。それができないのは、誰かに邪魔されているからです。「これはこういうふうにやるものだからこういうふうにやりなさい」と、ニューロユニバーサリティ的な発想に基づく学び方の指定・固定がされているから、一人一人が自分に合うやり方を見つけることができないだけだと私は思っています。
なので、現場の先生にお願いしたいのは、「邪魔をしない」ことです。必要なのは、一人一人が自分に合う学び方を見つけることへのエンパワーメントと、あとは試行錯誤を見守る余裕みたいなことです。さらに言えば、子どもたちの学びのメカニズムについて、認知科学や神経科学の観点から学んでいただいたら、子どもにどんな学び方が必要なのかを深められると思います。
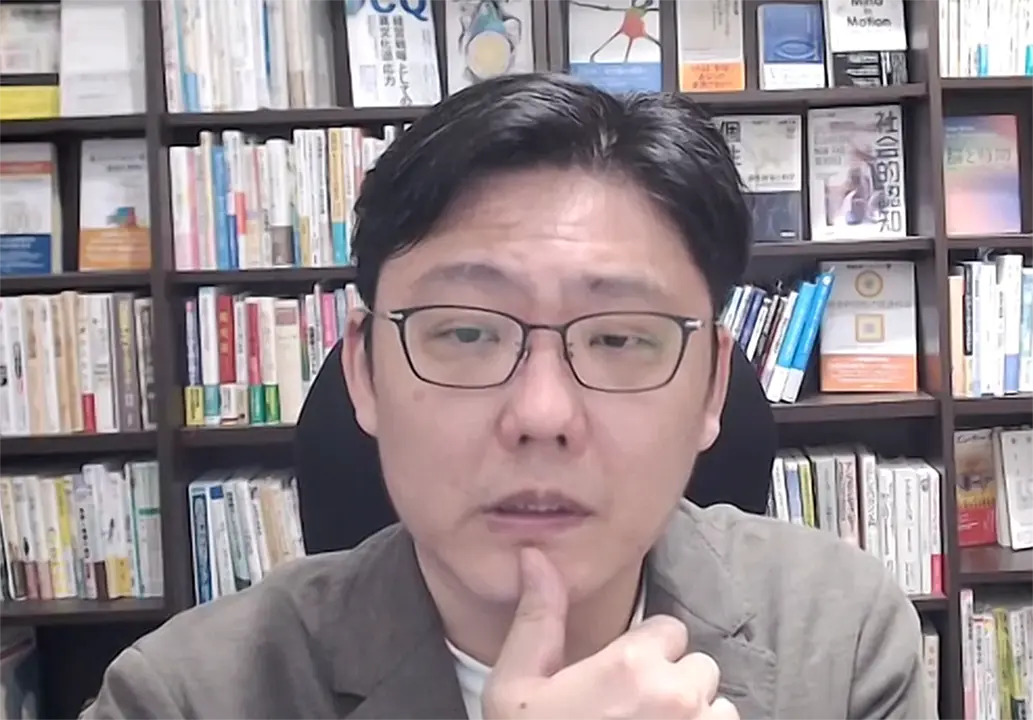
――知識や技能を習得するメカニズムは、人によって違うということですね。
私たち人間は、自分の人生しか生きられません。そのため、自分にとって最適なやり方が人類共通で最適なやり方だと思ってしまいがちです。でも、実際にはタイプが違えば全然違っています。
だから、自分が良かれと思った伝え方をしても、子どもにとっては分かりにくい説明になっていて理解されず、その子が「真面目にやっていない」「能力が低い」などと受け止められてしまうのです。だから、まずは「人間は全然違う」「一つのやり方が全部通用するなんて絶対あり得ない」「教え方にしても解き方にしても全員がそのやり方が合うことはあり得ない」という基本リテラシーを当たり前にしていくことが、認識の変化として大事じゃないかと考えています。
――学校だけではなく、企業や地域社会、家族の在り方などにも共通する話ですね。
今時点では「多様性」という言葉が、「マイノリティーで排除されてしまった人を大事にしよう」というレベルで終わってしまっています。それはもちろん大事なことですが、家族や職場、教室など身近なところに存在している多様性に、きちんと目を向けることが大事だと思っています。とはいえ、私たちの生活の中に存在する多様性は見えにくいものです。親子で言うと、自分と子どもが脳や神経由来の全然違うタイプだなんて、思わないでしょう。
教室で多様性を尊重し、発達障害や不登校など特別なニーズの子たちに合理的配慮をし始めると、周囲から「ずるい」と言われることもあります。でも、なぜ他の子が「ずるい」と言うかといえば、その子たちが自分に合った学び方を提供してもらえていないからです。自分に対して「調整してもらえている」「配慮してもらえている」と感じていれば「ずるい」という感情は出てきません。「ずるい」という言葉の裏側には「僕も我慢しているんだから、お前も我慢しろよ」という思いがあるんです。
この点は、日本社会全体における課題でしょう。自分に合った働き方、自分に合った学び方、自分に合った生活をちゃんと提供してもらえるという感覚を皆が持てれば、少数派に対する配慮も特別なものじゃなくなっていくと思います。自分に合う方法を認めてもらっている感覚、調整してもらえている感覚があるかないかはとても重要で、その感覚を全員が持てている状況がいわゆる「個別最適化」なんだろうと思います。
【プロフィール】
村中直人(むらなか・なおと)臨床心理士・公認心理師。(一社)子ども・青少年育成支援協会代表理事、Neurodiversity at Work㈱代表取締役。1977年生まれ。大阪市立大学卒業後、京都文教大学大学院で臨床心理学を学ぶ。2008年に学習支援事業『あすはな先生』立ち上げ。現在は「発達障害サポーター'sスクール」での支援者育成にも力を入れている。著書に『ニューロダイバーシティの教科書――多様性尊重社会へのキーワード』(金子書房)、『〈叱る依存〉がとまらない』(紀伊國屋書店)。