いじめの認知件数が68万1948件、重大事態が923件といずれも過去最多となり、国は10月に緊急対策パッケージを打ち出した。これまで数々のいじめ事案に第三者の立場で介入し、解決に導いてきたNPO法人プロテクトチルドレンの森田志歩代表は、「これ以上、学校に研修や罰則を課しても意味がない」と指摘する。その一方で、保護者の一方的な要求が学校を疲弊させ、当事者の子どもすら置き去りにしているケースも多いとして、保護者に対する啓発の必要性を強く訴える。
――いじめの認知件数、重大事態の発生件数が過去最多となりました。
いじめ防止対策推進法ができてから10年。一体、何をしていたのでしょうか。重大ないじめが起きるたびに、いわゆる「専門家」やマスコミは、学校と教育委員会を批判してきましたが、それで何か改善したでしょうか。学校側にはすでに数多くの対応が求められています。そこにさらなる研修や罰則を加えたとしても、空回りに終わるだけです。
学校側の対応を表面的に批判するよりも、なぜ学校側が適切に対応できなかったのか、そこに目を向けてほしい。保護者の問題はその最たるものです。感情的になった保護者が学校に過度な要求をすることは珍しくなく、学校側が法律にのっとって対処しようとしているにもかかわらず、保護者がそれを妨害することすらあるのが実態です。
政治家も官僚も、表立って「保護者に問題がある」とは言いづらいのでしょうが、もっと現場の実態を見てほしい。教育委員会や学校ばかりを問題視し、保護者の問題から目をそらしていては、この状況を打開することは難しいと思います。
――かねてより保護者の問題を指摘されています。
最近、埼玉県の虐待禁止条例の改正案が議論の的になりました。小学3年生以下の子どもだけで留守番させることや、子どもだけで公園で遊ぶことを禁止したことが批判を呼びましたが、私はむしろ、この条例案に賛同する部分もあるのです。
留守番中の子どもや、公園で遊んでいる子どもを狙った事件や事故は実際に発生しています。確かに地域の見守りなども重要ではありますが、第一義的な責任があるのは保護者です。万が一、子どもに取り返しのつかないことが起こったら、保護者は必ず後悔します。そうなる前に何らかの対策をすることも、保護者として必要ではないでしょうか。
いじめ問題を巡っては、学校や教育委員会を一方的に攻撃したり、子どものことを学校に任せっぱなしにしたりする、「お客さま」状態の保護者が本当に多くいます。本当に子どもを守りたいなら、保護者も法律やガイドラインをきちんと読み、子どものために何ができるのかを学校と共に考えてほしい。学校側だけにやるべき対応を課して、それができなければ厳罰を加えるなどと言っていたら、教員のなり手はいなくなりますよ。
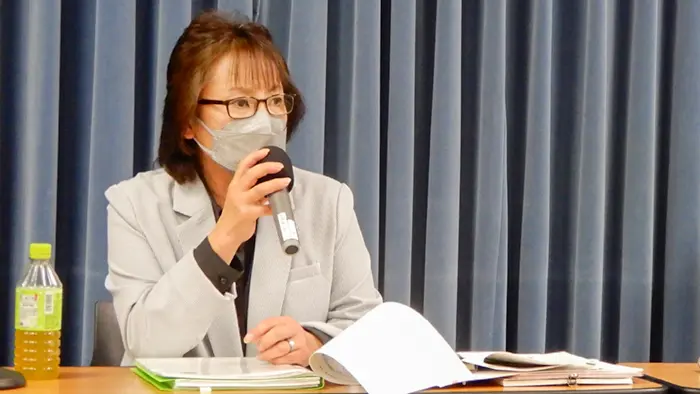
――問題行動調査によれば、いじめ重大事態の38.7%が、重大事態に至るまでにいじめとして認知されていませんでした。
数々の学校と関わった身として、教員が一切何もしていないという状況はちょっと考えにくいです。何らかのいじめの情報が入ったら、教員の多くはおそらく当事者の子どもや、クラスの子どもたちに聞くなどしているはずで、そこで「何も知らない」と言われてしまえば、確認できないことも当然あるだろうと思うのです。
そもそも学校は教育の場です。子どもたちがしたことが良いことなのか、悪いことなのかを考えさせ、悪いことならば改善を促していくところです。その一つ一つについて、いじめと認定するかどうかの判断まで求めるのは、無理があるように思います。
子どもたちの行動を取りこぼさず、学校のいじめ対策組織に報告せよと言うのならば、それができるような勤務環境を整えてからにしてほしいものです。適切な対応を求められるだけの体制や環境が整っていないにもかかわらず、次々と業務を増やせば、対応に不備が生じたり、新たな問題が発生したりしてしまうのは当然です。
――今後の重大事態対応の在り方をどう考えますか。
文科省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」には、「被害児童生徒や保護者から、『いじめにより重大な被害が生じた』という申し立てがあったときは(中略)、重大事態が発生したものとして報告・調査などに当たること」という方針があります。
学校で把握しづらい場所でいじめが行われている場合を想定したものですが、やはりこの対応には限界があります。保護者の要求に応じて、何でもかんでも重大事態にしていたら切りがないし、調査委員会を設置するための人も財源も足りません。どこかで線引きをする必要があります。
まず、このガイドラインの見直しは必須だと思います。保護者から申し立てがあった場合、全ての事案について調査委員会を設置するのではなく、申し立ての内容を重大事態として扱うべき事案であるかどうかを検証、または精査する組織を設け、判断する必要があると思います。
調査委員会を設置することになっても、学校側と保護者が対立して調査が進まないこともありますから、第三者の介入が鍵になります。調査の進め方について関係者の共通理解を図った上で、中立の立場に立ち、学校も保護者もきちんと納得させられるような専門家が必要です。制度設計に当たっては机上の空論でなく、現場に足を運び、現場の声に耳を傾けてほしいものです。