中部地方初となる公立の「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)」として、2021年4月に開校した岐阜市立草潤中学校。登校しても家庭にいても学べる、担任は生徒が選ぶ、校則や制服などの決まり事はないなど、不登校を経験した生徒のありのままを受け入れる「学校らしくない学校」として、開校当初から注目を集めてきた。生徒たちはこの3年、どのように過ごしてきたのか━━。草潤中の今を取材した。
昼食の時間、3年生4人が校長室にわらわらと集まってきた。聞けば、4人はよく校長室でお弁当を食べているそうだ。決まり事のない草潤中では、昼食も好きな場所でとることができる。教室で食べる生徒もいれば、図書室や中庭など、おのおのが好きな場所で過ごしている。
今は「ほぼ毎日登校している」という4人。不登校の経験について聞くと、「小学2年生の時、友達とのトラブルがきっかけで」「学校のルールに違和感があった」「先生からのプレッシャーが嫌で、小学5年生からだんだん行けなくなった」と、きっかけや期間はそれぞれだった。草潤中の良さを「自由なところ。絶対ルールみたいなものがない」「他の学年の授業も受けられる」「みんな同じ経験をしているし、友達はみんな優しい」などと口々に話す。
草潤中では担任を生徒が選べるシステムだが、「1年の時からずっと同じ先生」という生徒もいれば、「毎回、変えている」という生徒も。このシステムについて「ここの先生はみんな親しみやすいから、常にいろんな先生と話している。あんまり担任だからということにはこだわっていない」と生徒たちは口をそろえる。
年間総授業時数は770時間と、通常の中学校の4分の3程度の時数で編成されている草潤中。ある生徒は「授業が少ないから、やっぱり普通の中学校の子たちには勉強面では追い付けないと思う」と言うが、「でもこれ以上、授業は増えてほしくないかな」と正直な気持ちを明かす。
年に2回ある期末テストも強制ではなく、希望者が受ける。中には「自分が好きな教科のテストだけ受けている」という生徒もいる。テストだけでなく学習状況をもとに個別に評価を行うが、それでも3年生になると進路を意識し、自然とテストを受ける生徒が増えるという。
全校生徒40人のうち、3年生は19人。初めて3年間を草潤中で過ごした卒業生となる予定だ。夏休み中はそれぞれが気になる高校の見学会に参加し、卒業後の進路についても「ほぼ決めている」と言う。「テストを受けるかどうかや、卒業後の進路なども、全部自分で考えて、自分で決める。ここにきて、それが当たり前になっている」と、草潤中での日々を語る。
「開校当初に『きっとこうだろう』と想定していた以上に、心身が安定してエネルギーに満ちた生徒たちが学校に求めることは、多様に変化している」
そう話すのは鷲見佐知校長だ。例えば、草潤中にはさまざまなユニークな教室が用意されているが、「1人になりたい子が多数いるだろう」と用意した9つの個室ブースは、一時的な休憩場所として使われることがほとんどだという。
一方で、想定以上に活用されているのが、今年度からスタートした学び直しの教室。数学や国語などの別教材に加え、小学生のドリルも各種用意されている。「生徒たちの様子を観察していくと、勉強への抵抗感がある子が多いことが分かってきた。その子が分かるところまで戻って学び直せる体制をとっている」と説明する。

また、草潤中では「毎日登校する」「週の〇曜日と〇曜日は登校する」「家庭学習を中心とする」など、いくつかのパターンから登校スタイルを選択する。生徒たちは心身が安定すると「学びたい」「仲間と関わりたい」という思いが生まれ、学校へと足を運び、学校生活を楽しもうとする。そして、最初に決めた登校パターンは、その後、何度も変更されていくという。
「ただし、子どもたちの心身が安定するまでには時間もかかっている」と鷲見校長は振り返る。不登校を経験し、草潤中に入学してきた生徒たちは、最初はみんな大きな不安や緊張の中にいる。そこから教員が「この方法ならできるかな」「先生と一緒にやろう」と見守りながらもサポートしていく。そうしていくうちに、生徒は「自分もできるんだ」「先生が助けてくれる」と少しずつ安心し、草潤中が居場所となっていく。
その過程では、疲れて休むことや、不安になることもある。「それも当たり前だし、疲れて休むときも、ここの教員は『いいよ、大丈夫だよ』と生徒のありのままを受け入れてきた」と鷲見校長は語る。
「この3年、生徒たちは『自分で調整する力』を付けてきている。頑張る時と、休む時を安心して行き来できるような環境を用意しておくことが、子どもたちの成長につながっている」

取材に訪れた日の午後、全学年で総合的な学習の時間の授業が行われていた。グループごとにスポーツフェスティバルや、「草潤トラベル」という日帰りの校外学習、文化祭、クリスマス会などについて企画を立て、準備を進めていた。
草潤中では、学校行事は生徒の願いをもとに計画がスタートする。「何をするか」から生徒が決めるので、毎年同じ行事をするわけでもないという。スポーツフェスティバルを企画するグループの生徒は、「今年は『1、2年生』対『3年生』でやる。実施する種目やその順番、ハンデの付け方なども全て私たちで決めるんです」と声を弾ませる。
鷲見校長は「本校を選んできている子たちは、学校が嫌いだとか、学校なんて必要ないと思っているわけではなかった。勉強がしたい、運動会もやりたい、修学旅行も行きたい、友達とも関わりたいのだと、分かってきた」と生徒たちの様子に目を細める。
開校当初、草潤中は「学校らしくない学校」として注目を浴びた。鷲見校長は「最初は学校らしさを排除し、学校の“正反対”からスタートしたが、成長するうちに子どもたちは学習や仲間とのつながり、将来の夢と、多くのことを求めるようになった」と話す。
「安心を必要としている子や、目標に向かって努力する子……。どの生徒の思いにも応えられる柔軟性を持っていることが、この学校のありようなのではないか」と手探りの中、3年かけて見えてきた草潤中の現在地を語った。
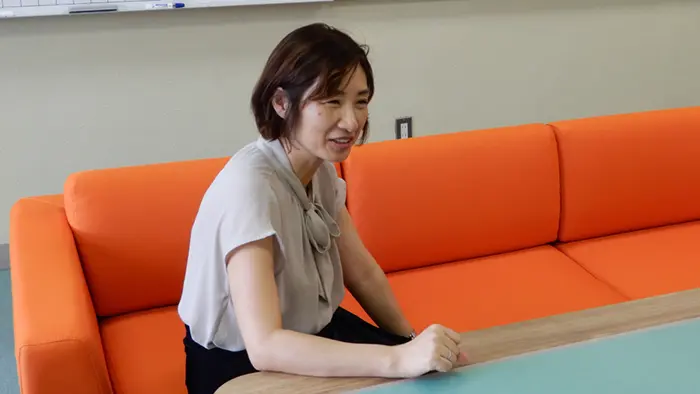
次回は、草潤中での勤務を希望し、3年間、生徒と共に学校をつくってきた教員へのインタビューを通し、不登校を経験した子どもたちへの支援の在り方を探る。