仕事の効率化の術をSNSで発信する柴田大翔教諭。実は月100時間超の残業で心身ともに疲れ果てていた時期もあったというが、当時はICTの先進校ということもあり、チームワークで乗り切る雰囲気に流されてしまっていたという。「このままでは続かない」と思い手に取った仕事術の本に刺激を受け、「何でも自分でやるのがいいことではない」と意識を変えたと当時を振り返る。今は定時には学校を出る日が実現できているという。(全3回)
――著書の中で印象的だったのが、「気持ち良く、早く退勤する秘訣」です。自分の仕事が終わっているけれど、帰っていいのか迷うときに、日頃から「学年のことで何かできることはないですか?」と声を掛けておいて、学年の仕事に協力する姿勢を見せる。すると退勤前に「今週中にこの仕事は終わらせた方がよさそうだね」と振られても、「分かりました! 明日、やっておきます。お先に失礼します」とさわやかに退勤できるという技がすごいなと思いました。
これは子どもが生まれて、本当に早く帰らざるを得ない状況になって生まれてきたものです。それまでは私自身、気にし過ぎる性格が災いして、自分の仕事が終わっていても他の先生の目を気にしたり、保護者からの電話が入ることを心配したりして、ずるずると学校に残っていました。でも、案外何事もなく、ただ在校時間が延びているだけのことも多かったんです。
子育てが始まると、そうは言っていられません。早く帰るために、日頃から学年の仕事を少しでも引き受けておくようにし、職場に信頼の貯金をつくるようにしました。特に学年に複数のクラスがあるときは、自分から積極的に声を掛けてコミュニケーションを取るようにし、学年の仕事を日々の仕事に割り振って残業にしないようにしていました。若い先生も、早く帰りたいのであれば普段から「何かできることはありませんか?」と積極的に話し掛けてみるとよいと思います。
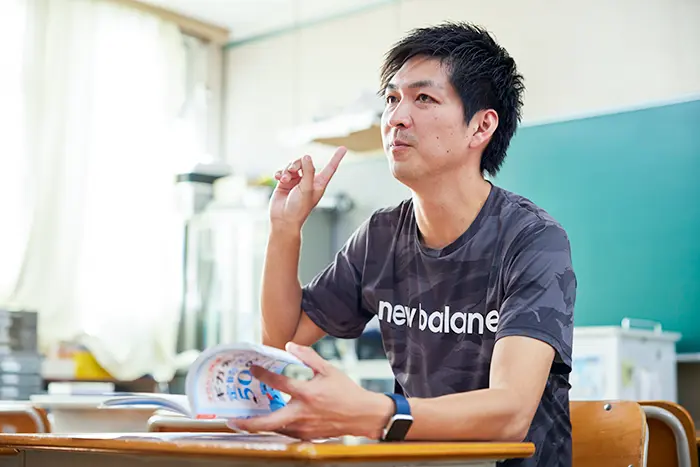
――他にもずるずると残業しないコツはありますか。
「プライベートの楽しみを設定する」ことではないでしょうか。以前の勤務校では先輩の先生に時々、退勤後にスーパー銭湯へ連れて行ってもらったり、串カツを食べにいったりと楽しいことに誘ってもらっていました。そうしたことを楽しみに、「今日はこれを頑張ろう!」と思いながら過ごしていました。コロナ禍ですっかりそういう機会が減ってしまいましたが、「何か楽しい予定を立てれば仕事がはかどる」という経験をさせてくれた先輩には感謝しています。
教師の仕事は、やろうと思えば無限に出てきます。そこに流されると残業時間が延び続けてしまいます。でも、何か楽しみを設定すれば、そこに向かって1日の仕事の区切りがつけられます。もちろん、スーパー銭湯に毎日行くわけにはいかないので、例えば「今日は帰ったらあのゲームをしよう」とか「近くにできた新しいケーキ屋さんに寄ってみよう」とか、ちょっとでもいいから自分へのご褒美をつくって、退勤に向かって仕事を終わらせる意識が持てるとだいぶ違ってきます。私自身は今、子育て優先なのでなかなか寄り道はできませんが、それでも研究授業やイベントの後には他の先生方と食事しに行ったりする機会を大事にするようにしています。
――柴田教諭自身も、かつては残業時間が長かったそうですね。
働き方改革が始まる前は、毎月の平均残業時間が100時間を超え、多いときは145時間にも上っていました。朝6時から夜10時ごろまでは学校にいました。
今思うと「何でも丁寧にする」のが長時間残業の原因だったと思います。子どものノートを頻繁に集めて全部にコメントを返すなどしていましたし、動線の無駄も多かったと思います。独身だったので、1日のタイムリミットも決めていませんでした。
きっと、自分の中に教師として譲れない部分があったんだと思います。授業準備にも「ここまではやっておきたい」というラインがありました。「早く帰るのは手を抜くことになりはしないか。それで学級が崩壊したらどうしよう」と不安がよぎることも多く、「納得いくまで頑張らなくては」という思いに駆られていました。

――それで疲れなかったんですか。
疲れていました。若かったから何とかなっただけで、今同じ働き方をしろと言われても無理ですね。食事もお弁当を買って済ませることが多かったですし、何より睡眠時間が足りていませんでした。でも、子どもを前にするとアドレナリンが出て、疲れを感じなかったんです。学校を出た後にどっと疲れが出て、眠気が襲ってくる。そんな毎日でした。
当時、周りにいた先生も同じような状況で、声を掛け合って「頑張ろう」という雰囲気でした。チームワークは良かったんですが、もしかしたらしんどい先生もいたんじゃないかなと思います。
――残業を減らすために、まず何から始めたのですか。
「このままではまずいな…」と思っていた頃、ふらっと入った書店で「仕事術」の本が目に入ってきました。その後、学校の先生が書いている時短術の本や、ビジネス系の仕事術の本を読みあさり、できるものから取り入れました。
例えば、「会って伝えるのをやめてメールにする」のは仕事術の本から学びました。全ての用件を対面で直接伝える必要はないはずですが、学校では「〇〇先生を探さなきゃ」となってしまいがちです。可能なものはメールで済ませるようにし、その文面も一から考えると時間がかかるのでテンプレートを作っておくようにしました。
――授業の進め方や学級運営にも、時短術を活用しているそうですね。
「宿題の丸付けをする」「提出物チェックは学級名簿で行う」といった新任の頃からやってきた仕事を手放し、テスト以外の答え合わせや提出物チェックは子どもに任せています。教師が全部やってしまうことで「子どもの成長を奪ってしまっている」と気付いたからです。

「丸付けを先生にしてもらうのが当たり前」「提出物の確認を先生にしてもらうのが当たり前」になってしまうと、子どもは誰かがいないと勉強できない人になってしまいます。そのため、学年の最初に答え合わせのやり方などを伝え、自主学習スキルを育てるようにしています。
子どもには「これからは自分たちで自分の学習を進められる人になってほしい」とはっきり伝えています。そうすることで担任の手が空き、学習につまずきのある子に寄り添う時間ができるのです。
【プロフィール】
柴田大翔(しばた・ひろと) 1990年、大阪府生まれ。大阪府の公立小学校教諭に勤務。月100時間以上の残業をほぼ毎日定時に帰れるまで激減させた経験を持ち、現在は日々授業や校務にタブレットをフル活用する。時短術、ICT活用、子どもたちが笑顔になる学級経営のコツをSNSで発信中。総フォロワー数は1万9000人を超える。著書に『今日から残業がなくなる!ギガ先生の定時で帰る50の方法』(学陽書房)、共著に『小学4年 学級経営ペディア』(明治図書)がある。