子どもの言葉を軸に自然と授業が進み、学びが深められていく――。そうした真の意味での「対話型授業」を実践し、注目を集めているのが新潟大学附属新潟小学校の中野裕己教諭だ。インタビューの第2回では、授業展開の裏側にある進め方の秘訣(ひけつ)や授業に抱く信念などを聞いた。(全3回)
――今回見せていただいた授業は、前回あった公開授業の続きですね。指導案を見ると、公開授業でやる予定だった後半部に当たるように見えます。
その通りで、公開授業の時は途中で終わってしまったんです。公開授業は本校の研究会で、私の授業にも100人くらいの方がいらしていました。国語の授業で教材文が「お手紙」だったので、手紙にまつわることで自分が経験していることと、教材文の中で手紙を巡って起きていることを比較させて、子どもに問題意識を持たせたかったんです。
「手紙に関わるあなたの経験と、教材文での出来事とでは、何が違うでしょう?」と問い掛けると、子どもたちは生活科の授業でタブレット端末に保存した学習記録から振り返るなどして、「手紙を書くときはこうしたね」とか「自分たちは直接渡しに行ったね」とか、そんなことを思い出しながら、教材文に出てくる「かえるくん」がどうしたかを見ていきます。そうやって問題意識を高め、集団の中で意見を交わし合うことで、問題を解決していくような授業展開を考えていました。
授業で何が起きたかというと、子どもたちが手紙を巡って思い出したり考え出したりしたことがたくさんあり過ぎて、それらを丁寧に扱っていたら、あっという間に45分が過ぎてしまったんです。
結局、最初の15分でやろうと思っていたことに45分を使ってしまいました。このことは一見ネガティブなことに思えるかもしれませんが、私はそうは思っていません。子どもたちが自分たちの経験したことと文章とをつなげて、じわじわと物語の本質的な部分に迫っていく、そんな展開が実現できたと思っています。ちなみにその授業は、子どもたちの問題意識が物語の本質的な部分にたどり着いたタイミングで、「『授業1』を終了します」と終了の放送が入ったんです。その時の子どもたちは、「えー!!」「あと2分だけやらして」と大騒ぎでした。「もっと授業をしたい」「もっと考えたい」という意欲の高まった子どもたちの姿は、教師主導ではなく、子どもたち主体で授業が進んでいたからこその姿だと思っています。
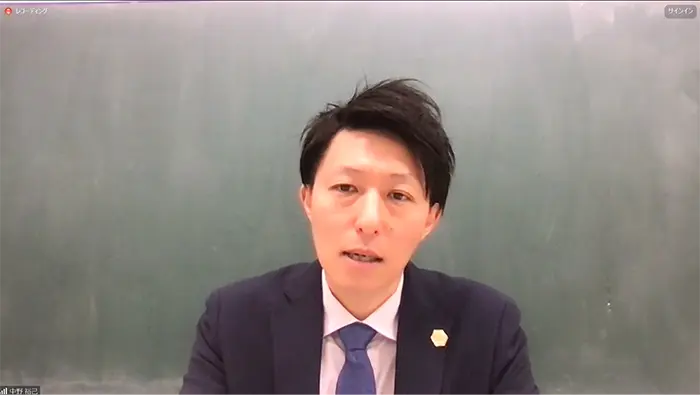
――今回拝見した授業も、指導案通りではないところがいくつかありました。特に、一人の子の発言を拾い上げて、そこから授業を展開していった流れに驚きました。子どもの発言を取りこぼさない中野教諭の瞬発力を感じています。
あの発言は、あの子が一人で考え出したものではなく、そこに至る学級での対話がベースになって生まれたものだったと思っています。
私からの問い掛けは「自分たちが書いた手紙と、物語で『かえるくん』が書いた手紙とでは、どんなところが違うかな?」というものです。低学年の子の場合、抽象的な思考が難しいので、まずは個別具体的なところから話していきます。切手や封筒など、比較できる具体物を集めていく。すると、次第に抽象的な事柄が見えてきたりするんです。
その子の「自分たちの手紙と『かえるくん』の手紙では、目的が違う」という発言は、それまで具体をたくさん聞き取ったり、考えたりしたからこそ出てきた言葉なんです。私が子どもたちにつかんでほしい本質はまさにそこだったので、とても感動しました。
おそらく、もともと他の子も気付きかけてはいたけれど抽象的で言葉にできなかった部分を、その子が言語化したんだと思います。みんなで学ぶ醍醐味(だいごみ)の一つが見えた瞬間でした。
――他の子どもがあれこれ言っている中で、この子は最初から「目的が違う」と分かっていたのだと思ったのですが、そうではなく、みんなで対話したからこそ出てきた発言だったんですね。
そうなんです。子どもには、本質的なものが出てくるまでの、いわばエンジンをかけている時間があるんです。大人には無意味そうに感じられるかもしれませんが、子どもにとっては非常に大事な時間です。その時間を待てるかどうかが、子ども主体の授業をつくっていく上で分かれ道になると思います。
――確かに、授業の間、一度もせかしたり発言をさえぎったりせず、子どもたちが対話を重ねて新しいことに気付くのを待っていました。これだけ瞬発力がありながら待てることに驚いたのですが、もともとそういった関わりをされてきたのでしょうか。
いえ、今のような授業スタイルが自分に定着したのは、ここ2~3年くらいのことだと思います。その背景には、コロナ禍の期間がありました。
現任校では毎年研究会をしていて、コロナ禍以前は授業を直接見に来ていただいていました。でも、コロナ禍になってできなくなったので、先生方を直接お呼びしなくても授業を通して学び合う仕組みをつくれないかと、みんなで話し合ったんです。
そうして、授業の動画を配信しようという話になりました。撮影した動画は、確認のために事前に見ることになります。すると、授業をしながらでは分からなかった子どもの学びがたくさん見つかったんです。「授業をしながらだと聞こえなかったけど、この子たちはこんな話をしていたんだ」と気付くことがたくさんありました。それで、子どもたちの考えていることやそれぞれの学びへの興味関心に、より一層拍車が掛かったのです。
このきっかけは特殊な例かもしれませんが、やはり子どものしていることを丁寧に見ることが授業を変えるきっかけになるのだと思います。どの子も学ぼうとしている、だからそれを理解し支えたい、そう思って授業をしています。

――中野教諭の働き掛けで意外だったのは、「静かに」「うるさい」「今は先生が話しています」といった注意が一切なかったことです。子どもたちが待てずにしゃべり始めた時も、いったん受け止めてから話し始めていました。
教員は「先生が話しているから君たちは黙るんだよ」というふうに、無意識で言ってしまいがちですが、そう指示したところで子どもたちは聞いてくれません。話すのはやめるかもしれませんが、頭の中は話したい気持ちでいっぱいになっているから、結果として聞いているふりをすることになります。
そう考えているので、「聞きなさい」「姿勢を正しなさい」「こっちを見なさい」などと言うのは必要最小限にしています。子どもたちが聞けるタイミングで私が声を出すというのを強く意識しているんです。子どもたちが盛り上がっている会話の切れ目を見つけて何かを提示するようにすると、子どもたちの声はピタッと止まります。
それから声のトーンも意識しています。普段のしゃべり方とちょっと違う、「ねえねえねえ」というような呼び掛けです。少しトーンを落とすことで、子どもたちは「あれ?」という感じでこちらを見てくれます。そうすることで、子どもたちが聞ける姿勢になると思っています。

――しゃべってしまう子に対しても、叱ったりするのではなく、「よく読んでいるから、いっぱい気付けるんだね」などと声掛けをしていました。その他にも子どもを個々に、あるいは学級全体を褒める様子が何度も見られました。
褒めることについては、意識しているというよりも、子どもたちがやっていることを見て素直に「すごいな」と思うことを言語化するようにしています。
例えば、今お話に出てきた子についても、何か考えついたときに教材文に目を落とすのは、小学2年生ではすごいことなんです。低学年の子は空想の中で自分の考えを作って話してしまうことが多く、「きちんと文章を読む」ことは意識しないとできません。そういうやり方が身に付いているのは、素直にすごいなと思います。
また、黒板を使って一斉授業を進行している時に、「はい! はい!」と手を挙げる子もすてきです。一方で、手は挙げていないけれど、先生が言ったことや友達の言ったことを聞いて、一生懸命ノートにメモしている子もすてきです。だから、子どもたちの「すごいな」「すてきだな」と思うところを見つけるのは無意識でやっていて、それを言語化するというのは意識的にやっているといった感じです。
【プロフィール】
中野裕己(なかの・ゆうき) 新潟大学附属新潟小学校教諭。1986年、新潟県生まれ。新潟市立小学校教諭を経て現職。全国国語授業研究会監事。授業改善コミュニティー「授業てらす」プロ講師。Google Educator Group Niigata Cityリーダー。 教員サークル「国語授業“熱”の会」代表。教員向けの研修で講師を務めることも多い。著書に『子供が学びを創り出す 対話型国語授業のつくりかた』『教科の学びを進化させる 小学校国語授業アップデート』(いずれも明治図書)など。新著『授業はタイミングが9割』(明治図書)を2月に刊行予定。