「子どもの問題行動に対しては、教員個人の責任ではなく学校全体で取り組むべきこととしたい」という考えから、徳島県教育委員会特別支援教育課の課長・田中清章さんが導入を立案した「ポジティブな行動支援(School-Wide Positive Behavior Support、スクールワイドPBS)」。インタビューの最終回では、導入による成果や今後の展望を聞いた。(全3回)
――子どもの望ましい行動を育てるスクールワイドPBSでは、指導後に成果が上がらなかった場合でも、子ども自身が「どうしたらいいか」を考え、改善に向けた行動を取るとのことでした。
「学級経営で困っていることや悩んでいることがある。学級がまとまらず、ついつい叱ってしまうことが多くなった」と悩んでスクールワイドPBSを導入した東みよし町立加茂小学校では、「学年が違っても大きな声であいさつしよう!」という行動目標を立てた際、児童会の子どもが朝のあいさつ運動をしました。その際、例えば7時20分~7時40分のように時間を決めて、「自分からあいさつした人」「児童会があいさつをしたら返した人」「あいさつをしなかった人」の数を数え、記録として残したんです。その記録を担当の先生がエクセルでグラフにし、子どもたちにフィードバックしました。
――記録は子どもたちが取ったのですね。
現場の先生方はとても忙しいので、できるだけ児童会や放送委員会など、既存の仕組みを使って取り組みを進めています。子どもが当事者として関われるという利点もあり、一石二鳥のやり方だと思っています。
そしてフィードバック後に、成果が見られなかったら方法を変えて、再度取り組みます。例えば、新たなキャンペーンとして全校集会で劇をして、あいさつの仕方を示すといった形です。加茂小学校は今、全国から視察が相次いでいるのですが、同校の教員からは「子どもたちが小学校時代に『学校を変える』という体験をできたのが非常によかった」「子どもたち自身が動いたのが効果的だった」という話をしています。
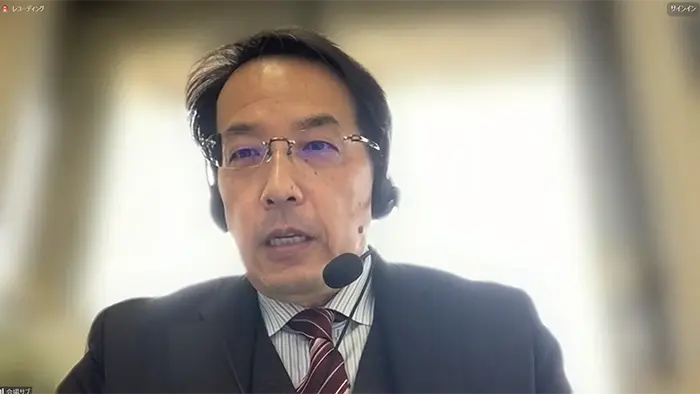
――スクールワイドPBSでは、専門家の派遣もしているそうですね。
県の教育委員会で発達障害教育の推進プロジェクトチームを立ち上げていて、応用行動分析学をベースにしたポジティブ行動支援を専門とする県外の先生が8人所属しています。この8人の先生方に、各学校現場で支援をしていただいています。
――予算は県から出ているのでしょうか。
県から出ています。米国ではスクールワイドPBSが法律により、エビデンスに基づいた実践を学校現場に導入しなければいけないことになっていますが、日本にはそうした法律がないので、県レベルでやっています。
今、スクールワイドPBSを県の施策として進めている自治体は、徳島県の他に広島県や宮崎県などがあります。徳島県では全国に先駆けて2016年度から取り組みを進めていて、今は指導主事や巡回相談員が各小中学校を回り、専門的な指導をしています。今年度は専門家チームを新たに立ち上げ、さらに組織的に取り組んでいきたいと考えています。
――成果が認められて、より一層取り組みが進むのですね。授業前や授業中の望ましい行動が身に付いたとのことで、学力向上にも効果があったのではないでしょうか。
そうですね。ただ、科学的なデータとしては取っておらず、学力向上やいじめの認知件数、不登校数に関しては現状でまだエビデンスがないんです。来年度からはデータを取っていきたいと思っています。
小学校ではスクールワイドPBSの考え方を授業に生かそうということで、専門家のアドバイスを受けながら取り組みを始めています。例えば算数の授業では、挙手や発言のほか、自分の考えや調べた内容などをまとめたノートを机上に置き、互いに教室内を自由に歩いて見て回る「ギャラリーウォーク」やペアトークなどを実施して、できるだけいろいろな子どもが授業に参加できるような授業づくりをしているところです。
そうした形で、授業の中で「できた」と感じる経験を繰り返すことによって、子どもたちが素早く作業に取り掛かれたり、発表にチャレンジできたり、単元テストの得点が上がったりといった成果は報告されています。とはいえ、科学的な研究データとするにはまだ不十分なので、来年度からはそうしたデータも取得していきたいと思っています。
その他にも、文部科学省の問題行動調査にある「自分が好きですか」「学校は楽しいですか」という評価項目で、取り組み前よりも評価が上がったというデータはあります。また、現状では県内の小中学校と園での取り組みですが、いずれは高校でも推進していきたいと考えています。
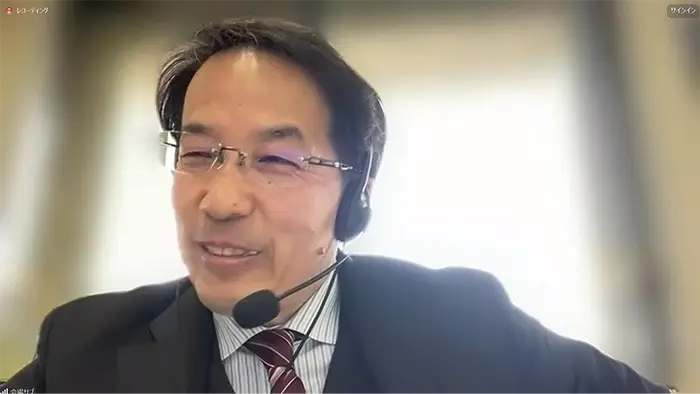
――スクールワイドPBSの事例の一つである「話を聞く」ための行動の支援など、校種を問わずに重要な指導もいくつもありますね。
そうですね。「話を聞く」は授業準備行動の一つで、授業を成立させるために教員が前に立ったらそちらの方に注目するというのが、幼稚園段階からの大きなポイントになります。でも、それができていない子どもが少なくありません。この時、「こっちを向きなさい」と言うのではなく、できている子を褒めることで、できていない子はできている子をまねしようとするのです。
幼稚園や小学校では合言葉を作った上で、年度初めに子どもたちに向けて「みんな、こっちに注目できてるね。じゃあ、今から先生が話し始めるよ」といった働き掛けをしています。何人か見ていない子がいたら、その際も注意するのではなく、できている児童を賞賛することで、適切な行動を強化します。
――集団の中で叱られるというのは、年齢が上がってもつらいことなので、こういった取り組みは中学や高校でも有効だと感じています。東みよし町立三加茂中学校の生徒たちが取り組んでいるロッカーや机の整理などは、高校生や大学生、社会人になってからも役立つスキルだと思います。
その通りだと思います。話は変わりますが、スクールワイドPBSへの理解が進まない理由の一つに、「これって当たり前のことじゃない?」と言われてしまうことが挙げられます。
――どういうことでしょうか。
「わざわざマトリクス表を作って先生方が共通理解して、子どもに掲示して行動練習して記録を取って…と、そこまでする必要があるんですか」という疑問です。そういった質問をよくいただきます。
確かに「できて当たり前のこと」ですが、現実にはできていない子どもがいるのだから、やるべきだと考えています。そういった疑問に対しては、一つ一つ丁寧にポイントを伝え、マトリクス表の作成を支援するなど、手順に沿ってサポートしているところです。
――「できていない子を注意すればいい」という考えもあるのかもしれませんが、実際に私が教員時代に勤務していた高校では問題行動をした生徒にチケットを渡し、一定数それがたまると居残り指導をするといった方法で改善を図っていました。でも、結果として生徒が委縮するようになったと感じました。
実はそれと似たような事例が米国で実際にあったんです。「ゼロトレランス方式」と言って、1990年代に当時のクリントン大統領の呼び掛けの下、「いかなる状況においても問題行動は許さない」「規律を破った生徒には有無を言わさず、停学や退学などの厳しい罰則を下す」などの措置が取られました。日本においても、「毅然とした生徒指導」という形で紹介された時期がありました。
でも、「ゼロトレランス方式」は暴力やいじめなど問題行動の抑止にはほとんど効果がなかったんです。停学によって子どもの学習機会を奪うことも問題視されました。そうした背景もあり、米国ではポジティブ行動支援を行うことが方針で示され、スクールワイドPBSを普及するためのセンターも設置されました。そうした経緯で急激に広まり、今では全米約2万7000校で実施されています。
「悪いところを教員が見つけて抑え付ける」という指導では、「怒られないように行動しよう」という考え方が強化されるだけです。スクールワイドPBSのポイントは、肯定的な目標を子どもたちに分かりやすく伝えて、「~してはいけない」ではなく「~できるようになろう」を目標に、伸ばしていくところです。
――スクールワイドPBSを本格的に展開できたら、真の意味でのインクルーシブ教育が進むように思うのですが、いかがでしょうか。
「インクルーシブ」については、いろいろな誤解があると思っています。障害がある子が通常の学級で過ごすことがインクルーシブ教育だと思われる方もいますが、私は特別支援学級や通常学級、特別支援学校などがある中で、子どもが選択して学べる状態がインクルーシブ教育だと思っています。
ただ、近年は通常の学級に在籍する障害のある子どもの数が非常に増えているんです。そうした状況がある中で、教員個人のスキルや努力で対処するのではなく、エビデンスに基づいた指導法を取り入れて、学校全体で推進すべきだと考えています。そうすることで、教員全員で目標を共有し、達成に向けて進んでいけると思うんです。
発達障害のある子どもは、権威のある人に褒められると非常に喜ぶ傾向があります。だから、担任が校長先生に「この子は目標のこの部分を頑張っているので、個別に声を掛けて褒めてあげてください」といったことをお願いすればよいと思います。
「廊下を走らずに歩く」という目標でも、多忙な担任はなかなか賞賛する時間が取れません。校長先生であれば、時間を決めて廊下を巡回すれば、子どもの行動を即座に褒めるなどできます。
そうやって賞賛する機会が重なれば、望ましい行動が強化できます。「廊下を走らずに歩く」といった当たり前の行動を褒められることはほとんどありません。それを見つけてもらって褒められたら子どもたちは喜ぶので、その意味でも学校全体で取り組むのには大きな意味があると考えています。
【プロフィール】
田中清章(たなか・きよふみ) 1994~2004年まで特別支援学校教諭。その後2年間、鳴門教育大学大学院に在籍した後、阿南市立富岡小学校の教諭として3年間、担任を務める。10~11年度に特別支援学校教諭となった後、12~15年に徳島県教育委員会特別支援教育課指導主事、16~17年度に徳島県立総合教育センター特別支援・相談課班長、18~20年度に徳島県教委特別支援教育課統括指導主事、21年度から同教委特別支援教育課課長を務める。徳島県が展開する「スクールワイドPBS」の推進役を担う。