日本社会は長年にわたり男女共同参画が叫ばれながら、OECD男女賃金格差ランキング(2022)で下から4番目、世界経済フォーラム「ジェンダーギャップ指数2023」では146カ国中125位と、いまだジェンダー平等が実現できていない。その背景に「学校教育の中の二重基準の問題がある」と指摘するのが、愛知東邦大学の虎岩朋加准教授だ。インタビューの第1回では、フェミニズムを中心に教育理論研究を行っている虎岩准教授に、ジェンダー平等の実現に果たすべき学校の役割などを聞いた。(全3回)
――昨年10月に著書『教室から編みだすフェミニズム』(大月書店)を出されました。日本のジェンダーバランスが国際的にも最低レベルと指摘されていますが、性差別の構造を作り出している原因として学校に着目した理由を教えてください。
学校は、男女平等の原則が忠実に守られている場所だと一般的には考えられています。しかし、最近では東京都立高校の男女別定員の問題や、医科大学での男女で異なる入試基準の問題が露呈するなど、実際には性に関する差別の構造が続いてきました。表向きは「男女平等」と言いながら、無意識の差別意識が裏側にはあるのではないでしょうか。
こうした二重基準が社会にも学校にも存在しています。特に学校文化は「男とか女とかことさら取り立てない」ことが実践されている文化なので、逆に性に基づく差別を意識することを妨げている面があると思います。
教育社会学の分野では、以前から「隠れたカリキュラム」として指摘されてきました。例えば、大阪大学の木村涼子教授が「隠れたカリキュラム」の特にジェンダーの側面を指摘されていて、学校が特定の女性らしさ・男性らしさを再生産しているという研究は蓄積されています。学校が性差別の構造を再生産している部分があると考えた背景としては、先行研究を踏まえて研究を続けてきた結果と言うことができます。
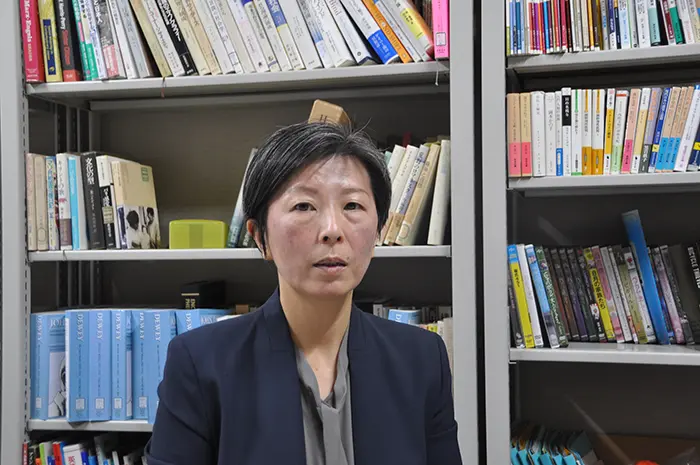
――これまで男女混合名簿や高校の男女共学化、家庭科の男女共修化などの取り組みがありました。学校現場の変化をどう受け止めていますか。
本質的なところでは正直、変わらないなというのが正直な実感です。例えば、先生の無意識の発言は、結構いろいろとあるんです。
私が指導した学生の一人が卒論研究の一環で、中学1年生の教室を1カ月間、観察したんです。そのとき、女性の先生が金属に関する授業でプラチナの話題を出したのですが、「プラチナ、覚えておきなさいよ、男子」と言ったそうなんです。「婚約指輪は給料の3カ月分」といったことを生徒たちに何気なく語ってしまうわけです。
このように、男性が経済的に成功していなければいけない、経済力を持っていなければならない、女性に婚約指輪を渡さなければいけないといったことを先生が当たり前に話すことで、子どもたちもそれを受け入れてしまうのです。先生が無意識に話した言葉を生徒たちが内面化して、性差別を再生産してしまっているのだと思います。
私自身も、自分に自信が持てない部分があります。そういう部分は、人からのいろいろな言葉掛けによって思い出され、自分の可能性を減じてしまったりする。そういうことはどんな人にも起きていると思いますが、特に日本は男性中心主義的な考え方がいまだに強いので、女性が受ける影響は大きいと感じます。
「小学校の低学年はベテランの女性教員がいい」「高学年は宿泊を伴う行事があるので男性教員がいい」といった考え方があります。今は学校現場の人手不足もあって必ずしもそうはなっていないかもしれませんが、意識的な部分ではやはり根強くあると思います。こんなに世の中が変わってきているし、良いか悪いかはともかくいろいろな分野に女性が進出しているにもかかわらず、学校はそうした考え方を無意識に習慣化していて、それ以外の考え方ができていません。学校が表向きは男女平等と言っておきながら、矛盾している状況に教職員や学校関係者が向き合わなければいけません。
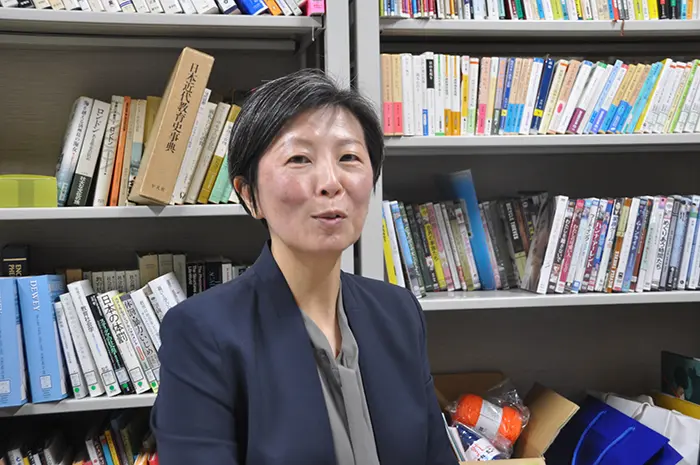
子どもたちは学校で成長して社会に出ていくわけですから、学校が意識的に変わろうとしないと、社会自体変わりません。鋳型ってあるじゃないですか。結局学校には限られた種類の鋳型しか用意されてない気がするんです。いろいろなやりとりが無意識に行われている結果として、「男の子はこっち」「女の子はこっち」というように、限られた種類の鋳型にはめられていくような印象があります。
一方で、子どもたちはそれらの鋳型に収まらないようなさまざまな表現をしているはずで、それを大切にすべきです。その瞬間を教員がきちんとキャッチする必要があると考えます。
キャッチしないと、無意識に子どもたちを鋳型にはめてしまいかねません。学校には、はみ出したものに対する感受性みたいなものが必要だと思うのです。「個性重視」「個別最適な学び」と言いながら、根っこの部分では昔と変わらず、平均的な人を生み出す装置として学校が存在してしまっている感じがします。
――例えば、一般企業では今でも女性社員が来訪者にお茶を出す慣習が続いています。学校現場でも来校者に女性の教職員がお茶を出すことが多い。そこで思い出したのが、15年ほど前に元リクルートの藤原和博さんが校長を務めていた中学校にうかがった時、校長室で「お茶はセルフサービスです」と言われたことです。それぐらい意識的でないと、学校も社会も変わらないかもしれません。
そうですね。例えば、夫婦で働いている子育て家庭で、父親が保育所への送り迎えに行くと、保育士さんが「お父さんは仕事も頑張って偉いですね」と言うようなことがあります。
――それは私も経験したことがあります。その保育士さんも、実は自分の子育てをしながら仕事をしている人でした。もちろん、そういう保育士さんばかりではありませんが。
そうなんです。保育士さん自身も同じように仕事をしているのに、そのことに気付いていない。私の本を読んで「初めてそう言われていることに気付いて、なんかモヤモヤし始めました」と感想を寄せてくれた方もいます。いくら成功していて、見掛けはバリバリやっている人でも、モヤモヤする。今の社会はそういうモヤモヤを多くの人が抱えながら、一生懸命生きているという感じなんだと思います。
女性自身も結局、無意識に自分を抑圧するような言葉を内面化してしまっているということです。人間は内面化したものを通していろいろなことを考えてしまいます。その結果として、性差別の構造自体を皆で一緒につくり上げてしまい、それによって自分自身も苦しめられています。
元をたどれば、学校での教師からの何気ない言葉掛けの影響も小さくありません。特に学校は見掛けの上では男女平等です。だからこそ、そうした構造の存在が見えなくなってしまっている側面があるんです。

【プロフィール】
虎岩朋加(とらいわ・ともか) 愛知東邦大学教育学部子ども発達学科准教授。1976年、名古屋市生まれ。名古屋大学大学院教育発達科学研究科単位取得退学、ニューヨーク州立大学バッファロー校教育学研究科博士課程修了。Ph.D. in Social Foundations。名古屋大学大学院教育発達科学研究科助教、敬和学園大学准教授を経て、現職。専門は教育学、社会哲学。著書に『教室から編みだすフェミニズム――フェミニスト・ペダゴジーの挑戦』(大月書店)など。