間もなく東日本大震災が起きてから13年を迎える。1月1日には能登半島地震が発生し、今もなお多くの人が避難を余儀なくされている。この間、学校施設などの耐震化、避難所としての機能強化は進み、さまざまな防災教育の実践が生まれている。一方で、能登半島地震の被災状況からは、防災に対する学びの課題点も感じられる。防災教育はこれからどう展開させていけばいいのか。取材をして見えてきたその鍵は、子どもと地域が主体となり、地域に根差した形で進化させていくことだった。
朝の通勤・通学の時間帯を襲った大阪府北部地震で、最大震度6弱を記録した大阪府高槻市。その高槻市にある関西大学初等部の6年生が2月、『やってみた!いのちを守る64の防災活動』(さくら社)という本を出版し、話題を呼んでいる。5年生のときに始まった探究学習「災害被害≒0プロジェクト」の集大成が詰まった一冊。しかし、本の完成までには紆余(うよ)曲折があった。
本では、同じキャンパスにあり、防災を研究する同学社会安全学部の教員が協力しているが、最初の子どもたちの原稿はファクトチェックが膨大になり、作業が追い付かないことが予想されたことから「むしろ子どもたちが体験したことや、そこから考えたことを書いてはどうか」と提案されたそうだ。すでに秋に差し掛かり、スケジュールを考えるとぎりぎりだったが、提案を受けて原稿は全面的に書き直されることになった。
そして出来上がった本では「家にあるもので防災食を作ってみた!」「自分の町の防災マップを作ってみた!」「地震について家族会議をしてみた!」など、子どもたちが実際にやってみた防災の取り組みが見開きでレポートされた構成となっている。一連の活動を指導してきた6年2組担任の堀力斗教諭は「格好よくまとめようとしたら大失敗したけれど、そのおかげで他ではあまり見られないパターンの本になったと思う」と胸を張る。
6年生の子どもたちは1年生のときに大阪府北部地震を経験していた学年でもある。しかし「大阪府北部地震を経験していたから防災意識がもともと高い子どもたちだったかというとそうでもなく、学習を始めたばかりのころは、防災について『自分たちは何もしていないよね』という感じだった」と堀教諭は振り返る。ちょうど5年生の宿泊学習で阪神・淡路大震災について学んだことをきっかけに、将来起こるとされている南海トラフ地震では大阪府だけでも7000人以上の死者が出ると予想されていることを知った子どもたちは、「もしかしたらその中に自分の大切な人や自分自身が含まれるかもしれない。どうしたら『みんな』が助かり、被害をゼロに近づけられるだろうか」と問いを立てて考えるようになったという。
その際、堀教諭は「最初、子どもたちはこの『みんな』というのを身近な家族や大切な人と考えていた。でも、その中には外国の人や高齢者、赤ちゃん、障害のある人など、いろいろな人が入っているのではないかと気付かせた上で学習に入っていった」と説明する。活動の中では、東京にあるネパール人学校ともオンラインでつながり、2015年に起きたネパール地震のことと自分たちの学びをリンクさせることもあった。実際に本の中でも、こうした災害時要配慮者の視点が取り入れられている。
さらに高槻市役所や関西大学社会安全学部とも連携し、どんどん学びを深めていった子どもたちは、5年生の最後に保護者や地域の人を呼んで体育館で「BOSAI FESTA」というイベントを開催し、グループに分かれてプレゼンテーションや体験会を実施した。イベントには100人以上の人が参加したものの、もっと多くの人に防災の意識を高めてもらわなければ「≒0」に近付けないと考えた子どもたちが2年目の目標に据えたのが、イベントに加えて本も出すことだった。出版にあたっては、出版社に企画を提案したり、費用をクラウドファンディングで集めたりもした。
堀教諭は「5年生の途中で最終目標がイベントをやることになった辺りから、子どもたちは自分たちで動き始めていた。本を作るときも、私は前に立たずに基本的に子どもたちが進めてきた。プロジェクトを立ち上げて動かしていく手だてを子どもたちは学んでいった。これを糧にして、これからもいろいろなことにチャレンジしてほしい」と、間もなく卒業を迎える子どもたちの成長に目を細める。

子どもたちを主体にした防災教育は、学校の中だけで行われるものではない。地域の側からアプローチする動きも出ている。
「地域では本来守ってあげなければいけない高齢者が『自主防災組織』を現役で運営しているところも多く、あと数年すれば立ち行かなくなるという課題を抱えている。そこに小学生や中学生、高校生がどんどん参加し、手伝うような仕掛けができないか」
そう提案するのは、全国各地で独自に開発した防災プログラムを通じて、防災に関わる人を増やす取り組みを展開しているNPO法人プラス・アーツの永田宏和理事長だ。プラス・アーツは阪神・淡路大震災の発生から10年を機に、兵庫県や神戸市から依頼を受けた永田理事長が開発した防災教育プログラム「イザ!カエルキャラバン!」がベースとなっている。そのコンセプトは「楽しく学べる」だ。
例えば、イベントではおもちゃ交換会が行われ、小さな子どもは遊ばなくなったおもちゃを持ってくると、スタンプを押してもらえる。さらにスタンプを集めて同じように誰かが持参した別のおもちゃと交換するためには、会場のさまざまなコーナーで防災に関する体験をしていく必要があるが、その体験は「水が使えないのでラップをかぶせて使う紙食器を作ってみよう」「毛布で担架を作り、けが人を運ぼう」「消火器でカエルの的当てに挑戦しよう」など、楽しみながら知らず知らずのうちに防災スキルを習得できるようになっている。他にも、ボードゲームやカードゲームで防災の知識を学ぶといった、オリジナル教材を数多く手掛けており、地域の自主防災組織や学校、自治体、最近は企業などからも問い合わせが寄せられているという。
プラス・アーツではこうした防災プロジェクトをやりたいという人たちに対し、まずは研修で実際に体験してもらい、本番のイベントでは「先生役(インストラクター)」となってもらうことを心掛けている。そうすることで、防災の取り組みが根付き、独自に発展していくことを狙っている。楽しいものであれば子どもたちやその保護者をはじめ多くの人が足を運ぶようになり、その中から運営を手伝いたいという人も増えていくというわけだ。
「小学校高学年くらいになれば、子どもたちもただ参加するだけじゃなくて、手伝いたいという声が出てくると思う。『総合的な学習の時間』で防災をテーマにした授業をする際に、地域の方が最初にインストラクターとして楽しく防災を学べる授業をして、その後、子どもたちが自分たちで考えたプログラムを実践してみる。さらに地域の防災イベントでも活躍してもらう。そんな活動を学校でできれば、災害時の地域と学校の連携もスムーズにいくのではないか」と永田理事長。実際にプラス・アーツが関わっている取り組みの中では、高校生が自ら考えたプログラムを地域の防災イベントで披露したり、中学生がボランティアで防災イベントを手伝ったりする事例も生まれているという。
「防災は、小学生も中学生も高校生も、やり方次第ですごく盛り上がる。イベントに関わる彼らは『やらされている』のではなく、自分から学んで伝えようという意識を持ち、地域に貢献している感覚が本人たちの自己肯定感にもつながっている。地域は防災の担い手がいなくて困っている。学校も防災の授業をどうやるか悩んでいる。その両者をつなぐ仕組みをつくり、将来の防災の担い手を一緒に育てていければ」と永田理事長は語る。
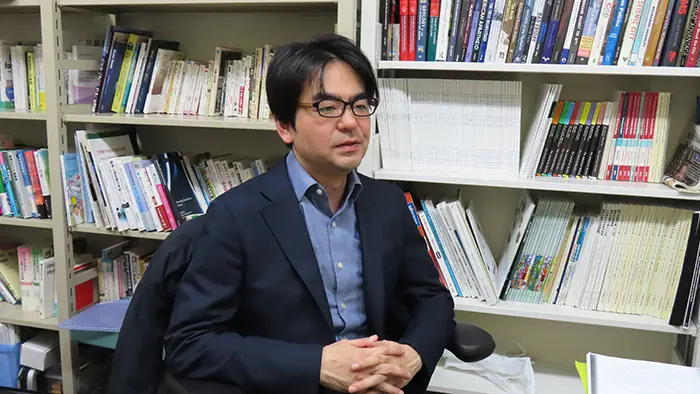
現行の学習指導要領でも「防災」の視点はより明確に位置付けられ、高校では「地理総合」が必修化されるなど、学校現場での防災教育の実践は重要性を増しているが、課題も多い。
日本安全教育学会理事で東京大学の小田隆史准教授(地理学)は、いかに身近な地域社会の「素因」に着目して災害リスクを想定するかが鍵になるとみる。
「素因」とは、その地域の地形や街並み、人々の暮らし、文化、産業、インフラ、どんな人が多く住んでいるかなど、その地域を物語るさまざまな側面の中でも、脆弱(ぜいじゃく)な部分だ。能登半島地震でも、交通インフラの整備が進んでいないことや高齢者が多いことといったもともと社会の弱い部分が、支援や避難の課題として浮き彫りとなった。小田准教授は、そうした地域ごとの「素因」の特性を複眼的に捉える力を養うのが「地理的な見方・考え方」だと強調する。
「2022年に閣議決定された第3次学校安全の推進に関する計画でも、『地域の災害リスクを踏まえた実践的な防災教育』がうたわれている。つまり、学校によってきちんとローカライズされた防災の取り組みをしなければいけないということであり、そのためには学校がある地域社会の『素因』を把握しないといけない」と小田准教授は指摘。防災に関する計画づくりや教員研修でも地域について学び、また地域からも学ぶこと。特に防災教育に関しては、特に防災教育に関しては、教科横断型の探究的な学びを実施していくべきだとし、能登半島地震をきっかけに各地で防災教育の実践を共有したり、見直したりして、アップデートさせていく必要性を呼び掛ける。