3月22日に検定合格した中学校の新しい教科書では、こども基本法の施行やこども家庭庁の発足を受け、子どもの権利に関する記述を充実させた教科書もあった。いじめ問題や近年、社会課題として認識されるようになったヤングケアラーなど、子どもたちを取り巻く問題についても多様な観点で取り扱っている。一方、技術・家庭科の家庭分野の教科書では、家族・家庭の多様性に気付かせようと各教科書会社が工夫を凝らしたページに対して「学習指導要領に示す内容に照らして、扱いが不適切」とする検定意見が付いた。
これまでも社会科の公民的分野では、国連の子どもの権利条約などを紹介してきた。今回合格した教科書では、2022年のこども基本法の成立を例にして、国会における立法過程を学んだり、23年4月からこども家庭庁が新設されたことを紹介したりする教科書が登場した。
日本文教出版は、国際的な人権保障を学ぶページの中に、子どもの権利条約について解説したコラムを掲載。世界で起きている児童労働の問題を掘り下げつつ、日本をはじめとする先進国でも虐待やいじめがあることに触れ、子どもの権利条約が定めている「生きる」「育つ」「守られる」「参加する」という4つの権利を説明している。同社編集部で社会科を担当する青木栄一部長は「公民的分野で子どもの権利条約は定番教材としてずっと取り扱ってきたが、日本の子どもも関係していることも今回から記述した」と説明する。
子どもの権利にページを割いた教科書は社会科以外の教科でも見られた。
現行の学習指導要領で幼児の発達への理解を充実させた技術・家庭科の家庭分野。教育図書の教科書は、家族・家庭生活の発展的な内容として、子どもの権利について解説した。子どもの権利が侵害される重大な事態として、児童虐待の増加を例に挙げ、虐待が疑われるときの対応や児童相談所虐待対応ダイヤル「189」などを紹介している。同社ものづくり事業部家庭科編集部の炭竈智次長は「(虐待について)何かあったら相談できる場所があるということは知っておいてもらいたいと思い、充実させた」と話す。
これまでもいじめや命の大切さを扱ってきた道徳科では、光村図書が新たに3学年共通で「共に生きるために必要なこととは?」というユニットを設け、他のユニットにはない特別な扉ページを付けた。人権について考える教材がここに集まっており、新型コロナウイルス禍で起きたさまざまな差別や偏見の事例と、元ハンセン病患者の言葉が紹介された記事を通して、どの時代にも存在する差別がなぜ生まれてしまうのかに気付かせる題材を用意したり、身近な生活の中にある人権について漫画で知るページを設けたりした。二次元コード(QRコード)の誘導先として、子どもの権利条約や世界人権宣言、日本国憲法の前文を見ることもできるようにしている。
同社編集第二本部第三編集部道徳課の藤崎雅栄課長は「道徳科で人権を正面から扱うことはこれまで難しさもあったが、ウクライナやガザで起きている紛争やヘイトスピーチ、いじめなどの問題の根底にあるのは、自分の人権も他者の人権も大切にできているかということだ。その感性を道徳で育んでいきたい」と、この人権を学ぶユニットづくりにこだわった理由を語る。
同じく道徳科の教科書を発行する日本文教出版は、人権課題について考えるコラムを3年生の教科書に載せた。子どもの権利条約や世界人権宣言を取り上げ、日本で子どもの人権を考えるための題材として、ヤングケアラーや子どもの貧困問題への取り組みを挙げている。同社は従来からいじめの問題の取り扱いに力を入れてきたが、今回は3学年全ての教科書において、QRコードから相談窓口にアクセスできるようにしたのも特徴だ。
同社中学校道徳編集部の杉岡潤一部長はヤングケアラーを扱ったことについて、「本当に苦しんでいるのだとすれば、本人の心の持ちようにも必ずつながる話で、道徳で扱うことに違和感はない」と説明する。ヤングケアラーやいじめなど、QRコードで子ども自身が相談窓口につながるチャンスを増やしたことに関しては、「知り合いに直接言うのはすごく勇気がいる。匿名でもいいから、自分が抱えているしんどさや苦しんでいることを伝えてもらえたら」と願いを込めた。
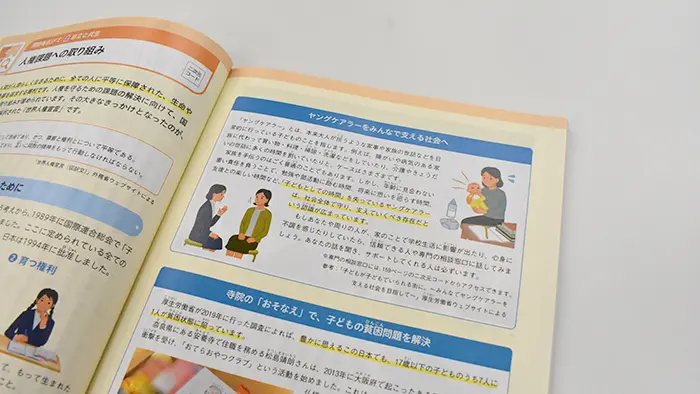
技術・家庭科の家庭分野では、学校と並んで子どもにとって身近なコミュニティーである家庭や家族の多様性を子どもたちに考えてもらうページを用意する教科書も。
今回の検定では、『名探偵コナン』など子どもたちに身近なアニメや漫画作品で描かれる家族や家庭に着目させたり、家族に関する絵本の紹介やイラストを通じてさまざまな家族の形があることを学んだりするページを各社が設けたが、いずれも家族・家庭の基本的な機能を扱うとしている学習指導要領に照らして不適切という意見が付き、記述の変更や図版の差し替えなどの修正を迫られた。
こうしたページや家庭分野の教科書づくりについて、教育図書の炭竈次長は「検定で意見が付いてしまったが、今はさまざまな家族・家庭の在り方や多様性を認める時代になっている。もしかすると中学生世代の方がそういったことへのバリアーはないようにも思うが、ジェンダーなども含めてできるだけ配慮していきたい」と話した。