6月19日、参院本会議で「こども性暴力防止法」が可決・成立し、教員や保育士など、こどもと関わる業務に従事する際に性犯罪歴がないことを証明する「日本版DBS」の制度が導入されることになった。教育・保育現場への日本版DBSの導入だけでなく、こどもの性犯罪防止対策を学校設置者などに義務付けているなどの特徴がある。これによって、学校現場はどのような対策が求められるのか。そして、これまでの議論を通して、依然として残っている課題や論点をQ&A形式で整理した。
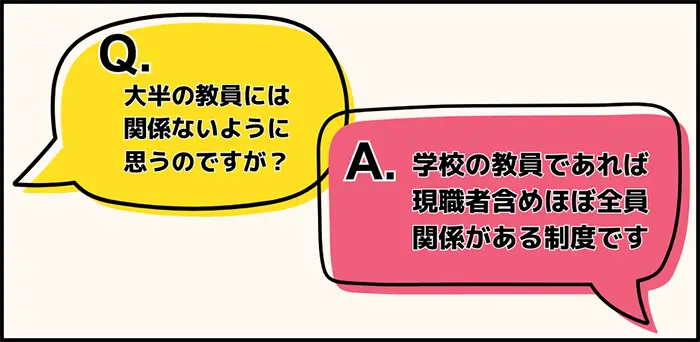
――そもそもDBSとはどういう制度なんですか? 大半の教員には関係ないように思うのですが。
これまで性暴力を絶対にしていないとしても、学校の教員であればほぼ全員、関係がある制度です。もちろん、今後新たに採用される人だけでなく、現職者も含まれます。
DBSとは、英国のDisclosure and Barring Service(前歴開示・前歴者就業制限機構)の略称で、教育・保育施設など、こどもと接する仕事に就く際に、性犯罪歴がないことの証明を義務付けた制度です。英国をはじめ、ドイツ、フランス、カナダ、韓国などで同様の制度がすでに導入されています。
こども家庭庁では、日本版DBSの対象業務の範囲についての考え方を①支配性(こどもを指導するなどし、非対称の力関係がある中で支配的・優越的立場にいること)②継続性(時間単位のものを含めて、こどもと生活を共にするなどして、こどもに対し継続的に密接な人間関係を持つこと)③閉鎖性(保護者などの監視が届かない状況下で預かり、養護などをするもので、他者の目に触れにくい状況を作り出すのが容易であること)――とし、派遣、委託関係にあるかや、こうした業務を有償・無償のいずれかで行っているかに関係なく、実態に即して判断する方向で検討することとしています。
学校であれば、管理職や教員はもちろん、それ以外の職員でも、①~③に該当する業務に従事していれば対象となる可能性が高いと言えます。
――日本でも、教員による性暴力・性犯罪は問題になっていますね。
その通りです。
対策強化のため、2021年に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(わいせつ教員防止法)が成立したことは記憶に新しいと思います。これにより、こどもへの性暴力を行って教員免許状が失効または取り上げ処分となった特定免許状失効者に関するデータベースの整備などが定められ、その附帯決議では、DBSのような性犯罪の前科がないことの証明を公的機関に照会する仕組みの検討を行うよう求められていました。
また、22年に成立した改正児童福祉法では、保育士の欠格事由の期間が延長され、こどもへの性暴力を行ったことで登録を取り消された人の再登録やデータベースの整備について、教員と同じような運用が行われることになりました。
さらに、21年12月に閣議決定された「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」では、こども家庭庁の創設などとともに、導入に向けた検討を進めることが盛り込まれました。こども家庭庁が昨年設置した有識者会議では、こどもと接する仕事に従事する人を対象にした性犯罪歴などの確認の仕組みを整備する必要性があると報告書で結論付け、制度設計や法整備に向けた検討を進めるよう求めました。
――最近、学習塾の講師が性犯罪をしていた事件がありましたよね。対象が学校や保育所だけでは不十分ではないですか?
日本版DBSの制度設計を巡っては、有識者会議の議論が始まって以降、関係者からもさまざまな意見が出ていて、法案が固まるまでは紆余(うよ)曲折がありました。まさに、学童保育や学習塾、スポーツクラブなどの民間の事業者を対象にできるかどうかというのも、論点の一つでした。
こども性暴力防止法では、DBSで職員の性犯罪歴を照会するのは、幼稚園や保育所、認定こども園、学校、児童福祉施設、児童相談所などの設置者としていますが、これに加えて、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者も、学校などと同等の対策を取ることで国による認定を受け、照会ができるようにしました。国としても関係省庁が連携して、民間事業者による認定の取得を促進する方針で、多くの民間事業者が認定を受けるために取り組みを強化することが期待されます。
また、もう一つ大きな論点になっていたのが、DBSが対象とする性犯罪歴の期間です。こども性暴力防止法では、性犯罪歴には痴漢や盗撮などの条例違反も含み、再犯リスクの実証的なデータなどを踏まえ、服役した場合は刑の執行終了から20年、執行猶予判決を受けてその期間が満了となった場合は裁判確定日から10年、罰金の場合は刑の執行終了から10年を、それぞれ対象期間と定めています。
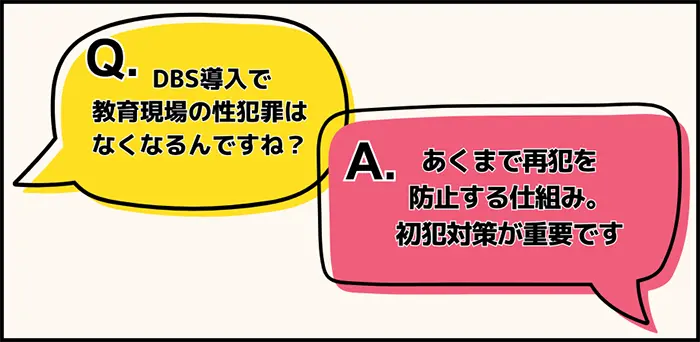
――なるほど。DBSが導入されれば、教育・保育現場での性犯罪はなくなるんですね。
それはちょっと違います。DBSはこどもの性犯罪被害を防ぐ切り札とはいえ、あくまで再犯を防止する仕組みに過ぎず、初犯対策をしっかりやらなければ、こどもを性犯罪から守るには不十分だからです。こども性暴力防止法が、DBSの導入だけでなく、こうした初犯対策にも力を入れているのはそのためです。
――学校現場には、どのような影響がありますか?
こども性暴力防止法では、学校設置者や民間教育保育事業者の責務として、教員や保育士をはじめ、こどもに接する仕事に従事する職員などによるこどもを狙った性暴力の防止に努めること、もしもそうした性暴力の被害を受けたこどもがいた場合に、そのこどもを適切に保護することを課しています。
その上で、こどもの安全を確保するための措置として、教職員などを対象にした研修の実施や、こどもが相談や面談をしやすくする体制を整備すること、被害が疑われる場合には、速やかに調査を実施し、被害に遭ったこどもを保護することを求めています。
そして、再犯対策としてのDBSの導入です。これは、新たに就業する人にも行われますが、現職者も3年以内に確認を行うこととされ、5年以内に再び照会をすることになるそうです。
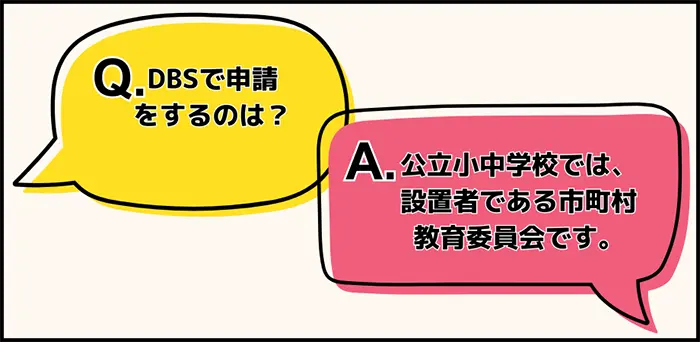
――新たに採用される人だけでなく、現職も対象なんですね。どういう手続きを踏むのでしょうか。
公立小中学校の場合、多くは市町村立なので、設置者である市町村教育委員会が、対象者がその業務に従事する前に、こども家庭庁が運用するシステムに照会することになります。これとは別に、対象者は戸籍情報を提出しています。
申請すると、対象者の性犯罪の前科の有無について記載した犯罪事実確認書が交付されます。このときに前科があった場合は、あらかじめ本人に通知が行われ、通知内容の訂正請求ができます。2週間の訂正請求期間中に本人が内定を辞退するなどすれば、申請が却下され、犯罪事実確認書は交付されませんが、訂正請求期間を過ぎると「犯歴あり」とされた犯罪事実確認書が交付されます。
市町村教委などは、犯罪事実確認書などを厳重に保管し、一定期間が経過したら破棄するなどの適切な管理が求められます。DBSによる申請の手続きだけでなく、職員らの犯罪事実確認書の管理にも神経を使うことになりそうです。
DBSによる性犯罪歴の前科の確認や、日常でのこどもとの面談・相談などによって、こどもへの性暴力が行われる恐れがあると認められる場合、その人を教育や保育などのこどもと接する業務に従事させないようにするなどの対策をしないといけません。
――まだ解決できていない課題や論点はありますか?
こども性暴力防止法の成立を受けて、こども家庭庁では具体的な研修や相談しやすい環境づくりなどについて調査研究を行い、ガイドラインの策定や省令の制定に着手する予定です。どのようなやり方が学校などの現場の負担をできるだけ抑える形で効果的なのかは、十分に検討する必要があるでしょう。
こどもを狙った性犯罪は、被害に遭ったことをこども自身から口に出せなかったり、自覚がなかったりして表面化しにくいケースもあります。「生命(いのち)の安全教育」の中で、身近な大人からの性被害もあり得ることを、幼いこどもでも理解できるように伝える取り組みも重要です。そして、こどもが相談しやすいようにし、その相談をきちんと受け止めることができるのかが、大人の側に問われていると言えます。
一方で、加害者についても、適切な治療やカウンセリングにつなげ、こどもと接触しないような環境の下で社会復帰できるようにしていくことを、もっと考えていくべきだという指摘もあります。
法案を議論する過程で、下着泥棒やストーカー行為などは性犯罪歴の前科に含まれないことを疑問視する意見もありました。果たして民間事業者がどれくらい認定を受けようとするのかも不透明です。こども性暴力防止法では施行から3年後の見直し規定を設けていますが、対象をどこまで広げるべきなのかといったことも議論が続きそうです。
くどいようですが、DBSが導入されたからといって、こどもへの性犯罪が完璧に防げるわけではありません。多くの大人がこどもへの性犯罪に対し、意識を高めていくことが求められています。