子どものライフジャケット着用の普及啓発に取り組む森重裕二さん。活動を始めたのは17年前、滋賀県甲賀市で小学校に勤務していた頃にさかのぼる。学生時代から障害のある人たちとカヌーに親しみ、競技カヌーにものめり込むなど、水の怖さやライフジャケットの必要性は理解していたはずだった森重さんだが、とある出来事が大きな転機になったと話す。インタビューの第2回では、当時の出来事とそれ以降のキャリアについて聞いた。(全3回)
――森重さんが、ライフジャケット着用の普及啓発に取り組み始めた経緯を教えてください。
自分が水辺で活動するときには当たり前に着けていたライフジャケットなのに、学校行事で子どもたちを川に連れて行った際には、持参していなかったのです。そして、子どもが一瞬溺れるという出来事がありました。その時は水深も浅く、間一髪、手を出して助けることができましたが、本当に紙一重でした。私自身も「ライフジャケットを着けた方が安全だろう」とは思ったのに、用意していなかったわけです。言い訳をすれば、まだ若かったので危ないと分かっていながら意見できなかったのです。
その出来事を機に「これではいけない」と考え、勤務校にライフジャケットをそろえてもらうように訴えました。最初はさまざまな団体から借りるなどしていましたが、翌年から数年間かけて計200着程度を購入してもらえました。
でも、その間の2007年に、滋賀県甲賀市の公民館が主催した行事で、2人の小学生が高知県の四万十川に遊びに行った際に、溺れて亡くなる事故が起きてしまいました。亡くなってしまった子はライフジャケットを着けていませんでした。加えて、事故についての報告書を読むと、ライフジャケットについてほとんど触れられていなかったのです。
「もう二度とこんなに悲しい出来事が起きてはいけない。今、自分が動かなくては」と教育委員会にライフジャケットの購入を直訴しました。当時、勤務校にはライフジャケットがそろいつつあり、四万十川の事故を受けて校内では多くの同僚が「森重先生の言っていたのはこういうことだったんだね」と理解を示してくれましたが、まだ校外では理解を得るのが難しい状況でした。そのため、SNSで活動を始めたのです。
すると、水難事故で子どもを亡くしたご遺族の方が応援してくださりました。今でも水の事故が起きると、全国から「こんな悲しいことが起きてはいけないから、ライジャケサンタの活動を頑張ってください」とメールが届きます。そのたびに、水の事故で大切な子どもを亡くすことが家族にとってどれほどつらい出来事なのかを思い知らされます。

――現在は香川県で活動をされていて、県内の学校ではライフジャケットの着用が普及してきていると聞きました。
妻の実家のある香川県に転居し、そこで3年間、教員をしていました。その後退職して、義父が営む石材店で仕事をしながらライジャケサンタの活動を並行して続けてきました。
そうした活動の中で、21年に県内の企業や団体の協力を得て、ライフジャケットが県に寄贈され、幼稚園やこども園、小中学校などに貸し出すようになりました。「ライフジャケットレンタルステーション」といい、県の環境管理課が50着、教育委員会が340着を無料で貸し出しています。貸出期間は原則1週間で、子ども用の「Mサイズ」と「Lサイズ」、大人用の「フリーサイズ」の3種類があります。ただし家族や個人への貸し出しは行っていません。23年度の貸出件数は1700件以上に上っています。また、寄贈数もさらに増え、今では香川県内の全ての市町がライフジャケットを保有し、活用しています。
レンタルを始めるのと同時に、香川県教育委員会では21年度に「学校における水難事故防止対策強化事業」、22年度にはスポーツ庁の委託事業として「ライフジャケット推進事業」を実施して、ライフジャケットを活用した水泳授業をするなど水難事故防止の取り組みを進めています。事業の推進委員会には香川大学教育学部、高松海上保安部、香川県B&G財団、香川ライフセービングクラブ、警察、消防、小児科の先生、県立総合水泳プールなどのほか、私も含めて官民のいろいろな立場の人が加わっています。

――学校の水泳の授業でライフジャケットを着ける指導をしているのですね。「そんなことをしたら泳げなくなる」などと言われませんでしたか。
以前はよく言われました。ライフジャケットを着けて水に入ったら、何もしなくても体が浮きますからね。確かに「水に浮く」「泳げるようになる」という目標とは相いれない部分があります。でも、中には泳げない子もいるわけで、そういう子どもたちが水の事故にあわないようにするには、やはりライフジャケットの着け方や浮き方を知っておくべきです。
現在は、そうした空気も徐々に変わりつつあります。県内のある小学校では、特別支援学級の子どもたちがライフジャケットを着用することで喜んでプールに入るようになったそうです。今までなら「入ったら危ないからやめておきなさい」と言われていたような子どもたちが、安全に水と関われるようになったわけです。
最近は、水泳の授業以外にも「行事で使うからライフジャケットを貸し出してください」と申し込んでくる学校があります。以前はどうしていたかと言えば、ライフジャケットを持たずに行事で川や海に出掛けていたわけです。何度も言いますが、ライフジャケットを準備せずに事故が発生して子どもが亡くなってしまえば、責任を問われるのは教員であり学校です。
貸し出せる仕組みがあって、ライフジャケットというものが準備されると、これまで使っていなかったところでもライフジャケットが使われるようになります。つまり、潜在的にニーズがあるのです。ライフジャケットが子どもたちの命を守るだけでなく、水と楽しく関われるツールなのだという認識は、これからもっと広がってくるだろうなと思います。
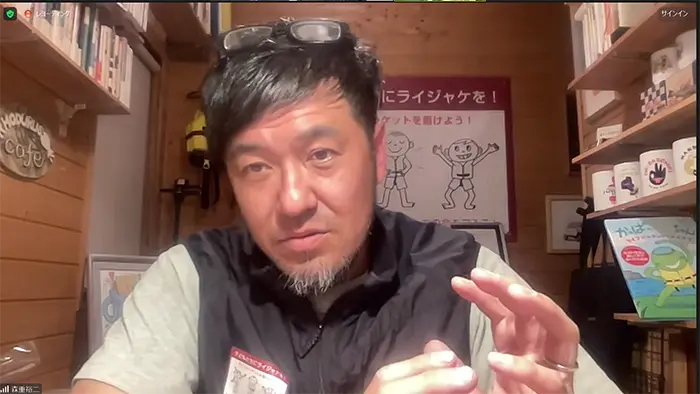
【プロフィール】
森重裕二(もりしげ・ゆうじ) 学生の頃からカヌーや渓流釣りなど水辺での遊びに親しむ。2019年春、約20年続けた小学校教諭を退職し、現在は庵治石細目「松原等石材店」の3代目として修行する傍ら、「ライジャケサンタ」としてライフジャケットを自治体に寄付するなど水辺の安全のための普及啓発活動をしている。クローズアップ「小野訓導殉職から100年 水の事故防止に取り組む元教諭」にも登場。