秋田県の「博士教員」として高校で生物を教えて9年目になる東海林拓郎教諭は、理系だけでなくこれからは文系も含めて、博士教員が増えてほしいと語る。生徒たちの課題研究を充実させていくには、指導者の研究経験の有無が大きいと感じてのことだという。インタビューの最終回では、博士号取得者の進路としての「学校教員」という選択肢について改めて聞くとともに、博士教員として学校教育の充実にかける思いなどを聞いた。(全3回)
――博士教員同士の横のつながりはあるのでしょうか。
そうですね。自分は子育ての関係であまり参加できていませんが、秋田県の博士教員7人で月に1回、オンラインミーティングをしています。学校の状況を共有しているほか、博士教員で開催している生徒の研究発表会が近くなると、その打ち合わせなどで頻繁にコミュニケーションを取っています。
この研究発表会は、以前は会場を借りて行っていましたが、コロナ禍以降は全てオンライン開催に切り替わりました。いわゆる学術団体がやっているオンライン形式の学会の、秋田県の高校生バージョンという感じです。でも、2024年度からはまた対面で集まるようになりました。
また、コロナ禍前には自分の専門に関する講座を開く「未来の博士養成講座」を毎年開催していました。コロナ禍後はオンデマンド教材を録画してYouTubeにアップし、それを見てレポートを書いてもらうスタイルに切り替えました。
それから年に1回、博士教員が県の教育委員会に集まって、現在の理科教育について協議する場もあります。ここでは県教委の人たちから、研究発表会などの自主的な取り組みに対して感謝の言葉をいただくこともあります。でも、一般の教員の多くは、博士教員の横のつながりや活動のことはほとんど知らないと思います。

――博士教員が増えてほしいと思いますか。
そう思いますね。恐らく第1期で採用された人が4~5人、第2期で採用された人も数人いたと思うのですが、初期に採用された人たちの中には大学の教員になるなどして辞めているのです。自分が採用されたときは先輩の博士教員が5人いましたが、「もう少し博士教員がいてもいいよね」という話は周囲とよくしています。
――「もう少しいてもいい」という理由は何でしょうか。
前回話した教員の研究経験の問題です。課題研究で、科学的な思考力に基づいて実験を計画して結果を出し、考察をするという活動を、高校の場合は1年~1年半でやる必要があります。研究経験がない教員がそうした活動をファシリテートするのなら、やはり相談できる人が近くにいた方がいいと思います。そうして教員がストレスを感じずに課題研究に向き合えれば、生徒の研究が充実することにもつながります。
中でもほしいのは、文系の博士教員です。特に教育学で博士号を取った人にどんどん現場に入って口出しをしてほしい。自分のように教材を作って授業をするだけでなく、もっと大きい視点から学校教育が進む方向性についてアドバイスをしてほしいと思います。
――文部科学省は博士号を持つ人の学校現場への採用を進めていく方針のようですが、博士号を持つ人の進路について、思うところはありますか。
やりたい仕事に就けるのが一番幸せだと思うので、研究者になりたい人は研究職に就ければいいと思います。ただ、「ポスドク1万人時代」という言葉があったように、正規職員として採用されていない人が大量にいる現状は、夢を食い物にしている部分もあるように思います。
それでも研究者になりたい人はその道を選べばいいと思いますが、この状況に疑問を持ったときの選択肢の一つとして、教員というのはありだと思います。研究領域専門性が生かされる単元は限られていますが、研究を通じて得た考え方やネットワークなどは十分に生かせると思います。

――教員になって来年度で10年目を迎えるわけですが、将来に向けて考えていることはありますか。
私自身、理系も文系も同じぐらい課題研究を充実させていかなければならないと思っていて、どうやって教員の指導力を高めていけばよいのか考えているところです。研修を受けてもらうという単純な話もありますが、各校のマネジメント次第で探究の時間をもう少し余裕を持って実施できるはずなので、そうした仕組みを構築できないかと考えています。
それから、もう少し学校間で競争していく必要性も感じています。今は公立学校も統廃合されていく時代です。そう考えると、統廃合された後に選ばれる学校になることも含め、学校はそれぞれ特色を出していく必要があります。もう少し、公立学校間の競争を促すような仕掛けがあってもよいのではないかと考えています。
――研究の道は考えていないのでしょうか。
もし、大学に戻れるチャンスが来れば気持ちがぐらっとくるかもしれません。ただ、他の博士教員とも話をしていますが、かつての専門分野の研究から10年以上も離れ、その間の研究業績がない人間が戻れる可能性は、限りなくゼロに近いのです。大学に戻るチャンスとしては、教養課程の教員の方が可能性はあります。実際、そうして大学に戻られた博士教員もいます。学校現場に長くいればいるほど、自分の専門分野には戻りにくくなります。
――自身のキャリアを振り返ってみて、学校教員に向いていたと思いますか。
向いていたと思います。今でも授業をつくるのは楽しいし、どうすれば生徒に知識を定着させ、理解を深めていけるかと日々考えています。教員になった当時は、そうした楽しさに気付いていませんでしたが、結果としては向いていたのだろうと思います。
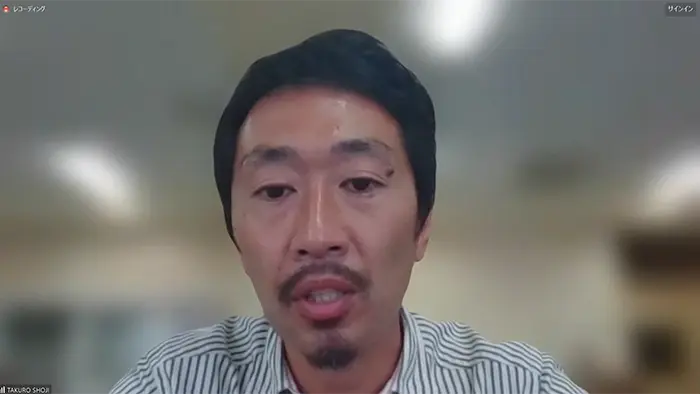
【プロフィール】
東海林拓郎(しょうじ・たくろう) 1981年生まれ。幼い頃から研究者に憧れ、秋田県立大学で修士、博士と土壌科学を研究。博士課程修了後、NPO法人に就職し、環境教育に取り組む。秋田県教育委員会が教員免許を持たない博士号取得者を教員に採用する特別選考を知り、「次世代への環境教育ができる」と考え応募。3校目の現任校では、1~3年の生物の授業を担当。探究活動を担当する同僚への助言や、他校に出向いての出張授業なども担当している。