いよいよ学習指導要領の改訂の議論が本格化しようとしている。学校管理職と自治体の教育改革の両方に携わってきた平川理恵氏、細田眞由美氏、森万喜子氏は、次期学習指導要領が描く2030年以降の学校教育について「子どもたちが自分で学びを選べるようになること」が最低限必要なことだと共通の見解を示す。鼎談(ていだん)の後編では、「ウェルビーイング」「人生100年時代のロールモデル」「余白」「探究的な学び」「自己決定」など、それぞれがこれからの学校教育に必要だと考える視点について語り合った。
━━次期学習指導要領の改訂に向けて、注目すべきはどんなことでしょうか。
細田 教育振興基本計画の第4期(23~27年度)における大きなコンセプトが「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」の2つです。これが、次期学習指導要領の方向性を考えていく一つの手がかりではないかと思っています。
また、今の日本社会や世界に欠けているものを考えたときに、自分がこの社会の当事者である、自分が社会を変えていく一員であるという自覚が持てるような教育の在り方が求められるのではないでしょうか。
平川 海外の研究では、日本の2007年に生まれた子の半分以上の子が、107歳まで生きると推計されている時代です。私自身、10年に1回キャリアが変わっていますが、これからは、自分のライフスタイルに合わせて、いくつもの職を経験するカリヨン・ツリー型のキャリアを形成していく時代になります。
ただ、そういう生き方をしている人と接して、ロールモデルを見せないと、子どもはそうはなりません。学校の教員や親だけでは、その役割を果たせません。学校教育の中にもっと多様な人が入ってきて、「いろいろな生き方ができるんだ」ということを、子どもたちにどう見せていくかが重要だと思います。

森 私は子どもたちに、もうちょっと自分の時間を取り戻させてあげたいと思います。今、「カリキュラム・オーバーロード」という言葉がよく出てきますが、子どもたちは本当に忙しく、やることがいっぱいの状態です。
しっかり学習指導要領を読み込むと、そんなに「あれもこれもやれ」とは書いていません。だけど、教員は学習指導要領より「教科書を終わらせなくては」と思ってしまっています。
もっと子どもたちが自分のことを考える時間を、余白をつくってあげられるようなカリキュラムを組むべきです。子どもたちが「生きるって何なのか?」を考える暇もなくなっているのは、間違っていると思いませんか。「いっぱい、いろんなことをさせなくては」となっているから、子どもの主体性がなくなっているのではないでしょうか。
細田 例えば、今年4月から東京都渋谷区が全公立小中学校でスタートさせている、午前中は教科を中心とした授業をして、午後は探究学習にするというチャレンジは、一つの面白い取り組みだと注目しています。教科授業もしっかりカリキュラム・マネジメントすると、各教科の授業時間数は1割減で済んでいるそうです。
渋谷区でこのような取り組みが出来ているというのは、次の学習指導要領の改訂に影響を与えるのではないかと、個人的には思っています。
平川 確かにそうですね。ただし、どこまでのクオリティーがあるかが問題だと思います。午後の探究学習が「ただ時間を過ごしているだけ」になっていては意味がありません。子どもたちがしっかりと、自分が何を学びたいのか、カリキュラムや学び方を含めて、選べるようにしていかなければなりません。
細田 ただ、日本の子どもたちに、自分が何を学びたくて、何をどのくらい、どんなふうに学びたいかという、自己決定する力が付いていないと思います。ですから、段階を踏んでいかなければならないし、大人たちがどうサポートしていくかも重要になってきます。
最終的には、子どもたちが学びたいものを、学びたい方法で、学びたいだけやれるような、そういうシステムを作っていくことが、学習指導要領の果たさなければいけない大きな役割の一つだと思います。
森 子どもたちが自己決定できないのは、「先生やママが言った通りやっていればいいんだよ」と、これまで大人が子どもの選択と決定を取り上げてきたからですよね。
先日、青森県で子どもたちに大規模な調査をしたのですが、その中に「自分で決めたい」という声がありました。例えば「学校の決まりを自分たちで決める学校がいい」とか「友達と一緒に学んだり、1人で学んだり、学び方を選ばせてほしい」といった声です。
子どもたちが小さい頃から自分で選択し、決定することが大事だし、それによってちょっと痛い目に合う経験も必要だと思います。
大人が子どもの自己決定を取り上げてきてしまったことは根深い。従順であることがすごく良いことのように思っている子も多いですからね。
もう一つ、これまでの学校は「どれもこれもできなきゃ駄目だ」と子どもたちに言ってきました。通知表にも「苦手なことを克服しましょう」という、余計なお世話を書いた経験が皆さんあるのではないでしょうか。私も「好きなことをもっとどんどんやれ」と言ってあげればよかったなと反省しています。
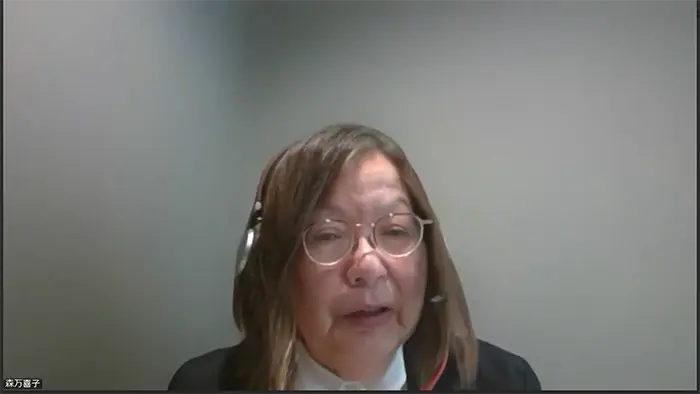
平川 次の学習指導要領の改訂では、子どもの声を入れてほしいですね。おじさん、おばさんばかりで考えていますが、それが日本の将来をつくる人たちなのでしょうか。せめて10代、20代、30代で学習指導要領を作ってほしいですね。
━━次期学習指導要領を学校現場の教員が過度な負担なく実践しやすくするには、どうすればよいと思いますか。
細田 学習指導要領は読み込むのも大変です。毎日授業をやっている教員が、どうやって自分の授業デザインに落とし込んでいったらいいのかが分かるような、授業に直結するようなシンプルなものにしてもらえると、手に取りやすいですし、実践しやすくなるのではないでしょうか。
平川 根本的な話になりますが、「教科書はいるのか?」ということです。教科書があることで、一定のクオリティーが保たれるということは言えるかもしれませんが、教員はそれに頼ってしまいます。
森さんが指摘したように、教員はみんな学習指導要領を読まずに、教科書を読みます。そうなるのは、教科書があるからです。だったら、なくせばいいと私は思っています。
しかも他国に比べて、日本の教科書はものすごく薄い。だから特に日本の高校生、大学生が勉強しなくなっていると、私は感じています。欧米の高校生や大学生はもっともっと勉強しています。そういう要因もあって、世界との差も広がっていると思います。
森 私も細田さんと同様、もっとシンプルで分かりやすいものにしてほしいというのが一点。そして、平川さんが指摘された教科書については、おっしゃる通り、教員は学習指導要領よりも教科書を頼り過ぎてしまっています。
しかも、教科書の1ページ目から最終ページまで全部やらなくてはいけないと思っている教員がたくさんいます。そういう誤解を生んでいるので「教科書は全部やらなくてもいい」ということを、もっと学校現場の教員に伝えていかないと、学習指導要領の理念を実践できるようにはならないと思いますね。
平川 それから、教員たちがチャレンジしやすい土壌が必要です。国や保護者や社会は、教員たちをもっと信頼してほしいし、リスペクトしてほしい。そうじゃないと、誰もバッターボックスに立たなくなってしまいます。
もう一つ、教員に限った話ではないのですが、日本人は完璧過ぎます。「まあ、いっか」というマインドがない。学校現場の教員が実践しやすい学習指導要領にするには、「まあいっか」という寛容さを入れてほしいですね。もっとアジャイルに、もっとあそびや余白があることが必要だと思います。
━━2030年代の学校の姿をどのように想像しているのか、教えてください。
森 多様なカリキュラムがあるようになっていてほしいですね。特に地方の高校は普通科がメインになっていますが、子どもたちも多様化しているのだから、多様なカリキュラムから生徒自身が選べる必要があると思います。
もう一つは、高校を何校か視察する中で、授業時数が多過ぎだと感じます。朝から晩まで授業をやっても、あまり効果がないように見える……。だったらもっと時数は軽くして、学校の外で学べるとか、社会に出て教員じゃない人から学ぶとか、いろいろな幅をつくって多様なカリキュラムにする方が良いのではないでしょうか。
このぐらいだったら、2030年代に少しは実現できているのではないかと思います。
平川 ちなみに私は、場合によっては「高校の学習指導要領は要らないのでは?」と思うこともあります。中教審で「義務教育ではないのに、余計なお世話ではないか」と発言したこともありました。
「どうして大学は学習指導要領がないのか?」「高校はなぜ義務教育ではないのか?」ということまで考えるべきだと思います。
細田 私はもともと高校の教員でしたが、高校生ほど多様な年代はありません。高校のこの厚い学習指導要領が何を物語っているかというと、結局、それだけ学力の幅や興味関心の幅が広いから、それらをなんとかカバーしようとしている苦肉の策なのだと思います。
私は高校の学習指導要領は「要らない」とまでは言わないけれども、もっとシンプルなものにしてもいいと思います。高校教員時代から、少なくとも教科、科目の単位数の縛りは要らないと思っていました。
そして2030年に話を戻すと……、2030年代の学校の姿は遠い未来ではありません。日本はすでに成熟した国家なので、なかなか理想形に一足飛びにはいかないもどかしさもありますが、私は、子どもたちが自分で学びのスタイルを選択できるようになっていてほしいと思っています。
同じ学び舎に集い、互いに刺激し合いながら学んでいくという学校の在り様にプラスして、個別最適な、探究的な学びが自由にできる。そういう学びをジョイントした形に、この先、全ての学校がなるのではないかと希望を持っています。
同じ年代の人間たちが同じ学び舎に集い、同じような学びをするという、今の学校の在り様は、もう終わりの始まりだと思っています。

平川 私はその頃にはオルタナティブの学校が2割になっていてほしいと思っています。全国の小中高校・特別支援学校を合わせると、約3万5000校 あるので、そのうち7000校がオルタナティブの学校になっている。それぐらい増えていかないと、日本の教育は変わらないし、不登校の児童生徒も増え続けると思います。
例えば、オランダでは公立校よりも私立校の方が多く、その中にオルタナティブもたくさん入っています。義務教育の間は公立校も私立校も無償で、学区もなく、保護者と子どもは自分の行きたい学校を自由に選ぶことができるので、どこかの学校にはマッチします。
森さんも細田さんも指摘されているように、これからの学校は子どもたちが「選べる」ことがキーワードになると思います。
◇◇◇
【プロフィール】
平川理恵(ひらかわ・りえ) 京都市生まれ。同志社大学卒業後、㈱リクルートに入社。留学仲介会社を起業後、2010年に全国で女性初の公立中学校民間人校長として横浜市立市ヶ尾中学校に着任、15年に横浜市立中川西中学校校長。18年4月から24年3月まで広島県教育委員会教育長を務める。24年10月より学校法人金蘭会学園(保育園・女子中高・女子大学・大学院)に関わり、「女子教育の再定義」に挑んでいる。著書に『クリエイティブな校長になろう』(教育開発研究所)など。
細田眞由美(ほそだ・まゆみ) 福井県生まれ。埼玉県立高校英語教諭、埼玉県およびさいたま市教育委員会、さいたま市立大宮北高校校長を経て、17年6月から23年6月までさいたま市教育委員会教育長を務める。文科省中教審初等中等教育分科会臨時委員、経産省産業構造審議会教育イノベーション小委員会委員などを歴任。現在はうらわ美術館館長、兵庫教育大学客員教授、東京大学公共政策大学院講師、各自治体の政策プロデューサーとして活躍。著書に『世界基準の英語力 全国トップクラスのさいたま市の教育は何が違うのか』(時事通信出版局)など。
森万喜子(もり・まきこ) 北海道生まれ。北海道教育大学特別教科教員養成課程卒業後、千葉市、北海道小樽市で美術教員として中学校で勤務。教頭職を7年務めた後、2校で校長を務め、23年3月に定年退職。23年7月からスタートした青森県教育改革有識者会議の副議長を務め、自治体の教育改革にも挑んでいる。また、文科省学校DX戦略アドバイザー、文科省CSマイスターも務める。著書に『「子どもが主語」の学校へようこそ!』(教育開発研究所)など。