社会的孤立を防ぐセーフティーネットを意味する言葉として「居場所」が使われるようになって久しい。石井正宏さんが代表を務める「パノラマ」は、横浜市北部エリアで子ども・若者支援をするNPO法人だ。今から10年前、卒業生の進路未決定者の割合が高かった神奈川県の公立高校で、図書館を活用した校内居場所「ぴっかりカフェ」を立ち上げた。以来、毎週木曜日の放課後に無料のお菓子やジュース、時には温かいみそ汁を生徒に提供し、さまざまな困難を抱えた生徒が支援と自立につながる拠点としてカフェは学校に根を下ろしている。「ぴっかりカフェ」はどのように誕生したのだろうか。(全3回)
――高校内で校内居場所カフェを作ろうと思ったきっかけは何だったのですか。
元々、僕は2000年からひきこもりの若者の支援をしていました。ひきこもっている若者の家庭に行ったり、家から出てきた若者と一緒に寮で生活しながら自立を目指す支援をしたりしていたのですが、ひきこもってからの支援は本人に負担がかかるし、多くは会えなくなってしまうのです。それで、なぜひきこもる前にこの人に出会えなかったのかという思いが強くなってきて、ひきこもる前の若者に会いたいと09年に起業しました。
現在の生活困窮者自立支援推進法ができる前の、内閣府モデル事業「よこはまパーソナル・サポートサービス」の相談員を依頼され、若者の相談を受けるようになったのです。そこにある公立高校の先生が「うちの学校は困難を抱えた生徒が多いので何か連携できないでしょうか」と連携先を探しに来られたのです。それで11年度から高校に入ることになりました。
支援することになった時、僕は相談室で相談を受ける形にしたくなかったのです。なぜなら生徒が相談室をノックするというのは「自分は困っている人です」という証明になってしまうから。「友達に見られたら恥ずかしい」「お前、相談に行っているんだ」というスティグマが生じるのがかわいそうだということと、高校生にとって知らない人に会うハードルが高いことも理由でした。
そこで、図書館を居場所にした支援ができないかを校長先生に提案したところ、学校司書さんがOKすればいいよ、ということになりました。そこでお願いをしに行ったら――その方が今パノラマの理事を務めてくださっています―、二つ返事で認めてくれたのです。実は彼女は、生徒たちに司書室を開放するということを実践してきた司書だったのですね。図書館を居場所として運営することに長(た)けた司書と、若者支援をしてきた僕が奇跡的なマッチングを果たして、毎週、図書館に行くようになったのが11年の6月ぐらいです。
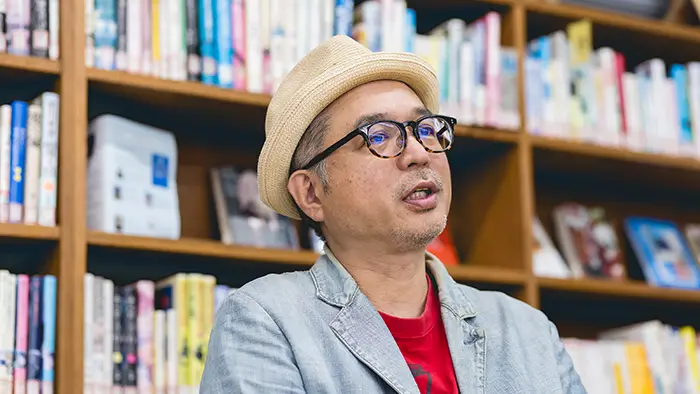
――学校としても初めての試みだったわけですね。
図書館に若者を支える「ユースワーカー」がいる、ということなんだけれども、前例がないから「やる」とは言ったものの、最初はどうすればいいか分からなかったんです。図書館に座っていても生徒たちは僕のことを無視するわけですよね。誰か分からないんだから当たり前ですけれど。「相談承ります」と看板を作ってみても来る生徒はまずいないわけです。
それで、生徒がいない時に司書さんと僕は、大好きなビートルズの話題でずっとおしゃべりしていて、司書室にも招いてくれたのです。司書室は軽音部のたまり場になっていて、昼休みや放課後は軽音部の子たちがおしゃべりやお弁当を食べにやってきます。そこで僕がギターを教えてあげたり、お弁当を一緒に食べて、僕のあんまり好きじゃない大学芋とかを分けてあげたりだとか、そういうことがどのくらい続いたか分かりませんけれど、ある時、ある生徒が「うち父子家庭なんだよね。週末にお父さんの彼女さんがうちに来るから、私が出てなきゃいけない」と悩みを語り始めたのです。他にも「うちは生活保護なんだよね」とか。
図書館のフロアにいた時は無視されていたけれど、司書室に入って一緒にギターを弾いたりお弁当を食べたりすると悩み事が出てきて、相談に乗れるようになった。僕はそれを「信頼貯金」という言葉で表しているんだけど、図書館に座っているだけの時の信頼貯金はゼロどころかマイナスです。司書室で生徒と過ごすとだんだんどんな人かが分かり、信頼の貯金がたまっていって、ある程度の残高になると、自分の悩みが話し出される。これがユースワークの神髄なのかなという手ごたえを得てからですね。図書館でも相談が始まり、みんながいる前で話しにくい場合は個別の相談を受けるようになりました。
高校1年生の6月でもう中退を決意している子がいて、「石井さんとお話してみて」と、先生に連れてこられたケースがありました。「住み込みの仕事を探して働く」と言うけれど、中卒で住み込みの仕事を検索してもハローワークの端末では0件なんです。その画面を見せたり、生涯賃金の違いを説明したりして「学校にいたほうが得だと思うから来たら?」と5分ぐらい話し、残りの時間はその子の好きなバンドの動画を一緒に見ていました。チャイムが鳴って教室に戻す時に「明日からちゃんと学校来なよ」と声をかけたら、その子が本当に学校に来るようになったのです。先生方は「奇跡だ」と大騒ぎでした。そんなことが続いていく中で、学校の中にいないと困る人に僕がなっていったのです。

――カフェになったのはその後ですか。
そうです。そのころ横浜市の委託事業が縮小され、会社の経営的にも苦しくなり、自宅から支援している高校に通う交通費すらぎりぎりという状態になってしまいました。そんな折、横浜でローカルのクラウドファンディングが立ち上がると聞いたので、正式にNPO法人化して、クラウドファンディングで100万円の寄付を集め、そして今まで居場所だけだったものを校内居場所カフェに切り替えることにしたのです。
これは高校の先生からの提案でした。ちょうど大阪府立西成高校で校内居場所「となりカフェ」が始まったという情報も入っていました。そんなわけで14年12月11日に「ぴっかりカフェ」がオープンしました。図書館は西日が入ってくる明るい場所で「ぴっかり図書館」という愛称がもともとあったんです。それにちなんで提案してくれた先生が名付けてくれました。
それまでは、いわゆる「図書館の住人」のような人たちにしか出会えなかったのが、「お菓子とジュースが無料で飲める居場所ですよ」と言ったことによって、普段、図書館に来ないような子たちにも会えるようになりました。オープン初日になんと95人も来たのです。それ以降、ボランティアスタッフを集めて、出会った生徒たちと日常会話の中で関係性を紡いで、支援につなげていくようになりました。生徒たちのつぶやきを集めて、それを学校に伝えていきながら、校内の専門家や児童相談所のような校外の専門家と高校をつなぎ合わせるソーシャルワークができるようになったんです。
現在、ぴっかりカフェは毎週木曜日に開いています。当初は昼休みと放課後に開いていましたが、コロナ後は放課後だけになっています。もともと飲食可の図書館なんで、ぴっかりカフェのない日も生徒たちは図書館に来ています。教室で「ぼっち」の子たちが集まってきて、図書館でご飯を食べるという使い方もされています。ちなみに司書さんが図書館を開放したきっかけも、トイレでお弁当を食べている子を発見したからなんです。「そんなところで食べていないで、司書室に来て食べなよ」と声をかけたところから始まっています。
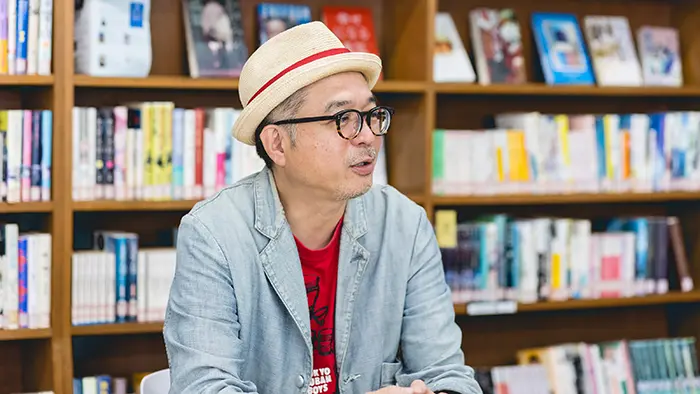
【プロフィール】
石井正宏(いしい・まさひろ) 2000年ひきこもり支援に取り組む。ひきこもる前からの予防型支援の必要性を痛感し、11年から神奈川県立高校内の図書館を居場所にした支援を開始し、14年に校内居場所カフェへと発展させる。横浜北部エリアで小学生から、老齢の親とひきこもりの子が孤立してしまう「8050問題」まで、途切れのない支援の構築をミッションに活動。NPO法人パノラマ理事長。フジロックNGO Village幹事。