2015年、神奈川県内のある公立高校の図書館に校内居場所「ぴっかりカフェ」を開き、運営に携わってきたNPO法人パノラマの石井正宏さん。見えてきたのは厳しい逆境にさらされる生徒たちの姿だった。生活困窮やいじめなどの経験から自尊感情が損なわれると、その影響は高校在学中のみならず卒業後にも及ぶ。途切れのない支援をしていくには、点在する地域の仕組みに横串を刺し、大人がつながっていくことが必要だと石井さんは指摘する。(全3回)
――カフェの写真を見ると、温かいものも出しているようですね。
ぴっかりカフェで一番人気のメニューはおみそ汁なんですよ。生徒の中で、お弁当を持って来られない子たちが多くてお昼を食べていないんです。お弁当を用意することができない、お昼代も持たされていない、中には交通費がなくて学校に来られなかった生徒もいたこともあるくらい、厳しい生活の状況があるんです。
それに気付いたのは、寄付で届いたインスタントのみそ汁を出した時でした。具とおみそのパックが別々になっていて、それを合わせてお湯を入れるタイプのものです。最後の方になるとみそのパックだけが残っているんです。なぜかというと、具が1個では足りないから一人で3個も4個も入れて、おかわりして、それで生徒たちはおなかを満たしていたんです。「みそのパックだけでもまだあるから、お湯を入れて飲んだら」と言っても、具がないから「いらない」と。それほどおなかがすいている生徒の実態が、カフェを始めたことによって顕在化してきたわけです。
だったら、ちゃんとしたおみそ汁を飲ませてあげたいよね、ということで野菜のご寄付を募ったり、おみそ汁だけでなく、おじやのような小腹にたまるものを出したりするようになりました。食べる前には列を作って、それこそ殺気立つような雰囲気だったのが、全員におみそ汁が行き渡ると、その場の空気が少し緩んでほんわかするんです。
だから、おなかがすいている子に授業や指導をしても、たぶん何も入っていかないんですよね。先生方もよくおっしゃっているけれど「調子が悪そうな子がいたら、病気の心配をするよりもご飯を食べているかどうかを心配した方がいい。大体当たっているから」と。本当にそうなんです。
僕の所に相談に来る子でも、元気がなく顔色も悪いから、たまたまあった水ようかんを「よかったら食べる?」と勧めたら、涙をポロポロ流して食べていた生徒もいました。そんな経緯も含め、ぴっかりカフェで月に1回、フードバンクで集めてきたお米などの食べ物配布会も始めました。
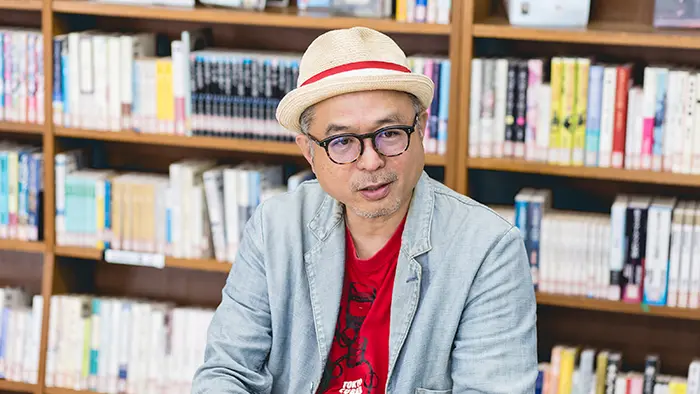
――校内居場所「ぴっかりカフェ」を始めてから、どんな変化がありましたか。
僕が高校に入った11年当時、毎年多くの進路未決定者が出ていると校長先生がおっしゃっていました。先生たちはあの手この手でいろいろんなことを試みているけれど、それでも進路未決定が減らないということで、学校としては「もう教員の専門性だけでは対応しきれない」ことを痛感していたんです。もちろん僕だけの力ではなく学校全体のサポートで、進路未決定がずいぶん減りました。
そんな中で続いてきたぴっかりカフェに期待されているのは、中退や進路未決定の予防支援です。ひきこもりの支援の現場に現れる若者は27、28歳ぐらいからなんです。17、18歳で学校という所属を失ってから支援を受けるまでに、10年の空白がある。この間に友達がいなくなり、親との関係が悪くなり、履歴書の空白が開いて、対人不安や恐怖が始まり、社会に出にくくなっていくんです。これを僕は「失われた10年」と呼んでいます。
ではなぜ、そうなる前に17、18歳の時点で彼らが支援の現場に現れないのか、なぜハローワークや地域サポートステーションに行かないのかを考えてみると、それは、そこに知っている大人がいないからです。
大人であれば、失業したからハローワークに行こうとか、どういう仕事に就いていいか分からないからキャリアカウンセリングを受けてみよう、夜、眠れないから臨床心理士に相談してみようと、専門家を頼る発想になるけれど、子どもたちはそうはならないんです。石井さんに聞いてみよう、〇〇さんに話してみよう、と「人」に頼るのです。なので、15、16歳ぐらいから僕のような支援者に会っておくことで「失われた10年」を縮めることができます。
僕は生徒たちからマスターと呼ばれているんですが、「マスターに相談に学校に行こう」っていうふうになったらいいなというのも、ぴっかりカフェを続けている理由の一つです。

――小中学生の居場所や、若者支援の拠点を横浜市北部エリアで展開しています。
僕が相談に乗っている子たちは、小学校・中学校時代にいじめられた経験を持つ生徒が多いんです。学校に対して良い思い出がまるでないような子でも、高校では何かリベンジしたい、学校生活を楽しみたいと思っています。でも、自尊感情はズタボロです。僕はひきこもりの支援をしていた時に、ひきこもってからでは遅いと思って高校に入ってはみたけれど、高校に入ったらもう遅いなというのを感じたんです。自分で自分をかわいがれない、そういう状況になるもっと前から会わなくてはいけない、と。
そこで、横浜市の委託事業として2022年1月から小中学生の放課後の居場所「青葉区寄り添い型生活支援事業」を開始しました。青葉区内に居住し、サポートを必要とする生活困窮などのご家庭の子どもが、放課後に多様な生活経験をする場です。見ていると、やはり小学3、4年生ぐらいから授業に付いていけていない状況が分かってきました。そんな子たちが高学年になってくると「高校に行きたくない」と話すんです。そこで、私たちが支援に入っている高校ならパノラマのスタッフも来ているし、僕もいるよと伝えようと思っています。「知っている大人がいるなら高校に行ってもいいかも」と思ってくれたら、小中高で接続した支援が可能になると考えています。
さらに、ひきこもりなどを経験した15歳から39歳までの若者と、その家族を対象に、相談と居場所の提供をする「よこはま北部ユースプラザ」も運営しています。高校を中退した人や、進学先でつまずいた人などと、そのご家族への支援をしています。高校の卒業生が訪ねてくることもあって、それはやはり、僕や、ぴっかりカフェで出会った大人がそこにいるからなんです。
――幅広い年齢を対象に、一つのエリアで支援事業・機関を運営するパノラマのようなNPOは多いのですか。
あまりないと思います。でも、そういう支援が大事だろうと思っています。というのも今、居場所を使っている小学生が、10年後、若者対象の居場所を使っている可能性があるからです。今は小学校、中学校、高校、若者とそれぞれ大人の縦割りの中で支援していて、互いのネットワークが途切れているから、子どもたちも途切れていくんです。
それを僕たちのようなNPOが横串を刺して、居場所同士をつなげていけば、子どもたちが小学校から中学校、高校と上がっても、次の居場所にスムーズに入っていけます。僕たちが取り組んでいる横浜北部エリアの「パノラマモデル」のようなものが自分たちのエリアにもあったらいいよねと、他の地域でもまねしてもらえるようになったらいいですね。僕たちはノウハウを伝えますから。それが今、小中学生と高校生を同時に支援している意味だと思っています。

【プロフィール】
石井正宏(いしい・まさひろ) 2000年、ひきこもり支援に取り組む。ひきこもる前からの予防型支援の必要性を痛感し、11年から神奈川県立高校内の図書館を居場所にした支援を開始して、14年に校内居場所カフェへと発展させる。横浜北部エリアで小学生から、老齢の親とひきこもりの子が孤立してしまう「8050問題」まで、途切れのない支援の構築をミッションに活動。NPO法人パノラマ理事長。フジロックNGO VILLAGE幹事。