岐阜県飛騨市のJR高山線・飛騨古川駅や周辺の街並みはアニメ映画「君の名は。」の舞台として知られている。そこに点在する古民家や旧ホテルをリノベーションして講義室、ゼミ室などとして活用するユニークな大学が、2026年4月に開校予定だ。現在、文部科学省に設置認可申請中のコー・イノベーション大学(仮称)=Co-Innovation University(仮称)、略称「CoIU」(コーアイユー)。キャンパスの形態だけでなく、そのカリキュラムも独特という。理事長候補として開校準備を進める井上博成さん(一般社団法人CoIU設立基金代表理事)に聞いた。
――なぜ、大学を設立しようと思ったのですか。
生まれ育った岐阜県北部、飛騨地方は大学のない空白地帯。高校卒業後、多くの人が地域の外へ出てしまいます。「飛騨に大学があったら」という人は多く、自分も地域課題解決のためにも必要だと思いました。高校生の頃からキャリアを積んだ上で大学を設立したいと考えていましたが、大学生の時、東日本大震災が起こり、一つの転機となります。福島第一原発事故と合わせ、トップダウンではなくボトムアップの必要性、持続可能な地域づくりの必要性を感じました。
京都大学の恩師、植田和弘名誉教授には「地域で事業をやり、関係者に支えてもらいながら資金をためて大学を設立するのが良い」と言われました。池上惇先生には「理論と実践を往復する考え方が重要」とご指導を仰ぎ、諸富徹教授からは海外での研究を勧められました。
自分の中で「なぜ、大学をつくりたいのか」という思いを突き詰めると、世界の中では、社会変革の起点に大学があり、産業構造の転換のうねりの中心に大学があると感じました。例えば、米カリフォルニア州のスタンフォード大学はGAFA創出に関係し、大学が起点となってシリコンバレーに一つの大きな産業が生まれました。日本でも産業構造の変革や大きなビジョンの創出、他者と共にイノベーションを起こしていく時、その中心に大学があっていいのではないかと考えました。
それが街に根差し、街と一緒に産業構造をつくり変えていくというのが私の思い。出身地・岐阜県高山市は大阪府面積と同程度の日本一の森林面積があり、一方で年間約450万人の観光客を有しますが、高山市の市内総生産(GDP)は約3500億円。岐阜県内の最有力企業は年間の連結売上高が6000億円台であり、その半分程度。高山市の GDPのうち、第三次産業が多くを占め、一方、日本一の資源でもある山林資源が生かしきれていないことが分かりました。
私は飛騨地方の重要な資源である山林の価値化により、地域の産業構造の変革を目指し、木質バイオマスエネルギー事業、小水力発電事業にも取り組んでいます。地域資源の価値に気付き、それを生かす取り組みを学生と一緒にやっていきたい、教育を通じて産業構造、地域の未来像を一緒に考えたいと思い、大学づくりを始めました。
――CoIUはどんな大学ですか。
地域、組織、立場などを超越し、異なる環境に属する人たちがおのおのの知識や経験を掛け合わせ、複雑な課題の解決を目指して一緒に行動する「共創」をテーマに、その実現に向けて理論・対話・実践を行き来するプロセスを通じて課題解決、社会変革を実行する力を備えた人材を育てていきます。
1年生は飛騨で学びます。キャンパスは飛騨市中心部の街中に点在するリノベーション施設で、高山市中心部からは車で約20分の距離にあります。
2年生は全国に点在する拠点に、企業や自治体などの長期実践型インターンシップ「ボンディングシップ」のプロジェクトを中心に学びます。その拠点は北海道から福岡県まであり、今後も拡大していく方針です。週3日はボンディングシップに取り組み、残る2日はオンラインで講義を受講します。受け入れ企業は自治体を含め、既に約150社と合意しており、さまざまな地域での実践が可能な状況にあります。
3年生の最初には一度、飛騨に集まり、その後の2年間で学ぶ実践のテーマを決めて、3、4年生は全国各地で地域課題の解決・社会変革に向けた実践を通して学びます。
◇ ◇ ◇
CoIUの共創学部地域共創学科の定員は120人。1年を4学期に分けるクォーター制を導入。アドミッションポリシーには、①高校卒業までに学習した知識、基礎学力を十分に備えている②他者の意見を理解し、自己の考えを口頭または文書で表現できる③知的好奇心があり、学び続ける意欲が高い④地域の活性化に向けて積極的に行動ができる⑤大学の理念への共感、地域や社会の課題に関心がある――を掲げる。
◇ ◇ ◇

――どんな高校生に入学してほしいですか。また、高校生に対し、「このような学びができる」と提案できることはありますか。
相性が良いのは、地域の課題に関心のある生徒や地域活性化にチャレンジしたいと心から思っている生徒です。いろいろなチャレンジができる準備があります。
総合型選抜の比重も高くしたいと考えています。オープンキャンパスでは生徒、保護者の関心も高く、各地の高校生から「受けてみたい」という感触を得ています。
高校の先生には、新しい大学のコンセプトが故に「うちの生徒はたぶん受けない」という声もある一方、「(生徒は)絶対に関心を持ちます」という応援のメッセージも多く、特に、探究学習に熱心な先生は感度高く見守ってくれています。CoIUの特徴を理解し、親和性の高いと考えられる探究学習、地域課題に向き合っている先生に関心を持っていただけたら、うれしいですね。
――共創学部とはどのような学部で、どんな人材を育てようとする学部ですか。
九州大学共創学部、愛媛大学社会共創学部、高知大学地域協働学部など、地域課題に当たる人材を育てる学部はありますが、CoIUの特徴は日本全国の地域課題を対象に取り組む点です。
一つの地域だけで見える課題は限界があるということ。場所を変え、地域を変え、いろいろな地域とつながりながら、新しい社会をつくるため連携したい。飛騨の地域だけではできなかったことが実現できると思います。
卒業生のキャリアイメージは4つのカテゴリーに分ければ、①起業②事業継承③政治、行政への関わり④企業への就職――が考えられます。アントレプレナーシップを持って起業にチャレンジする人材や後継者不在で黒字倒産する企業も多い中、事業継承できる人材、行政、地方自治体、企業で地域課題、社会課題に立ち向かう人材を育成したいと思います。
――「街中がキャンパス」の具体的な構想、イメージはどのようなものですか。
飛騨古川はコンパクトで回遊性の高い街です。飛騨古川駅周辺の街並みに1~3号館といった古民家、旧ホテルをリノベーションした施設が点在しています。大きな敷地、大きな建物といった従来の大学のキャンパス、校舎とは違いますが、駅前の旧ホテルには120人が受講できる講義室があり、他にもゼミ室や自習室、グループワークができる場所、事務室を準備しています。駅近くに27年度開業予定の共創拠点「soranotani」にも大学の施設が入ります。
また、飛騨市は地域課題の最先端を行く地でもあり、将来、多くの地域が直面することが想定される課題が多くあり、価値化されていない地域資源があります。学生は授業の間に街中を移動し、地域のいろいろな人と交わり、地域のプログラムが準備され、街全体で学べるようになっています。
◇ ◇ ◇
1号館は旧料理店を改装。1階に事務室、2階はグループ演習室、ゼミ室。教授とオープンに対話できる空間、学生がグループディスカッションできる部屋があり、落ち着いた雰囲気。2号館は古い街並みの中にある静かな雰囲気の古民家で、図書閲覧室、自習室などがある。3号館は駅から徒歩1分の旧ホテルで、講義室、研究室を配置。授業の合間などに使えるスペースもある
◇ ◇ ◇

――ボンディングシップとは、どのような取り組みですか。
「ボンディングシップ」は「ボンド(絆)」と「インターンシップ」を掛け合わせたCoIU独自の新しい言葉です。インターンシップは近年、採用を主目的として学生を見定めるために実施する企業・団体が多く存在します。一方で、日本におけるインターンシップは教育的要素を含んだ形で展開されることも多く、教育を重視して実施する企業もあります。その実態はそれぞれ異なり、一つの言葉にいろいろなものが含まれ、捉え方もまちまち。
大学教育としてCoIUが実施しようとする中身を理解してもらう上で、言葉の定義を塗り替えることが必要不可欠だと考えました。つまり、教育のサポート、地域の付加価値を生んでいくことを重視するプログラムを開発することが必要で、そして、受け入れ企業にも継続的なメリットがないと持続しません。
CoIUの学び方は、理論、対話、実践の往還を掲げています。新しい価値を生み出すために理論を活用し、問いを立て、仮説をつくり、実践してみる。これこそ課題解決を実行できる人に成長していく学びのサイクルで、実践の部分を担保していくのがボンディングシップです。
――学長候補は幅広く活躍するデータサイエンティスト、慶應義塾大学医学部教授・宮田裕章さん。どんなことを期待していますか。
21年11月、宮田さんの学長候補就任を発表しました。
クリエーティブディレクター・水野学さんと「いま、文明に問う。」というステートメントを考えました。「文明」という共通キーワードがあり、宮田さんの考えに共鳴、一緒にやりたいと強く思いました。宮田さんと出会い、やりたいことを突き詰めてビジョンをつくりました。
また、これからは「個」の時代だと思います。一人一人の「個」が輝きながら、しっかり自分自身をメタ認知して、自分が何をやりたいか理解し、同時にいろいろな人とともに共創していく。誰一人取り残さず、互いを尊重し、つながりながら新しい英知を重ねて未来を共創していくのです。「共に文明をつくっていこう」という、その先に新しい社会がある。その根幹を支える教育でありたい。そういう未来像を宮田さんと一緒につくっていきたいと思います。
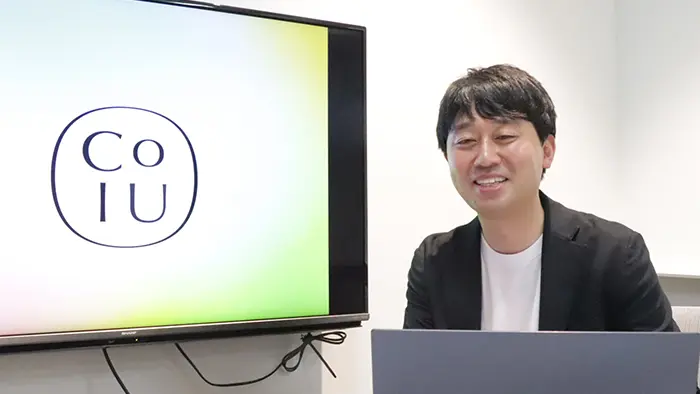
【プロフィール】
井上博成(いのうえ・ひろなり) 1989年生まれ。岐阜県高山市出身。京都大学、同大学院では自然資本と地域金融を研究。研究指導認定退学後の24年に博士号(経済学)取得。小水力発電や地域信託の会社を設立するなど法人も経営する。