教員の処遇改善などに向けた給特法改正案が5月15日、衆院本会議で可決され、参院に送られた。教職調整額の引き上げなどを盛り込んだ当初案に加え、与野党合意による修正で、2029年度までに教員の時間外在校等時間を月平均30時間程度に縮減する目標などが明記された。
同法案や修正内容、さらに今後の課題などについて、識者はどう見ているのか。多くの学校の働き方改革を手掛け、中教審初等中等教育分科会臨時委員などとして給特法改正案のベースとなる議論にも加わった「先生の幸せ研究所」の澤田真由美代表と、学校の働き方改革や教員のメンタルヘルス対策などに取り組んでいるNPO法人「共育の杜」の藤川伸治理事長に聞いた。
同法案では、教職調整額を4%から段階的に引き上げて10%にすることや、教育委員会に教員の業務量を適切に管理する計画の策定・公表を義務付けることなどが盛り込まれた。さらに与野党合意による修正で、29年度までに教員の時間外在校等時間を月平均30時間程度に削減する目標が示され、そのための措置として、教員1人当たりの授業時数の削減や教職員定数の標準の改定などが附則として明記された。
こうした法案の修正については、澤田代表、藤川理事長ともに一定の評価を示した。澤田代表は、附則で「勤務の状況について調査を行い」(第6条)などと追加されたことで、幅広く政策のPDCAサイクルを回していくことへの期待を示した。藤川理事長は時間外在校等時間の削減に向けて授業時数の削減などが盛り込まれた点などを「意味のある修正だった」と述べた。
今後の課題や期待について澤田代表は、附帯決議で「教育課程上の工夫を含めた業務改善の取組を整理・共有する」と加えられた点に触れて、「現状の枠組みでも工夫できることがたくさんある」として、学校関係者がこうした点に気付くきっかけにするとともに、現在、進められている次期学習指導要領を巡る中教審の議論にも参加してほしいと呼び掛けた。
藤川理事長は、法案の修正を経ても業務改善に向けた具体的な財源に踏み込んでいないとして、「目標達成の責任を教委に丸投げしている印象もある」と批判したのに加え、「教員の健康確保措置」を巡る議論が深まらなかったことを問題視し、参院でしっかり議論する必要があると強調した。
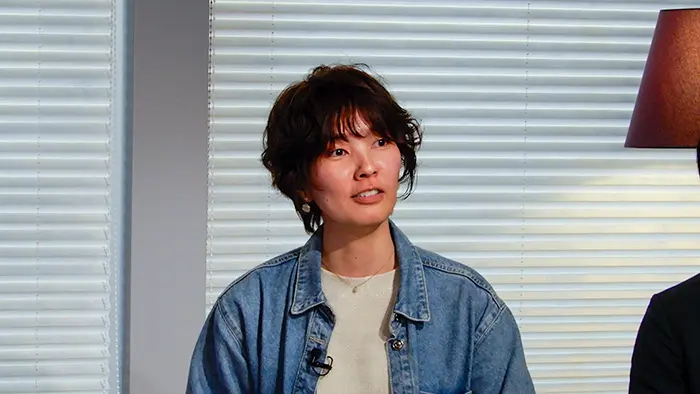
給特法改正案は、中教審で働き方改革・指導運営体制・処遇改善の一体的推進をまとめたものが形になっており、内容は妥当だと考えている。教員の業務量管理などの措置や計画を策定・公表・総合教育会議に報告することなどにプレッシャーを感じる自治体もあると思うが、全体で改革を進める上で制度化することは必要であり、首長部局の理解を得るためにも有効と考えている。
また、学校運営協議会の話題に業務削減を含めていることも、地域を巻き込むことに二の足を踏む学校が多い中で評価できるポイントだと考えている。
法案の修正も全体的にはプラスになったと思う。例えば改正案にはなかった「勤務の状況について調査を行い」(第6条)が追加された。こうした定点観測を生かして、教職調整額だけでなく幅広く政策のPDCAサイクルを回していくことを期待したい。
附帯決議で、学校・教師が担う業務に係る3分類(※注)の確実な実施に向けて、国および地方公共団体は「財政措置等の条件整備を」とあるので実行されれば効果的だろう。また、国は「教員が担うべきではない業務」を明確に示すというかなり踏み込んだ表現もある。ハラスメントと言えるような保護者への対応などがこれに当たる可能性があると考えるが、これを国が示すことができれば、現場はそれを後ろ盾に改革を進めやすくなるのではないか。
これに続く「教委や学校段階で教育課程上の工夫を含めた業務改善」という部分については、多くの学校や教委のコンサルを通して、教育課程上の工夫で相当のことができることを見てきており、こうしたことに気付く学校や教委が増えることを期待したい。標準を大きく上回る授業時数の見直しや、日課表の改善などにより、余白作りが実現できている例もある。ただ、国がこれらを整理・共有することという点については、すでに事例集をはじめ、さまざまに整理・共有されており、これまでと重複するのではないか。
現状の制度の枠組みでも、工夫してできることはたくさんある。中教審の「質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」の答申の別紙には、上記3分類の対応実例が詳しく掲載されている。残念ながらあまり現場に浸透していないが、こうした資料にも目を通してほしい。
さらに附帯決議に「教員の授業時数を軽減するための教育課程の実施」と盛り込まれたのは、次期学習指導要領の改訂も意識していると感じられる。現在、中教審で議論を進めているが、文部科学省は「裁量的な時間」など各回踏み込んだ論点で、課を超えて大変な熱量で臨んでおり、今回の動きを機に教員や教委の関係者にはこうした場を傍聴して議論に参加してほしい。この中から働き方改革や負担を軽減する教育課程編成についてのヒントも得られると思う。
今後、法案が成立すればいろいろな枠組みが決まっていくことになるので、各学校現場ではそれを後ろ盾に裁量を発揮してほしいし、教委も文科省もしっかり支え、後押ししてほしい。
(※注 「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが負担軽減が可能な業務」の14項目3分類)

衆議院の与野党逆転によって、野党からの修正要求がかなり受け入れられた点は評価できる。
例えば1カ月の時間外在校等時間を30時間に減らす目標に向けて、授業時数の削減や教職員定数の改定などが盛り込まれた。また、明記はされていないが、多くの関係団体が要望している定数改善に向けた、学校の教職員定数を算出する際の「乗ずる数」の見直しも今後、検討の俎上(そじょう)に載ると読めるので、非常に意味のある修正だったと言える。
ただし、時間外在校等時間を減らしていくために必要な財源に触れられていないのは、大きな課題だ。市町村教委は業務改善に向けて、施設整備や非常勤スタッフ配置などの予算を首長部局に要求して確保に努める必要があり、果たすべき役割は非常に重いが、自治体の財政力には格差がある。同法案8条には、教委の義務規定が数多く書かれているが、財政事情によって実施可能な教委とできない教委が出てくる。そういう意味ではこの法案は地方の教委に冷たく、目標の達成は教委の責任だと丸投げしている印象もある。
教職員の勤務実態調査の実施は今回の法案の一つの争点であり、多くの野党国会議員が繰り返し主張していたが文科省の抵抗が強く、与野党間の折衝でも難航したとみられる。ただ、修正案で教職員の勤務の状況について調査を行うことが付記され、附帯決議でこれまでの実態調査に留意するとの項目が設けられており、「合わせ技一本」とも読める。実態調査への含みも残す形で、よくここまで政治決着できたとも感じている。
衆議院で議論が深まらなかった重要な課題として、「教員の健康確保措置」が挙げられる。教員の精神疾患による休職は過去最多に上り、心身の健康が脅かされている状況であるにもかかわらず、具体的な対策について議論されなかった。
長時間勤務を解消しても精神疾患が減らないことは、いろいろな調査で明らかになっている。心身の健康を守るために具体的にどう取り組み、国はどう支援すべきかは大変重要なテーマであり、参議院ではしっかり議論してほしい。(談)