夏休みが近づいたある日の朝、2年生の男の子が校門にいた私に近寄ってきて、
「校長先生、夏休みになったらこのじょうろをどこにおいておけばいいですか」
と相談してきた。5月に学校菜園に植えた夏野菜に男の子は、じょうろを下駄箱に入れておいて毎朝必ず水やりをしていた。夏休みになったら下駄箱は入口が閉まってしまうことを1年生の夏休みで知っていた。だから、毎日の水やりを夏休みにも続けていきたくても、じょうろを持ち帰らなくてはいけないのだろうかと考えて、じょうろの置き場所をどこにしたらよいのか困っていたみたいだった。
夏休みには今と状況が変わり、今まで通りではいかないことに気付いた男の子の主体性に感心したのと、それを聞いた担任の先生が、男の子に「菜園の横に苗を運ぶかごがあるけど、そこにじょうろを入れてもいいですよ。他にどこかに置いておきたい場所がありますか」とその子の想いを聞いてあげたことにまた感心しました。そのような学級経営をしてきたから、この子のように主体性が養ってきているのだろうと思いを巡らせた朝でした。
「こうしなさい」ではなく「あなたはどうしたいの」と言える先生が、考える子どもたちを育てていくのだと感じた何でもないエピソードでした。
(稲垣隆佳・安城市立今池小学校長)

江戸時代の教育学者、細井平洲の言葉に「人の子を教育するは菊好きの菊を作る様にはすまじく、百姓の菜大根を作る様にすべきこと」というものがある。菊好きは、理想的な好みの形を目指して育てる。百姓は形や大きさにかかわらず「おいしくなあれ」と育てる。最近は、自身が「菊好き」なのでは、と悩む先生たちによく出会う。菊好きから百姓への転換の難しさも、非常に多く見聞きする。
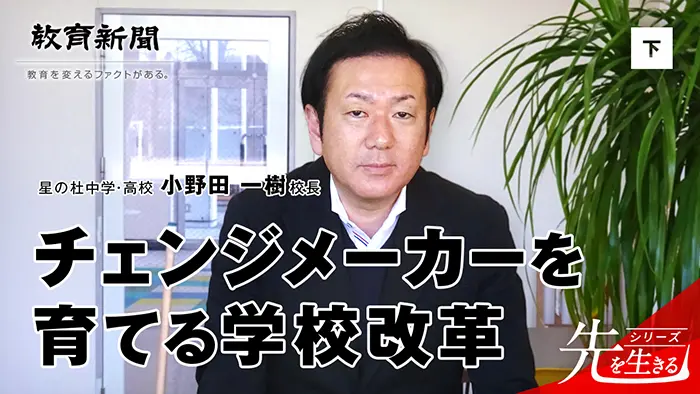
伝統的なカトリック系ミッションスクールだった宇都宮海星女子学院中学・高校は、2023年度に星の杜中学・高校として生まれ変わった。世界10都市以上で海外留学を経験できる制度の導入など積極的にグローバル教育に取り組み、入学希望者も年々増加するなど注目を集めている。また、24年度には全国の私立中学・高校12校とコンソーシアムを立ち上げ、国内留学などの連携も始めた。これらの施策を推進する小野田一樹校長に、学校改革の現状や、私学を中心としたこれからの学校教育の在り方などを聞いた。
広告ブロック機能を検知しました。
このサイトを利用するには、広告ブロック機能(ブラウザの機能拡張等)を無効にしてページを再読み込みしてください



